【まとめ】施設ケアマネと居宅ケアマネの違いについて分かりやすく解説
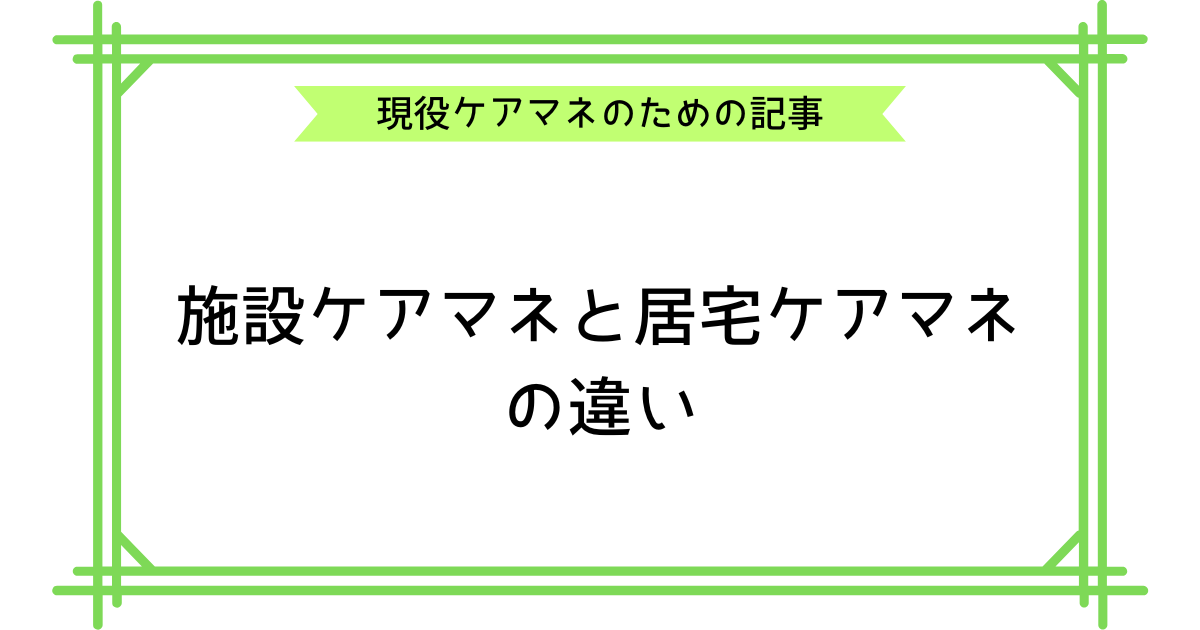
介護支援専門員(ケアマネジャー)には大きく分けて「施設ケアマネ」と「居宅ケアマネ」の2種類があります。
どちらもケアプランを作成し、利用者の生活を支援する役割がありますが、働く場所や対象となる利用者、業務の進め方などに違いがあります。
「これからケアマネを目指したい」「転職を考えているけれど、どちらが自分に合っているか知りたい」という方のために、本記事では施設ケアマネと居宅ケアマネの違いを表や具体例を交えて分かりやすく解説します。
施設ケアマネと居宅ケアマネの違いを表で比較!
まずは、両者の違いを一目で把握できるよう、主な比較項目を表にまとめました。
| 比較項目 | 施設ケアマネ | 居宅ケアマネ |
|---|---|---|
| 勤務先 | 介護老人福祉施設(特養)などの入所施設 | 居宅介護支援事業所 |
| 対象利用者 | 施設に入所している利用者 | 在宅で生活している利用者 |
| 担当件数の目安 | 約100人前後(施設全体) | 一人あたり35件が上限 |
| ケアプランの種類 | 施設サービス計画書 | 居宅サービス計画書 |
| 他職種との連携 | 施設内の職員と密な連携 | 外部事業所・医療機関との調整が中心 |
| 業務の特徴 | 利用者の日常を常に把握しやすい | 訪問により状況を確認する必要がある |
居宅ケアマネの特徴と役割を詳しく解説
居宅ケアマネは在宅生活を支えるケアの司令塔
居宅ケアマネは、主に在宅で生活する高齢者を支援します。本人・家族と面談を行い、アセスメントに基づいてケアプランを作成し、介護サービスの調整やモニタリングを行います。
居宅ケアマネの主な業務内容
- 月1回以上の自宅訪問
- ケアプランの作成・更新
- サービス担当者会議の実施
- サービス提供事業所との連絡・調整
- 介護保険の給付管理や請求事務
居宅ケアマネは外部連携が多く、調整力が求められる
居宅ケアマネは、訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具業者など、複数の外部事業者と連携する必要があります。病院や包括支援センターとの調整も多く、広い人間関係を築く力が必要です。
居宅ケアマネはこんな人に向いている
- 一人ひとりの生活背景に寄り添いたい
- フットワーク軽く外回りができる
- 自主的にスケジュール管理ができる
施設ケアマネの特徴と役割を詳しく解説
施設ケアマネは入所者の生活全体をサポートする役割
施設ケアマネは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、入所施設に勤務し、そこに暮らす利用者のケアプランを作成・管理します。施設内での生活全体を支えるポジションです。
施設ケアマネの主な業務内容
- 施設サービス計画書の作成
- 利用者・家族との面談
- 看護師・介護士・栄養士などとの連携
- 施設内会議での情報共有
- 利用者の生活状況の把握・調整
施設ケアマネはチームケアの中核を担う存在
施設では、医療・介護・リハビリ・栄養など多職種が在籍しており、日々の情報共有がしやすい環境です。ケアマネはこれら職種の中心に立ち、利用者にとって最適なケアが提供できるようマネジメントを行います。
施設ケアマネはこんな人に向いている
- チームで動くのが得意
- 安定した勤務スタイルを希望する
- 施設ケアに興味がある
居宅ケアマネと施設ケアマネのそれぞれのメリット・デメリット
居宅ケアマネのメリット
- 利用者との密な信頼関係を築ける
- 比較的自由度の高い働き方ができる
- 多様な事業者とのつながりが持てる
居宅ケアマネのデメリット
- 外出や移動が多く、体力的にハード
- 一人職場が多く、相談相手が少ない
- 書類業務や請求業務に追われがち
施設ケアマネのメリット
- 同僚とすぐ相談・連携できる環境
- 利用者の状態を日常的に観察できる
- 外出が少なく、天候に左右されにくい
施設ケアマネのデメリット
- 担当人数が多く、個別支援に時間が取れない
- 施設の方針に縛られることがある
- 施設業務との兼務になる場合が多い
施設ケアマネと居宅ケアマネの向き・不向き
自分の価値観・働き方に合わせて選ぼう
どちらのケアマネにも、それぞれのやりがいと課題があります。以下のポイントを参考に、自分の働き方や希望に合うほうを選びましょう。
居宅ケアマネが向いている人
- 自由にスケジュールを組みたい
- 利用者とじっくり関わりたい
- 幅広い知識・対応力を身につけたい
施設ケアマネが向いている人
- チームワークを重視したい
- 安定した環境で働きたい
- 一度に多くの利用者を支援したい
まとめ
施設ケアマネと居宅ケアマネは、同じ「介護支援専門員」という資格でありながら、その働く環境や役割、必要とされるスキルには大きな違いがあります。
居宅は個別性の高い支援が魅力で、自由度がある一方、孤独感や事務業務の多さが課題です。
施設はチームで支える体制が整っており、安定した勤務が可能ですが、多忙さや制度上の制限もあります。
自分の性格や希望する働き方に合わせて、どちらが合っているかをじっくり見極めて選択することが、長くケアマネとして働き続けるためのポイントです。















