ケアマネの仕事を突然辞めるのはあり?そんな時の注意点やトラブル対策を解説
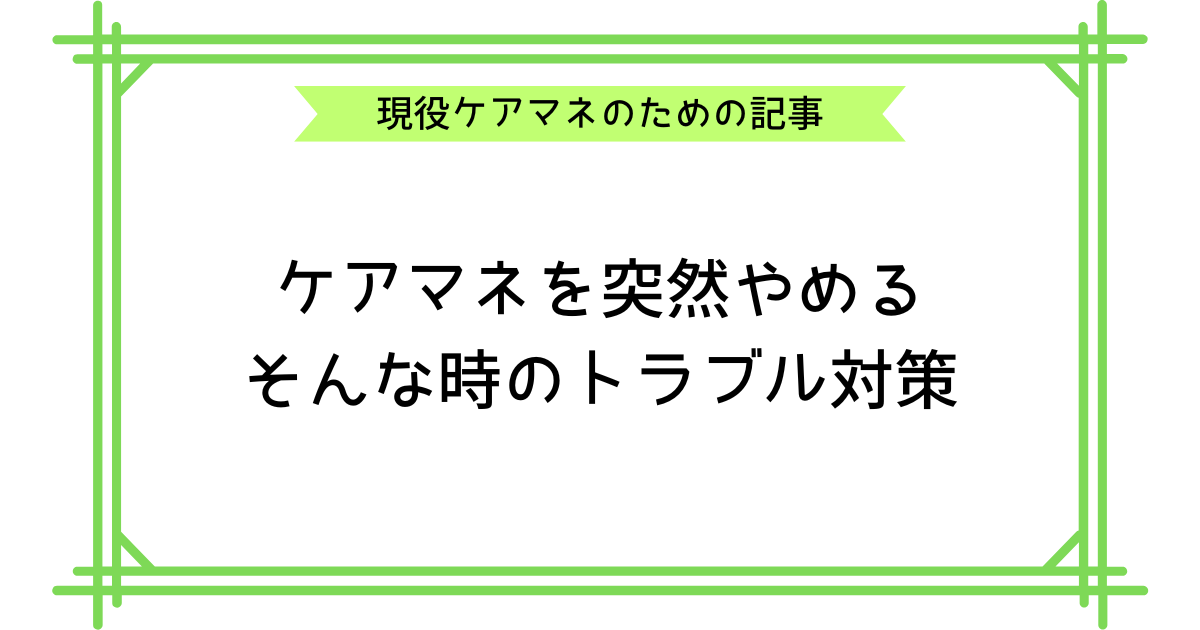
「もう限界…」「今すぐ辞めたい…」
ケアマネジャーの仕事は、業務量の多さや責任の重さ、人間関係のストレスなどから、「突然辞めたい」と思うことも珍しくありません。
しかし、急な退職は事業所や利用者に大きな影響を及ぼすこともあります。
本記事では、ケアマネが突然辞めることは可能なのか、辞める際の注意点やトラブルを避けるための対策について詳しく解説します。
どうしても辞めたい時の判断材料として、ぜひ参考にしてください。
ケアマネの仕事を「突然辞める」のは法律的に可能?
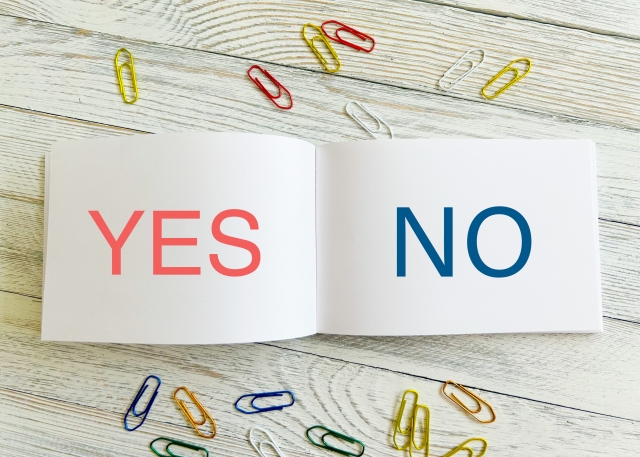
民法上は「退職の自由」が認められている
民法627条では、「労働者は2週間前に申し出れば退職できる」とされています。つまり、ケアマネであっても退職の意思を伝えてから2週間経過すれば、法的には辞めることができます。
ただし、実際の現場では「すぐ辞められる」わけではないケースも多く、業務引き継ぎや利用者対応などの事情から、就業規則で「1ヶ月前までに申し出る」と定めている職場もあります。
就業規則や雇用契約書の確認が重要
突然辞めたことによって「損害を与えた」としてトラブルになることもあるため、まずは就業規則や雇用契約をしっかり確認しましょう。
突然辞めることで起こりうるトラブルとは?

利用者への支援が途絶える可能性がある
ケアマネは担当利用者の生活を支える“司令塔”です。突然辞めることで、以下のような支援上のリスクが生じることがあります。
- ケアプランが未作成のまま次月を迎えてしまう
- 利用者や家族が不安を感じる
- 新しいケアマネへの引き継ぎが不十分になり、サービスが混乱する
事業所との関係悪化・損害請求の可能性も
極端に急な退職や引き継ぎ放棄があると、事業所側から損害賠償を求められたり、協会や地域との信頼関係に影響を与えることも。
トラブル例:
- 「加算が取れなくなった」として損害を主張される
- 引き継ぎ記録がなく、後任が対応に困る
- 所長や管理者との関係が険悪になり、退職後の紹介・再就職に支障が出る
どうしても辞めたい!そんなときのステップと対応

ステップ1:直属の上司・管理者に相談する
「突然辞めます」ではなく、まずは落ち着いて管理者に状況を相談しましょう。体調不良やメンタル不調、人間関係の問題など、辞めたい理由を誠実に伝えることで、理解が得られやすくなります。
相談時のポイント:
- 状況と気持ちを正直に伝える
- 引き継ぎや退職時期について前向きに提案する
- 書面で退職届を提出するタイミングを確認
ステップ2:引き継ぎ可能な範囲を整理する
退職日までに最低限引き継げる内容をまとめておくと、後任への負担が減り、スムーズな退職につながります。
例:
- 利用者ごとのアセスメント状況と今後の予定
- 関係事業所との連絡履歴
- ケアプランの進捗状況と注意点
「自分がいなくても大丈夫」と思える準備が、自分の安心にもつながります。
ステップ3:体調・メンタルが限界の時は退職代行も検討
本当に精神的・身体的に限界の場合は、無理に職場と話し合いをせず、退職代行サービスを利用するという選択肢もあります。ただし、信頼できる業者を選ぶこと、最終的にはご自身で年金・保険などの手続きを行う必要があることに注意しましょう。
円満退職に向けた具体的な準備と配慮

退職届は文書で提出する
退職の意思表示は口頭でも有効ですが、文書で提出した方が記録として残り、トラブル回避になります。
文書には以下の内容を記載:
- 退職の意思
- 退職希望日
- 理由(必須ではないが記載してもOK)
有給休暇の消化は計画的に
退職前に有給休暇が残っている場合は、管理者と相談しながら計画的に取得しましょう。業務引き継ぎと重ならないように調整するのがベストです。
利用者・家族への説明も忘れずに
可能であれば、担当利用者や家族に「退職のご挨拶」を行い、信頼関係を壊さずに離職できるよう配慮しましょう。メールや電話でも構いませんが、事業所の方針に従いましょう。
「辞めたい」と思ったら知っておきたい対策と心構え

完璧を目指さない働き方を意識する
ケアマネの仕事は責任が重く、すべてを自分で抱え込むと心が折れてしまいます。まずは「できる範囲で支援する」という姿勢で、自分を追い詰めない働き方を見直してみましょう。
第三者に相談して客観的な視点を持つ
同僚、家族、友人、または外部のカウンセラーに話を聞いてもらうことで、気持ちを整理し、冷静な判断ができることもあります。
他の職場や働き方を調べておく
「今の事業所が合わないだけ」という可能性もあります。他の事業所、地域包括支援センター、施設ケアマネ、パート勤務など、自分に合った働き方を探すことで、気持ちに余裕が生まれることも。
まとめ

ケアマネの仕事はやりがいがある一方で、精神的・業務的な負担も大きく、突然辞めたいと思うこともあるでしょう。
法律的には2週間前の申し出で退職は可能ですが、実務上は引き継ぎや周囲への配慮も求められます。
トラブルを避けて円満に退職するためには、冷静な相談、文書での意思表示、引き継ぎ準備が鍵となります。
心と体が限界になる前に、自分を守る選択をすることも大切です。無理なく、納得できる形での退職・転職を目指しましょう。















