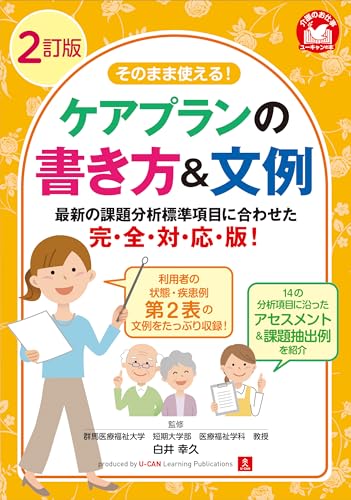【ケアマネが仕事で使える】訪問リハビリテーションのケアプランの文例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
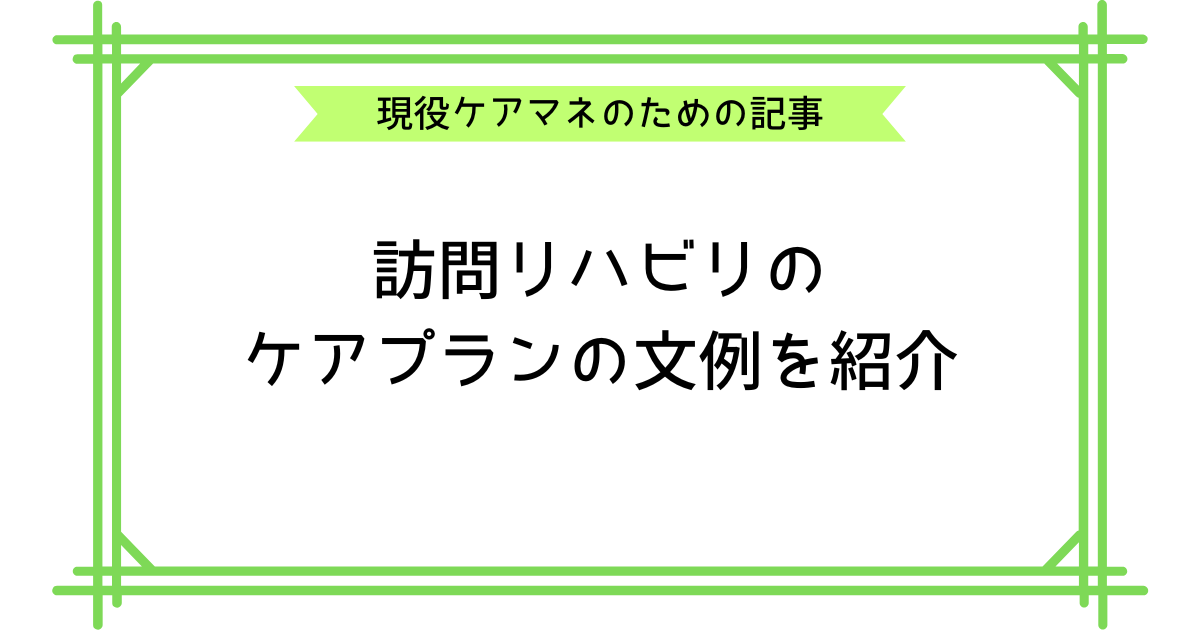
ケアマネジャーとして働く中で、訪問リハビリテーションのケアプラン作成に悩むことはありませんか?
通所リハとは違い、訪問リハは利用者の“生活の場”である自宅を中心に支援が行われるため、在宅生活との関連性を意識したプランニングが重要です。
加えて、医師の指示書を基に、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などとの連携も求められます。
本記事では、訪問リハビリのケアプラン作成に役立つ文例を、ケアプラン第1表・第2表に分けて目的別に多数ご紹介。
実務で即使える表現をまとめましたので、ぜひご活用ください。

ケアマネはこの本を持っておくと便利だよ!
目次
訪問リハビリテーションとは?ケアプラン作成時の視点
「生活リハビリ」に直結するサービス
訪問リハは、PT・OT・STが利用者宅を訪問し、住環境や生活動作に即した支援を行うサービスです。支援の場が“自宅”であることから、**「生活行為の再獲得」**を明確に意識した目標設定が求められます。
医療的視点×生活の視点が必要
- 医療的視点: 疾患・機能障害への対応、再発予防、疼痛管理
- 生活視点: トイレ動作、食事動作、家事動作の再獲得、QOL向上
単に「歩けるようになる」だけでなく、「●●ができるようになって何をしたいのか」を含めた目標設定が鍵となります。
第1表:アセスメント・課題分析の文例
本人の意向(例文)
- 「入浴は介助してもらっているけど、できれば自分で入りたい。」
- 「杖で歩けるようになって、自分の部屋からトイレまで行きたい。」
- 「料理ができるようになって、また家族にご飯を作ってあげたい。」
- 「声が出づらくて電話ができない。はっきり話せるようになりたい。」
家族の意向(例文)
- 「一人でトイレに行けるようになれば、介護負担がかなり軽減される。」
- 「入浴時の転倒が怖いので、浴室での動作訓練をお願いしたい。」
- 「本人が料理を再開したいと言っているので、キッチンでの訓練をしてもらいたい。」
- 「言葉が出づらくて意思疎通が難しいので、STに関わってもらいたい。」
ケアマネによる課題分析(例文)
- 脳梗塞後の左上下肢麻痺により、移動・更衣・入浴に一部介助を要する。本人は自立意欲が高く、自分でトイレ・入浴を行いたいという意向があるため、訪問リハによりADLの再獲得支援を行う必要がある。
- 家屋内での段差や狭さがあり、住環境調整も含めた支援が求められる。家族は介護意欲はあるが、腰痛など身体的負担があり、本人の自立が介護負担軽減につながると考えられる。
第1表:総合的な援助方針の文例
- 利用者の「できることを増やしたい」という意向を尊重し、自宅での生活動作訓練を通じて生活の自立度向上を目指す。
- 訪問リハ職と連携し、本人の身体状況と住宅環境に応じた現実的な目標を設定し、段階的な支援を行う。
- 家族との情報共有を密にし、本人・家族双方の負担軽減に向けた支援を行う。
第2表:ニーズ・長期目標・短期目標・サービス内容の文例
ニーズ例(目的別)
- 杖や歩行器を使って自宅内移動ができるようになりたい
- 浴槽への出入りを安全に行いたい
- 発語がはっきりせず会話が成立しにくい
- 食事中にむせることがあり、安全に食べられるようになりたい
長期目標の文例
- 自宅内の移動・トイレ動作を自立で安全に行えるようになる
- 自宅浴室で一人で入浴できるようになる
- 家事(料理・掃除・洗濯)の一部を再び行えるようになる
- 家族とスムーズに会話ができ、意思疎通が図れるようになる
- 食事中のむせが減り、常食での食事が可能となる
短期目標の文例
- 1ヶ月以内に杖歩行で10mの移動が安全に行えるようになる
- 入浴時の浴槽またぎ動作を練習し、週1回の自立入浴を目指す
- キッチンで10分間の立位保持が可能となり、簡単な調理を開始する
- STによる発声訓練を週1回実施し、家族との2語文での会話が可能になる
- 食事時のむせが週1回以内に減少することを目指す
サービス内容の文例
- 週2回の訪問リハビリを実施し、PTによる移動動作訓練(寝返り・起き上がり・歩行)を行う
- OTが浴室での動作訓練を行い、入浴自立に向けた段階的支援を行う
- STが構音訓練・会話訓練・嚥下体操を実施し、発語機能と安全な摂食を支援
- 住宅改修(手すり設置)に向けた環境評価・動線確認をリハ職と連携して行う
サービス担当者会議の記録例(要点)
- 主治医より「生活行為向上が在宅継続の鍵」との意見があり、訪問リハの継続に同意
- PTより、立ち上がり動作・屋内歩行についての現状と今後の訓練方針が説明された
- OTより、本人の料理再開意欲に応じたキッチン訓練の提案あり
- STより、発語困難・食事中のむせについてアセスメントがあり、対応内容が共有された
- 家族より「訓練内容が明確で安心した」「進捗に応じて無理なく進めてほしい」との意見あり
モニタリング記録の視点(例文)
- 訪問リハ3回実施。ベッドからの立ち上がりに対する不安が軽減し、介助なしでも安定して実施可能に
- STより、発声練習時に音量・発語の明瞭さが改善傾向との評価あり
- 家族より「以前より本人の動きがしっかりしてきた」との声があり、訓練への意欲も継続中
- 引き続き、自立支援を目的に訓練内容の再評価とプラン修正を行う予定
まとめ
訪問リハビリのケアプランは、通所系サービスと異なり、「利用者の住まいにおける課題」に直結した目標設定が求められます。
支援は医療的な視点だけでなく、「生活を取り戻す」ための具体的なゴール設定が重要です。
本記事で紹介した文例を参考に、本人の意向や生活課題をしっかり捉えた、実践的なケアプラン作成につなげてください。
チームでの連携と継続的なモニタリングにより、支援の質をさらに高めていきましょう。