ケアマネは何でも屋?そう言われる理由を解説します!
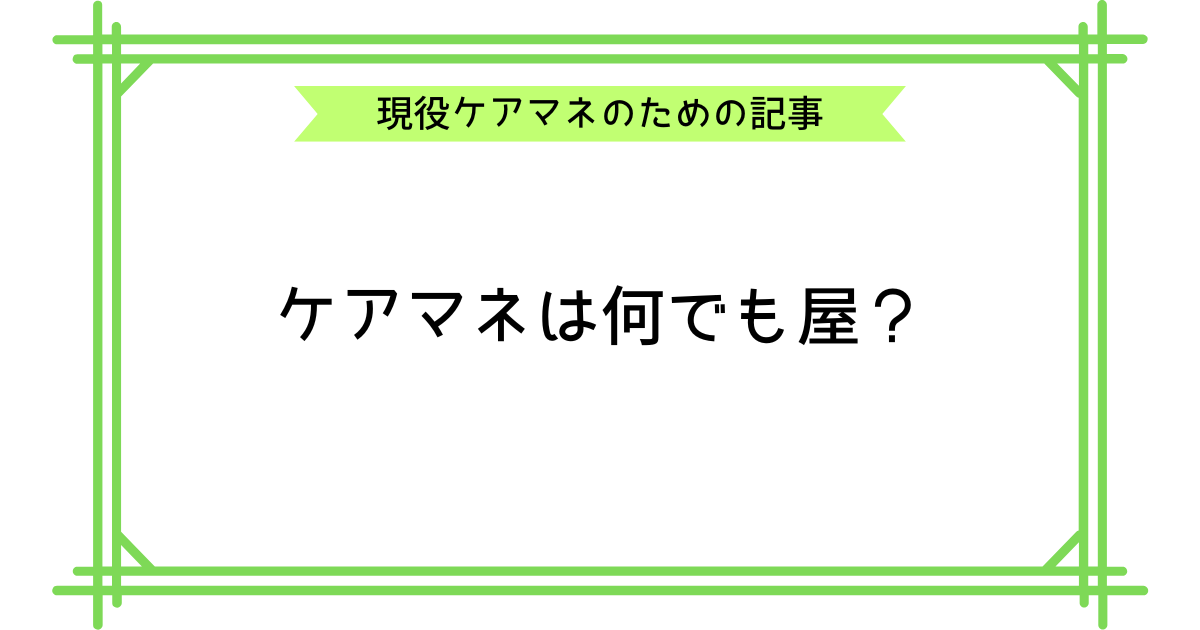
ケアマネジャー(介護支援専門員)は「何でも屋」と言われることがあります。
その言葉の背景には、介護に関する幅広い業務や、現場で求められる柔軟な対応力がありますが、一方で「専門職なのに…」という違和感を持つ方も少なくありません。
本記事では、なぜケアマネが「何でも屋」と表現されるのか、その理由や現場の実態、そして本来の役割とのギャップについて詳しく解説します。
介護に関わる方々に、ケアマネという職業の正しい理解を深めていただければ幸いです。
ケアマネはなぜ「何でも屋」と呼ばれるのか?
ケアマネジャーは、本来「介護サービスの調整役」であり、ケアプランの作成や関係機関との連絡・調整を担う専門職です。しかし、実際の現場では、その枠を超えてあらゆる相談や対応を求められることが多く、「何でも屋」と言われてしまうことがあります。たとえば、介護以外の生活相談や、ごみ出し、買い物、近隣トラブルの相談にまで対応することもあり、利用者や家族からは「困ったときはとりあえずケアマネに」と思われがちです。
このような幅広い役割がある一方で、ケアマネ自身が専門職としての本来の業務に集中できず、業務過多やストレスを感じる原因にもなっています。つまり、「何でも屋」と呼ばれるのは、その多様な業務と過度な期待の現れとも言えるのです。
ケアマネの本来の業務とは?
ケアプランの作成とモニタリングが中心
ケアマネの主な業務は、利用者の状態や希望をもとにしたケアプランの作成です。そして、作成したケアプランが適切に実施されているかを確認し、必要に応じて修正する「モニタリング」も重要な役割です。月1回以上の訪問を通じて、サービスの状況や利用者の変化を把握することが求められています。
関係機関との連絡調整
介護サービスは、訪問介護、デイサービス、福祉用具、訪問看護など多岐にわたるため、それぞれの事業者と連携を図ることもケアマネの大切な仕事です。連絡・調整を円滑に行い、利用者が必要なサービスを確実に受けられるようにする調整役としての能力が求められます。
要介護認定に関する手続き支援
利用者が介護保険サービスを利用するためには、要介護認定が必要です。ケアマネは、認定申請のサポートや更新手続きの代行、主治医意見書の依頼なども担当します。これらの行政手続きの支援を通じて、利用者がスムーズに介護サービスを受けられるようサポートしています。
実際にはどんな「何でも」を頼まれているのか?
生活全般の細かい相談
ケアマネのもとには、「電球が切れた」「水道が壊れた」「お風呂の掃除ができない」など、本来は生活支援サービスの範疇にある内容まで相談が寄せられます。高齢者世帯では、頼れる人がいないため、ケアマネが窓口となってしまうことも多いのが現実です。
医療・福祉を超えた相談も
たとえば「相続のことを聞きたい」「近隣とトラブルになっている」「息子と連絡が取れない」といった、医療・福祉とは直接関係のない相談が舞い込むこともあります。ケアマネ自身が対応できない場合でも、行政や関係機関に繋げるなどして対応を求められることが少なくありません。
時には介護とは無関係の雑用も
利用者や家族の依頼によっては、ちょっとしたお使いや荷物の受け取り代行など、「ケアマネの仕事ではない」と明確に線引きできる内容であっても、断りづらい場面があるのも事実です。善意や信頼関係から引き受けてしまい、結果的に業務量が増えることもあります。
ケアマネが「何でも屋」になってしまう背景とは?
人手不足と制度の限界
介護業界全体の人手不足が深刻化しており、本来別の職種が担うべき業務がケアマネに回ってくるケースも多く見られます。また、制度上のサービスでカバーできない「ちょっとした困りごと」が現場には多く、それを補完する存在としてケアマネに期待が集中するのです。
利用者・家族との信頼関係が厚いからこそ
ケアマネは、利用者や家族との関係性を築く中で、頼りにされやすい立場になります。そのため、「何でも相談できる人」として見られやすく、気軽に頼みごとをされてしまう傾向があります。この信頼は嬉しい一方で、境界線が曖昧になることも問題の一因です。
「断りにくい」環境
介護現場では、断ることで信頼関係が壊れるのではないかという不安から、本来の業務外の依頼にも応じてしまうケースが多くあります。事業所側もケアマネを守る体制が整っていない場合があり、個人の裁量に任される部分が大きいのが現状です。
「何でも屋」にならないための対策と意識
業務範囲の明確化と説明
ケアマネ自身が、自分の業務範囲を明確に把握し、利用者や家族にも丁寧に説明することが重要です。「それは訪問介護の担当になります」といった具体的な案内ができれば、信頼を損なわずに依頼を断ることも可能になります。
チームケアの徹底と連携強化
ケアマネがすべての課題に対応しようとせず、他の職種や地域資源と連携して対応する体制を整えることが重要です。地域包括支援センターや民生委員、訪問介護員などと役割を共有し、チームでの支援を進めることで負担の集中を避けられます。
事業所のサポート体制の強化
ケアマネを孤立させず、事業所全体で支える体制づくりも必要です。困ったときに相談できる上司や、判断を一緒にしてくれる体制があることで、業務外の依頼を無理に受けることを防げます。また、定期的なミーティングでケースを共有することも有効です。
まとめ
ケアマネが「何でも屋」と呼ばれる背景には、信頼の厚さや制度の限界、人手不足などさまざまな要因があります。
しかし、本来の役割はあくまでも「介護の調整役」であり、すべての問題を一手に引き受ける必要はありません。
業務の線引きと説明、チームでの連携、そして事業所の支援体制があれば、ケアマネとしての専門性を発揮しつつ、過剰な負担を避けることが可能です。
利用者や家族との関係性を大切にしながら、持続可能な働き方を実現するためにも、「何でも屋」からの脱却は重要なテーマとなっています。















