ケアマネジャーのモニタリング業務のコツやポイントについて解説
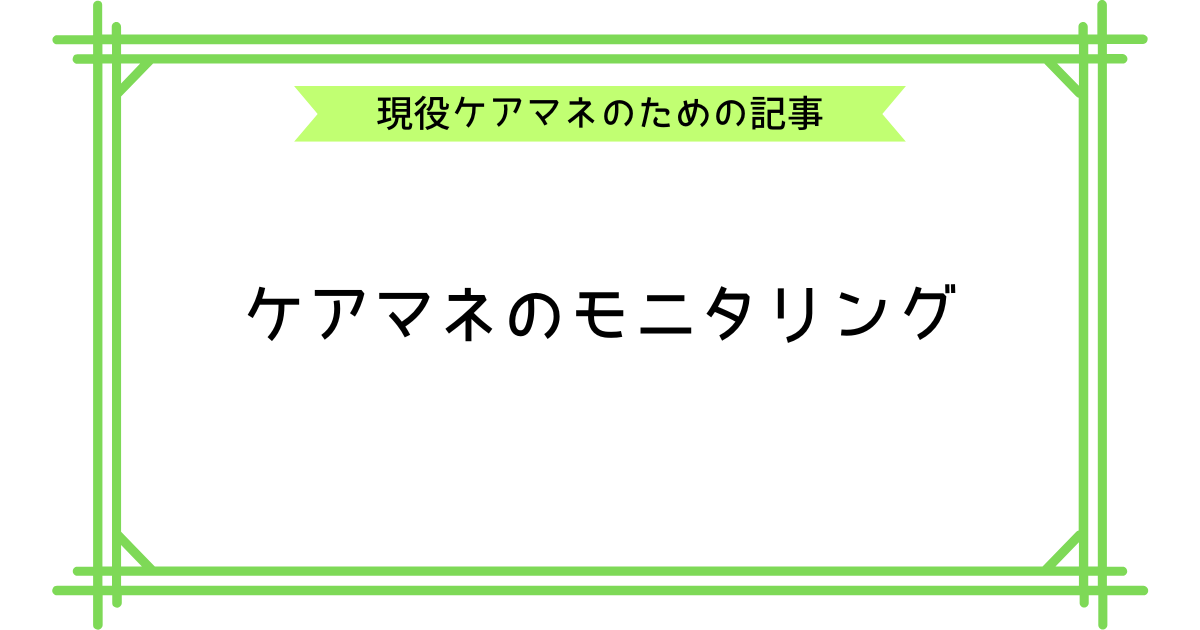
ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務の中でも、モニタリングは非常に重要な役割を担っています。
ケアプランが適切に実施されているか、利用者の状態に変化がないか、サービスが実際に生活に合っているかを確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行うことがモニタリングの目的です。
しかし、ただ月1回訪問するだけでは不十分な場合も。
本記事では、ケアマネとして質の高いモニタリングを行うためのコツや注意点、現場でのポイントを徹底解説します。
新任ケアマネの方や、モニタリングの質を上げたい中堅の方にも役立つ内容です。
モニタリングとは?業務の目的と基本的な流れを解説します
モニタリングとは、介護保険サービスを利用する高齢者が適切な支援を受けられているかどうかを、定期的に確認・評価するケアマネジャーの業務のひとつです。通常は月に1回以上の訪問が基本とされており、利用者の生活状況・身体状況・精神状態・サービス利用状況を総合的に観察します。
このモニタリングを通じて、必要に応じてケアプランの見直しやサービスの再調整を行います。例えば、転倒によってADL(日常生活動作)が低下した場合や、認知機能が変化した際には、サービスの内容や頻度を変更する必要があります。つまり、モニタリングはケアプランの“点検・調整”の場であり、ケアマネの判断力と観察力が求められる場面でもあります。
質の高いモニタリングを行うための基本的なコツ
1. モニタリング前の事前準備を怠らない
モニタリングは訪問してから即座に対応するのではなく、事前に利用者の最近の情報を確認しておくことが重要です。前回のモニタリング内容、サービス事業者からの連絡内容、通院記録や生活の変化などをチェックし、今回の確認ポイントをあらかじめ洗い出しておくことで、短時間の訪問でも的確な観察と聞き取りが可能になります。
2. 主観と客観を意識した観察をする
利用者の言葉だけに頼るのではなく、表情や声のトーン、生活環境の変化なども観察し、主観と客観の両方の視点で状況を把握しましょう。「大丈夫」と言っていても、体重が減っていたり、冷蔵庫の中が空だったりするケースもあります。五感を使った観察が質の高いモニタリングにつながります。
3. 家族やサービス事業者からの情報収集も忘れずに
利用者本人だけでなく、家族や訪問介護員、通所サービスの職員などからの情報も大切です。本人が言わない・気づかないことも周囲が気づいている場合があります。複数の視点から状況を把握することで、より正確な判断が可能になります。
モニタリング記録の書き方と注意すべきポイント
主観的情報と客観的情報を分けて記録する
記録には、利用者本人が述べた内容(主観)と、ケアマネ自身が観察・確認した事実(客観)を明確に分けて書くことが重要です。例えば、「本人は『問題なく過ごせている』と話していたが、足元にふらつきが見られた」など、矛盾点も含めて記載しておくと、後の判断材料として有効です。
事実を具体的に記録する
「元気そうだった」「特に問題なし」といった抽象的な表現は避け、具体的な内容を記載することを心がけましょう。たとえば「訪問時、利用者は居間にて杖を使用しながら移動していた。転倒歴はこの1か月でなし」「食事は1日3食摂取。食器は洗われており、清潔な印象」など、観察可能な事実を文章に残すことが大切です。
変化の有無を明確に記録する
モニタリングでは、前回との比較が重要です。「前回に比べて歩行速度が遅くなっている」「体重が1.5kg減少していた」「服薬管理が自立から見守りに変更された」など、変化の有無を記載することで、ケアプランの見直しの根拠として活用できます。
ケアマネとしての視点で気をつけるべき判断ポイント
「小さな変化」に早く気づく感度が大切
モニタリングは“異常の有無”を探すだけでなく、“微細な変化”に気づくことがカギです。体調の小さな変化、生活リズムの崩れ、表情の曇りなど、小さな兆候が大きな問題の前触れであることも少なくありません。毎月の訪問を“当たり前”にしない工夫が必要です。
サービスのミスマッチに注意
介護サービスが本人の状態や希望に合っているかどうかを客観的に確認することも大切です。「デイサービスを嫌がるようになった」「訪問時間に寝ていて利用できていない」などのサインがあれば、ケアプランの見直しや事業所との再調整が必要となります。
家族の介護負担にも目を向ける
利用者本人だけでなく、家族の介護疲れやストレスが顕在化していないかもチェックしましょう。家族の様子に変化がある場合は、介護サービスの追加やショートステイの提案など、サポート体制を見直すきっかけにもなります。
モニタリングの質を高めるための工夫と取り組み
モニタリング項目のチェックリストを活用する
訪問時に確認するべき項目を事前にリスト化しておくと、漏れなく観察・聞き取りが行えます。身体状況、精神状態、服薬状況、サービス満足度、家族の介護負担などを毎回同じ基準で確認することで、変化に気づきやすくなります。
ICTツールやアプリの活用
最近では、モニタリングの記録や情報共有を効率化するためのICTツールやアプリも増えてきました。サービス事業所との情報共有がスムーズになれば、モニタリングの精度も向上します。記録をリアルタイムで確認できる仕組みを活用するのも一つの方法です。
チーム内でのケース検討の実施
モニタリングで得た情報をチームで共有し、多職種でのケース検討を行うことで、より客観的で適切な判断が可能になります。他職種の視点を取り入れることで、ケアマネ一人では気づけなかった課題や対応策も見つかります。
まとめ
ケアマネジャーのモニタリング業務は、介護サービスの継続と質の維持に直結する非常に重要な業務です。
表面的な観察だけでなく、利用者の小さな変化や家族の状況までを丁寧に把握し、適切な記録と判断を行うことが求められます。
事前準備、主観と客観のバランス、記録の工夫などを意識すれば、モニタリングの質は確実に高まります。
また、チーム連携やICT活用など、現場全体で支える仕組みづくりも今後ますます重要となるでしょう。
日々のモニタリングを「ただの訪問」にしないための視点を大切にしましょう。















