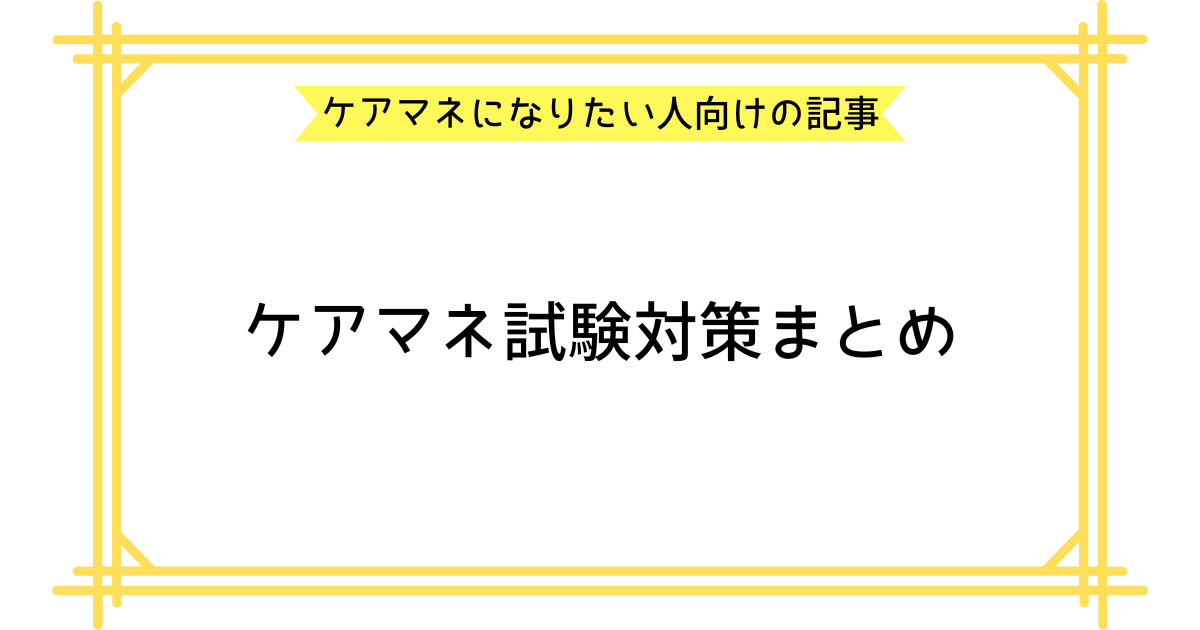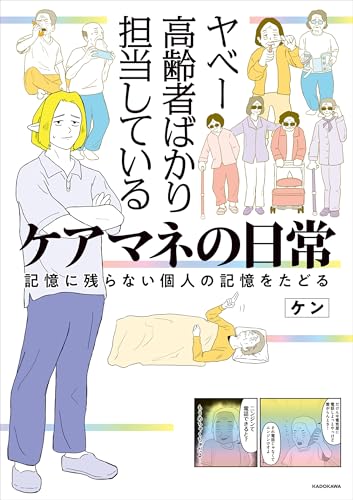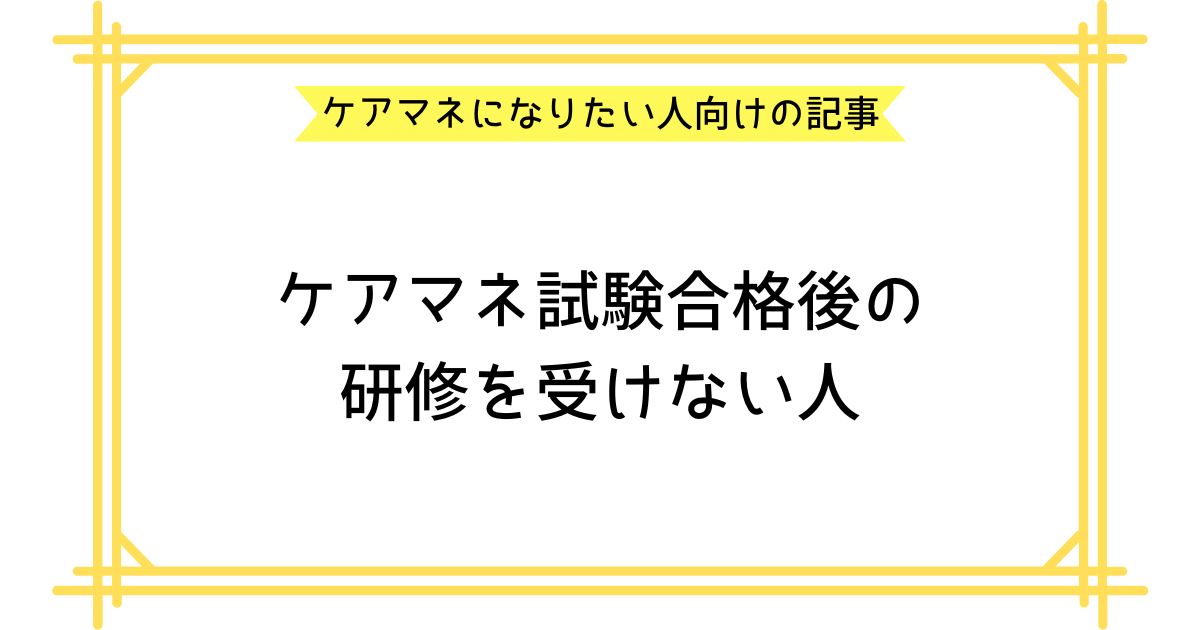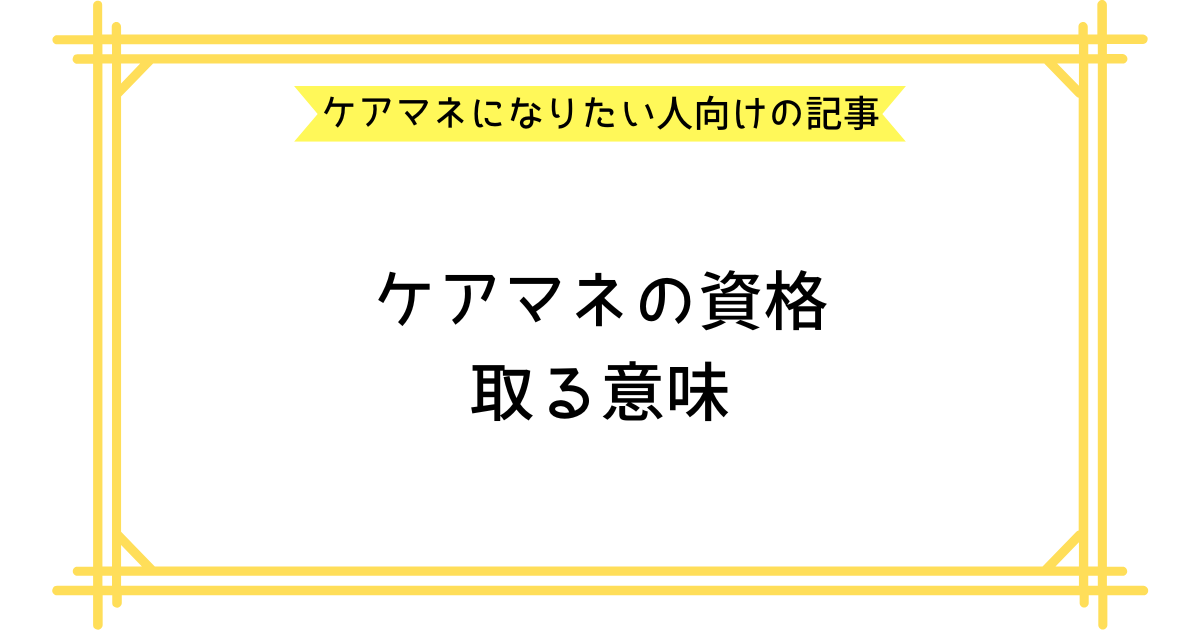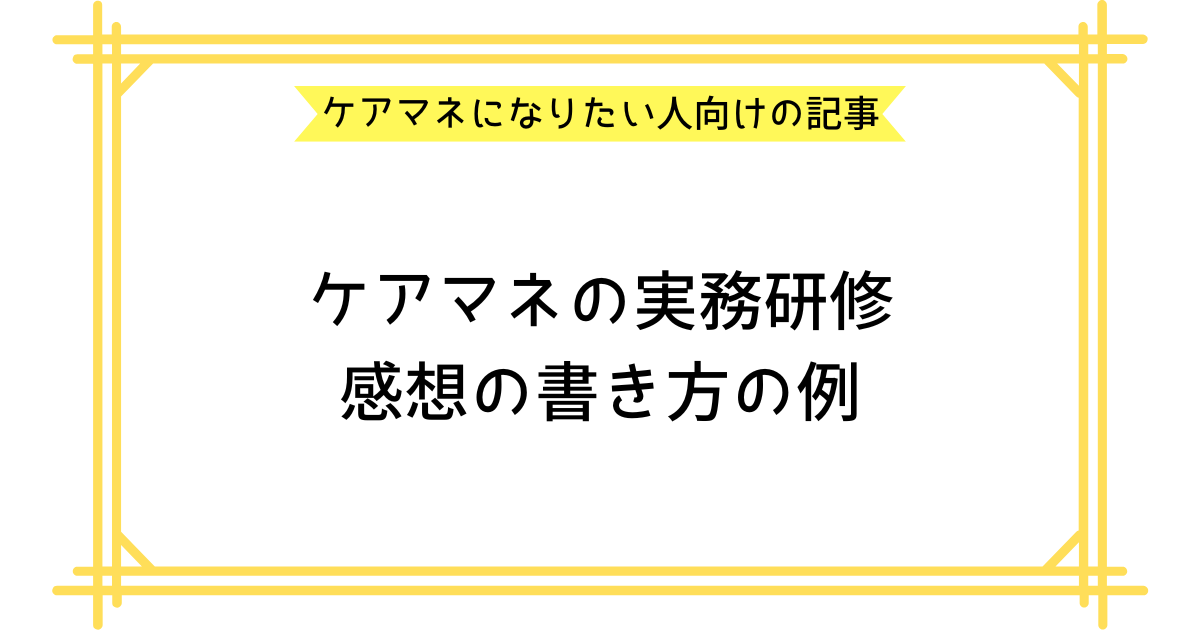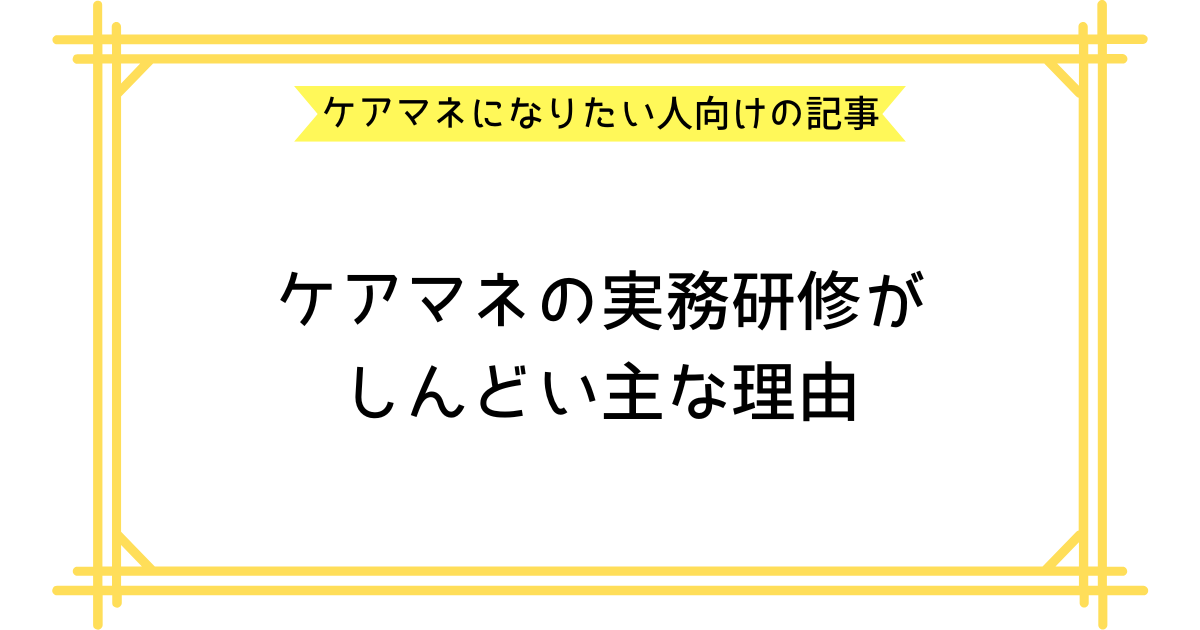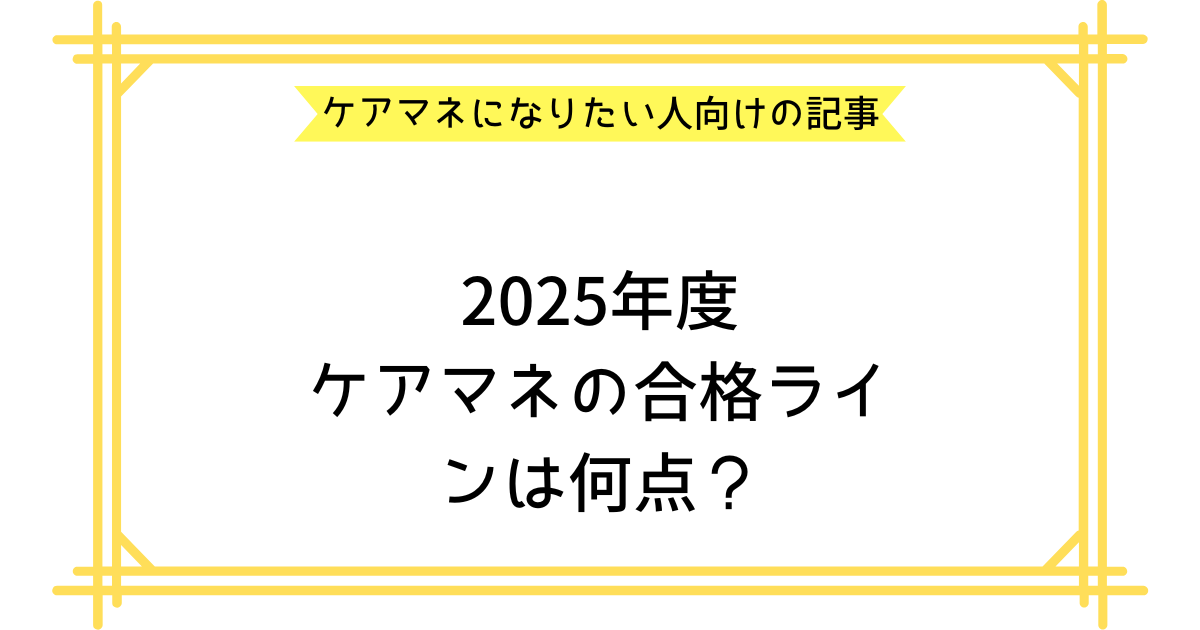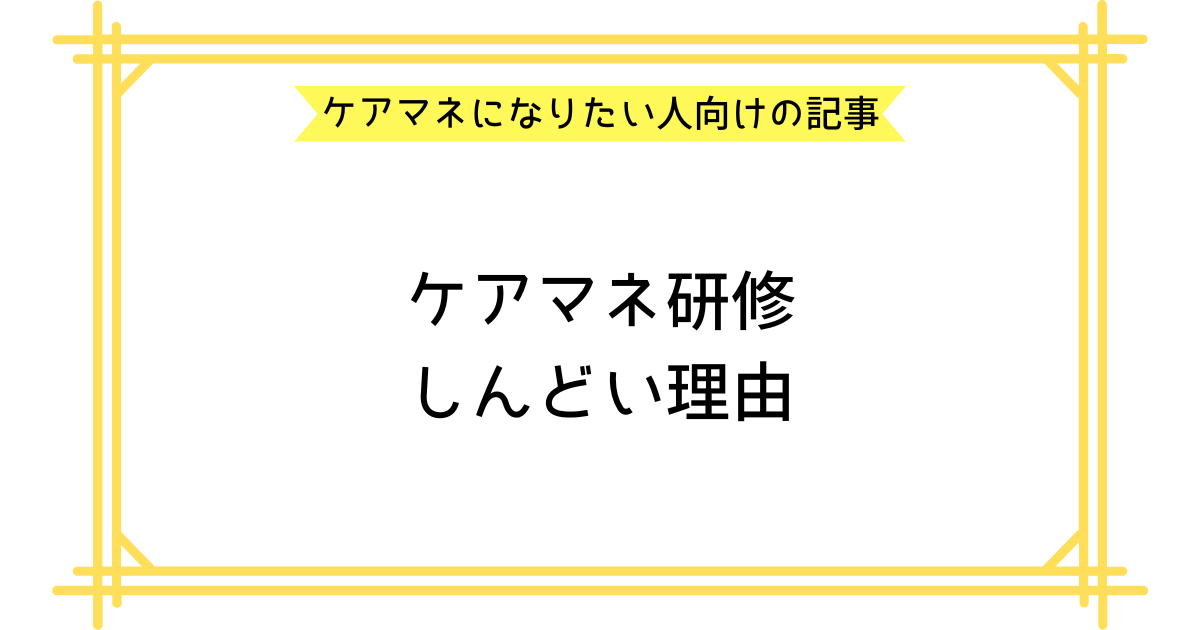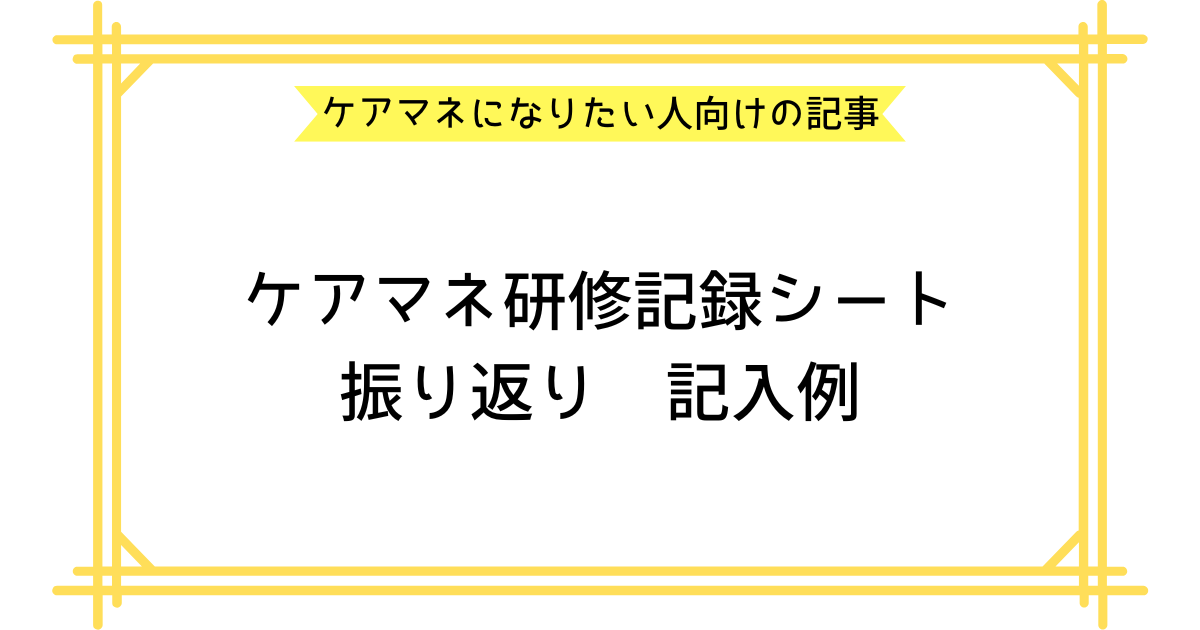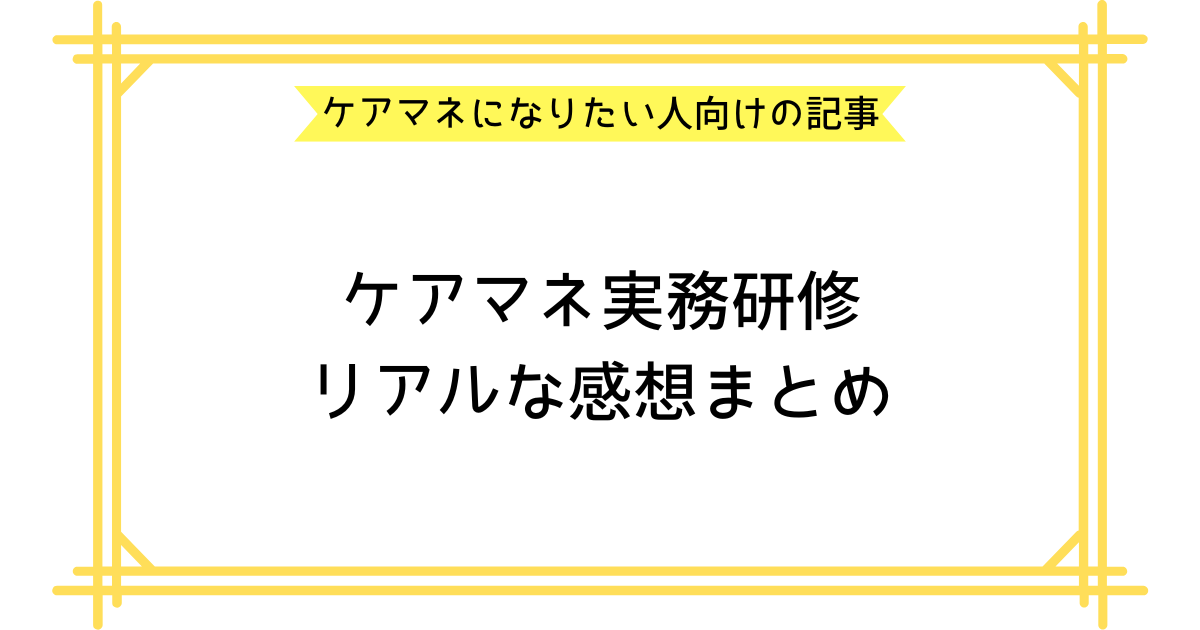介護支援専門員の試験形式とは?勉強方法のポイントも解説
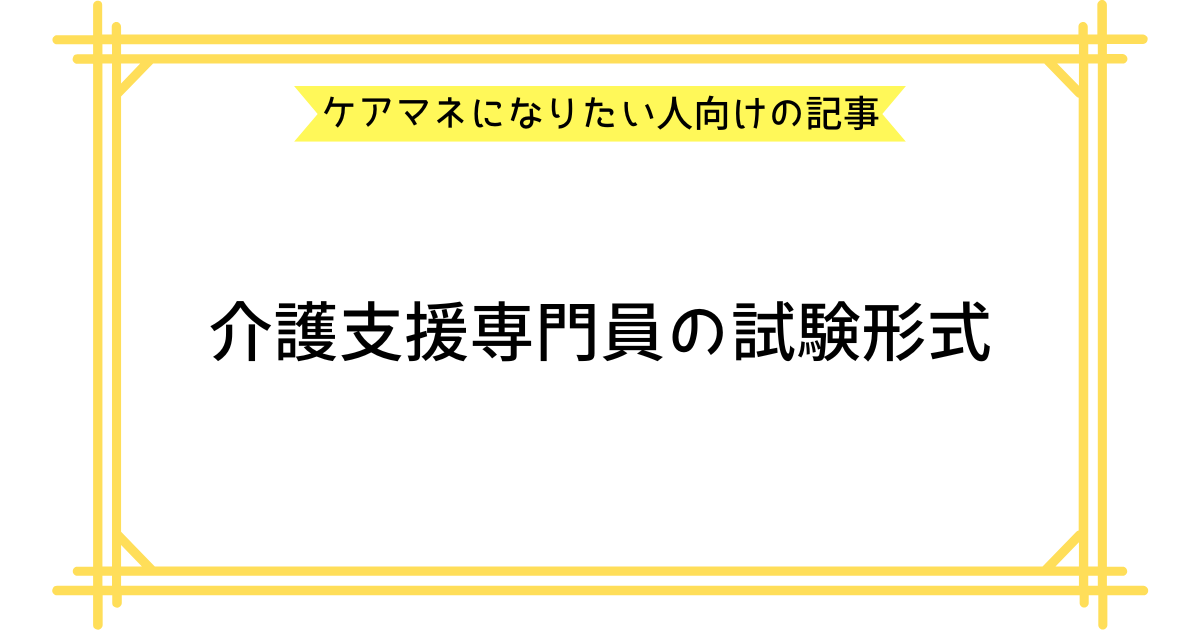
介護支援専門員(ケアマネジャー)を目指す方にとって、試験形式の理解と効果的な勉強方法は合格への第一歩です。
年に一度実施されるこの試験は、医療・福祉・介護に関する幅広い知識が問われる難関資格として知られています。本
記事では、試験の具体的な形式や出題範囲、合格するために押さえておきたい勉強方法についてわかりやすく解説します。
効率的に学習を進めたい方や、試験対策に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験形式とは?
介護支援専門員の試験は、毎年10月頃に実施され、全国一斉に行われます。
試験形式は「全問マークシート方式」で、五肢択一式の選択問題となっており、記述問題は出題されません。
出題数は全60問で、「介護支援分野」が25問、「保健医療サービス分野および福祉サービス分野」が35問となっています。
試験時間は120分で、途中退席は原則として不可です。
合格基準は年度によって若干変動しますが、例年、各分野で一定以上の得点が求められ、全体で約70%程度の正答率が目安とされています。
出題範囲が広いため、単なる暗記ではなく、制度の理解と現場感覚の両方が問われます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験勉強方法とは?
ここからは、ケアマネ試験に合格するために効果的な勉強方法を紹介します。
ご自身のライフスタイルや学習スタイルに合った方法を選ぶことが合格への近道です。
過去問で勉強する
最も基本かつ効果的な勉強方法が、過去問を繰り返し解くことです。過去問を通じて、出題傾向や問題のレベル感を把握できます。特に本試験と同じ形式(五肢択一)に慣れておくことは非常に重要です。直近3〜5年分の過去問を最低2周以上解き、解答・解説を読み込むことで知識の定着が期待できます。また、間違えた問題はなぜ間違えたのかを分析し、次に同じ間違いをしないように工夫すると効果的です。問題集形式の書籍やアプリも活用しやすく、スキマ時間に取り組むのにも適しています。

動画で勉強する
最近ではYouTubeなどの動画プラットフォームを使った学習も人気です。特に、難解な制度や法律に関する内容は、図解やナレーションを通して視覚的・聴覚的に学べるため理解が深まりやすいです。現役ケアマネや講師が解説している信頼性の高い動画も多く、無料で視聴できるのも魅力です。また、家事や移動中に音声だけで学べるのも大きなメリットで、働きながら勉強している方には非常に有効な手段となります。ただし、動画だけに頼るのではなく、問題演習と併用してバランス良く進めることが大切です。
ケアマネのワークブック、テキストで勉強する
体系的に基礎から学びたい方には、ワークブックやテキストを使った学習が最適です。「ユーキャンのケアマネジャー講座」や「みんなが欲しかった!ケアマネジャーの教科書」など、市販のテキストはイラストや図解が豊富で初心者にも分かりやすく構成されています。また、章ごとに演習問題が付いているものも多く、理解度を確認しながら学習を進められます。さらに、厚生労働省の制度改正など最新の情報を反映したテキストを選ぶことが合格への鍵となります。毎日少しずつ読み進める習慣をつけることが合格率アップにつながります。
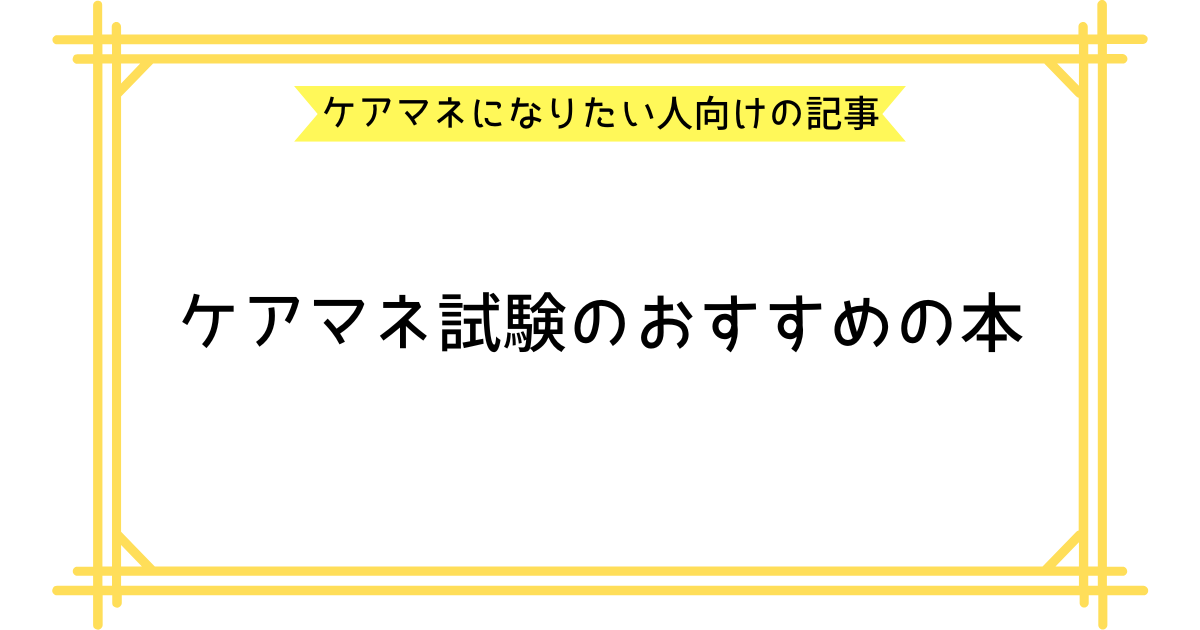
まとめ
介護支援専門員(ケアマネジャー)の試験は、60問の五肢択一式マークシートで構成されており、介護・医療・福祉にわたる幅広い知識が問われます。
合格するためには、過去問で出題傾向をつかみ、動画やテキストを活用して理解を深めることがポイントです。
それぞれの勉強方法にメリットがありますので、自分に合ったやり方を見つけて、計画的に取り組むことが成功への近道です。
難関資格ではありますが、着実に準備を進めれば必ず合格を目指せます。
焦らず、コツコツ積み重ねていきましょう。