【例文あり】居宅サービス計画(ケアプラン)の総合的な援助の方針 第1表の記載例100パターン紹介
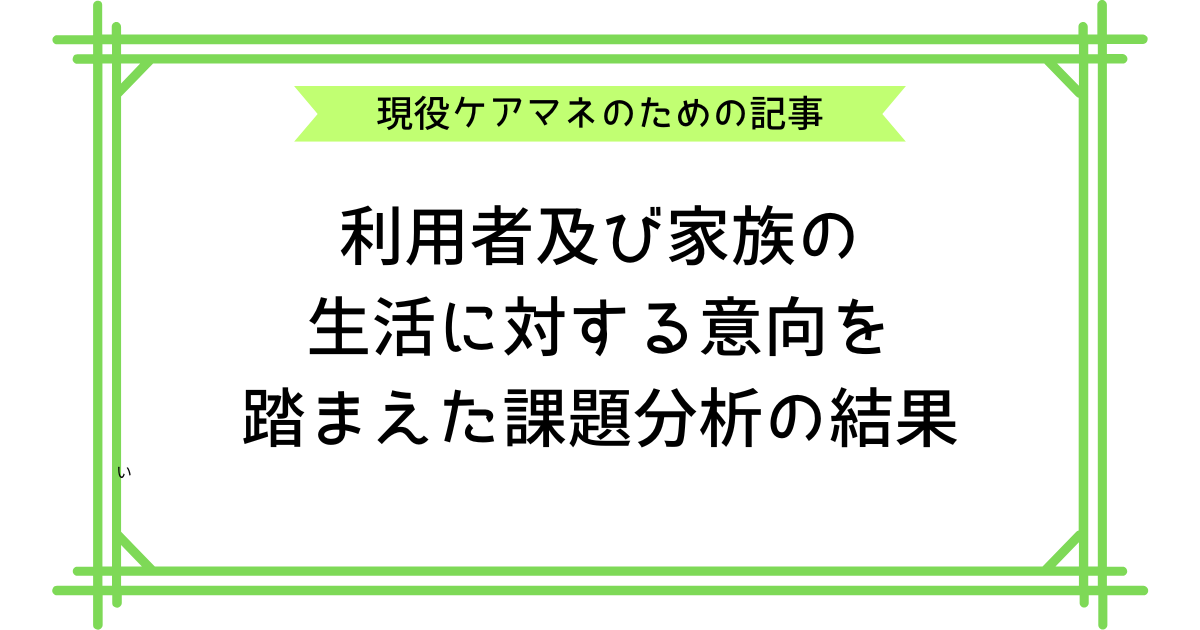
居宅サービス計画(ケアプラン)の第1表に記載する「総合的な援助の方針」は、ケアマネジャーにとって頭を悩ませやすいポイントです。
「本人の意向をどう盛り込むか」「サービス導入の方向性をどう表現するか」など、記載内容に迷うことは少なくありません。
そこで本記事では、【そのまま使える例文100パターン】をまとめました。
生活全般、身体機能、認知症、医療的ケア、家族支援、在宅継続の6つの視点に分けて掲載しています。
パクリOK形式で紹介しますので、ぜひ日々のケアプラン作成にご活用ください。
ケアプランの総合的な援助の方針とは?
総合的な援助の方針は、本人や家族の生活意向を踏まえ、アセスメントの結果に基づいて「どのようにサービスを組み合わせ支援するか」を記載する部分です。
- 本人の希望を反映する
- 家族の意向も取り入れる
- 現状の課題を踏まえた方向性を示す
- 医療や介護サービスとの連携を明確にする
これらを簡潔にまとめることで、ケアプラン全体の方向性がブレずに、利用者・家族・サービス事業者が共通理解を持ちやすくなります。
【パクリOK】総合的な援助の方針 記載例100パターン
生活全般の自立・継続に関する例文
利用者が住み慣れた自宅で生活を継続できるよう、訪問介護や通所介護を活用して日常生活動作を支援する。
できることは本人に任せ、不足部分はサービスで補い、自立心を尊重しながら生活を維持する。
独居であるため、定期的な安否確認と見守りを導入し、安心して生活できるよう支援する。
掃除や洗濯などの家事が困難であるため、訪問介護で生活環境を整える。
食事準備が難しく栄養バランスが偏りやすいため、配食サービスを活用する。
本人の意欲を尊重し、デイサービスで社会交流を図りながら生活リズムを維持する。
閉じこもり傾向があるため、通所介護や地域活動への参加を支援する。
生活全般に見守りを行い、本人の自立を促進する。
金銭管理に不安があるため、家族や地域の協力を得ながら支援する。
本人の「できるだけ自分で生活したい」という思いを尊重し、サービスを最小限に組み合わせる。
買い物支援を導入し、生活必需品の確保を安定させる。
独居高齢者としての不安を軽減するため、定期訪問での見守りを行う。
本人の趣味活動が継続できるよう、送迎支援や通所利用を組み合わせる。
在宅生活の継続を最優先に、必要な福祉サービスを組み合わせていく。
生活リズムが乱れやすいため、通所介護の利用で規則的な活動を支援する。
家事能力の低下を補うため、訪問介護による家事援助を導入する。
地域との関わりを持ち続けられるよう、自治会活動やサロン参加を支援する。
孤独感を軽減するため、ヘルパーや通所での交流機会を提供する。
生活機能の維持を目的に、必要な福祉用具を導入して安全を確保する。
本人の意思を尊重しながら、家族と協力して在宅生活を支える。
身体機能・ADL維持に関する例文
歩行が不安定で転倒リスクがあるため、福祉用具と訪問リハビリを導入して安全を確保する。
入浴が困難であるため、訪問介護やデイサービスでの入浴支援を行う。
排泄動作に不安があるため、ポータブルトイレや排泄介助を導入する。
体力低下が見られるため、通所リハビリで継続的な運動機会を提供する。
痛みが強く活動が制限されているため、医師と連携し適切なケアを行う。
下肢筋力が低下しているため、歩行訓練と転倒予防の環境整備を行う。
立ち上がりが困難であるため、ベッドや椅子の高さ調整を検討する。
関節痛が強いため、生活動作に介助を組み合わせて自立を支援する。
食事動作は自立しているが嚥下に不安があるため、見守りと食形態調整を行う。
体位変換が困難であるため、褥瘡予防を目的に介助とマットレス導入を行う。
移動範囲を広げるために車椅子を導入し、外出機会を増やす。
立位保持が難しいため、手すり設置や福祉用具を活用する。
屋外移動に不安があるため、通所介護での送迎を利用する。
活動範囲の縮小を防ぐため、通所リハビリで体力維持を図る。
食事摂取に時間がかかるため、介助と栄養補助食品を組み合わせる。
痛みによる活動制限を緩和するため、服薬管理とリハビリを組み合わせる。
トイレ動作を維持するため、福祉用具と介助を導入する。
姿勢保持が難しいため、体幹安定のための支援を行う。
呼吸苦が出やすいため、無理のない活動範囲を設定する。
本人の「できる範囲で自分で行いたい」という意向を尊重し、介助を調整する。
認知症・精神面に関する例文
認知症の進行により不安が強いため、デイサービスで社会交流を増やし安心感を持てるよう支援する。
服薬管理が困難なため、訪問介護と家族で確認を行い、誤薬を防止する。
夜間の不眠があるため、見守りと環境調整で生活リズムを整える。
被害妄想が出ているため、信頼関係の構築を重視し、安心感を得られるよう支援する。
金銭管理が困難なため、家族と協力して安全な生活環境を整える。
昼夜逆転が見られるため、通所介護を活用して規則的な生活を支援する。
認知症による徘徊があるため、家族と地域での見守り体制を整える。
不安感が強いため、訪問時の声かけや相談支援を積極的に行う。
介護サービスを拒否しがちなため、本人の気持ちを尊重した関わり方を工夫する。
生活リズムが乱れているため、通所サービスで活動機会を増やす。
認知症による混乱があるため、訪問看護と連携して落ち着いた環境を整える。
抑うつ傾向があるため、趣味活動や外出機会を増やし気分転換を図る。
幻覚が見られるため、医師と連携しながら適切に対応する。
認知症により調理や火の管理が困難なため、火を使わない生活環境を整える。
記憶障害があるため、家族と一緒に予定管理を行い混乱を防ぐ。
同じ質問を繰り返すため、安心できる対応を心がける。
不安が強いため、ヘルパーや通所で安心感を得られる環境を作る。
家族の介護負担を軽減するため、短期入所を組み合わせる。
認知症進行に伴い生活機能が低下しているため、福祉サービスを増やす。
本人の不安を和らげるため、日常的に声かけや傾聴を重視する。
医療的ケア・健康管理に関する例文
糖尿病の管理が必要であるため、食事療法や服薬管理を徹底し健康維持を図る。
在宅酸素療法を行っているため、訪問看護と連携して適切な管理を行う。
褥瘡リスクが高いため、体位変換や清潔保持を徹底し悪化を防止する。
がん治療の副作用があるため、体調変化に応じて医師と訪問看護が連携する。
服薬数が多いため、薬剤師の関与を強化し誤薬を防止する。
高血圧が不安定なため、定期的な測定と服薬確認を行う。
心疾患があるため、無理のない生活と健康チェックを継続する。
呼吸器疾患により体力低下が見られるため、活動範囲を調整する。
インスリン管理が必要であるため、訪問看護の支援を導入する。
慢性疼痛があるため、服薬とリハビリを組み合わせ生活を支える。
嚥下障害があり誤嚥リスクがあるため、食形態の調整と見守りを行う。
終末期を迎えているため、本人の希望を尊重し緩和ケアを優先する。
医療依存度が高いため、24時間対応できる体制を整える。
退院後の体調変化に注意が必要であり、訪問看護を導入する。
服薬副作用が懸念されるため、医師と薬剤師が連携してモニタリングする。
感染症リスクが高いため、清潔保持と衛生管理を徹底する。
体力低下により生活全般が制限されているため、医療と介護の両面で支える。
血糖コントロールが難しいため、生活習慣と服薬の両面で支援する。
終末期医療に備え、在宅での緩和ケア体制を整える。
本人と家族の希望に沿って、在宅医療と介護を一体的に提供する。
家族支援に関する例文
家族の介護負担を軽減するため、訪問系サービスとショートステイを組み合わせる。
介護者が高齢であるため、介護力を補う支援体制を整える。
介護方法の理解を深めてもらうため、専門職からの助言を行う。
介護により家族の心身疲労が強いため、レスパイト支援を提供する。
家族は在宅介護を望んでいるため、必要なサービスを導入し継続可能な体制を作る。
家族の就労と介護の両立を支えるため、デイサービスや訪問介護を活用する。
介護未経験の家族が不安を抱えているため、相談支援を充実させる。
介護に対する不安が強いため、情報提供と支援を行う。
介護ストレスが大きいため、相談窓口や地域資源を紹介する。
家族が安心して介護できるよう、支援体制を整える。
介護負担が偏らないよう、家族間で分担を促す。
介護に伴う経済的負担を軽減するため、制度利用を提案する。
介護による生活リズムの乱れを調整するため、サービス利用を組み合わせる。
家族の休養時間を確保するため、ショートステイを活用する。
介護方法の改善を図るため、専門職による助言を行う。
家族の体調不良があるため、介護サービスで補う。
介護力が不足しているため、訪問介護や福祉用具で支える。
介護者の負担軽減のため、通所介護を導入する。
家族の希望を尊重しつつ、現実的な支援体制を整える。
介護に疲弊した家族が安心できるよう、継続的に支援を行う。
在宅継続・施設入所検討に関する例文
本人は「自宅で生活を続けたい」と強く希望しており、在宅サービスを最大限活用する。
家族は在宅介護を望んでいるが、将来的には施設入所も視野に入れている。
独居で緊急時対応に不安があるため、緊急通報システムを導入する。
在宅療養を継続するため、医療と介護の連携を強化する。
施設入所を検討しつつも、本人の意向を尊重し在宅生活を優先する。
在宅生活継続には多職種連携が不可欠であり、医師・看護師と連携して支える。
終末期を在宅で迎えたいという本人の希望に沿い、医療と介護の体制を整える。
家族の介護力が限界に近づいているため、施設入所の検討も進める。
本人は「できるだけ自宅で」と希望しており、サービス導入を強化する。
将来的な選択肢として施設入所も視野に入れ、柔軟に対応できる体制を整える。
在宅生活を継続できるよう、住宅改修や福祉用具の導入を進める。
家族が安心できるよう、介護支援と相談体制を充実させる。
本人の希望を尊重しつつ、施設との連携も視野に入れて支援する。
在宅生活を支えるため、地域包括支援センターとの連携を強める。
本人の生活意欲を尊重し、可能な限り在宅での生活を維持する。
施設入所の希望がないため、在宅支援を充実させる。
今後の病状変化に備え、在宅と施設の両方を選択肢として準備する。
本人の生活環境を整えることで、安心して在宅生活を続けられるようにする。
在宅生活を支える家族の負担を軽減しつつ、本人の希望を実現する。
本人・家族・多職種が協力し、最適な生活環境を提供する。
まとめ
「総合的な援助の方針(第1表)」は、ケアプラン全体の方向性を決める重要な記載欄です。
本人や家族の意向を踏まえつつ、課題を整理し、必要なサービスをどのように組み合わせるかを明示することで、より効果的で根拠のあるケアプランを作成できます。
今回紹介した100例を活用すれば、表現の幅が広がり、日々のケアプラン作成に役立つはずです。















