【コピペOK】意欲低下のケアプラン文例を180紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
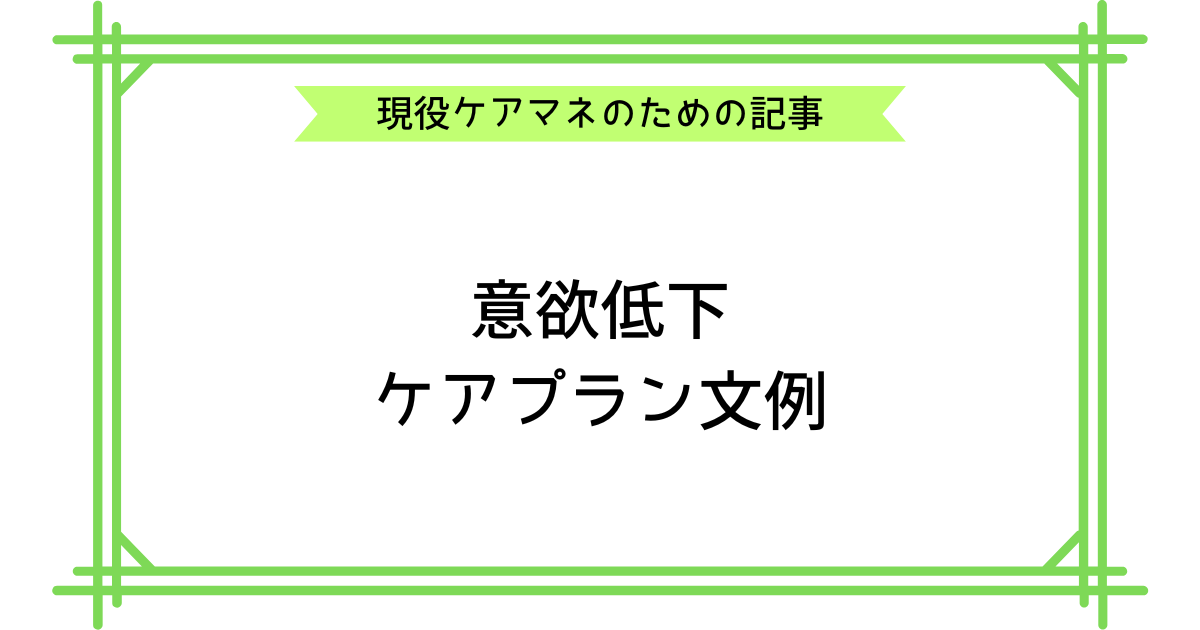
高齢者のケアプランを作成する際、よく課題として挙げられるのが「意欲低下」です。
外出や活動を嫌がる、食欲がない、趣味に興味を示さなくなった、といった状態は生活の質(QOL)を下げるだけでなく、身体機能の低下にもつながります。
そのため、ケアマネジャーや介護職員は、利用者一人ひとりの状態に応じて「意欲を高めるための目標設定」を工夫しなければなりません。
とはいえ「どんな表現にすれば良いか分からない」「ケアプランの文例が欲しい」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、そのままコピペして使える意欲低下に関するケアプラン文例を180パターン 紹介します。
実務に直結する内容ですので、ぜひ参考にしてください。
目次
意欲低下に関するケアプラン作成のポイント
意欲低下をテーマにケアプランを作る際には、以下の視点を持つことが大切です。
- 本人の好きなことや関心を引き出す
→ 料理、園芸、趣味活動、買い物など - 小さな達成感を積み重ねる
→ 短時間の散歩や簡単な家事から始める - 社会的なつながりを意識する
→ デイサービスや家族との交流を取り入れる - 心身の両面から支援する
→ 生活リズム、栄養、運動、リハビリを組み合わせる - ネガティブ表現は避け、前向きな言葉を使う
これらの視点を踏まえて、文例を紹介していきます。
【コピペOK】意欲低下のケアプラン文例集
長期目標例
- 生きがいを持ち、自分らしい生活を継続できるよう支援する。
- 日常生活の中で楽しみを見つけ、活動意欲を取り戻せるようにする。
- 外出や交流の機会を増やし、社会参加の意欲を維持する。
- 趣味活動を再開し、生活に張り合いを持てるよう支援する。
- 家族や友人との関わりを通じて、笑顔の時間を増やす。
短期目標例
- 週に1回は近所を散歩できるようにする。
- 1日1回は外の空気に触れる習慣をつける。
- デイサービス参加を月4回以上継続できるようにする。
- 週に2回は趣味活動(手芸・園芸など)に取り組む。
- 毎日の食事で「美味しい」と感想を口にできるようになる。
サービス内容例
- デイサービスで趣味活動のプログラムに参加を促す。
- 訪問介護で一緒に簡単な調理を行い、食への意欲を高める。
- 訪問リハビリで達成感のある運動を取り入れる。
- 家族と連携し、週末に一緒に外出する機会をつくる。
- 地域の交流サロンを紹介し、参加を支援する。
状況別文例
- 「最近何もやる気が出ない」と訴える方に対して、好きな音楽を聞きながら散歩を行い、気分転換を図る。
- 食欲低下が見られる方に対して、本人の好物を取り入れ、食事への意欲を高める。
- 外出を拒む方に対して、まずは玄関先で日光を浴びる習慣をつける。
- 趣味に関心がなくなった方に対して、過去の活動を振り返り、一緒に話題にすることで意欲を引き出す。
- 人との関わりを避けがちな方に対して、少人数から始め、徐々に交流の場を広げる。
実践的な文例
- 「今日はできた」という小さな成功を一緒に共有し、自己肯定感を高める。
- 毎日の生活に声かけを取り入れ、活動への動機づけを行う。
- 本人のペースに合わせ、焦らずに取り組める目標を設定する。
- 「疲れるからやりたくない」という訴えに対して、短時間でも達成感を得られるプログラムを選ぶ。
- 季節のイベントに合わせた活動(花見・正月準備など)を計画し、楽しみを持てるよう支援する。
- 日々の生活リズムを整えることで、自然に活動意欲が出るよう環境を整える。
- 運動や体操を「健康のため」ではなく「楽しむため」と位置づける。
- 介護職員が一緒に行動することで安心感を与え、やる気を引き出す。
- デイサービス送迎時に笑顔で声をかけ、不安を和らげる。
- 「できない」ではなく「少しずつできる」を意識した支援を行う。
長期目標例
- 季節ごとの行事に参加し、生活に変化と楽しみを感じられるようにする。
- 自宅での生活に張りを持ち、日常動作を自ら進んで行えるように支援する。
- 食事や入浴などの日課に前向きに取り組み、生活のリズムを整える。
- 人と関わることを楽しめるようになり、孤立を防ぐ。
- 自分の役割を持ち、生活に充実感を感じられるようにする。
短期目標例
- 1日1回、好きなテレビ番組や音楽を楽しむ習慣を持つ。
- 1週間に1回は家族や友人と会話する機会を設ける。
- 毎朝着替えをする習慣をつけ、生活のけじめを保つ。
- 週に2回は軽い運動や体操に取り組む。
- 1か月以内に「やってみたい」と自ら発言できるようにする。
サービス内容例
- デイサービスでの集団体操に参加し、達成感を味わえるように支援する。
- 訪問介護で掃除や片付けを一緒に行い、生活に主体性を取り戻す。
- 訪問リハビリで「できることが増えた」と実感できる活動を取り入れる。
- 家族と協力し、本人が役割を持てる家事を一部担当してもらう。
- 地域ボランティアの訪問を導入し、会話や交流を促す。
状況別文例
- 「何をしても楽しくない」と話す方に、過去に打ち込んだ趣味を一緒に再開してもらう。
- 気分の落ち込みが強い方に対して、心理的負担の少ない短時間活動から支援を始める。
- 食事を面倒がる方に、盛り付けを一緒に行って楽しみながら食卓に向かえるようにする。
- 外出が困難な方に、室内で植物を育てる活動を取り入れ、生きがいを感じてもらう。
- 声をかけても拒否的な態度が見られる方に、無理強いせず選択肢を提示して自主性を尊重する。
実践的な文例
- 「今日はここまで頑張った」と振り返る機会を設け、自己評価を高める。
- 毎日、朝の挨拶を通じてコミュニケーションを図り、生活への関心を持たせる。
- 本人の体調や気分に合わせて活動量を調整し、成功体験を積み上げる。
- 活動を記録し、本人や家族と共有することで達成感を可視化する。
- 「やらなければならない」ではなく「やってみたい」と思える環境を工夫する。
- 職員が笑顔で関わることで安心感を与え、意欲を引き出す。
- 役割を与えられることで「必要とされている」と感じられる支援を行う。
- 利用者自身が活動を選択できるようにし、主体性を大切にする。
- 周囲の人からの「ありがとう」の言葉を意識的に伝え、やる気につなげる。
- 活動の目標を細分化し、「今日はここまで」という小さな成功を積み重ねる。
長期目標例
- 自分のペースで活動を継続し、日常生活に前向きな姿勢を取り戻す。
- 健康維持のために生活習慣を整え、意欲的に取り組める生活環境をつくる。
- 季節の行事や地域イベントに参加し、社会とのつながりを感じられるようにする。
- 自宅で安心して暮らしながら、やりがいを持って生活する。
- 笑顔で過ごす時間を増やし、生活全体の満足度を高める。
短期目標例
- 毎日1回は声を出して挨拶できるようにする。
- 週3回は好きなテレビ番組や新聞を読む習慣を持つ。
- 月2回は家族や友人と電話やオンラインで会話する。
- 1日1回は体操やストレッチを行う。
- 毎日の食事を残さず食べられるように支援する。
サービス内容例
- デイサービスで個別活動プログラムを提案し、参加意欲を高める。
- 訪問介護で掃除や洗濯を一緒に行い、達成感を感じてもらう。
- 訪問リハビリで楽しめる体操や歩行練習を導入する。
- 家族と協力して週末に買い物に出かける習慣をつくる。
- ボランティアや地域活動を紹介し、本人の興味を広げる。
状況別文例
- 「疲れるから何もしたくない」と話す方に、短時間でも楽しめる活動を提案する。
- 認知症による無気力が見られる方に、日課としての習慣化を支援する。
- 一人で過ごす時間が長い方に、定期的な訪問や電話で交流を持つ。
- 趣味がなくなった方に、新しい活動を体験してもらい関心を引き出す。
- 気分の落ち込みが強い方に、声かけと共感を中心とした支援を行う。
実践的な文例
- 活動に参加したら必ず褒め、次の意欲につなげる。
- 小さな役割(新聞を取りに行く、花に水をやる)を与える。
- 活動後に本人が感想を話す機会を設ける。
- 笑顔や頷きを積極的に返し、安心感を持ってもらう。
- 本人の意思を尊重し、選択肢を複数提示する。
- 毎日の変化を家族に共有し、協力体制を強める。
- 一緒に行動することで孤独感を軽減する。
- 絵日記や活動記録をつけ、達成感を可視化する。
- 季節感を取り入れた活動で生活に彩りを持たせる。
- 「できた」経験を積み重ね、自己肯定感を育む。
長期目標例
- 心身の機能を維持しながら、主体的に生活できるようにする。
- 日常生活で「やりたいこと」を見つけ、実行に移せるよう支援する。
- 家族や地域と関わりながら、孤立を防ぎ生活の質を高める。
- 自ら進んで外出や活動を行えるようになる。
- 自分の存在価値を感じ、前向きに生活できるようにする。
短期目標例
- 週1回はデイサービスに参加し、交流を持つ。
- 1か月以内に新しい活動を1つ試みる。
- 毎日1回は体操や散歩で体を動かす。
- 1週間に2回は「ありがとう」と言葉を発する。
- 家族に自分の気持ちを伝えられるようになる。
サービス内容例
- デイサービスで調理活動に参加し、食への意欲を高める。
- 訪問介護で衣類整理を一緒に行い、生活の役割を持つ。
- 訪問リハビリで階段昇降など挑戦的な運動を行う。
- 家族と連携し、本人が決めた活動を一緒に実施する。
- 地域のカフェやサロンを紹介し、外出の機会を増やす。
状況別文例
- 生活リズムが乱れがちな方に、起床・就寝時間を一定にする支援を行う。
- 意欲低下により外出を拒否する方に、玄関先で日光を浴びる習慣を導入する。
- 食事を嫌がる方に、本人好みの料理を一緒に作る機会を設ける。
- 交流を避ける方に、少人数のグループから関わりを始める。
- 「できない」という言葉が増えた方に、できる活動を一緒に確認し自信を持たせる。
実践的な文例
- 毎日1つ成功体験を積み重ねるよう支援する。
- 本人の生活歴を活かした活動を取り入れる。
- 他者に感謝される役割を担ってもらう。
- 活動を写真に残し、成果を視覚化する。
- 会話の中で本人の長所を意識的に伝える。
- 失敗を責めずに挑戦を評価する。
- 予定をカレンダーに書き込み、見える化して意欲を高める。
- 本人の得意分野を活かした活動を日課にする。
- 他の利用者との協力作業で達成感を味わう。
- 職員や家族が一緒に楽しむことで活動意欲を喚起する。
長期目標例
- 活動を通じて自信を取り戻し、前向きに生活できるようにする。
- 趣味や楽しみを見つけ、生活に張りを持たせる。
- 毎日の生活を自分らしく過ごし、満足感を得られるようにする。
- 家族や地域社会との関わりを維持し、孤立を防ぐ。
- 健康を維持し、自立した生活を長く継続する。
短期目標例
- 週に2回は外の空気を吸いに出る。
- 毎日好きな飲み物を楽しみながら会話をする。
- 月1回は家族と一緒に外食する。
- 週に1度は新しい体操やゲームに挑戦する。
- 活動後に必ず「よかった」と感想を言えるようにする。
サービス内容例
- デイサービスでレクリエーションに積極的に参加する。
- 訪問介護で料理の下ごしらえを手伝ってもらう。
- 訪問リハビリで歩行距離を少しずつ延ばす。
- 家族と協力して役割を持てる家事を分担する。
- 地域の交流活動を紹介し、参加を支援する。
状況別文例
- 「疲れる」と横になりがちな方に、短時間でも座位保持を促す。
- 会話を拒否する方に、共感を中心とした関わりを持つ。
- 認知症による無気力がある方に、過去の思い出を一緒に語る。
- 趣味への関心が低下した方に、少しずつ過去の活動を再導入する。
- 季節の行事を取り入れ、生活に変化を与える。
実践的な文例
- 小さな成功を共有し「できたね」と声をかける。
- 本人が主体的に活動を選べる環境を整える。
- 「楽しい」と感じたことを記録に残す。
- 職員が一緒に取り組むことで孤独感を軽減する。
- 本人が興味を持つ話題から活動につなげる。
- 利用者会議や交流で役割を持ってもらう。
- 短い活動を積み重ねることで意欲を引き出す。
- 活動を写真や作品として残すことで達成感を持たせる。
- 「ありがとう」と言葉を返す習慣を育む。
- 本人が納得できるペースで活動を進める。
長期目標例
- 前向きな気持ちを持ち、生活の質を高める。
- 自分らしい役割を持ち、社会参加を続ける。
- 健康維持に努め、生活意欲を持ち続ける。
- 人との関わりを大切にし、笑顔で過ごす。
- 趣味や娯楽を通じて生活に張りを持たせる。
短期目標例
- 毎日新聞を読み、感想を話せるようにする。
- 週に1回は外出の機会をつくる。
- 1日1回は会話に積極的に参加する。
- 新しい活動を月1回試す。
- 「やってみたい」と自発的に発言できるようになる。
サービス内容例
- デイサービスで季節のイベントに参加する。
- 訪問介護で一緒に買い物を行い、主体的に選択してもらう。
- 訪問リハビリで段階的に運動負荷を増やす。
- 家族と協力して趣味活動の時間をつくる。
- 地域ボランティア活動に参加する。
状況別文例
- 孤立しがちな方に、地域交流の場を紹介する。
- 生活意欲が低下した方に、少しずつできることを増やす。
- 認知症のある方に、簡単な作業で成功体験を提供する。
- 食欲低下がある方に、好物を取り入れて楽しみを持たせる。
- 外出を嫌がる方に、玄関先から段階的に外に出る習慣をつける。
実践的な文例
- 本人の意見を尊重し、無理なく活動を進める。
- 職員が一緒に参加することで安心感を持たせる。
- 活動を小さな目標に分け、達成感を積み重ねる。
- 笑顔や感謝を意識して伝え、前向きな気持ちを育む。
- 本人の強みを活かした役割を与える。
- 交流を通じて「必要とされている」感覚を持たせる。
- 成果を家族と共有し、本人のモチベーションを高める。
- 季節や時期に合わせた活動で変化を感じてもらう。
- 本人が楽しいと感じたことを継続的に取り入れる。
- 「今日は楽しかった」と振り返れる支援を行う。
まとめ
意欲低下に関するケアプランは、小さな成功体験・本人の関心・社会的つながり を意識して作成することが重要です。
今回紹介した【コピペOK】180文例は、そのまま活用しても良いですし、利用者の背景やニーズに合わせてアレンジすれば、より効果的なケアプランになります。
意欲の回復は一朝一夕ではなく、継続的な支援が必要です。
前向きな言葉を使い、本人のペースに合わせながら、生活に張りを取り戻せるようなプランを立てていきましょう。















