【コピペOK】失語症・言語障害のケアプラン文例を100紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
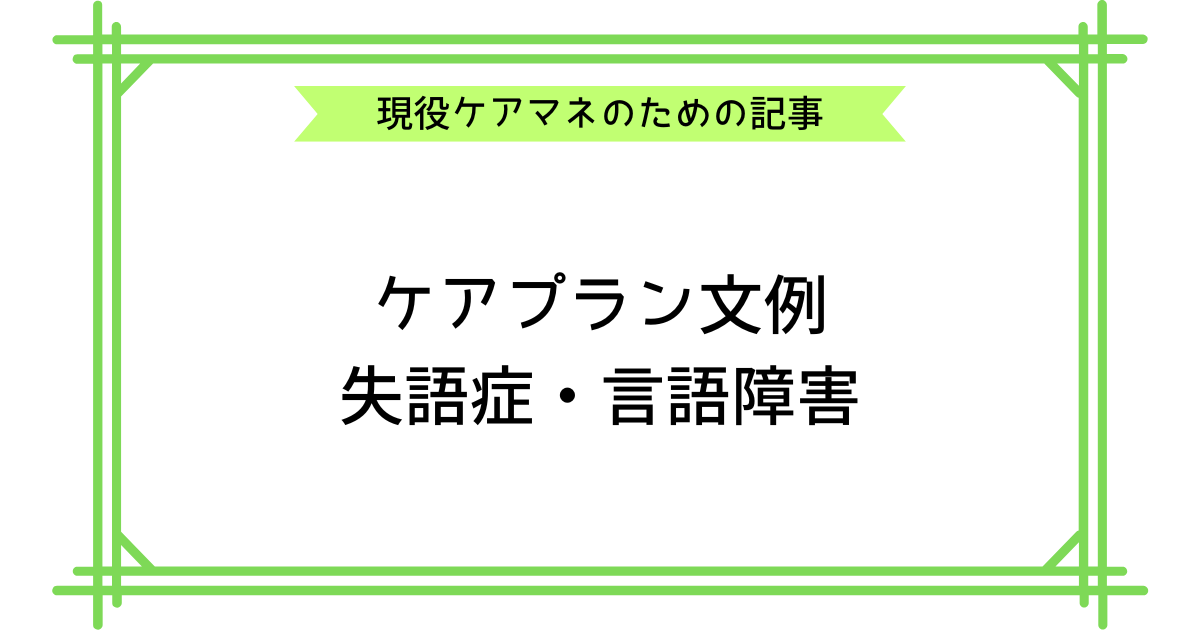
脳血管疾患の後遺症や加齢に伴い、失語症や言語障害 を抱える方は少なくありません。
発語や理解の困難さは、本人の生活の質(QOL)を下げるだけでなく、孤立感やストレスを生みやすくなります。
そのためケアプランでは、言語リハビリの継続・意思疎通手段の確保・心理的支援・家族教育 などを多面的に組み込む必要があります。
この記事では、失語症・言語障害に対応するケアプラン文例を100事例 用意しました。
施設・居宅・通所リハ・訪問リハなど幅広い場面で活用可能です。
目次
失語症・言語障害のケアプラン文例100
【基本的な意思疎通支援】
- 短く分かりやすい言葉で話しかける。
- 筆談を活用し、意思疎通を図る。
- 絵カードや写真を用いて理解を助ける。
- 本人が表情やジェスチャーで伝えられるよう支援する。
- 会話速度をゆっくりにし、理解しやすくする。
- 大きな声ではなく、落ち着いた声で話す。
- 本人が返答に時間をかけられるよう待つ。
- 質問は「はい/いいえ」で答えやすい形にする。
- 分からない場合は繰り返し説明する。
- 本人の発語を遮らず、最後まで待つ。
【言語リハビリとの連携】
- 言語聴覚士(ST)の指導に基づいて発声練習を行う。
- 言葉の復唱練習を支援する。
- 語彙を増やすため、カードや絵本を使用する。
- 発音が難しい言葉を繰り返し練習する。
- 発声練習を日課に組み込み、習慣化する。
- 曜日や日付を言う練習を継続する。
- 口腔体操を取り入れ、発声しやすくする。
- 音読を一緒に行う。
- STのリハビリ結果を職員間で共有する。
- 言語訓練の記録を残し、経過を確認する。
【代替手段の活用】
- コミュニケーションボードを使用する。
- スマートフォンやタブレットを活用する。
- 指差し表を作成し、意思表示できるようにする。
- 「トイレ」「水分」など基本的なニーズを絵で表現する。
- コミュニケーションアプリを導入する。
- ボイス出力機器を利用する。
- 写真アルバムを使って希望を伝えられるようにする。
- 文字盤を活用する。
- タッチパネルで簡単に選択できるようにする。
- 本人が使いやすい方法を優先して導入する。
【心理的支援】
- 発語の失敗を責めず、受け止める。
- コミュニケーションがうまくいった際に褒める。
- 不安な気持ちを傾聴する。
- 落ち込んでいるときに励ましの声をかける。
- できることに焦点を当てて自己肯定感を高める。
- 交流の場を設け孤独感を軽減する。
- 不安が強いときは安心できる職員を固定する。
- 本人のペースを尊重する。
- 自己表現できた成功体験を積ませる。
- 趣味や得意分野を活かして自信を持てるよう支援する。
【家族支援】
- 家族に正しい声かけ方法を説明する。
- 家族にSTの指導内容を共有する。
- 家族に筆談や絵カードの活用を勧める。
- 家族に本人の発語を遮らず待つことを伝える。
- 家族に焦らず対応するよう助言する。
- 家族に家庭でできる発声練習を提案する。
- 家族に本人の進歩を報告し安心を与える。
- 家族に誤った対応で本人を傷つけないよう伝える。
- 家族と一緒にコミュニケーション訓練を行う。
- 家族にケアプランの内容を説明し協力を依頼する。
【日常生活での工夫】
- 食事前に発声練習を取り入れる。
- 買い物リストを本人が書けるようにする。
- 電話の応答練習を行う。
- 自分の名前を言えるよう練習する。
- 家事動作を通じて発話の機会を作る。
- 「ありがとう」「お願いします」など日常表現を練習する。
- テレビや新聞を一緒に見て言葉を引き出す。
- 歌を通じて発声を促す。
- 家族や友人との会話の場を増やす。
- 日記を書く習慣をつける。
【社会参加】
- デイサービスで発表の機会を設ける。
- グループ活動に参加し、発言を促す。
- 地域のイベントに参加する。
- ボランティア活動に関わる。
- サークル活動で交流を広げる。
- 趣味活動を通じて言語表現を引き出す。
- 簡単な役割を担い自信を持てるよう支援する。
- 利用者同士でゲームを行い、発話を促す。
- 地域交流を通じて社会参加を広げる。
- 社会参加の成果を記録し、本人と共有する。
【認知症併存時対応】
- 簡単な言葉で繰り返し伝える。
- 認知症による混乱が強い場合は絵で説明する。
- 認知症症状を否定せず受け止める。
- わからない時は「大丈夫」と安心させる。
- 会話が途切れたときは別の話題に切り替える。
- 本人の生活歴を活かした会話を行う。
- 過去の写真を用いて回想法を行う。
- 感情を優先し、論理的な説明に固執しない。
- 認知症と失語症を併せて支援できるよう工夫する。
- 認知症カフェなどに参加し交流を持つ。
【安全・医療管理】
- 発語困難により意思表示ができない場合に備え観察を強化する。
- 体調不良を訴えられない場合にバイタル測定を行う。
- 医師に症状を正確に伝えられるよう家族と協力する。
- 緊急時に備え、意思表示カードを携帯させる。
- 入浴や食事時に体調異変を確認する。
- 薬の副作用を観察し、言葉にできない症状を把握する。
- 本人が表現できない痛みを行動から読み取る。
- 医療機関との情報共有を強化する。
- 定期的にST評価を受ける。
- 医師・看護師と連携し治療とケアを調整する。
【将来を見据えた支援】
- 言語機能の回復状況を定期的に評価する。
- 機能維持を目標にリハビリを継続する。
- 機器やICTを活用して意思疎通を補う。
- 状況に応じてケアプランを見直す。
- 本人と家族の希望を反映する。
- 在宅生活継続を見据え支援する。
- 将来的な施設入所も含め選択肢を検討する。
- 終末期においても意思表示を尊重する。
- 多職種で連携し、総合的に支援する。
- 失語症・言語障害があっても安心して生活できることを最終目標とする。
まとめ
失語症や言語障害のケアプランは、意思疎通支援・言語リハビリ・代替手段の活用・心理的ケア・家族支援・社会参加 など多方面からのアプローチが必要です。
今回紹介した100の文例は、そのままコピーしても、利用者の状態に合わせてアレンジしても活用できます。
ケアプラン作成時の参考にしていただき、本人の「伝えたい」「理解したい」という思いを支えるケアに役立ててください。















