月途中で区分変更があった場合の支給限度額はどうなる?仕組みと注意点を解説
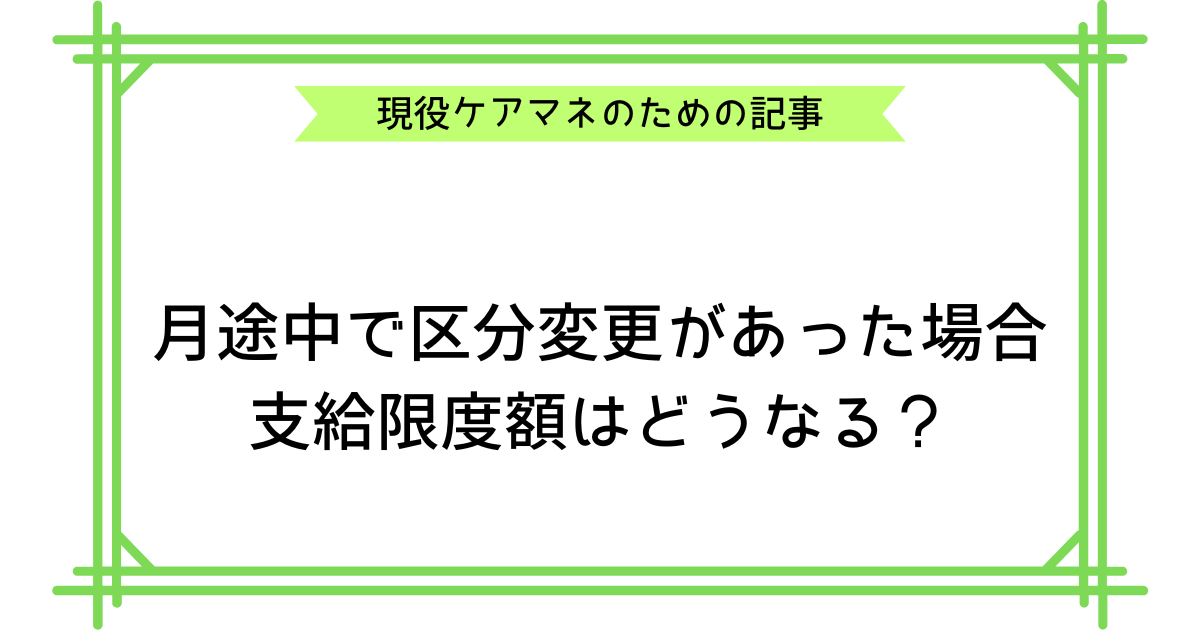
介護保険を利用している高齢者の状態が変化し、月の途中で要介護度が変わる(区分変更)ことは珍しくありません。
このとき多くの家族やケアマネが疑問に思うのが「支給限度額はどう計算されるのか?」という点です。
介護サービスは1か月単位での限度額管理が基本ですが、月の途中で区分変更があった場合には特別な取り扱いがされます。
本記事では、月途中の区分変更と支給限度額の関係、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
介護保険の支給限度額とは?
介護保険サービスを利用できる金額には、要介護度ごとに上限(支給限度額)が定められています。
例えば(2024年度基準):
- 要支援1:5,003単位
- 要支援2:10,473単位
- 要介護1:16,765単位
- 要介護2:19,705単位
- 要介護3:27,048単位
- 要介護4:30,938単位
- 要介護5:36,217単位
この枠内であれば1割〜3割の自己負担で利用できますが、限度額を超えると全額自己負担となります。
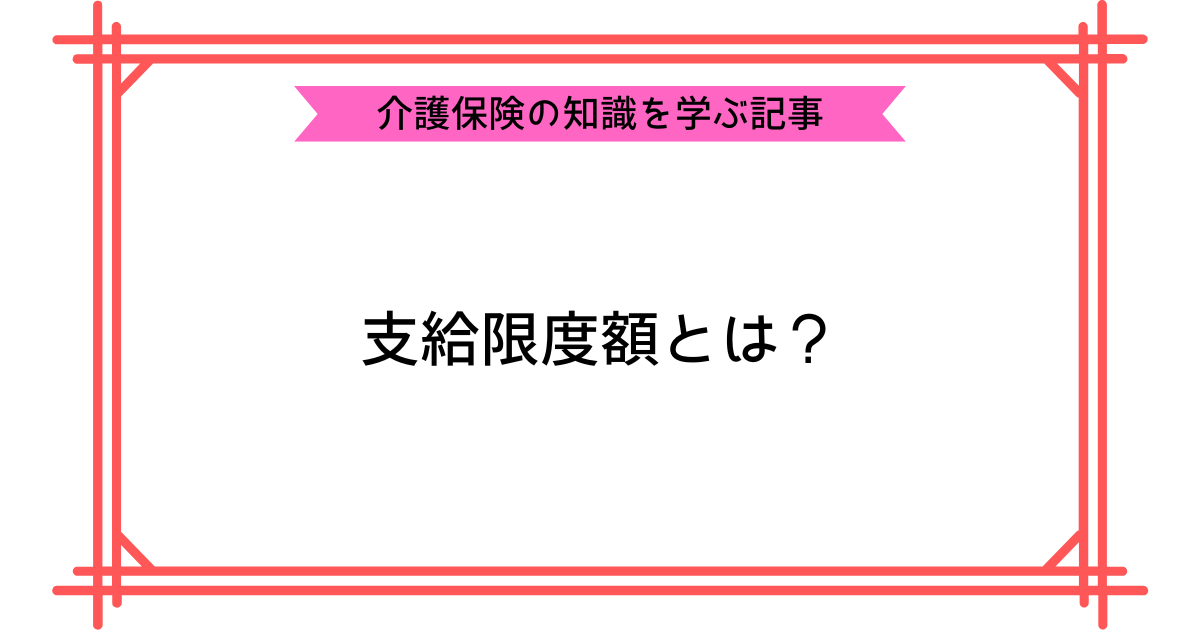
月途中の区分変更時の支給限度額の取り扱い
新しい介護度の限度額がその月から適用される
区分変更で要介護度が上がった場合、原則として 認定結果が出た日(効力発生日)から新しい支給限度額が適用されます。
→ 例:5月10日に要介護2から要介護3に変更 → 5月は要介護3の支給限度額(27,048単位)がそのまま使える。
月の途中で「限度額が分割される」ことはない
「前半は要介護2の枠」「後半は要介護3の枠」と分割されるのではなく、月全体として新しい区分の支給限度額が適用される仕組みです。
変更前に使ったサービスも新限度額でカウントされる
月初から区分変更前に利用したサービスも含め、その月の利用単位は新しい限度額で管理されます。
実務での注意点(ケアマネ・家族向け)
サービス計画の調整が必要
区分変更の認定結果が出るまで時間がかかるため、結果が出た後にサービス量を再調整する必要があります。特に要介護度が上がった場合、限度額に余裕ができるため追加サービスが検討可能です。
支給限度額オーバーに注意
要介護度が下がった場合は、支給限度額も減るため、結果的に「その月の利用単位がオーバーする」可能性があります。この場合、オーバー分は全額自己負担となるため、事前に利用者・家族へ説明しておくことが重要です。
市区町村からの通知を確認する
区分変更後の効力発生日や限度額は、市区町村から送られてくる認定結果通知書に記載されています。実務では必ずこれを確認し、ケアプランや請求に反映させましょう。
家族が理解しておきたいポイント
- 区分変更が月途中でも、新しい介護度の限度額がその月から適用される
- 変更前に利用したサービスも新しい限度額で計算される
- 要介護度が下がった場合は自己負担が増える可能性がある
- ケアマネに早めに相談し、サービス調整をしてもらうことが大切
まとめ
月途中で区分変更があった場合でも、その月の介護サービスの支給限度額は「新しい介護度」の基準で適用されます。
限度額が分割されることはなく、変更前のサービスも含めて新限度額で計算されます。
ただし、要介護度が下がった場合は自己負担が発生する可能性があるため、家族としては早めにケアマネと連携してサービス内容を見直すことが大切です。















