【コピペOK】心不全のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
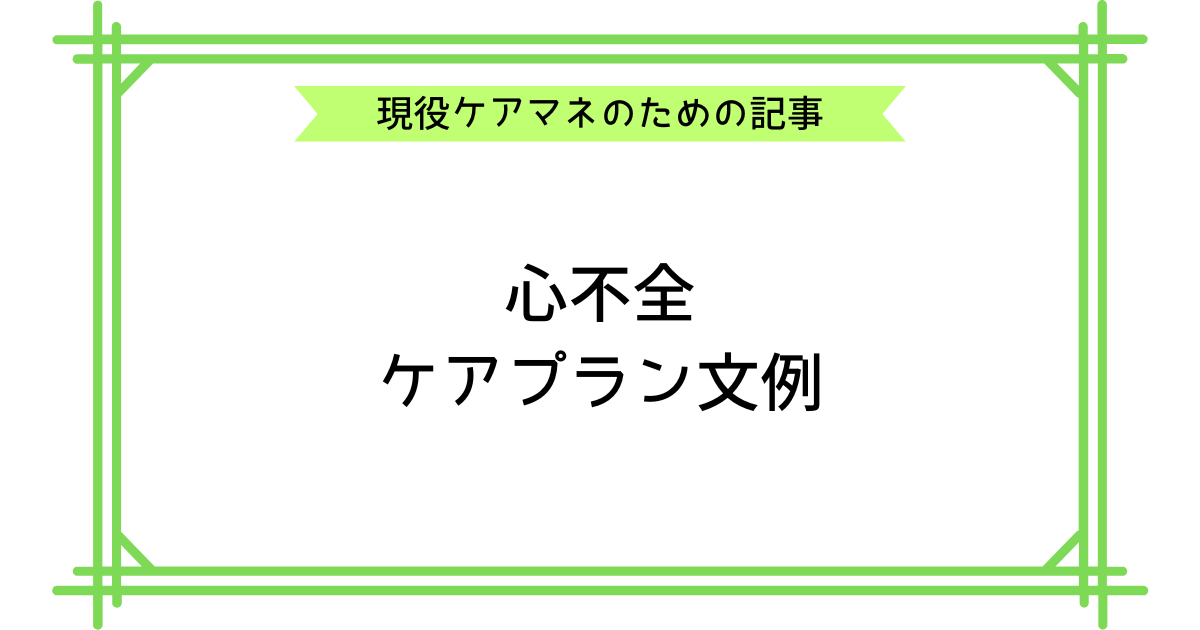
心不全は高齢者に多い疾患であり、再入院のリスクが高いため、在宅や施設での介護支援においても重要なテーマです。
ケアマネジャーは、日常生活支援だけでなく医療との連携を常に意識したケアプラン を作成する必要があります。
ここでは、心不全に対応できるケアプラン文例100事例 を、カテゴリ別に整理しました。
現場ですぐにコピー&ペーストして使えるようにしています。
目次
心不全のケアプラン文例
移動・安静保持
- 息切れがあるため、移動は介助を行い無理のない範囲で行う。
- 階段昇降は避け、生活動線を平面で完結できるように整備する。
- 疲労が強いため、こまめに休憩をとれるように支援する。
- 長距離移動は介護タクシーを利用し、心臓への負担を軽減する。
- 外出時は車椅子を活用し、安全に移動できるようにする。
- 急な動作を避け、声かけを行いながらゆっくりと移動する。
- 息切れ時は座って休めるように椅子を配置する。
- 室内移動は見守りを行い、安全と安心を確保する。
- 移動介助を通じて、活動量を無理なく維持する。
- 身体への負担を軽減するため、必要に応じて酸素を使用する。
- 移動時に苦痛があればすぐに休める環境を整える。
- 外出は短時間とし、疲労を防止する。
- 体調に合わせて移動距離を調整する。
- 夜間の移動は見守りを行い、転倒と急変を防ぐ。
- 安静を守りながらも、日常生活の範囲内で活動を続ける。
- 急変時に備えて緊急連絡体制を整える。
- 体位変換を行い、呼吸が楽になる姿勢を保持できるよう支援する。
- 心不全の状態に応じて、活動量を段階的に調整する。
- 家族と連携し、活動制限を理解してもらう。
- 移動支援を通じて、心不全の悪化を予防する。
排泄支援
- 排泄時に息切れがあるため、声かけを行い無理のない動作を支援する。
- トイレ移動は介助し、心臓への負担を軽減する。
- 夜間排泄はポータブルトイレを使用し、移動距離を短縮する。
- 便秘を予防するため、水分・食事管理を行う。
- 下衣の着脱を一部介助し、動作の負担を減らす。
- 排泄時に体調変化がないか観察し、必要に応じて医師に報告する。
- 息切れや動悸が出た場合は、すぐに動作を中止し休息を取る。
- トイレ環境を整理し、短時間で排泄できるようにする。
- 定時のトイレ誘導を行い、失禁を予防する。
- 排泄支援を通じて、安心して生活できるようにする。
- 心不全による浮腫に配慮し、排尿状況を記録する。
- 排泄時の負担を軽減するため、和式ではなく洋式トイレを使用する。
- トイレへの動線を短くし、呼吸困難を予防する。
- 家族と連携し、排泄介助の方法を統一する。
- 尿意の訴えに応じて迅速に誘導する。
- 排泄時はプライバシーに配慮し、尊厳を守る。
- 下痢時は迅速に対応し、脱水を予防する。
- 排泄ケアを通じて、本人が安心できる環境を整える。
- 失禁がある場合はパッドを適切に使用し、清潔を維持する。
- 排泄支援を通じて、QOLを維持する。
入浴・清潔保持
- 入浴は短時間で行い、心臓に負担をかけないよう支援する。
- 浴槽ではなくシャワー浴を基本とする。
- 入浴前後に体調を観察し、異常があれば中止する。
- 浴室に椅子を設置し、座位で洗身できるようにする。
- 入浴は週2〜3回とし、清拭で補完する。
- 入浴中はこまめに休憩を取り、無理のない範囲で行う。
- 入浴時に息切れがあればすぐに中止し、休息を取る。
- 清拭を行い、皮膚を清潔に保つ。
- 入浴後は体調観察を行い、異常時は医師に報告する。
- 入浴後は十分な休養を確保する。
- 浴室の温度差を調整し、心臓に負担をかけないようにする。
- 入浴介助を通じて、清潔保持と生活の満足感を高める。
- 入浴前に服薬や体調を確認し、無理を防ぐ。
- 季節に応じて入浴頻度を調整する。
- 爪切りや整髪を行い、清潔感を維持する。
- 入浴時のプライバシーに配慮する。
- 入浴後は水分補給を行い、脱水を防ぐ。
- 入浴介助時は声かけを行い、安心感を持てるようにする。
- 入浴・清潔支援を通じて、生活の質を高める。
- 緊急コールを浴室に設置し、安心して入浴できるようにする。
食事・栄養管理
- 減塩食を提供し、心不全の悪化を予防する。
- 水分摂取量を管理し、体重増加を防ぐ。
- 摂取内容を記録し、栄養状態を把握する。
- 少量多回食を取り入れ、心臓への負担を軽減する。
- 食欲低下時は好物を取り入れて摂取量を確保する。
- 家族に減塩調理法を指導する。
- 食事中は誤嚥を防ぐため、座位保持を徹底する。
- 体重測定を定期的に行い、浮腫や心不全増悪を早期に察知する。
- 栄養補助食品を活用し、栄養状態を維持する。
- 食事環境を整え、落ち着いて食べられるようにする。
- 食欲が低下した際は、医師・管理栄養士と連携する。
- 水分制限の必要性を理解できるよう、繰り返し説明する。
- 食後の休養を確保し、心臓への負担を軽減する。
- 季節の食材を取り入れ、食事を楽しめるようにする。
- 食事支援を通じて、生活の満足感を高める。
服薬・医療管理
- 服薬管理を徹底し、内服忘れを防ぐ。
- 利尿薬の服薬状況を確認し、効果を観察する。
- 薬の副作用に注意し、異常時は医師に報告する。
- 血圧・脈拍を定期的に測定し、変化を記録する。
- 酸素療法を導入し、呼吸状態を安定させる。
- 通院スケジュールを管理し、受診の漏れを防ぐ。
- 医療機関と情報共有を行い、連携を強化する。
- 急変時の対応手順を家族に指導する。
- 医師の指示に基づき、安静度を調整する。
- 医療連携を通じて、心不全の増悪を予防する。
- 薬剤師と連携し、服薬内容を確認する。
- 医師の指示のもと、点滴や処置を行う。
- 家族に服薬の重要性を説明し、理解を促す。
- 医療との連携を通じて、安心した療養生活を支援する。
- 急変時は迅速に救急搬送できる体制を整える。
生活意欲・家族支援
- 本人の希望を尊重し、できる範囲で趣味活動を継続する。
- 家族と一緒に過ごす時間を増やし、生活意欲を高める。
- 季節の行事に参加し、社会交流を維持する。
- デイサービスを利用し、活動機会を確保する。
- 会話の機会を増やし、孤独感を軽減する。
- 家族に心不全のケア方法を説明し、不安を軽減する。
- 介護負担を軽減するため、レスパイトケアを導入する。
- 家族と協力し、食事・服薬管理を徹底する。
- 家族の気持ちに寄り添い、精神的負担を和らげる。
- 本人と家族が安心して生活できるよう、医療と介護の連携を強化する。
まとめ|心不全のケアプランは「急変予防」と「生活の質維持」が鍵
心不全は慢性的に経過しながらも、急変や再入院のリスクが常に伴う疾患 です。ケアプランでは、
- 移動・安静保持で心臓への負担軽減
- 排泄・入浴での安全確保
- 減塩・水分制限などの食事管理
- 服薬・医療との連携
- 家族への説明と支援
が特に重要となります。
今回紹介した100の文例は、在宅・施設どちらの現場でも応用できる内容です。コピー&ペーストで使いながら、利用者の状態や生活背景に応じて調整してご活用ください。















