【コピペOK】若年性認知症のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
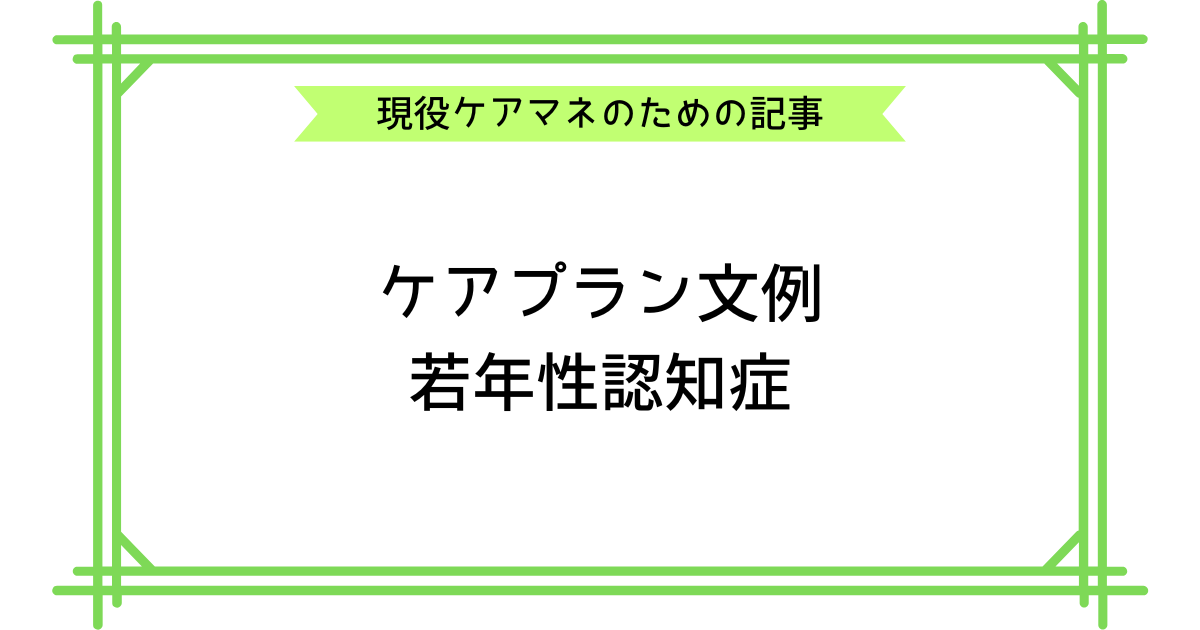
若年性認知症は、アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症などが含まれ、就労や家庭生活の最中に発症するため、当事者だけでなく家族への影響も大きい特徴があります。
本記事では、ケアマネジャーがケアプラン作成時に参考にできる 若年性認知症に対応したケアプラン文例を100事例 紹介します。
生活支援、社会参加、家族支援、医療的対応などを網羅的にカバーしました。
目次
若年性認知症のケアプラン文例(100事例)
1. 生活支援(1〜20)
- 毎日の服薬確認を行い、飲み忘れを防止する。
- カレンダーやメモを活用して予定を可視化し、生活リズムを維持する。
- 金銭管理を家族と連携して行い、浪費や支払い忘れを予防する。
- 冷蔵庫の中身を定期的に確認し、賞味期限切れ食品の誤食を防ぐ。
- 鍵や財布の置き場所を固定し、紛失を防止する。
- 毎日の服装を事前に準備し、着替えをスムーズに行えるよう支援する。
- 家電操作の誤りを防ぐため、リモコンやスイッチにラベルを貼る。
- 家事動作を分担し、本人の残存能力を活かせるようにする。
- 買い物を家族や支援員と同行して行い、誤購入を防ぐ。
- ごみ出しや掃除を一緒に行い、生活環境を清潔に保つ。
- 服薬カレンダーを導入して服薬習慣を支える。
- 就寝・起床時間を一定に保ち、生活リズムを整える。
- 調理は火を使わない方法を取り入れ、安全に配慮する。
- 冷蔵庫や収納にラベルを貼り、取り間違いを防ぐ。
- 本人ができる範囲の役割を担えるように家事を一部継続する。
- 外出時には連絡カードを携帯し、迷子時の対応を容易にする。
- 家族が留守中でも安心して過ごせるよう見守りサービスを導入する。
- 定期的に訪問介護を導入し、生活支援と安否確認を行う。
- 本人の興味関心に応じた活動を生活に取り入れ、生活意欲を高める。
- 家の中での危険箇所に注意し、転倒や事故を予防する。
2. 就労・社会参加支援(21〜35)
- 就労継続の可否を医師と相談し、可能な範囲での仕事継続を支援する。
- 就労移行支援事業所と連携し、本人の希望に合った活動を探す。
- 本人の得意分野を活かせるボランティア活動を紹介する。
- デイケアに参加し、生活リズムと社会性を維持する。
- 趣味活動の継続を支援し、生きがいを保つ。
- 地域活動に参加し、孤立を防ぐ。
- 外出機会を増やし、閉じこもりを防止する。
- 本人が役割を持てるよう、家庭内での軽作業を支援する。
- 作業所や地域の集まりに参加し、社会交流を図る。
- 本人の強みを活かした趣味クラブへの参加を支援する。
- 外出同行を行い、安心して社会参加ができるようにする。
- デイサービスを利用し、仲間との交流機会を確保する。
- ICT機器を活用し、遠方の知人や家族との交流を支援する。
- 本人が得意な作業を役割として続けることで自尊心を保つ。
- 地域包括支援センターと連携し、本人に合った社会資源を紹介する。
3. 医療的対応(36〜50)
- 定期的な受診を確実に行えるよう家族と調整する。
- 診察内容を記録し、本人と家族が理解できるよう支援する。
- 内服管理を徹底し、病状の進行予防に努める。
- 合併症の有無を定期的に確認する。
- 発熱や体調変化があれば迅速に医師へ報告する。
- 精神症状(不安・抑うつ)に対して主治医と相談する。
- 睡眠障害の有無を観察し、必要に応じて医師に報告する。
- 栄養状態を把握し、低栄養を予防する。
- 薬の副作用に注意し、異常があれば早期対応する。
- 認知症専門医療機関との連携を強化する。
- 定期的な血液検査を受け、身体合併症を早期に発見する。
- 運動機能低下を予防するため、リハビリを継続する。
- 嚥下障害の兆候を観察し、誤嚥性肺炎を予防する。
- 服薬指導を受け、本人と家族に理解を促す。
- 医療・介護・福祉が一体となって本人を支える体制を整える。
4. 家族支援(51〜65)
- 家族に認知症ケアの知識を提供する。
- 介護方法を指導し、家族の負担を軽減する。
- 家族が安心して外出できるよう、見守りサービスを活用する。
- 家族介護者のストレスを傾聴し、支援機関につなげる。
- 介護負担軽減のためにショートステイを導入する。
- 家族会を紹介し、同じ立場の人と交流できるようにする。
- 家族が休養を取れるよう、レスパイトケアを活用する。
- 経済的負担に関する相談を地域包括支援センターと共有する。
- 家族と連携し、緊急時の対応を事前に決めておく。
- 介護離職を防ぐために、就労支援制度を紹介する。
- 家族の介護スキルを高めるために研修情報を提供する。
- 介護記録を共有し、情報伝達を円滑にする。
- 家族に心理的サポートを提供し、孤立を防ぐ。
- 認知症カフェに家族と参加し、社会的つながりを持つ。
- 家族が過度な負担を抱えないよう、ケアマネが定期的に状況を確認する。
5. 安全確保・事故予防(66〜80)
- ガスの元栓を家族が管理し、火の不始末を防ぐ。
- コンロをIHに変更し、安全性を高める。
- 電話の詐欺被害防止のため、留守番電話設定を徹底する。
- 外出時にはGPS機能付き端末を活用する。
- 家の段差に手すりを設置し、転倒を予防する。
- 夜間のトイレ移動に照明を設置する。
- 床に物を置かず、転倒リスクを減らす。
- 外出時の迷子対策として、連絡先カードを携帯する。
- 誤飲や誤食を防ぐため、薬や食品の管理を徹底する。
- 自動火災報知器を設置し、安全性を高める。
- 入浴時は家族が付き添い、溺水を防止する。
- ベッド柵を設置し、夜間の転落を予防する。
- 居室の整理整頓を支援し、安全な環境を保つ。
- 緊急通報システムを導入し、迅速な対応を可能にする。
- 定期的に住宅環境を確認し、安全を維持する。
6. 精神的ケア・生活意欲(81〜100)
- 本人の気持ちを傾聴し、不安の軽減を図る。
- 好きな音楽を日常に取り入れ、気分の安定を促す。
- 回想法を取り入れ、生活意欲を高める。
- 季節の行事に参加し、生活に変化を持たせる。
- デイサービスでの交流を通じ、孤立を防ぐ。
- 本人が得意だった作業を継続できるように支援する。
- 家族との会話時間を確保し、安心感を得られるようにする。
- 不安時に安心できる物品(写真・手紙)を身近に置く。
- ペットセラピーを取り入れ、心の安定を図る。
- ガーデニングなど自然と触れ合う活動を支援する。
- デイケアで役割を持てるように支援する。
- 本人が希望する趣味活動を日課に取り入れる。
- 認知症サポーターとの交流を支援する。
- 自分のペースで活動できる環境を整える。
- 外出を支援し、気分転換を図る。
- リラクゼーションや呼吸法を取り入れ、落ち着きを取り戻せるようにする。
- 本人の意見を尊重し、自己決定を大切にする。
- 家族と共に将来の生活について話し合い、不安を軽減する。
- 本人の役割を見つけ、生活に意欲を持てるようにする。
- 心理的支援を継続的に行い、安心して生活を送れるようにする。
まとめ
若年性認知症は、発症年齢が若いために 就労・家庭・社会参加 など幅広い課題を抱える点が特徴です。ケアプランには、生活支援、医療連携、家族支援、安全確保、精神的ケアをバランスよく盛り込むことが重要です。
今回紹介した100事例は、そのままコピペして活用できる文例集として、ケアマネジャーの実務に役立つ内容となっています。利用者と家族の生活の質を高めるために、ぜひ参考にしてください。















