【コピペOK】アセスメントのケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
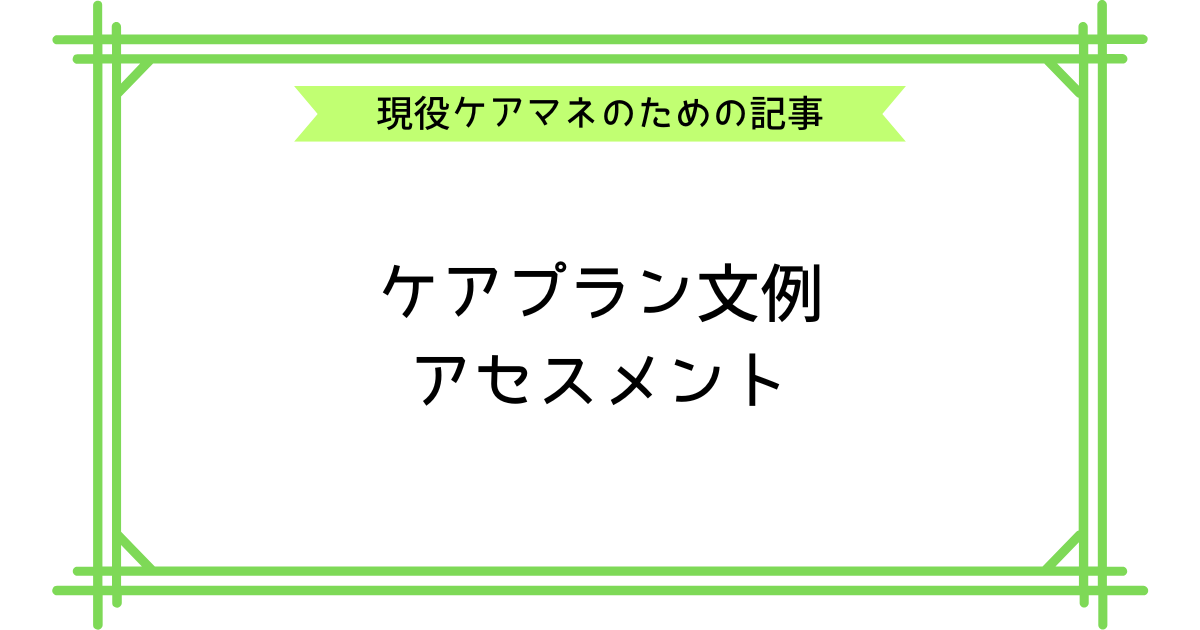
アセスメントは「利用者を理解すること」から始まります。
身体状況、認知機能、ADL、IADL、生活歴、家族関係、環境要因など、多角的に整理し、利用者が本当に必要としている支援を見極めるプロセスです。
この記事では、アセスメント場面でそのまま使える文例を 100事例 紹介します。
ケアマネジャーが日々の業務で効率的に使えるよう、目的別に整理しました。
目次
アセスメント文例(100事例)
1. 身体状況に関するアセスメント(1〜20)
- 高血圧の既往があり、日常的に服薬管理が必要である。
- 心疾患を抱えており、労作時の息切れに注意が必要である。
- 糖尿病のため、定期的な血糖測定と食事管理を行っている。
- 脳梗塞の後遺症により右片麻痺があり、ADLに一部介助を要する。
- 脊椎圧迫骨折の既往があり、長時間の立位保持が困難である。
- パーキンソン病の進行により動作緩慢が目立ってきている。
- 呼吸器疾患により在宅酸素療法を導入している。
- 皮膚が脆弱で褥瘡リスクが高く、定期的な体位変換が必要である。
- 関節リウマチにより手指の可動域制限があり、家事動作が困難である。
- 転倒歴があり、今後の転倒予防に重点を置く必要がある。
- 慢性的な腰痛があり、ADL全般に支障をきたしている。
- 嚥下機能の低下が見られ、誤嚥性肺炎のリスクがある。
- 足関節の可動域制限により歩行に不安定さがある。
- 頻尿傾向があり、夜間の排泄動作に見守りが必要である。
- 糖尿病性神経障害によるしびれを訴えている。
- 血圧変動が大きく、体調不良時の早期発見が必要である。
- 服薬副作用によるふらつきがあり、観察が必要である。
- 慢性的な便秘があり、下剤の使用頻度が高い。
- 認知症による体調変化の訴えが乏しく、観察が重要である。
- 下肢筋力の低下が著明で、歩行補助具の使用が必要である。
2. 認知機能・精神状態(21〜35)
- 認知症の進行により、時間や場所の見当識が不安定である。
- 物忘れが強く、服薬や予定の忘却が頻発している。
- 幻覚症状が出現することがあり、安全確保が必要である。
- 抑うつ傾向が見られ、生活意欲の低下が課題である。
- 睡眠リズムの乱れがあり、昼夜逆転傾向にある。
- 不安感が強く、一人での外出に支障がある。
- 認知機能低下により金銭管理が困難になっている。
- 認知症周辺症状として易怒性が見られ、家族対応に負担がある。
- 同じ質問を繰り返す傾向があり、忍耐強い対応が必要である。
- 活動意欲の低下により閉じこもり傾向がある。
- 認知機能低下により、調理や火の管理が困難となっている。
- 記憶障害により約束を守れないことが多く、見守りが必要である。
- 不眠が続き、日中の活動に支障をきたしている。
- 孤独感を訴えることが多く、社会参加の機会が求められる。
- 認知機能障害が進行しているが、日常生活動作には一部自立が見られる。
3. ADL(日常生活動作)に関するアセスメント(36〜55)
- 食事は自立しているが、配膳や調理は困難である。
- 排泄は見守りがあれば自立可能である。
- 入浴は全介助を要している。
- 更衣は動作緩慢で、部分的な介助を必要とする。
- 移乗動作に不安定さがあり、転倒リスクがある。
- ベッド上での寝返りは可能だが、起き上がりに介助を要する。
- 整容は自立しているが、動作が雑になり清潔保持が不十分である。
- 歩行は杖を使用すれば可能であるが、屋外歩行は困難である。
- トイレまでの移動は可能だが、夜間は見守りが必要である。
- 食事摂取は時間がかかるが自立している。
- 水分摂取の声かけがなければ不足しがちである。
- 階段昇降は困難で、1階での生活が中心となっている。
- 調理動作は不可能で、家族の援助を要する。
- 掃除や洗濯は困難で、生活援助が必要である。
- 歩行距離が短く、在宅での移動に制限がある。
- 車椅子での移動が主体となっている。
- 食事動作に失行が見られる。
- 入浴動作に恐怖心があり、支援が必要である。
- 更衣の順序が分からず、介助が必要である。
- 移動にふらつきがあるため、手すりの設置が望まれる。
4. IADL(手段的日常生活動作)(56〜70)
- 金銭管理は困難で、家族による代行が必要である。
- 公共交通機関の利用は難しく、外出に介助が必要である。
- 買い物はリストがあれば可能だが、単独では困難である。
- 調理は火の取り扱いが危険であり、家族が代行している。
- 洗濯は一部自立しているが、干す作業が困難である。
- 掃除は動作が雑で清潔保持が難しい。
- 電話対応が困難で、家族が代行している。
- ゴミ出しは難しく、地域のルールを守れない。
- 薬の管理は本人のみでは困難である。
- 郵便物の管理が難しく、請求書を見落とすことがある。
- 家電製品の操作に混乱が見られる。
- 金融機関での手続きは家族が付き添って行っている。
- スケジュール管理が困難で、約束を忘れることがある。
- 公共料金の支払いが困難で、家族に依存している。
- 外出の際に道に迷うことがあり、単独行動は危険である。
5. 環境・家族背景(71〜85)
- 配偶者が主な介護者として支援している。
- 子どもが遠方に住んでおり、介護負担が配偶者に集中している。
- 独居であり、定期的な安否確認が必要である。
- 家屋に段差が多く、転倒リスクが高い。
- トイレまでの動線が長く、排泄動作に不安がある。
- 入浴環境に手すりがなく、介助が必須である。
- 住宅改修の必要があるが、経済的負担が大きい。
- 家族が仕事を持っており、介護時間が限られている。
- 家族の介護疲れが強く、レスパイトの導入が必要である。
- 近隣に親戚や知人がおらず、地域との関わりが少ない。
- 家族が介護に協力的であり、チームケアが可能である。
- 独居で緊急時の対応に不安がある。
- 家族間で介護方針に違いがあり、調整が必要である。
- 高齢の配偶者が介護を担っており、支援強化が必要である。
- 経済的に困難を抱えており、制度利用の工夫が必要である。
6. 本人の希望・生活意欲(86〜100)
- できる限り自宅で生活を続けたいという強い希望がある。
- 趣味の園芸を続けたい意欲がある。
- 外出の機会を増やしたいという希望がある。
- デイサービスに通い、仲間との交流を楽しみたいと考えている。
- 身の回りのことはできるだけ自分でしたいという希望がある。
- 家族に迷惑をかけたくないという思いがある。
- 食事は自分の好みに合わせたいという要望がある。
- 入浴は自分のペースで行いたいという希望がある。
- 孫との交流を楽しみにしている。
- 地域の行事に参加したいという意欲がある。
- 自分の役割を持ちたいと考えている。
- 家で過ごす時間を大切にしたいという希望がある。
- 読書やテレビ鑑賞など趣味の時間を確保したいと考えている。
- 家族との団らんを大切にしたいという気持ちがある。
- 最期まで自宅で過ごしたいという希望がある。
まとめ
アセスメントはケアプラン作成の土台であり、利用者の心身状態・生活環境・希望を正確に把握することが欠かせません。
今回紹介した100事例は、ケアマネジャーが実際の業務でそのまま活用できる文例です。
アセスメントを丁寧に行うことで、利用者の生活に寄り添ったケアプランを実現できます。















