ケアマネの24時間連絡体制とは?義務内容や対応方法をわかりやすく解説
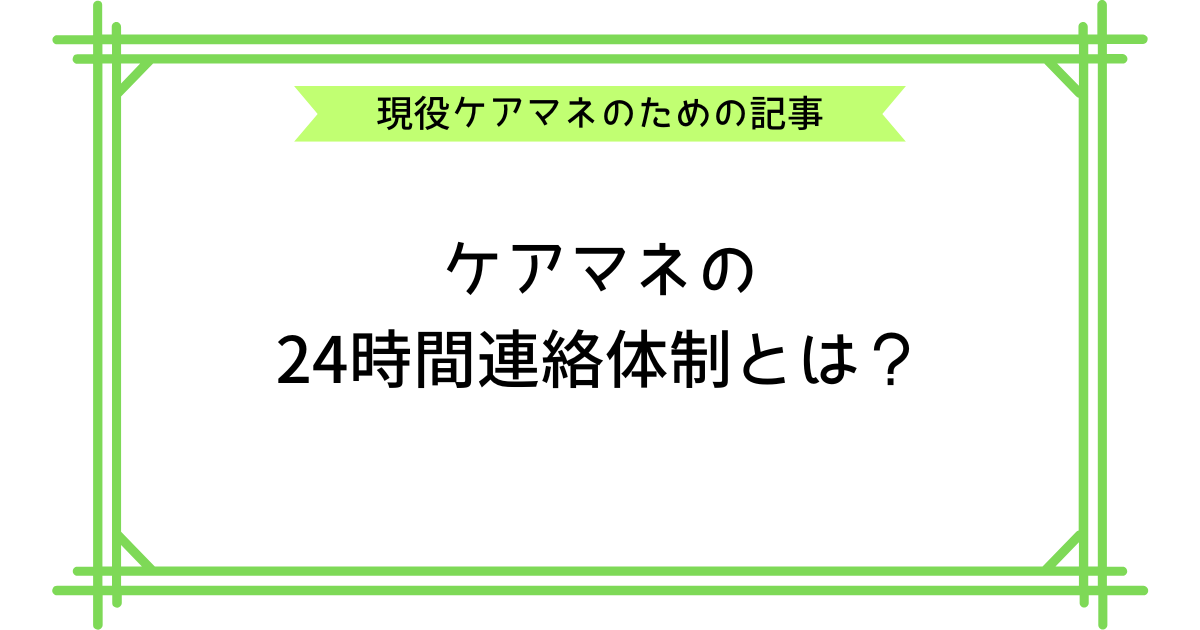
居宅介護支援事業所やケアマネジャーにとって「24時間連絡体制」は必須の体制整備のひとつです。
しかし、「なぜ必要なのか?」「どのように整えるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、ケアマネジャーに求められる24時間連絡体制の意味、制度上の義務、実際の運用方法、導入時の注意点をわかりやすく解説します。
実務に役立つポイントも盛り込みながら、最新の情報に基づいてまとめていますので、事業所運営者や現場のケアマネの方はぜひ参考にしてください。
ケアマネに求められる「24時間連絡体制」とは?
「24時間連絡体制」とは、その名のとおり利用者や家族からの緊急時の連絡に、昼夜を問わず対応できる体制を指します。
居宅介護支援事業所が居宅介護支援を提供するための人員・運営基準(介護保険法施行規則)に明記されており、加算要件や指定基準に直結する重要なポイントです。
特に在宅生活を支える利用者は、夜間や休日に急な体調不良や介護トラブルが起こることもあります。
その際に連絡手段が途切れないこと=安心感の確保につながり、利用者・家族の信頼を得ることができます。
24時間連絡体制が必要とされる背景
介護保険制度では「在宅生活の継続」を重視しています。
しかし、在宅介護は家族の負担や不安が大きく、夜間や休日にトラブルが起こった際に相談できる窓口がないと安心して暮らせません。
このため、ケアマネを配置する事業所には利用者の生活を途切れなく支える仕組みとして、24時間の連絡体制を整えることが義務づけられています。
特に以下のようなケースでは重要性が高まります。
- 急な発熱や体調変化で訪問看護・往診の調整が必要
- 家族の介護疲れや不安から緊急相談が発生
- 転倒や事故などで介護サービスの追加調整が求められる
法的な位置づけと運営基準
介護保険制度において、居宅介護支援事業所が指定を受けるためには運営基準を満たす必要があります。
その中で「利用者や家族からの相談に対して24時間連絡を受けられる体制を確保すること」が定められています。
また、厚生労働省通知や各自治体の指定要綱でも「24時間体制の連絡先を利用者に周知し、実際に機能させること」が求められています。
単に「電話番号を伝えるだけ」では不十分で、実際に夜間・休日も対応できる仕組みがなければならないのです。
実際の連絡体制の整え方
電話によるオンコール対応
最も一般的なのが事業所の代表番号に転送をかける方法です。夜間はケアマネが交代でオンコールを担当し、緊急連絡を受け付ける体制を整えます。
専用携帯電話を持ち回り
専用の携帯電話を事業所で契約し、当番のケアマネが持ち回りで管理する方法です。シンプルで確実に利用者に連絡先を周知できます。
委託型のコールセンターを利用
近年は外部の24時間コールセンターと提携する方法も広まっています。初期受付を外部に任せ、必要時のみケアマネへ連絡が入る仕組みを取れば、業務負担を軽減しながら基準を満たすことが可能です。
ケアマネにとっての負担と課題
一方で、この24時間連絡体制はケアマネにとって大きな負担となりやすいのも事実です。
- 夜間・休日のオンコールが心身の負担に
- 人員が少ない事業所では当番の偏りが発生
- プライベートとの両立が難しく、離職理由になるケースも
そのため、事業所としては公平なシフト管理や外部委託の活用などで負担軽減を図る必要があります。
利用者・家族への周知の仕方
24時間連絡体制を整備したら、必ず利用者や家族に周知する必要があります。具体的には以下の方法があります。
- ケアプラン交付時に「緊急時連絡先一覧」として明示
- 契約書・重要事項説明書に記載
- 電話番号を記したカードやマグネットを配布
周知が徹底されていないと、実際に緊急時に機能せず、トラブルにつながります。
24時間連絡体制に関連する加算・報酬
介護報酬上、居宅介護支援事業所の「特定事業所加算」や「医療連携加算」などでは24時間連絡体制の有無が評価されます。
つまり、単なる義務としてではなく、報酬面でも事業所にとってメリットがある仕組みなのです。
実務上よくあるQ&A
Q1. 夜中にすぐ駆けつけなければならない?
A. 24時間連絡体制は「連絡が取れること」が要件であり、必ずしも即時訪問を義務づけるものではありません。ただし、状況に応じて適切に対応できる体制が必要です。
Q2. 1人事業所でも対応できる?
A. 可能ですが現実的には困難です。地域包括支援センターや他事業所と連携して、代替体制を組む方法もあります。
Q3. 利用者が増えると負担が増えるのでは?
A. はい。そのため、外部委託やICTツールの導入が現場では進められています。
ICTの活用で負担を軽減
最近は、LINE公式アカウントや専用アプリを用いて利用者からの相談を一元管理する取り組みも出てきました。また、AIチャットボットや録音対応システムを導入し、緊急性を自動振り分けする仕組みを導入している事業所もあります。
ICTの活用は、ケアマネの負担軽減と利用者の安心を両立できる方法として注目されています。
まとめ
「ケアマネ 24時間連絡体制」とは、利用者や家族が安心して在宅生活を継続するために不可欠な仕組みです。
制度上も義務づけられており、報酬面にも影響しますが、ケアマネの負担が大きいという課題もあります。今後は公平な当番体制や外部委託、ICTの活用を組み合わせて、持続可能な仕組みとして整えていくことが求められます。
事業所としては「義務だからやる」ではなく、利用者とケアマネ双方の安心を支える重要な基盤として積極的に整備していくことが大切です。















