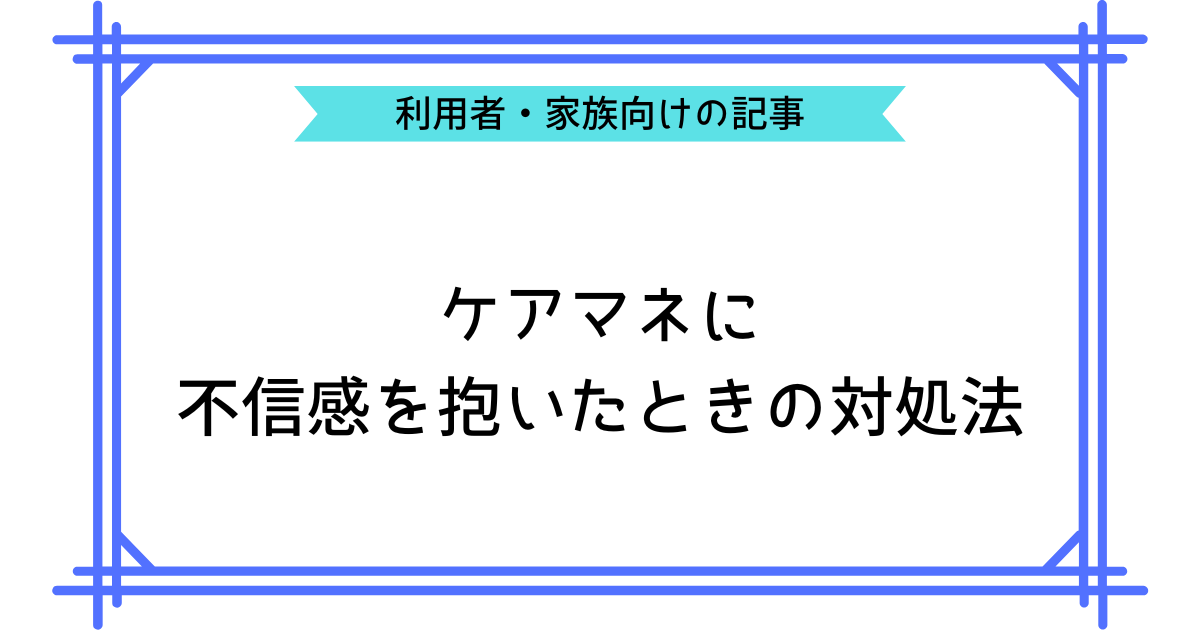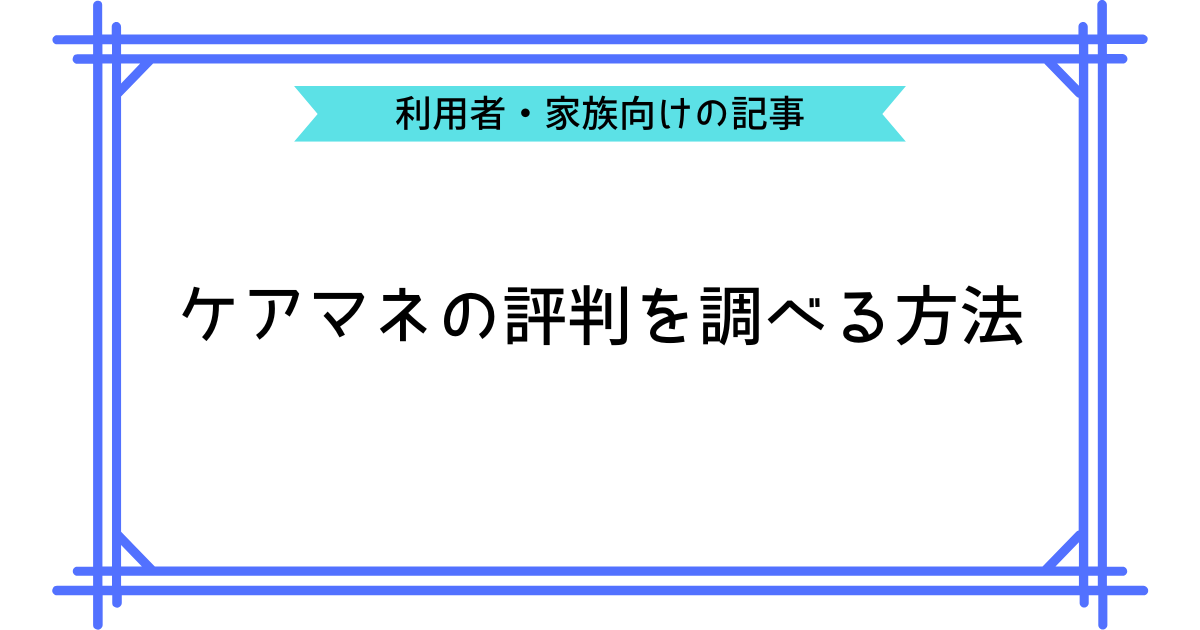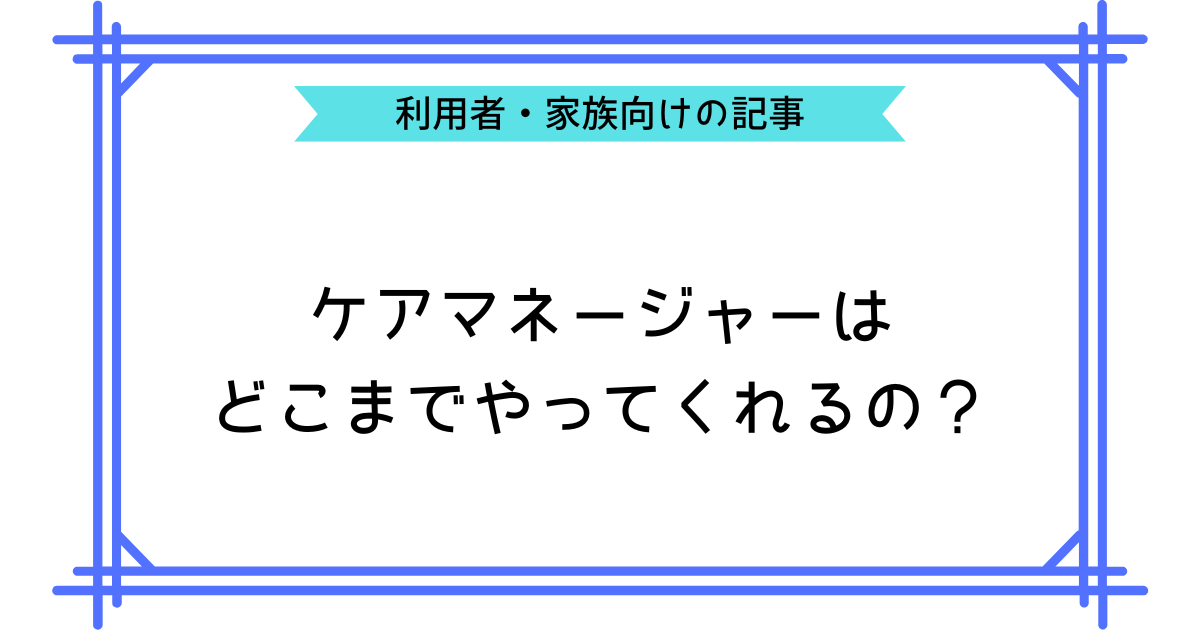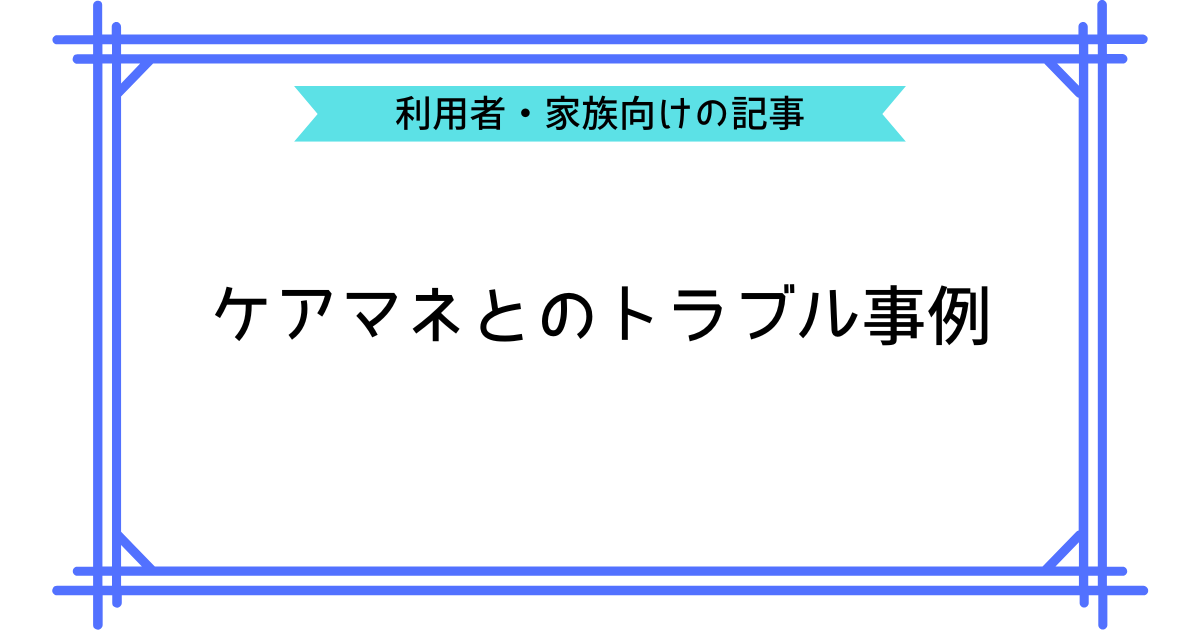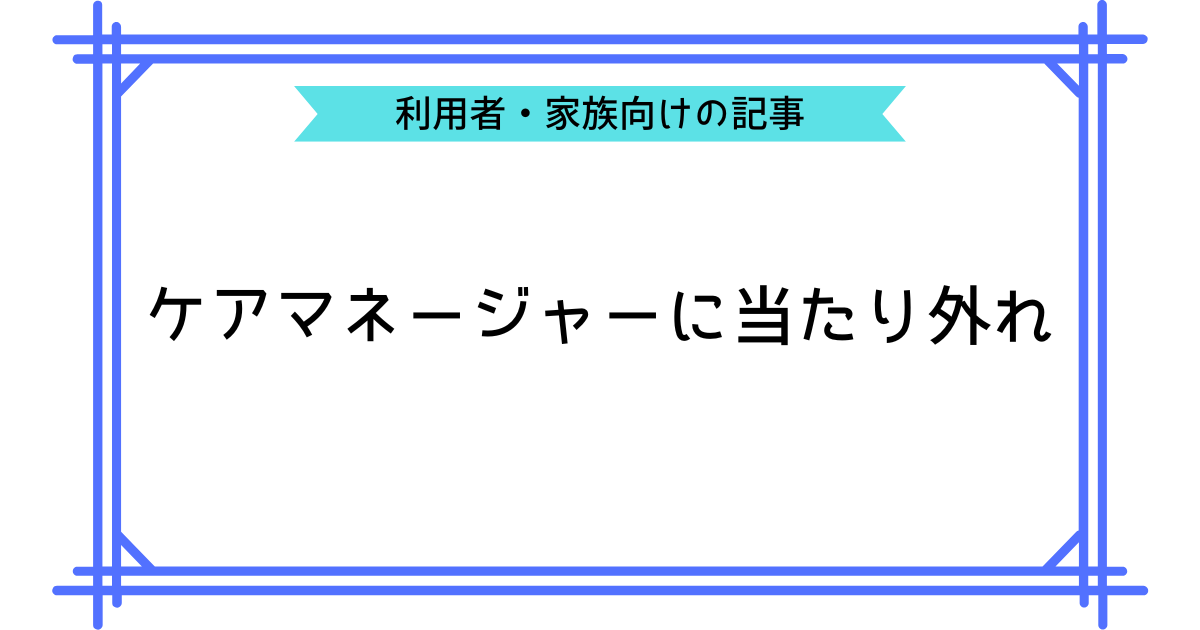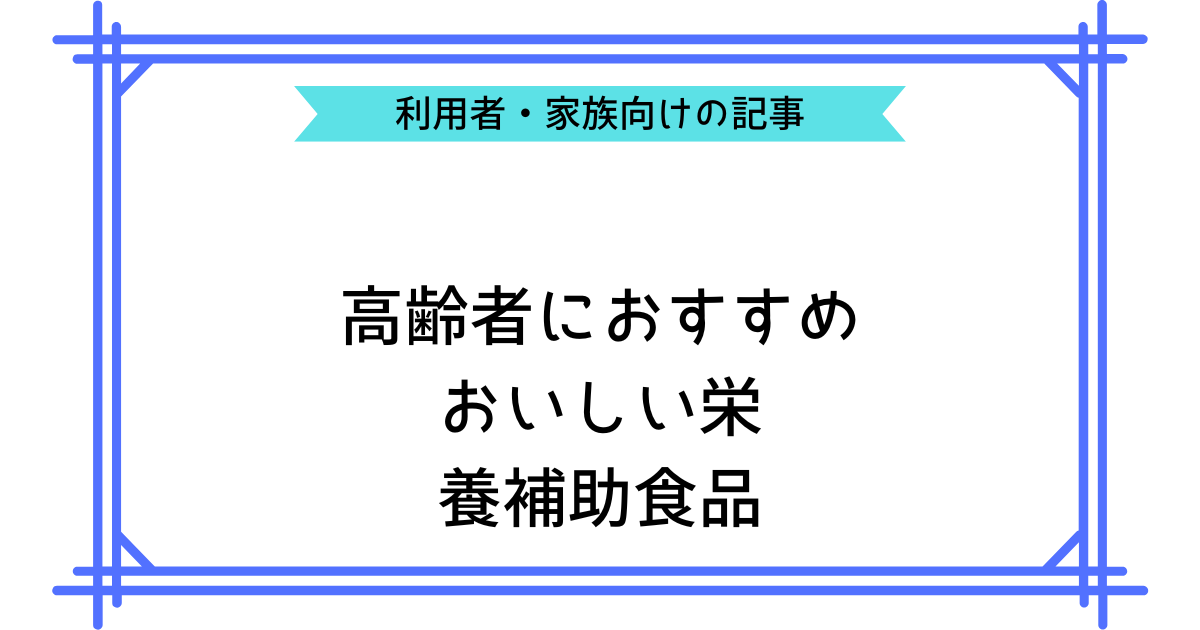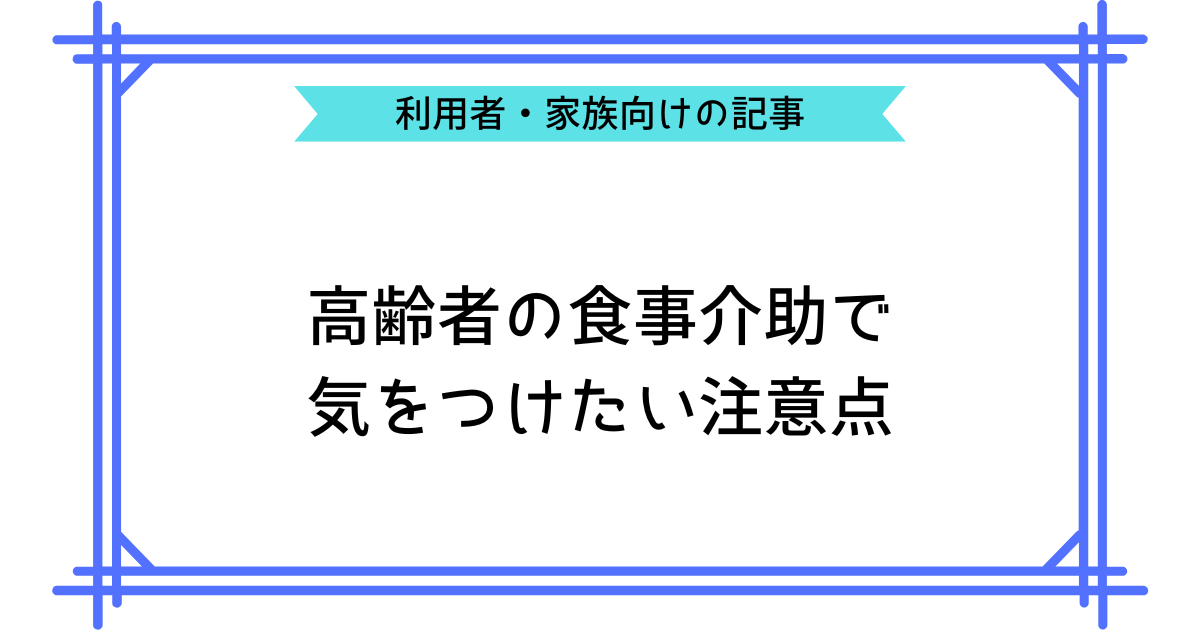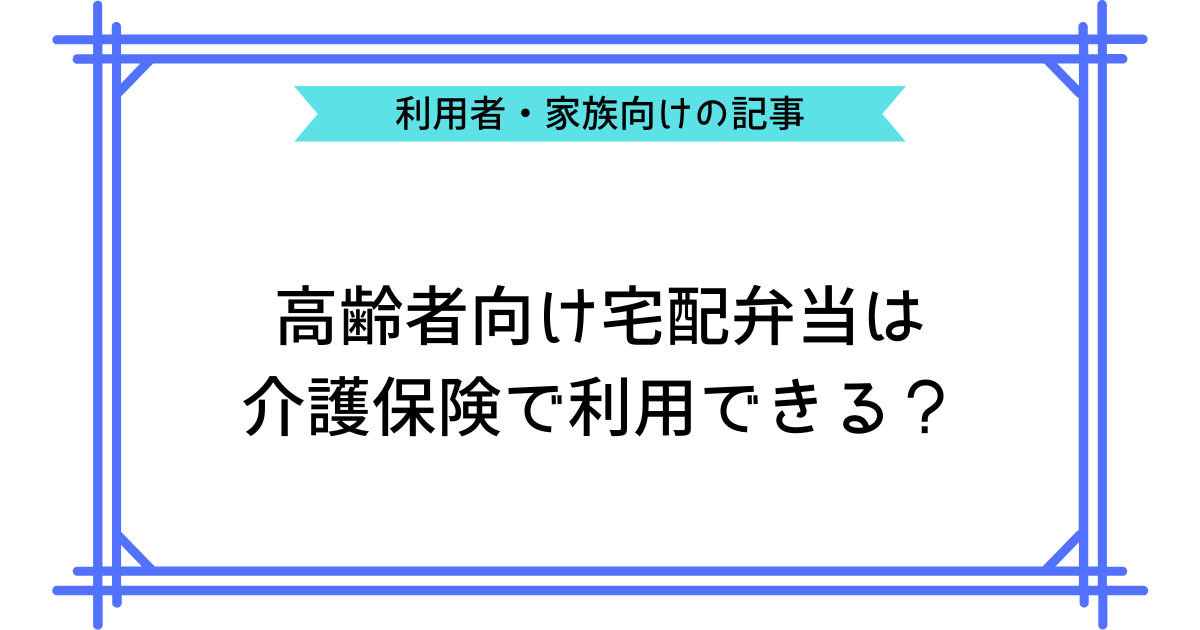認知症の進行を予防する方法を解説|家族が今日からできるケアと生活習慣

「最近、同じ話を何度も繰り返す」「物忘れが増えたような気がする」——
そんな変化に気づいたとき、多くの家族が感じるのが“認知症の進行を少しでも止めたい”という思いです。
認知症は完治が難しい病気ですが、適切な生活習慣と関わり方によって進行を遅らせることは可能です。
実際、介護や医療の現場でも、日常の工夫で生活の質(QOL)を長く保っている人はたくさんいます。
この記事では、
・認知症が進行する仕組み
・進行を遅らせる具体的な方法
・家族ができる関わり方と環境づくり
を、専門的な知識をわかりやすく解説します。
認知症の進行とは?まずは正しく理解することから
認知症とは、「一度獲得した記憶や判断力などの認知機能が、病気によって持続的に低下する状態」をいいます。
原因となる病気の代表はアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などで、徐々に進行していくのが特徴です。
認知症が進行するとどうなるのか
・記憶障害(同じ質問を繰り返す、予定を忘れる)
・判断力の低下(お金の管理、調理などが難しくなる)
・感情の変化(不安、怒りっぽさ、抑うつ)
・生活動作の低下(着替え、食事などに支援が必要になる)
しかし、早期に気づき、生活習慣や周囲の支援を整えることで進行を遅らせることが可能です。
「できることを続ける」「自尊心を保つ」ことが何よりの進行予防になります。
認知症の進行を予防する5つの柱
厚生労働省や専門学会のガイドラインでも、認知症の進行予防には「生活習慣の見直し」と「社会的つながりの維持」が重要とされています。
ここでは、家庭で取り組みやすい5つの柱を紹介します。
1. 脳を刺激する「適度な活動」を続ける
認知症予防で最も有名なのが、脳への刺激です。
新しいことを覚える、体を動かす、会話することで脳の神経細胞が活性化されます。
家でできる脳活アクティビティの例
- 計算・クロスワード・塗り絵などの軽い知的活動
- 料理や裁縫など手を使う作業
- 買い物メモを書く、新聞を音読する
- 家族や友人と会話する
大切なのは「できる範囲で、楽しみながら続けること」。
無理に“訓練”のようにしないことが、長続きの秘訣です。
2. 運動習慣を持つ|脳の血流を良くする
運動は脳への血流を改善し、認知機能の維持に直結します。
特にウォーキングや軽い筋トレは、うつ予防にも効果的です。
おすすめの運動習慣
- 1日30分程度の散歩(朝または夕方)
- ラジオ体操・ストレッチ・椅子体操
- 家事の合間に立ち上がって歩く習慣をつける
無理のない範囲で“体を動かす習慣”を生活の中に組み込むことが重要です。
家族が一緒に歩くことで、会話も生まれ、社会的つながりも保たれます。
3. 栄養バランスを整える|地中海式・和食が効果的
脳の健康を保つためには、食生活の見直しも大切です。
研究では、野菜・魚・オリーブオイルを多く含む「地中海式食事」や、塩分を控えた和食が進行予防に効果があるとされています。
ポイント
- DHA・EPAを含む魚(サバ・イワシなど)を週2回以上
- ビタミンE・ポリフェノールが多い野菜や果物
- 減塩・低糖質を意識
- 甘いお菓子や清涼飲料は控えめに
また、水分不足は脱水やせん妄(意識の混乱)を引き起こすことがあるため、1日1.5リットルを目安に水分補給しましょう。
4. 睡眠と生活リズムを整える
夜更かしや不眠は、脳の疲労回復を妨げ、認知症の進行を早める原因になります。
睡眠中には脳内の老廃物が排出されるため、**良質な睡眠は“脳の掃除”**にもつながります。
睡眠の質を高めるコツ
- 就寝・起床時間を毎日そろえる
- 寝る前のスマホやテレビを控える
- 昼間に日光を浴び、体内時計をリセット
- 夕食後のカフェインは避ける
もし夜中のトイレや不眠が続く場合は、医師に相談して薬の調整を行うのも大切です。
5. 社会とのつながりを持ち続ける
人と関わる機会が減ると、脳の刺激も少なくなり、うつ傾向や認知機能低下を招きます。
家族以外との会話や社会参加を意識的に続けることが、最も自然な脳トレになります。
おすすめの関わり方
- デイサービス・サロン・地域の体操教室に参加
- 近所の人とのあいさつや立ち話を習慣に
- 家族で一緒に買い物・外食・行事に出かける
「人との関わり=脳への刺激」です。
外出や趣味を通じて、社会との接点を持ち続けることが進行予防のカギになります。
家族ができる認知症ケアのポイント
認知症は本人だけでなく、家族にとっても長い時間を共に歩む病気です。
焦らず、安心して過ごせる環境を整えることが、何よりの支えになります。
1. 否定せず、共感する姿勢を持つ
認知症の方は「できない自分」に不安を感じています。
間違いを指摘したり、強く注意したりすると、混乱や不安を助長してしまうこともあります。
「そうなんだね」「一緒にやろうか」など、肯定的に関わることで安心感を与えられます。
「できたことを褒める」「役割を持ってもらう」ことで自尊心を保つことも大切です。
2. 環境を整えて混乱を防ぐ
認知症の進行予防には、わかりやすい・安心できる環境づくりも欠かせません。
- 部屋のレイアウトを頻繁に変えない
- カレンダーや時計を見やすい位置に
- よく使う物の場所を固定する
- 明るい照明で夜間の転倒を防止
「混乱しない生活環境」は、脳へのストレスを減らし、進行を遅らせる効果もあります。
3. 家族自身のストレスケアも忘れずに
介護する家族が疲弊してしまうと、本人への対応も難しくなります。
無理をせず、「相談する・休む・頼る」こともケアの一部です。
- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談
- デイサービスやショートステイを活用
- 家族会やオンラインコミュニティで悩みを共有
介護は「チーム戦」です。家族が笑顔でいられることが、本人の安心にもつながります。
認知症の進行を遅らせる「医療的サポート」も活用しよう
生活習慣の改善だけでなく、医療やリハビリのサポートも有効です。
医療機関で受けられる主な支援
- 薬物療法:進行を遅らせる薬(ドネペジルなど)
- 認知リハビリ:作業療法士・言語聴覚士による訓練
- 訪問リハビリ・デイケア:自宅での活動を支援
早期に主治医やケアマネジャーへ相談し、専門的なサポートを受けることが大切です。
まとめ|「できることを続けること」が進行予防の第一歩
認知症の進行を完全に止めることは難しくても、
「できることを続ける」「安心して過ごす」ことによって、生活の質を大きく保つことができます。
そのために家族ができることは、
- 生活リズムを整え、脳と体を動かす
- 否定せず、安心できる関わりを心がける
- 家族自身も無理せず支援を受ける
認知症と共に生きるということは、「あきらめる」ことではなく、「支えながら暮らしを続ける」ことです。
今日からできる小さな工夫で、明日の笑顔を守りましょう。