ケアマネ支援経過の書き方例文100事例|そのまま使える文例集
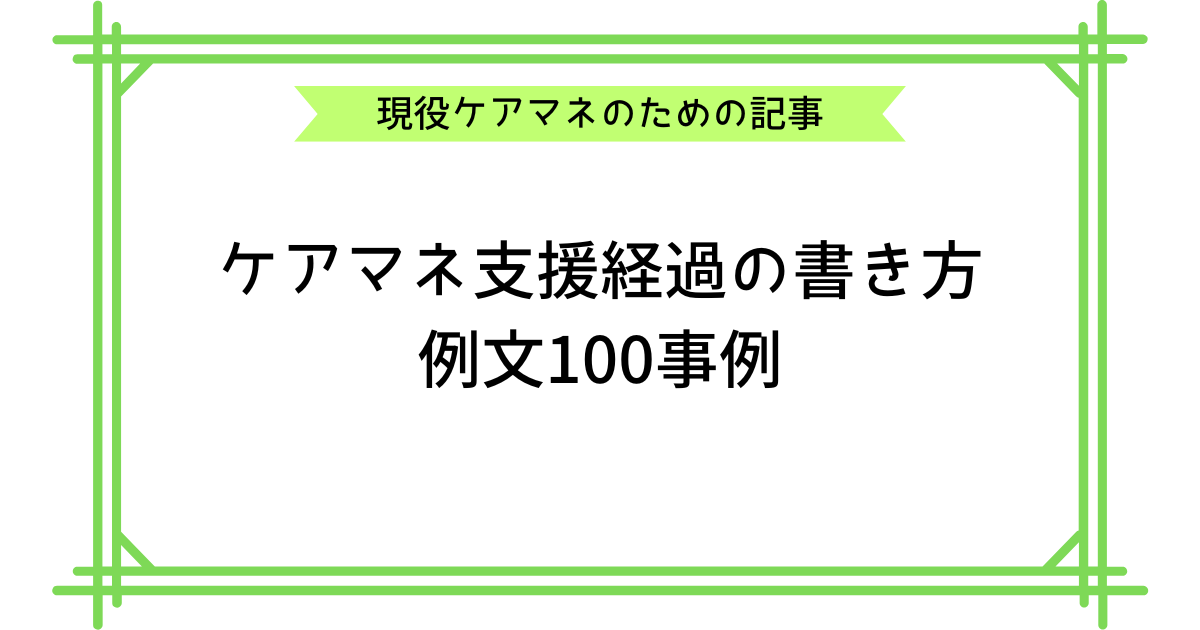
ケアマネジャーとして日々の記録業務の中で、最も悩みやすいのが「支援経過の書き方」です。
利用者の状態やサービス調整内容を正確かつ簡潔に記録する必要がありますが、「どう書けばよいか分からない」「表現が単調になる」と感じる方も多いでしょう。
この記事では、支援経過の基本的な考え方や記載ポイントを解説した上で、実際に現場で使える100の書き方例文をカテゴリー別に紹介します。
すぐにコピー&ペーストして使える実用的な文例集です。
支援経過とは?ケアマネにとってなぜ重要なのか
支援経過とは、ケアマネジャーが利用者に対して行った支援の「経過」を時系列で記録したものです。
ケアプランの実施状況、課題解決の進捗、関係機関との連携内容などを客観的に残すことで、サービスの継続的な改善や第三者評価にも活用されます。
支援経過の目的は単なる「記録」ではなく、支援の根拠を示すことです。
万一のトラブルやクレーム対応の際にも、支援経過がしっかり残っていれば、事実に基づいた説明が可能になります。
したがって、誰が見ても分かる形で簡潔かつ具体的に記録することが求められます。
支援経過の書き方の基本とポイント
支援経過を書く際の基本は「5W1H」を意識することです。
- いつ(When):訪問・連絡した日時
- どこで(Where):訪問先・連絡先
- 誰が(Who):ケアマネ・利用者・家族・サービス事業者など
- 何を(What):行った支援・確認した内容
- なぜ(Why):支援の目的・背景
- どのように(How):対応の方法や今後の方針
また、文体は「です・ます調」ではなく、「〜を確認」「〜と連絡あり」などの記録調が適しています。
例:「利用者より食欲低下の訴えあり。主治医へ情報提供を実施。次回訪問時に再確認予定。」
支援経過の具体的な書き方例文100事例
①モニタリング訪問時の支援経過(10例)
- 利用者宅を訪問。体調良好で食事・排泄・睡眠に問題なし。前回課題の転倒リスクも改善傾向。
- 定期訪問にて、家族より「夜間トイレ時にふらつく」との訴えあり。手すり設置を検討。
- サービス提供後の満足度を確認。「デイサービスが楽しみ」と笑顔あり。
- 血圧安定、服薬管理も適切。訪問看護と情報共有済み。
- ご家族から「ヘルパーの変更希望あり」と連絡。事業所に調整依頼。
- 今週は通所回数を1回増加。利用者の意欲向上がみられる。
- 自宅内移動に不安を訴える。PTに評価依頼予定。
- 食事摂取量が減少傾向。栄養士に相談。
- 定期訪問にて、転倒歴なし。次回モニタリングは2週間後。
- 家族介護の負担増加。レスパイト入所を提案。
②家族対応・相談内容(10例)
- 家族より「介護疲れ」の訴え。ショートステイ利用を提案。
- ご主人より「夜間対応に不安」との相談。夜間巡回型サービスを紹介。
- 娘より「デイサービスの送迎時間を変更したい」と相談あり。事業所と調整。
- 家族より入浴介助に関する悩みあり。福祉用具業者と浴槽台検討。
- 家族より服薬管理の難しさを訴え。訪問看護師と連携。
- 介護保険更新手続きに関する問い合わせあり。方法を説明。
- ご家族が医療同意書の記入に不安あり。主治医へ同行支援。
- 家族からのストレス訴えあり。介護教室の利用を勧めた。
- 長期不在の家族より緊急連絡体制の再確認。
- 今後の在宅継続に不安あり。施設見学を提案。
③サービス調整・連携(10例)
- ヘルパー事業所より訪問時間変更の連絡あり。利用者へ説明済み。
- デイサービス職員より「歩行が不安定」と報告。PTへ共有。
- 通所先で食事拒否あり。栄養士と対応検討。
- 医師より「利尿剤の調整実施」と報告あり。家族に伝達。
- 薬局から「服薬残量が多い」との情報。服薬支援見直しを依頼。
- 訪問看護より「創部状態良好」と報告。処置継続。
- 介護タクシー予約を代行。利用者に確認済み。
- 住宅改修の見積もり提示。家族了承。
- サービス担当者会議日程を調整。参加者全員に通知済み。
- 新規福祉用具導入(歩行器)。効果をモニタリング予定。
④体調変化への対応(10例)
- 発熱(37.8℃)あり。訪問看護に連絡、受診調整。
- 転倒あり。擦過傷のみ。安静を促す。
- 咳嗽続く。主治医へ報告、薬変更。
- 食欲低下が続くため、栄養補助食品導入提案。
- 体重減少(−2kg/1ヶ月)確認。医師に情報共有。
- 下肢浮腫あり。受診を勧めた。
- 排便回数減少。下剤調整依頼。
- 睡眠障害の訴え。生活リズム整備を助言。
- 服薬忘れ頻発。服薬カレンダー導入検討。
- 血圧不安定。測定記録を訪問看護に共有。
⑤サービス担当者会議関連(10例)
- 会議を実施。全員一致で現行プラン継続。
- 医師より在宅継続可能との意見。
- 介護職より夜間転倒リスク指摘。手すり設置を決定。
- 家族からの介護負担軽減希望あり。デイ利用増を提案。
- リハビリスタッフよりADL維持傾向の報告。
- 看護師より「服薬自己管理が困難」と報告。服薬支援強化。
- 新規プラン案を提示。全員了承。
- 次回会議は3か月後に設定。
- 記録を各関係者へ共有済み。
- 議事録作成完了。事業所へ配布。
⑥退院・退所時(10例)
- 病院より退院日決定。訪問看護開始調整。
- 主治医指示書受領。サービス開始準備中。
- 退院前カンファに参加。自宅環境確認。
- ベッド・手すり搬入日を決定。
- 家族へ服薬内容の変更を説明。
- 初回サービス調整完了。ケアプラン交付。
- 退院当日、安定した状態。
- 退院後のフォロー訪問実施。
- デイサービス初利用。笑顔多くみられる。
- 入所先から在宅復帰の相談あり。支援継続。
⑦ 認知症対応の支援経過(10例)
- 訪問時、冷蔵庫に古い食品が多数あり。家族に廃棄を依頼し、ヘルパーの訪問回数を週3回へ増加。
- 利用者が服薬を忘れる場面あり。服薬カレンダーを導入し、訪問時にチェックする体制を整備。
- デイサービスから「帰宅願望強く、午後に落ち着かない様子」と報告あり。環境調整を依頼。
- 夜間徘徊が頻発。玄関にセンサーライトを設置。家族へ注意喚起。
- 同じ質問を繰り返す傾向あり。否定せず共感的に対応し、家族へ説明。
- 日中の不穏行動が増加。訪問看護へ相談、医師と薬剤調整を検討。
- 金銭トラブル発生。通帳管理を家族に一任する方向で合意。
- 記憶低下により食事回数が不明。食事記録表を導入し、デイ職員と共有。
- 掃除が行き届かず衛生状態悪化。環境整備サービスを追加。
- 家族より「感情の起伏が激しい」と相談。介護教室の利用を勧めた。
⑧ 看取り期支援の支援経過(10例)
- 医師より「看取り期に入った」と説明。家族へ情報共有し、今後の方向性を確認。
- 症状緩和のため訪問看護の回数を週3回に増加。家族も了承。
- 食事摂取困難。主治医指示のもと、経口摂取中止。家族へ説明済み。
- 家族より「苦しそうで見ていられない」との訴え。看護師より呼吸状態の説明を行い、安心を促す。
- 夜間も看護体制を強化。オンコール体制を家族へ再確認。
- 訪問時、意識レベル低下を確認。呼吸浅く、看護師へ緊急連絡。
- 家族より「最期まで自宅で過ごしたい」と希望あり。訪問体制を再構築。
- 死後処置について、家族に説明し葬儀社連絡先を確認。
- 永眠確認後、訪問看護より医師へ報告。関係機関へ情報共有。
- 家族より「自宅で看取れてよかった」と感謝の言葉あり。支援終了。
⑨ 金銭・手続き支援の支援経過(10例)
- 公費負担医療証の更新時期を確認し、家族へ案内。申請サポートを実施。
- 高額介護サービス費の申請方法について説明。必要書類を市役所へ提出。
- 利用者本人より「介護保険負担割合証を紛失」との申し出。再発行手続きを支援。
- 家族より「介護保険料の引き落とし口座を変更したい」と相談。方法を説明。
- 負担限度額認定証の有効期限切れを確認。更新申請を同行支援。
- 預金残高不足によりデイ利用料が未払い。家族へ連絡し対応。
- 介護用品購入に関する助成金制度を紹介。申請方法を説明。
- 税控除(医療費控除)について家族より相談あり。必要資料を案内。
- 利用者の金銭管理が困難となったため、成年後見制度の活用を提案。
- 行政より「介護保険負担割合変更」の通知あり。家族へ内容を説明。
⑩ 緊急時対応の支援経過(10例)
- 家族より「転倒して動けない」との連絡。救急搬送を手配し、病院へ同行。
- デイサービスより「発熱38.5℃」との報告。帰宅後に主治医受診を調整。
- 夜間に嘔吐あり。オンコール体制にて看護師が対応。翌朝状態確認。
- 利用者が玄関前で転倒。擦過傷あり、訪問看護で処置実施。
- 電話連絡が取れず安否確認。家族に連絡し、訪問を実施。無事確認。
- 家族より「呼吸が苦しそう」との連絡。救急搬送後、入院。関係機関に報告。
- デイ利用中に血圧上昇。医師の指示で安静・経過観察。
- 通院時に転倒。骨折疑いあり、医療機関へ同行支援。
- 台風接近により訪問中止を判断。代替支援日を調整。
- 施設職員より「意識レベル低下」と連絡。救急対応を指示し、家族へ報告。
支援経過を上手に残すコツ
100事例を見ても分かる通り、支援経過は「観察・報告・判断・対応・今後の予定」の流れで構成されます。
たとえば「〇〇の訴えあり → 関係機関へ報告 → 対応方針を決定 → 今後も経過観察」など、一連の流れが明確であることが重要です。
また、実際の現場では以下のような工夫をすることで、記録業務の効率化が図れます。
- テンプレート化して共通表現を保存
- 事実と感想を分けて記録
- 重要な情報は「誰に」「いつ」「どのように伝えたか」を明確にする
- ケアマネ1人で判断せず、記録を通してチームで共有
まとめ
支援経過はケアマネ業務の「根幹」と言えるほど重要な記録です。
一文一文が支援の証拠であり、利用者の安心とサービスの質を守る役割を果たします。
今回紹介した100事例は、日常業務でそのまま活用できる実用例ばかりです。
ケースに応じて語尾や表現を調整しながら、自分の現場記録に活かしてみてください。















