災害時のケアマネージャーの役割とは?南海トラフ地震などに備えよう!
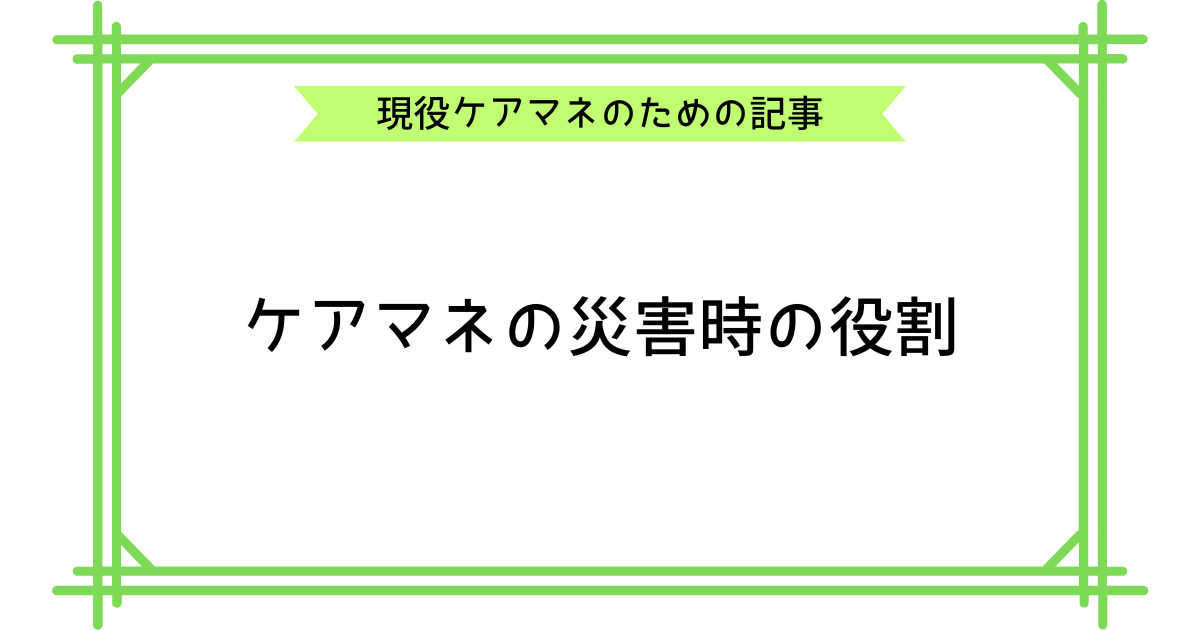
地震や豪雨、台風といった自然災害が全国各地で頻発する中、高齢者や障がい者など要配慮者の命を守る体制づくりがますます重要になっています。
特に「南海トラフ地震」など、甚大な被害が想定される災害に対しては、事前の備えが不可欠です。
この記事では、災害発生時におけるケアマネージャーの具体的な役割と、日ごろからできる備えについてわかりやすく解説します。
災害時におけるケアマネージャーの重要な役割

災害が起きた際、ケアマネージャーは「福祉の最前線」で利用者とその家族を支える存在です。
普段から利用者の生活状況や支援ニーズを把握しているケアマネだからこそ、緊急時にも迅速に動ける役割があります。
安否確認と支援ニーズの把握
災害時、最初に求められるのは「利用者の安否確認」です。電話や訪問を通じて、利用者やその家族が無事かどうかを確認します。また、被災状況や必要な支援(食事、水、医療、福祉用具など)を把握し、自治体や事業所、関係機関と連携して支援につなげる必要があります。
特に独居高齢者や認知症の方は避難が遅れる可能性が高く、優先的な安否確認が求められます。
避難支援のコーディネート
災害時には避難が必要になるケースも多く、避難所での生活は要介護者にとって大きな負担となります。ケアマネは、避難先でどのような支援が必要かを整理し、支援が届くよう情報をつなぐ「コーディネーター」の役割を果たします。
たとえば、オムツや食事の配慮、服薬支援、認知症対応など、避難所での生活をできるだけ安全に、安心して送れるよう関係機関と連携して調整を行います。
支援体制の継続と再構築
被災後は、介護サービス事業所が被災して一時的にサービスが受けられなくなるケースもあります。そのようなときには、代替サービスの手配やケアプランの見直し、利用者の生活再建支援などを行います。
また、仮設住宅への転居や施設入所が必要になる場合には、本人や家族の意向を確認しながら、支援体制の再構築を支えるのもケアマネの大切な役割です。
平時からできるケアマネの「災害対策」

ケアマネージャーが災害時にしっかりと役割を果たすためには、平時からの準備がとても重要です。
ここでは、普段の業務の中でできる災害対策を紹介します。
利用者の「災害時個別支援計画」を作成する
地域によっては、高齢者の避難支援に向けて「災害時要援護者名簿」や「避難行動要支援者登録制度」があります。ケアマネとしては、これらと連動する形で、利用者ごとの災害時対応方法を記した「災害時個別支援計画」を作成することが大切です。
- 誰が安否確認を行うのか
- どの避難所に行く予定か
- 持病や薬、食事制限への配慮
- 連絡先の最新情報確認
などを記載しておくことで、いざというときの対応がスムーズになります。
家族やサービス事業所と情報を共有する
災害時は、ケアマネだけでなく、訪問介護、通所サービス、医療機関、家族などとの連携が不可欠です。そのため、災害対応に関する情報は事前に共有しておく必要があります。
- 家族に避難経路を確認してもらう
- 訪問系サービス事業所に安否確認体制を確認
- 地域包括支援センターや自治体と連携する窓口を把握しておく
といった形で、支援の“チーム力”を高めておくことが求められます。
ケアマネ自身の安否確認体制も確認
災害時、ケアマネ自身が被災して動けなくなる可能性もあるため、事業所内での安否確認ルールや、代替対応のフローを整備しておくことも大切です。BCP(業務継続計画)として、災害時マニュアルを整備しておくことで、組織としても迅速な対応が可能になります。
南海トラフ地震への備えは特に重要
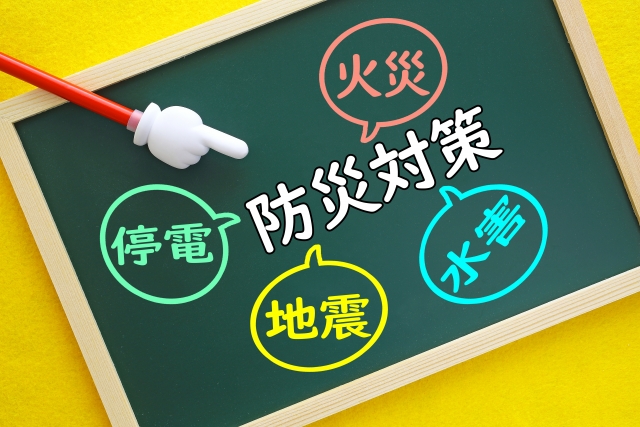
南海トラフ地震は、政府の地震調査研究推進本部によれば、今後30年以内に70~80%の確率で発生するとされています。
太平洋沿岸部を中心に大きな被害が予想されており、特に高齢者人口の多い地域にとっては深刻なリスクです。
ケアマネは、地域の実情に応じた「避難支援」「命を守る計画づくり」を積極的に担うことが求められています。
国や自治体も、福祉専門職との連携強化を進めており、ケアマネ自身の役割の重要性は今後さらに高まっていくと考えられます。
まとめ

災害時におけるケアマネージャーの役割は、「命と生活を守る支援の要」といえるほど重要です。安否確認や避難支援、サービスの再構築など、多くの業務が求められますが、そのすべてが利用者と家族の安心につながる大切な仕事です。
そしてその対応力を高めるためには、平時からの準備と地域との連携が欠かせません。特に南海トラフ地震のような大規模災害が想定される今、ケアマネ一人ひとりが「防災意識」を持ち、日常業務の中で備えていくことが求められます。
「もしも」に備え、「いまできること」を一歩ずつ。ケアマネの災害支援は、地域と命を守る大きな力になります。















