【パクリOK例文あり】ケアプランの長期目標・短期目標を1200例紹介
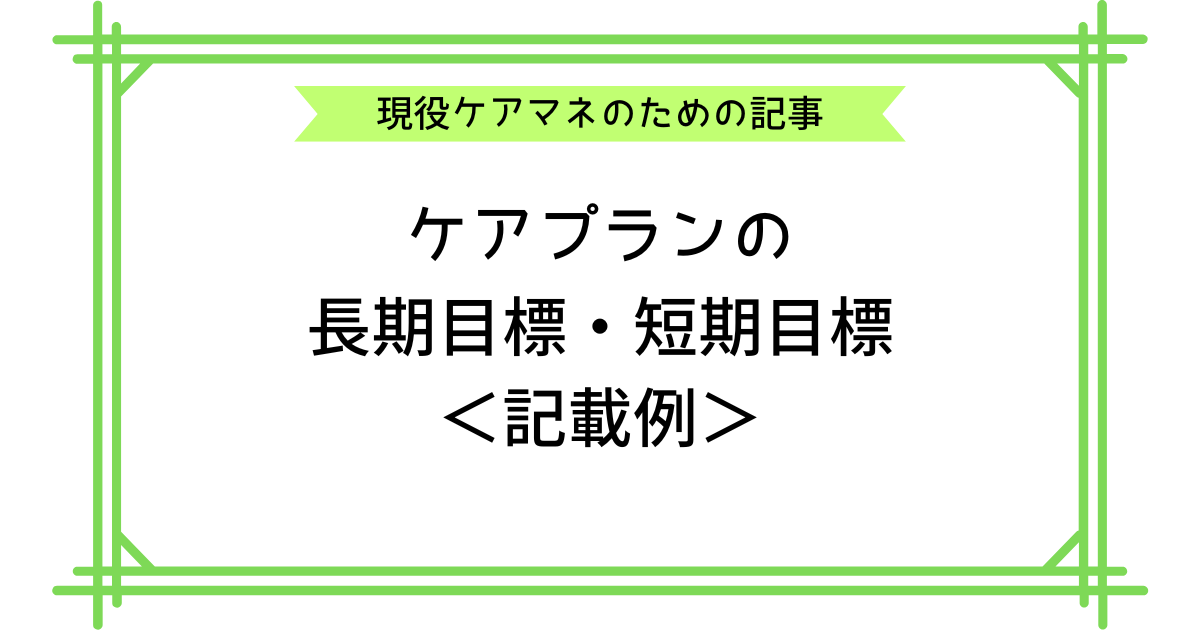
ケアマネジャーがケアプランを作成する際に悩みやすいのが、「長期目標」と「短期目標」の記載です。
表現がワンパターンになってしまったり、利用者の意向をうまく反映できなかったりすることも多いでしょう。
そこで本記事では、居宅サービス計画(ケアプラン)の 長期目標600例・短期目標600例、合計1200例 をまとめました。
ADL維持、認知症支援、医療的ケア、家族支援、社会参加、在宅継続といったカテゴリごとに分けていますので、利用者の状況に合わせてすぐに活用できます。
① 生活全般・ADL維持に関する長期目標(100例)
自宅で安全に生活を続けられるようにする。
住み慣れた地域で安心して暮らし続ける。
転倒なく屋内を移動できるようにする。
入浴・排泄・食事の基本的ADLを維持する。
自立できる部分は本人が継続できるようにする。
家族の支援を受けつつ生活を続けられるようにする。
趣味や余暇活動を楽しみながら生活できるようにする。
日常生活で本人の意思を尊重しながら暮らせるようにする。
家庭内で安心して過ごせるように生活を整える。
生活リズムを安定させて健康を維持する。
孤独感を軽減し、人との交流を保ちながら生活する。
自宅での生活に満足感を持てるようにする。
清潔で快適な住環境を維持できるようにする。
服薬や食事を安定して継続できるようにする。
本人ができる範囲で家事を行えるようにする。
閉じこもりを防ぎ、活動的に過ごせるようにする。
生活に支障がないよう体力を維持する。
安心して睡眠がとれるよう生活リズムを整える。
健康を維持しながら自立した生活を続けられるようにする。
食事・水分をバランスよく摂取できるようにする。
外出時に安全に移動できるようにする。
居室内の転倒を防ぎ、安全に過ごせるようにする。
生活習慣を安定させて健康を守る。
家族と良好な関係を保ちながら生活を続ける。
家事の一部を継続して行えるようにする。
自立を尊重しながら必要な部分を支援する。
安全で衛生的な生活環境を整える。
服薬を正しく継続し、体調を安定させる。
生活上の不安を軽減し安心して暮らせるようにする。
適度な運動を取り入れ、生活体力を維持する。
食事を楽しみながら摂取できるようにする。
外出や社会参加を継続できるようにする。
日常生活の中で自己決定を尊重できるようにする。
家族に頼りすぎず生活を送れるようにする。
生活習慣病の予防に努める。
環境を工夫して自立的に生活できるようにする。
日常生活で事故なく過ごせるようにする。
趣味を継続して生活の質を高める。
生活に楽しみを持ちながら健康を維持する。
体調の変化に応じて柔軟に生活を整えられるようにする。
安心して在宅療養を続けられるようにする。
日常生活に満足感を持てるようにする。
生活動作に必要な筋力を維持する。
生活習慣を安定させ、家族も安心できるようにする。
自立支援を意識しながら生活を続ける。
孤立せず地域と関わりながら生活する。
自分らしい生活を維持する。
生活の中で安全を優先できるようにする。
介護サービスを受けつつ自宅生活を維持する。
住環境を整え転倒リスクを減らす。
生活全般の自立を長く保てるようにする。
社会参加を続けながら生活の質を高める。
睡眠・食事のリズムを整え体調を維持する。
安心して一人暮らしを続けられるようにする。
活動性を高め生活に充実感を持てるようにする。
家庭内で役割を持ちながら生活を続ける。
自己管理力を高め健康維持に努める。
生活で困難を感じた際は支援を受けられるようにする。
栄養状態を維持して体力を保つ。
室内外で安全に移動できるようにする。
災害時にも安心して生活できるように準備する。
生活を通じて健康寿命を延ばす。
本人の意向を尊重し生活に反映する。
家族が安心して支えられるような生活を維持する。
自宅で安心して療養を続ける。
必要な支援を受けつつ生活の質を維持する。
生活の中で喜びを感じられるようにする。
日常生活において事故を防止する。
安全に通院を継続できるようにする。
生活に対する不安を軽減する。
本人の望む生活を継続できるようにする。
地域との交流を保ちながら生活する。
自宅での生活を長く継続できるようにする。
安心して食事をとれるようにする。
住環境を改善し安全性を高める。
家族との関わりを大切に生活を続ける。
自分らしく生活できるように支援する。
必要な介護を受けつつ自立を尊重する。
家庭内で役割を担い生きがいを持てるようにする。
生活リズムを安定させ活動性を維持する。
室内外での活動を安全に行えるようにする。
安心して休息をとれるようにする。
栄養と水分をしっかり摂取できるようにする。
生活を整え介護負担を軽減する。
社会資源を活用しながら生活を続ける。
生活上の課題を解決し安定した生活を送る。
健康的な生活を維持する。
趣味や活動を継続できるようにする。
本人の希望を尊重して生活を支援する。
生活機能を維持し在宅生活を続ける。
安心して家で過ごせるようにする。
生活全般に満足感を持てるようにする。
本人の思いを生活に反映する。
生活リズムを安定させ、健康を守る。
生活の中で達成感を持てるようにする。
家族に支えられながら生活を続ける。
安全な生活環境を保つ。
自立支援を意識し生活を続ける。
生活に喜びを見出せるようにする。
在宅生活を安心して継続する。
本人の意向を尊重し支援方針を立てる。
生活の中で自己決定を大切にする。
① 生活全般・ADL維持に関する短期目標(100例)
手すりを活用して安全に立ち上がれる。
週3回入浴できるようになる。
服薬カレンダーで誤薬なく服薬を継続できる。
ヘルパー支援を受けながら簡単な家事を行う。
日中のベッド上生活を2時間減らす。
週1回は外出し地域とのつながりを保つ。
水分摂取量を増やし脱水を防ぐ。
週2回は買い物に同行し、自分で選べるようにする。
転倒予防体操を継続する。
食事を規則正しく1日3回摂取できる。
服薬を家族と確認しながら実施する。
訪問介護の支援で掃除を行い清潔を保つ。
洗濯を週2回は実施する。
起床・就寝時間を安定させる。
散歩を週3回継続する。
本人が好む家事を1つ継続する。
トイレ動作を介助つきで安全に行う。
日中の活動時間を増やす。
家族と一緒に夕食を準備する。
新聞を毎日読む習慣を継続する。
簡単な調理を1品できるようにする。
服薬チェックを毎食後に実施する。
外出時に杖を正しく使用できる。
買い物リストを作り忘れを防ぐ。
日中はリビングで過ごす。
家事の一部を継続できる。
家族との会話時間を1日30分確保する。
ゴミ出しを週1回行う。
昼寝の時間を1時間以内にする。
水分補給をこまめに行う。
栄養補助食品を活用する。
体操を朝夕2回行う。
入浴を週2回実施する。
ヘルパーと一緒に料理を行う。
ベッドから安全に起き上がれる。
福祉用具を使い移動できる。
服薬を忘れず実施する。
家事を1つ自立して行う。
散歩で近隣住民と交流する。
趣味活動を週1回行う。
外出を月4回実施する。
体重を週1回測定する。
排泄の失敗を減らす。
掃除を週1回実施する。
外食を月1回楽しむ。
服薬支援を受けながら自立を促す。
就寝時間を一定に保つ。
新聞を週5回読む。
洗濯物をたたむ。
趣味活動に参加する。
体操を継続する。
1日2リットル水分を摂取する。
服薬チェックを習慣化する。
安全に通院できるようにする。
日中はベッドで過ごさない。
週3回はデイサービスに参加する。
散歩を20分継続する。
入浴を1人で安全に行えるようにする。
手すりを正しく使えるようにする。
体力測定を実施し維持を図る。
趣味を継続する。
食事を残さず食べる。
週2回は掃除をする。
起床時間を一定にする。
日常生活で事故を減らす。
趣味の園芸を続ける。
テレビ体操を毎日行う。
福祉用具を活用する。
外出時の不安を減らす。
食事内容を日記に記録する。
日中活動を2時間確保する。
服薬ミスを減らす。
就寝時間を22時にする。
週4回は歩行訓練を行う。
体力維持のための運動を継続する。
趣味活動を週2回行う。
食事を家族と一緒に摂る。
新聞を声に出して読む。
外出を週1回行う。
ゴミ出しを1人で行えるようにする。
体重を管理する。
水分摂取を習慣化する。
入浴準備を自分で行う。
日中はベッド以外で過ごす。
趣味を家族と共有する。
外食を楽しむ。
掃除を家族と分担する。
食事を栄養バランスよく摂取する。
日中の活動を増やす。
排泄リズムを整える。
睡眠リズムを安定させる。
服薬を家族と確認する。
散歩を家族と一緒にする。
趣味を週3回行う。
デイサービスで交流する。
水分を意識して摂取する。
掃除を継続する。
新聞を読む時間を作る。
食事を残さず食べる。
外出を増やす。
趣味活動を維持する。
生活に満足感を持つ。
健康を維持する。
② 認知症・精神面に関する長期目標(100例)
安心感を持って在宅生活を継続できるようにする。
認知症の進行に合わせた支援を受けながら生活できるようにする。
不安や混乱を減らし、穏やかに過ごせるようにする。
家族や支援者と良好な関係を維持できるようにする。
見当識を保ちながら日常生活を送れるようにする。
社会的交流を継続し孤立を防ぐ。
介護拒否を減らし、安心してサービスを受けられるようにする。
服薬を正しく継続し、体調を安定させる。
安心できる環境で生活できるようにする。
夜間の不安を軽減し、睡眠を安定させる。
本人の希望を尊重し、できることを続けられるようにする。
介護者との信頼関係を保ちながら生活する。
生活に対する不安を軽減し落ち着いて暮らせるようにする。
認知症の症状があっても自分らしく生活できるようにする。
感情の起伏を穏やかに保ちながら生活する。
生活にリズムを持ち、混乱を減らす。
外出を継続し、社会とのつながりを持つ。
安心できる人間関係を築きながら生活する。
本人が安心できる習慣を維持する。
家族と円滑にコミュニケーションを取れるようにする。
周囲と協力して安心した生活を送る。
社会的孤立を防ぎ、交流を持ち続ける。
介護サービスを受け入れながら生活を続ける。
本人の意思を尊重し生活を支援する。
認知症があっても生活の質を維持できるようにする。
安心して介護を受けられるようにする。
地域との交流を保ちながら生活する。
日中を穏やかに過ごせるようにする。
本人の不安を軽減して生活を安定させる。
介護拒否を減らし穏やかに生活する。
安心して日常生活を続けられるようにする。
家族が安心して支援できるようにする。
認知症に伴う混乱を軽減する。
生活習慣を維持し安定した生活を続ける。
本人が楽しみを感じられる生活を送る。
介護負担を軽減しながら在宅生活を続ける。
穏やかな気持ちで過ごせるようにする。
介護サービスを無理なく受け入れられるようにする。
生活上の危険を減らし安心して暮らす。
自宅で安心して過ごせるようにする。
家族と共に落ち着いた生活を送る。
安心感を得られる環境で生活を続ける。
介護への不安を軽減しサービスを利用できるようにする。
日常生活に喜びを感じられるようにする。
社会参加を維持して生活に張りを持つ。
不穏行動を減らし穏やかに過ごす。
安心して在宅介護を受けられるようにする。
認知症進行に応じて柔軟に生活を整える。
介護者が安心して支えられるようにする。
本人の意向を生活に反映する。
介護サービスを受け入れやすい環境を整える。
感情の安定を維持できるようにする。
不安を抱かず日常生活を続ける。
介護者と協力しながら生活を送る。
安心できる習慣を保ち生活を続ける。
本人が望む生活を維持できるようにする。
夜間の不眠を減らし生活リズムを整える。
穏やかに療養生活を送る。
安心して地域で生活できるようにする。
介護に抵抗なく過ごせるようにする。
本人が笑顔で過ごせる生活を目指す。
生活に落ち着きを持てるようにする。
介護拒否を減らし協力的に生活できるようにする。
本人の不安を和らげ安心して暮らせるようにする。
家族との関わりを大切にしながら生活する。
安心して医療・介護を受けられるようにする。
生活に満足感を持てるようにする。
地域とのつながりを持ち続ける。
介護サービスを活用し安心して生活する。
本人の意志を尊重した生活を送る。
生活の質を保ちながら在宅生活を続ける。
安心して介護を受け入れる。
本人が自分らしく生活できるようにする。
生活に喜びを持ち続けられるようにする。
介護者が無理なく支援できるようにする。
社会との関わりを保ちながら生活する。
不安を減らし安定した生活を送る。
介護を受け入れ生活に安心感を持つ。
本人が安心して暮らせる生活を続ける。
日常生活に落ち着きを持ち続ける。
介護サービスを活用して穏やかに過ごす。
認知症があっても安心して生活できるようにする。
介護拒否を減らしスムーズに支援を受ける。
家族の支援を受けつつ生活を続ける。
本人の安心感を優先して生活を整える。
生活に笑顔を増やせるようにする。
日常生活で混乱を減らす。
介護サービスを自然に受け入れられるようにする。
安心して自宅生活を続ける。
本人の思いを生活に反映する。
不穏行動を減らして落ち着いた生活を送る。
生活習慣を維持し混乱を防ぐ。
介護拒否を軽減して協力的に支援を受ける。
本人が安心できる生活を送る。
社会交流を継続し孤独を防ぐ。
介護サービスを通じて安心して暮らす。
日常生活に穏やかさを保つ。
本人の希望を尊重し生活を支える。
家族が安心して介護できるようにする。
安心した生活を続ける。
認知症が進行しても安心できる生活を整える。
② 認知症・精神面に関する短期目標(100例)
デイサービスに週2回参加し社会交流を持つ。
服薬を家族と一緒に確認し忘れを防ぐ。
夜間の不眠を軽減するため就寝時間を一定にする。
介護者の声かけで安心して生活できる。
同じ質問を繰り返しても穏やかに対応する。
日課を整理し混乱を減らす。
日中の活動を増やし夜間の睡眠を安定させる。
日記を活用し予定を忘れないようにする。
服薬カレンダーを使って誤薬を防ぐ。
安心できる人と会話する機会を増やす。
不安を感じた際に落ち着ける工夫を取り入れる。
デイサービスで趣味活動に参加する。
訪問介護で服薬確認を行う。
家族と一緒に買い物に行く。
日常生活の中で安心できる習慣を維持する。
夜間の徘徊を防ぐため見守りを導入する。
介護サービスを拒否せず受け入れる。
週1回は地域サロンに参加する。
本人の不安を和らげる声かけを行う。
介護者の説明を理解できるよう繰り返す。
夜間トイレに誘導して転倒を防ぐ。
食事を一緒に摂って安心感を持たせる。
訪問看護で健康状態を確認する。
予定をホワイトボードに記録する。
日中の活動時間を増やす。
短時間の外出を継続する。
趣味を週2回継続する。
不安が強い時は音楽を聴いて落ち着く。
介護サービスに慣れるため短時間から利用する。
家族と会話の時間を持つ。
服薬を毎回確認して行う。
不穏行動が見られた際は声かけで落ち着ける。
夜間の不眠を減らすため環境を整える。
社会的交流を週2回持つ。
生活リズムを一定に保つ。
趣味活動で達成感を得る。
外出を継続し孤立を防ぐ。
家族の支援を受けながら生活する。
介護サービスを無理なく受け入れる。
日常生活で安心できるよう支援する。
デイサービスで会話を楽しむ。
介護拒否を減らす。
家族と協力して生活を送る。
日課を繰り返し伝える。
外出時に付き添いを受ける。
安心できる空間で過ごす。
予定を繰り返し説明して理解を促す。
短時間の散歩を行う。
本人の不安を軽減する声かけを続ける。
デイサービス利用で生活リズムを整える。
服薬を1日3回確認する。
日常生活で混乱を減らす。
夜間の安全を確保する。
安心感を持って生活できる。
趣味を通じて気分転換を図る。
日中の活動を意識的に増やす。
介護サービスに慣れる。
本人の希望を尊重する。
食事を楽しく摂る。
短時間の会話を毎日持つ。
見守りを導入する。
地域交流に参加する。
夜間の徘徊を減らす。
本人の安心を優先する。
介護者と一緒に予定を確認する。
趣味活動を維持する。
外出を週1回行う。
介護サービスを受け入れる。
日課を繰り返す。
不安を軽減する工夫を行う。
介護者と共に生活する。
日中は外で過ごす。
睡眠を安定させる。
服薬を確実に行う。
不安を減らす。
趣味活動に参加する。
家族との会話を増やす。
社会交流を続ける。
安心できる環境で生活する。
不穏行動を減らす。
予定を確認する。
家族の支援を受ける。
介護拒否を減らす。
生活に喜びを持つ。
地域との交流を維持する。
介護サービスに慣れる。
本人の希望を尊重する。
生活習慣を安定させる。
安心して外出する。
日課を整理する。
介護者と協力する。
社会参加を続ける。
趣味を楽しむ。
不安を軽減する。
介護サービスを受ける。
生活リズムを整える。
安心感を持つ。
家族と交流する。
生活に満足感を持つ。
本人の思いを尊重する。
③ 医療的ケア・健康管理に関する長期目標(100例)
糖尿病を適切に管理し、合併症を予防しながら生活を続ける。
高血圧を安定させ、脳卒中などのリスクを減らす。
心疾患の悪化を防ぎ、安全に在宅生活を継続する。
在宅酸素療法を適切に行い、呼吸状態を安定させる。
服薬を正しく継続し、体調を維持する。
医療機関との連携を保ちながら安心して療養生活を送る。
感染症を予防し、健康を維持する。
褥瘡を予防し、清潔で快適な生活を送る。
終末期を穏やかに在宅で過ごせるようにする。
嚥下障害による誤嚥を防ぎ、安全に食事を続ける。
慢性疾患と向き合いながら生活の質を保つ。
服薬副作用を予防し、安全に治療を続ける。
退院後も安定した体調で生活を続ける。
栄養状態を維持し、体力の低下を防ぐ。
痛みを軽減し、日常生活を快適に送る。
がん治療を継続し、生活の質を維持する。
通院を継続して健康を保つ。
医師の指示に従い療養生活を続ける。
自宅で安心して医療的ケアを受ける。
終末期でも本人の意思を尊重した療養を行う。
インスリン管理を確実に行い血糖値を安定させる。
心不全による息切れを予防し生活を維持する。
呼吸困難を和らげ、安心して在宅生活を送る。
透析治療を継続し安定した生活を送る。
慢性腎不全の進行を抑え健康を維持する。
薬剤師や看護師と連携し、安全な服薬管理を行う。
医療依存度が高くても安心して在宅療養できるようにする。
発作や急変時に迅速に対応できる体制を整える。
安定した睡眠を確保し、体調を整える。
食事制限を守り健康を維持する。
栄養補助食品を活用し体力を保つ。
慢性的な便秘を改善し快適に生活する。
下痢や脱水を防ぎ健康を守る。
服薬を誤らず生活に取り入れる。
痛みをコントロールし生活の質を高める。
医療機器を安全に使用し生活を続ける。
褥瘡予防を徹底し皮膚を健康に保つ。
退院後の体調悪化を防ぐ。
在宅点滴を安全に継続できるようにする。
医療と介護の連携を維持して生活を支える。
血糖コントロールを安定させる。
精神的安定を維持し健康を保つ。
健康チェックを定期的に行い体調を整える。
通院や検査を計画的に行う。
医療機関との連携で安心感を持って生活する。
服薬の飲み忘れを防ぎ体調を維持する。
治療を継続し生活の質を保つ。
本人の希望を尊重した医療ケアを行う。
介護と医療を調和させ安心した生活を支える。
慢性疾患があっても自宅で過ごせるようにする。
感染症流行時にも健康を維持する。
安定した呼吸状態を維持する。
血圧をコントロールし安心した生活を送る。
嚥下機能を保ち安全に食事を続ける。
脱水を防ぎ健康を維持する。
定期的に検査を受け体調を管理する。
在宅療養を家族と共に安心して継続する。
健康への不安を軽減する。
副作用のリスクを減らす。
リハビリを取り入れて体力を維持する。
医師の指導に従い治療を継続する。
在宅で緩和ケアを受けながら穏やかに過ごす。
生活の中で健康を意識できるようにする。
発作のリスクを減らし安心して暮らす。
症状の悪化を防ぎ生活を安定させる。
家族と協力して健康を維持する。
必要な時に医療支援を受けられるようにする。
治療に対する理解を深め安心して受け入れる。
通院を無理なく継続できるようにする。
体調変化に気づき早めに対応できるようにする。
医療的ケアを自然に生活に取り入れる。
自己管理を意識しながら生活する。
健康を維持し趣味活動を続けられるようにする。
病状の進行を遅らせる。
家族が医療ケアを理解し安心して支えられるようにする。
必要な医療機器を活用して生活する。
在宅療養を本人らしく継続できるようにする。
体調不良を早期に把握し対応する。
服薬を確実に行う。
定期通院を継続し安定した生活を送る。
医療と介護を調和させて支援する。
医療依存度が高くても生活を維持する。
健康管理を継続できるようにする。
生活の中で健康への意識を持ち続ける。
慢性疾患に向き合いながら安心して暮らす。
食事制限を守り健康を保つ。
水分摂取を継続して脱水を防ぐ。
生活において健康を優先する。
医療職の支援を受けながら生活する。
体調に合わせた生活を続ける。
本人の意思を尊重した医療支援を行う。
健康を維持して在宅生活を続ける。
治療と生活を両立させる。
安定した体調で日常生活を送る。
医療機関と連携して生活を支える。
安心して医療的ケアを受ける。
本人と家族が医療に理解を持つ。
生活に医療ケアを自然に取り入れる。
健康を守り自宅での生活を続ける。
③ 医療的ケア・健康管理に関する短期目標(100例)
血糖測定を毎日行う習慣をつける。
血圧を毎朝測定して記録する。
服薬を1日3回確実に行う。
服薬カレンダーを活用して誤薬を防ぐ。
訪問看護師と連携して体調を確認する。
水分摂取を1日1.5リットル以上確保する。
体温を毎日測定し記録する。
通院予定を家族と共有し忘れを防ぐ。
服薬副作用に注意し記録を残す。
医師の指示を受けて血糖を管理する。
週に1回体重測定を行う。
定期的に検査を受ける。
夜間の呼吸状態を確認する。
皮膚状態を毎日確認し褥瘡を予防する。
咳や痰の状態を記録する。
排泄状況を記録して体調を把握する。
インスリン注射を忘れず行う。
食事内容を記録し栄養を管理する。
服薬を家族が確認する。
定期的に血液検査を受ける。
咳や呼吸苦の有無を確認する。
水分補給を1日8回行う。
排便リズムを整える。
睡眠時間を毎日記録する。
服薬時間を一定に保つ。
訪問看護で創部の観察を行う。
食事をバランスよく摂取する。
外来受診を忘れず行う。
医師の指示に従い食事制限を守る。
感染予防のため手洗いを徹底する。
マスクを使用し感染症予防を行う。
医療機器を正しく使用する。
排尿の状態を毎日確認する。
排便状況を記録する。
服薬管理を習慣化する。
睡眠を安定させるため環境を整える。
水分を1日2リットル摂取する。
栄養補助食品を活用する。
食事時間を一定に保つ。
定期的にストレッチを行う。
リハビリを週3回実施する。
血圧の変動を記録する。
食欲の状態を確認する。
訪問看護で体調をチェックする。
家族と体調を共有する。
服薬チェックリストを使う。
脱水を防ぐため飲水を促す。
夜間のトイレ回数を記録する。
食事を残さず摂る。
水分補給を促す声かけを行う。
外来受診を忘れないようにする。
服薬の副作用を観察する。
排便を週3回以上確保する。
褥瘡予防の体位変換を行う。
ストレスを減らす工夫をする。
睡眠環境を整える。
手洗いを1日5回行う。
体重を週2回測定する。
呼吸状態を家族と共有する。
咳や痰の状態を毎日確認する。
排泄後の清潔を保つ。
食事を規則的に摂取する。
服薬時間を守る。
訪問看護師の指導を受ける。
感染予防を徹底する。
睡眠時間を7時間以上確保する。
体力を維持する運動を行う。
呼吸リハビリを実施する。
排尿を観察する。
便秘を改善する。
水分補給を毎時間行う。
医師の指示を守る。
外来検査を忘れない。
体調変化に気づいたら記録する。
服薬確認を1日3回行う。
食事を栄養バランスよく摂る。
手洗い・うがいを習慣化する。
体重の増減を管理する。
排便日誌をつける。
水分摂取を促す。
血糖を毎食後測定する。
睡眠時間を安定させる。
リハビリを継続する。
服薬を必ず確認する。
発熱時に医師へ連絡する。
脱水予防のゼリーを摂取する。
家族が服薬を見守る。
食事量を記録する。
便秘予防のため繊維質を摂る。
感染症流行時に外出を控える。
体調不良を早期に共有する。
訪問看護で異常を確認する。
服薬を正しく実施する。
医師の指示書を守る。
生活の中に体調管理を組み込む。
体重を管理し健康を維持する。
水分を十分に摂る。
呼吸状態を安定させる。
体調を意識して生活する。
服薬忘れをなくす。
栄養補助を継続する。
健康管理を習慣にする。
④ 家族支援に関する長期目標(100例)
家族が心身ともに健康を保ちながら介護を継続できるようにする。
介護負担を軽減し、家族の生活を守る。
介護と仕事を両立できるようにする。
介護と育児を両立できるようにする。
介護による疲労を減らし、安心して支援できるようにする。
家族の休養時間を確保し、心身を整える。
介護方法を学び、適切に支援できるようにする。
家族間で介護を分担し、負担を減らす。
介護ストレスを軽減し、家庭内の雰囲気を穏やかにする。
家族が自信を持って介護を行えるようにする。
介護者が安心して外出できるようにする。
介護者が孤立しないようにする。
介護者の健康状態を維持する。
介護を通じて家族関係を良好に保つ。
介護を続けても家族の生活が破綻しないようにする。
介護に伴う経済的負担を軽減する。
介護方法に関する知識を深める。
介護の不安を減らし安心感を持てるようにする。
介護者が安心して眠れるようにする。
介護と社会参加を両立できるようにする。
介護経験が浅い家族が安心して支援できるようにする。
家族全体で協力して介護を継続する。
介護者の体力を維持し、無理なく介護を行う。
家族の希望を尊重しながら支援を調整する。
介護に関する相談先を確保する。
介護者が安心して休養できる体制を整える。
介護で生活が制限されないようにする。
介護負担を軽減し家族が笑顔で過ごせるようにする。
家族の気持ちを尊重し介護を支える。
介護者の生活リズムを守る。
介護と就労のバランスを取れるようにする。
介護に対する家族の不安を減らす。
介護を無理なく続けられるようにする。
介護に必要な支援を活用できるようにする。
家族の生活を守りながら介護を行う。
介護によるストレスを適切に発散できるようにする。
介護負担を感じすぎず生活できるようにする。
介護による睡眠不足を防ぐ。
介護による健康被害を防ぐ。
介護に対する理解を深める。
介護と趣味活動を両立できるようにする。
家族の生活を豊かに保つ。
介護で家庭不和が起きないようにする。
介護を通じて家族が安心感を持つ。
介護に協力的な体制を整える。
介護負担を軽減して在宅生活を続ける。
介護に伴う不安を共有できるようにする。
介護と学業を両立できるようにする。
介護に対する相談先を持つ。
介護に伴う孤立を防ぐ。
介護に対して前向きに取り組めるようにする。
介護で家庭生活が破綻しないようにする。
介護と休養のバランスを取る。
介護に関して家族が協力的になる。
介護を続けても安心できる生活を保つ。
介護者が支援を受け入れられるようにする。
介護によるストレスを軽減する。
介護で家庭内の関係を良好に保つ。
介護を続けても健康を維持する。
介護に伴う経済的負担を減らす。
介護に関する理解を深める。
介護を通じて家族が成長する。
介護に前向きに取り組めるようにする。
介護に協力する人を増やす。
介護の負担を分散させる。
介護と仕事の両立を可能にする。
介護による不安を減らす。
介護に伴う疲労を軽減する。
介護と地域活動を両立する。
介護によるストレスを家庭内で共有する。
介護に伴う孤独を防ぐ。
介護と生活のバランスを取る。
介護者が安心して医療職と連携できるようにする。
介護者の理解を深める。
介護の継続に自信を持てるようにする。
介護を続けても生活に満足感を持つ。
介護で家庭不和を防ぐ。
介護に関する情報を得られるようにする。
介護者が安心して相談できるようにする。
介護と自己実現を両立できるようにする。
介護で家族が疲弊しないようにする。
介護に対する家族の理解を深める。
介護者が前向きに生活できるようにする。
介護に対する支援体制を強化する。
介護者が支援を拒まないようにする。
介護と経済の両立を支える。
介護に関する相談を定期的に行えるようにする。
介護で家族関係を悪化させない。
介護に対する協力体制を強める。
介護で無理をしすぎないようにする。
介護に対するストレスを軽減する。
介護を通じて家族が支え合えるようにする。
介護に伴う孤独感を減らす。
介護に関する不安を解消する。
介護を続けても家族全体で安心できるようにする。
介護に伴う体調不良を予防する。
介護に対して前向きになれるようにする。
介護負担を軽減し家族が元気に暮らせるようにする。
④ 家族支援に関する短期目標(100例)
ショートステイを月2回利用して介護者の休養を確保する。
デイサービス利用時に家族が休養時間を持つ。
介護方法をヘルパーから学ぶ。
訪問看護時に家族が介護方法を確認する。
介護負担を軽減するため週3回訪問介護を導入する。
介護に関する相談を月1回行う。
介護者が睡眠をしっかり取れるよう支援する。
介護者が食事をゆっくり摂れるようにする。
介護者の通院時間を確保する。
介護に関する情報提供を月1回行う。
介護ストレスを軽減するため相談窓口を利用する。
介護者が安心して外出できるようにする。
介護の分担を家族内で話し合う。
介護と就労を両立する方法を検討する。
介護ストレスを発散できる活動を行う。
介護者の趣味時間を確保する。
介護方法を週1回確認する。
介護負担を減らすため訪問介護を利用する。
介護者が安心して眠れる環境を整える。
介護について家族で相談する時間を持つ。
介護者がストレスを軽減できるよう相談を活用する。
介護の協力体制を整える。
介護ストレスを日記に記録して振り返る。
介護者の体調を毎週確認する。
介護と学業を両立できるように調整する。
介護者の健康状態を把握する。
介護ストレスを軽減する工夫を取り入れる。
介護方法を毎月見直す。
介護者の休養日を作る。
介護方法を家族全員で共有する。
介護と家事を分担する。
介護に関する相談先を確認する。
介護ストレスを和らげる趣味活動を行う。
介護負担を減らすサービスを導入する。
介護方法を専門職に学ぶ。
介護者が週に1回休養できるようにする。
介護と生活を両立できる工夫をする。
介護ストレスを軽減する運動を取り入れる。
介護について地域包括に相談する。
介護者が安心して過ごせる時間を持つ。
介護に関する本を読む。
介護方法を家族で復習する。
介護者の体調を見守る。
介護負担を軽減する方法を試す。
介護についての情報を整理する。
介護者が1日30分自分の時間を持つ。
介護と仕事の両立を工夫する。
介護負担を共有する。
介護ストレスを軽減するリフレッシュ時間を作る。
介護者が外出できる時間を確保する。
介護と休養を両立する。
介護負担を減らすためにヘルパーを活用する。
介護ストレスを相談で発散する。
介護者の生活を守る。
介護者が安心して過ごすために休息を取る。
介護負担を軽減する工夫を取り入れる。
介護ストレスを週1回振り返る。
介護者の健康を守る。
介護負担を軽減する体制を整える。
介護方法を専門職から学ぶ。
介護者が安心して生活できるようにする。
介護と生活のバランスを取る。
介護ストレスを共有する。
介護者が前向きになれる時間を作る。
介護に対する相談を継続する。
介護方法を毎週復習する。
介護者が安心して休養できる。
介護ストレスを軽減する工夫を学ぶ。
介護者の生活をサポートする。
介護と趣味を両立できるようにする。
介護ストレスを日常で発散する。
介護者の休養を計画的に取る。
介護者の健康チェックを行う。
介護ストレスを相談で減らす。
介護者の自立を尊重する。
介護者が安心して医療職と連携できるようにする。
介護者が介護方法を実践する。
介護と学業を調整する。
介護ストレスを軽減する工夫を見直す。
介護者の体調を支援する。
介護負担を減らす。
介護者が安心して趣味を続ける。
介護ストレスを記録し対応を考える。
介護者が外出できるように調整する。
介護者の希望を尊重する。
介護と家族生活を両立する。
介護負担を分散する。
介護者が安心できる支援体制を整える。
介護ストレスをケアマネに相談する。
介護者が前向きに生活できるようにする。
介護に対して無理をしないようにする。
介護者が笑顔で生活できるようにする。
介護負担を見直す。
介護者の健康を守るため休養を確保する。
介護者の相談先を増やす。
介護ストレスを共有できるようにする。
介護者が無理なく介護できるようにする。
介護者が安心して支援を続けられるようにする。
⑤ 社会参加・生活の質向上に関する長期目標(100例)
地域活動に参加し、生きがいを持って生活できるようにする。
趣味活動を継続し、日常生活に喜びを感じられるようにする。
友人や近隣住民との交流を維持し、孤独感を減らす。
家族や孫との交流を楽しみ、生活に張りを持つ。
地域行事に参加し、社会とのつながりを維持する。
ボランティア活動を継続し、自分の役割を持つ。
趣味を通じて日常生活に活力を持つ。
地域サロンへの参加で社会性を維持する。
友人との関係を維持し、会話や交流を楽しむ。
買い物や外出を継続して社会参加を続ける。
家庭内で役割を担い生活に充実感を持つ。
文化活動や趣味活動を継続する。
近所とのつながりを維持する。
本人の望む趣味を継続する。
外出の機会を維持して生活に刺激を持つ。
社会的孤立を防ぎ、生活の質を保つ。
本人の希望を尊重し、生活に取り入れる。
地域活動を通じて生活に喜びを持つ。
世代を超えた交流を楽しむ。
地域との関係を保ちながら生活する。
趣味を継続して達成感を得る。
家族と共に外出を楽しむ。
旅行など本人の希望を実現する。
日常的に社会との接点を持つ。
地域包括と関わりを持つ。
本人が望む活動を尊重して継続する。
趣味を継続して生活に張りを持つ。
地域交流を通じて孤立を防ぐ。
本人の意向を尊重した活動を支援する。
趣味や活動を通じて生活に彩りを持つ。
社会参加を続けて生活の質を高める。
家庭内で役割を担い自己肯定感を高める。
活動を通じて心身の健康を維持する。
地域行事に参加し生活に張りを持つ。
本人の希望を優先して活動を支える。
社会資源を活用して交流を続ける。
友人との交流を維持する。
外出を習慣化して生活を楽しむ。
活動を通じて心の安定を得る。
趣味を深め生活に満足感を持つ。
地域交流を維持して孤独を防ぐ。
文化活動に参加して生活を楽しむ。
本人の望む役割を継続する。
社会参加を維持して自立を促す。
交流を通じて安心感を得る。
趣味や活動を生活の一部にする。
本人が喜びを感じる活動を続ける。
家庭内で役割を果たし生活に意欲を持つ。
地域交流で人との関わりを保つ。
活動を通じて孤立を予防する。
社会参加を続けて生活に刺激を持つ。
趣味活動を通じて自己表現をする。
外出機会を持ち生活を楽しむ。
本人の希望に沿った活動を支える。
地域活動を継続し社会とつながる。
活動を通じて健康を維持する。
趣味を継続して達成感を持つ。
社会との関わりを維持する。
友人との会話を続ける。
家庭内で役割を持ち意欲を維持する。
趣味を続けて心身の活性化を図る。
地域交流で安心感を持つ。
活動を通じて気分転換を図る。
趣味を通じて生活の質を向上する。
本人の希望を生活に反映する。
社会参加を続けて生活を支える。
地域とのつながりを保つ。
趣味や文化活動を継続する。
本人の意向に沿った社会参加を支援する。
生活に喜びを持てる活動を行う。
地域活動に積極的に参加する。
本人が望む外出を続ける。
社会的孤立を防ぐ。
活動を通じて家庭外の交流を保つ。
趣味を通じて生活を充実させる。
本人の意志を尊重して活動を行う。
外出習慣を維持する。
趣味活動を通じて心の健康を保つ。
地域の集まりに参加する。
社会参加を維持して自己実現を図る。
家庭内で役割を持ち生活を整える。
本人が望む趣味を続ける。
交流を通じて不安を減らす。
活動を生活の中に取り入れる。
趣味活動で生活の質を高める。
社会参加を続けて安心感を得る。
友人との交流を通じて孤立を防ぐ。
本人の意向を尊重して生活を支える。
趣味や文化活動を日常に取り入れる。
活動を通じて心身の安定を維持する。
本人が希望する外出を支援する。
地域との交流を続ける。
社会参加を継続し自立を支える。
生活に喜びを持ちながら暮らす。
本人の望む役割を果たす。
地域活動を続けて生活に張りを持つ。
趣味活動を通じて笑顔を増やす。
社会とのつながりを深める。
家庭内で意欲的に役割を担う。
本人の希望を尊重した活動を続ける。
⑤ 社会参加・生活の質向上に関する短期目標(100例)
週1回は地域サロンに参加する。
月2回は趣味活動に参加する。
週3回は散歩を行い地域住民と交流する。
孫と月2回は遊ぶ時間を持つ。
週1回は買い物に出かける。
月1回は友人と外出する。
趣味の作品を月1つ仕上げる。
地域行事に参加する。
週1回は外出して社会との接点を持つ。
デイサービスで趣味活動に参加する。
友人と電話で週1回会話する。
家庭内で役割を担う。
週1回は料理を作る。
外出の機会を月4回持つ。
趣味活動を週2回続ける。
月1回は家族と外食を楽しむ。
地域活動に参加する。
週1回は図書館に行く。
週2回は散歩をして近隣と交流する。
趣味活動を家族と共有する。
友人と交流する時間を作る。
デイサービスで作品を作る。
外出習慣を維持する。
月1回はイベントに参加する。
趣味活動を週3回行う。
外出して地域住民と交流する。
孫と遊ぶ時間を持つ。
週1回は園芸を行う。
趣味を通じて達成感を得る。
週1回は友人と会う。
地域包括の活動に参加する。
趣味を週2回継続する。
週1回は手工芸を行う。
外出を習慣化する。
月2回は地域活動に参加する。
週1回は外出先で交流する。
趣味を通じて気分転換を図る。
週1回は料理を作る。
月1回は友人に会う。
外出を家族と一緒に行う。
趣味を週2回楽しむ。
地域サロンに参加する。
外出時に地域住民と交流する。
趣味の展示会に参加する。
外出を月3回行う。
週1回は地域活動を行う。
友人と交流を持つ。
趣味を継続する。
月1回は映画を観に行く。
週2回はデイサービスに参加する。
外出の機会を継続する。
趣味を家族と共有する。
週1回はカラオケを楽しむ。
外出習慣を持つ。
月2回は地域交流に参加する。
趣味を継続して行う。
外出を月4回続ける。
週1回は作品を完成させる。
地域交流を継続する。
趣味を通じて会話を増やす。
週1回は友人と食事をする。
月1回は買い物に出かける。
週2回は散歩を続ける。
趣味活動を週3回維持する。
外出の頻度を増やす。
友人と交流する機会を増やす。
趣味を家族と共有する。
地域活動に月1回参加する。
週1回は交流を持つ。
外出を習慣化する。
趣味を続ける。
月1回は親族と集まる。
週2回は外出を行う。
趣味を通じて楽しみを持つ。
週1回は絵を描く。
地域サロンに定期参加する。
趣味活動で達成感を得る。
週3回は外出する。
趣味を週2回続ける。
外出習慣を週1回持つ。
地域交流に参加して孤立を防ぐ。
週2回は友人と会う。
外出を継続する。
趣味を楽しむ。
週1回は音楽活動を行う。
外出を通じて交流する。
趣味を週3回維持する。
地域活動を通じて交流を増やす。
週1回は地域イベントに参加する。
外出を通じて気分転換する。
趣味を家族と一緒に楽しむ。
週1回はデイサービスで活動する。
外出機会を週2回持つ。
趣味を通じて生活を豊かにする。
週3回は散歩する。
外出を月2回行う。
趣味を週1回行う。
地域活動を月2回参加する。
週1回は友人と会話する。
外出を継続し社会とのつながりを保つ。
趣味を家族と楽しむ。
⑥ 在宅継続・施設入所検討に関する長期目標(100例)
本人の希望に沿ってできる限り在宅生活を継続する。
住み慣れた自宅で安心して療養生活を続ける。
在宅生活を継続できる支援体制を整える。
将来的な施設入所も視野に入れながら在宅を優先する。
家族と共に在宅生活を続けられるようにする。
地域資源を活用しながら在宅療養を継続する。
医療と介護が連携した在宅生活を維持する。
本人の意思を尊重し、終末期も自宅で過ごせるようにする。
在宅での療養を安心して続ける。
施設入所を希望する場合に備え準備を行う。
在宅生活を安全に継続する。
家族の介護負担を軽減しながら在宅を維持する。
在宅で自立した生活をできる限り続ける。
緊急時に対応できる体制を整える。
施設入所が必要になった際に円滑に移行できるようにする。
在宅での生活を安心して長く続ける。
医療ニーズがあっても在宅で過ごす。
介護と医療を組み合わせ在宅生活を維持する。
在宅での生活に本人の希望を反映する。
施設入所を検討する際も本人の意向を尊重する。
在宅療養を最期まで継続できるようにする。
施設との連携を取りながら在宅を優先する。
在宅生活を維持しつつ必要時に施設を活用する。
地域包括と連携し在宅を支える。
在宅で安心して介護を受ける。
本人と家族が納得して生活を選べるようにする。
施設入所を含め選択肢を持ち安心して生活する。
在宅での生活を長く継続する。
家族が安心して在宅介護を続けられるようにする。
本人の希望を最優先して在宅を支える。
施設入所を回避しながら在宅を続ける。
終末期を自宅で迎えることを目指す。
在宅療養を安心して行う。
地域の支援を受けながら在宅を続ける。
本人が望む生活を在宅で実現する。
施設入所の準備を家族と共に進める。
在宅でできる限り過ごす。
家族支援を強化し在宅を継続する。
医療依存度が高くても在宅を維持する。
本人の希望を大切に生活を整える。
在宅と施設の両立を考え柔軟に対応する。
在宅生活に安心感を持てるようにする。
施設入所を検討する際に混乱を防ぐ。
在宅を継続するために福祉用具を活用する。
介護者の負担を軽減し在宅生活を守る。
在宅療養を無理なく継続する。
地域とつながりながら在宅を続ける。
在宅療養を最期まで支える。
施設と連携して在宅生活を補完する。
本人の生活の質を保ちながら在宅を続ける。
家族が安心して介護できるようにする。
在宅と施設の選択肢を持ち柔軟に対応する。
本人が納得して生活できるようにする。
施設を利用しても本人の希望を尊重する。
在宅生活を支える体制を強化する。
在宅と施設の両立を検討する。
本人の希望を叶える生活を維持する。
在宅で安心して介護を受ける。
家族の希望を尊重しながら在宅を続ける。
在宅生活を継続する準備を整える。
施設入所の選択を本人と共有する。
在宅で生活を続ける意欲を持ち続ける。
本人の希望を最期まで支える。
施設入所を検討する場合に備える。
在宅療養を地域で支える。
在宅を維持するために多職種と連携する。
本人と家族が安心して暮らせるようにする。
在宅生活を長期的に支える。
施設と在宅を行き来できるようにする。
在宅を続けながら施設も検討する。
地域包括と協力して在宅を支える。
本人の意向を尊重して支援する。
施設入所に移行する際の混乱を防ぐ。
在宅生活を安心して続けるため支援する。
在宅療養を最優先に考える。
本人が希望する生活を叶える。
施設を含めた選択肢を広げる。
在宅生活をできる限り長く維持する。
在宅を支えるために制度を活用する。
家族と相談しながら生活を選択する。
本人の安心感を大切にする。
在宅療養を地域と共に支える。
在宅生活を本人らしく続ける。
施設入所を検討する時期を見極める。
在宅での安心を最優先にする。
本人と家族が納得する生活を支援する。
施設入所を無理なく進める。
在宅療養を長く続ける。
地域資源を活用して在宅を維持する。
在宅生活を本人の希望通りに続ける。
施設入所を検討する際に安心して選べるようにする。
在宅で最後まで過ごせるようにする。
⑥ 在宅継続・施設入所検討に関する短期目標(100例)
緊急通報装置を導入し安心して生活する。
週2回の訪問介護を導入して在宅を支える。
ショートステイを月1回利用して家族負担を軽減する。
訪問看護を週1回導入し健康管理を行う。
福祉用具を導入して安全を確保する。
通所介護を週2回利用して生活リズムを整える。
家族と施設入所の可能性を話し合う。
災害時の避難方法を確認する。
緊急連絡体制を整える。
地域包括に相談して支援体制を確認する。
在宅医療を導入して健康を維持する。
訪問介護で家事援助を受ける。
デイサービスで交流を持つ。
ショートステイの利用を体験する。
施設見学を行い選択肢を広げる。
訪問リハビリを導入して体力を維持する。
通所リハビリを利用する。
家族と介護の分担を話し合う。
在宅療養計画を確認する。
訪問看護で服薬を確認する。
訪問診療を導入して医療を安定させる。
緊急時の対応方法を家族と共有する。
施設パンフレットを取り寄せる。
在宅生活に必要な制度を確認する。
通所サービスを週3回利用する。
訪問介護を増やして在宅を支える。
在宅療養に必要な物品を準備する。
施設入所を検討する時期を話し合う。
在宅生活を安心して続ける工夫を行う。
訪問看護を増やして医療管理を行う。
ショートステイを利用して家族の休養を確保する。
通所介護を継続利用する。
在宅を支える制度を活用する。
施設の見学日を設定する。
緊急連絡先を整備する。
在宅療養に必要なケアを導入する。
通所サービスで生活を整える。
家族の負担を軽減する方法を話し合う。
訪問リハビリを週1回行う。
通所リハビリを週2回行う。
施設入所の準備を家族と始める。
訪問介護で掃除を支援する。
緊急通報システムを試用する。
在宅療養に必要な情報を集める。
施設入所について本人の意向を確認する。
在宅医療と介護の連携を確認する。
訪問介護を継続して利用する。
通所介護で活動を増やす。
在宅療養の課題を見直す。
家族と定期的に話し合う。
施設入所に必要な書類を確認する。
訪問看護で健康状態を確認する。
ショートステイを調整する。
通所リハビリで体力を維持する。
施設入所について説明を受ける。
在宅生活に必要な改修を検討する。
緊急連絡網を作成する。
在宅療養の不安を相談する。
施設利用の体験を行う。
訪問介護で調理を支援する。
通所介護を利用して交流を持つ。
在宅療養に必要な支援を整える。
施設入所について情報を集める。
訪問看護を週2回利用する。
在宅生活を安心して続ける工夫を行う。
通所サービスを増やす。
ショートステイで介護者の休養を確保する。
施設入所の候補を決める。
在宅を支える制度の利用を開始する。
訪問リハビリを導入する。
通所リハビリで運動を行う。
施設入所を検討する話し合いを行う。
訪問介護を利用して排泄を支援する。
在宅生活を安心して続ける準備をする。
施設利用の費用を確認する。
緊急対応の手順を整える。
在宅療養を支援する。
通所介護を利用して活動を増やす。
施設入所を視野に入れた計画を立てる。
訪問看護を導入する。
在宅生活の安全対策を強化する。
通所サービスを利用して生活を支える。
施設の候補を見学する。
在宅療養を続ける支援を強化する。
ショートステイを利用する。
訪問介護を増やす。
通所リハビリを導入する。
施設入所の相談を地域包括に行う。
在宅療養の体制を整える。
家族と施設利用の話し合いをする。
訪問看護を増やす。
在宅生活を安心して継続する。
通所サービスを続ける。
施設入所の準備を進める。
在宅療養を安全に行う。
ショートステイを調整する。
訪問介護を利用する。
通所介護を継続する。
施設入所に向けた情報収集を行う。
在宅生活を支援する体制を整える。
緊急通報装置を整える。
施設利用を体験する。
在宅生活を守るため支援する。















