ケアプランは押印廃止でOK?署名だけで可能?徹底的に分かりやすく解説
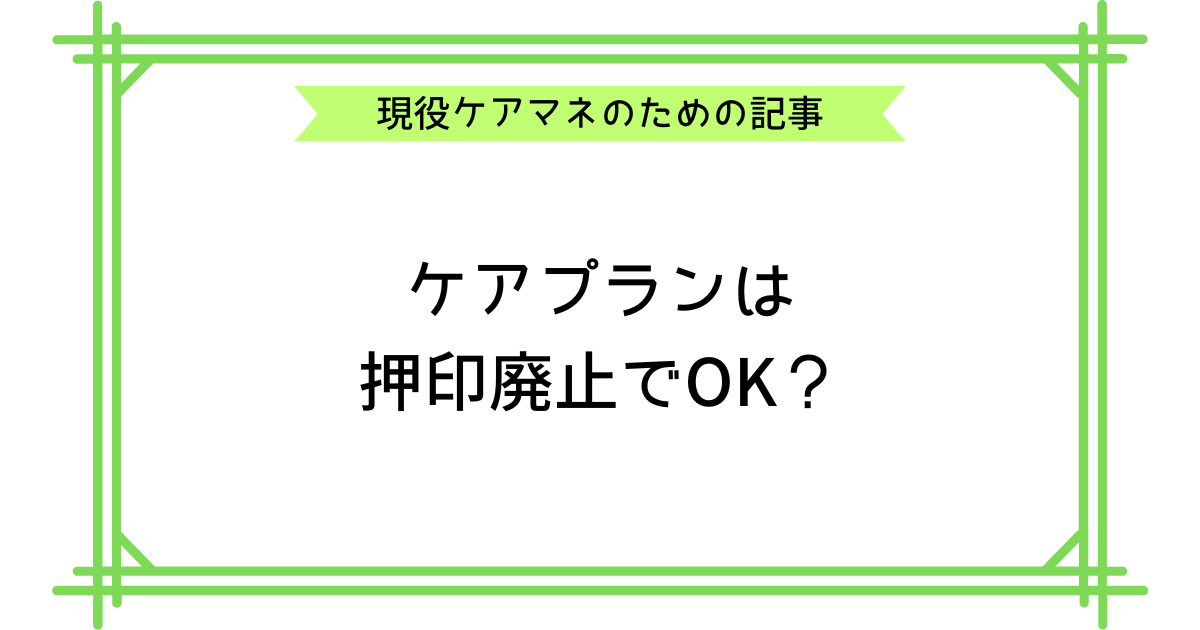
2021年度以降、介護分野では「押印の見直し」と「電磁的な説明・同意」の原則解禁が進み、ケアプラン(居宅サービス計画書)をはじめ多くの書類で押印は原則不要になりました。
さらに、署名も“代替手段”があれば求めないことが可能とされ、電子署名、メール・SMS・録音記録などで同意の事実を残せば足りる、という運用が認められています。
ただし、自治体(保険者)や法人の内規で「署名は引き続き求める」等のローカルルールが残る場合があるため、現場ではその確認と“証跡の残し方”が実務の肝になります。
本稿では、法令・通知の根拠、OK/NGライン、電子同意の残し方、監査で揉めない記録例までを一気通貫で解説します。
結論:押印は原則不要。署名も“代替手段”があれば不要にできる——ただしローカル運用は要確認
2021年の見直しでは、①書面での説明・同意等は電磁的記録での対応を原則認める、②利用者の署名・押印は求めないことが可能(その場合は代替手段を明示し、様式例から押印欄を削除)——と厚労省が明確化しました。
したがって、ケアプランへの押印は原則不要、署名もメール・電子署名・録音等の代替手段を提示・実施できるなら省略可能です。
いっぽうで、自治体QA等で「署名は従来どおり必要(押印は不要)」と運用する例もあるため、貴事業所の所在自治体・法人ルールは必ず確認しましょう。
制度の根拠と経緯:押印見直し→報酬改定→電磁化へ
- 押印見直しの省令改正(令和2年12月公布)で、厚労省は“押印を求める手続”の原則見直しを実施。介護分野でも押印廃止の方向が示されました。
- 2021年度 介護報酬改定で、利用者への説明・同意の電磁的対応を原則容認、署名・押印は求めないことが可能と明示され、様式例から押印欄を削除する扱いが提示されました。
- 以後、契約・同意の電子化や標準様式の見直しが進展。2023年以降も周知・普及が図られ、自治体様式でも押印・署名欄の見直しが促されました。
どの書類が「押印不要」になったの?
ケアプラン(居宅・施設サービス計画)、重要事項説明書、各サービス計画書、サービス担当者会議の記録、利用票・提供票系など、介護分野で慣習的に押印していた多くの書類が見直し対象です。
厚労省は「国が定める様式・添付書類には押印又は署名欄は設けないことを基本」と周知し、自治体側にも見直しを求めています。
実務では、自治体や法人が示す様式に合わせつつ、押印なしでも“本人確認の代替手段”を確実に残すことがポイントです。
注意:自治体が独自様式を持つ場合や、事業者の契約書の扱いは法人裁量が残る余地があります(例:押印不要だが署名は引き続き要とする自治体QA)。最終判断は必ず保険者の最新通知・QAで確認を。 大阪市
「署名なし」で同意を残す代替手段(電子化の具体)
1) 電子署名・タブレット手書き署名
利用者(家族)の電子署名やタブレット画面への手書きサインで同意を取得。電磁的記録での交付・保存が原則認められているため、紙の押印に代替できます。電子署名の提供事業者や介護ソフトの署名機能を活用すると、タイムスタンプ・改ざん防止等の証跡も同時に確保しやすいのが利点です。
2) メール・SMS・LINE等による同意記録
説明資料(PDF等)を送付し、「内容確認・同意」の返信(日時・送信者アカウントが特定できること)をもって同意とみなす方法。返信はそのまま保存し、計画書・モニタリング記録に紐づけましょう。
3) 電話同意(録音・記録)
やむを得ず対面・電子署名が難しい場合は、電話での説明・同意でも可。誰が/いつ/何を説明し/どの点に同意を得たかを「モニタリング」や「担当者会議記録」に残し、可能なら録音データも保管。同意に至る過程が追跡可能であることが重要です。
4) 会議記録やケアプラン本文への明記
サービス担当者会議の「結論」欄や第1表「総合的な援助の方針」末尾に「利用者・家族に説明し、同意を得た(取得方法:電子署名/メール返信等)」と具体的に記載。交付方法(紙/PDF)と日付も併記すれば監査での説明がスムーズです。
自治体・法人の“ローカル運用”で押さえるべき3点
- 自治体QA・通知の最新確認
自治体によっては「署名は必要(押印は不要)」と整理している例があります(大阪市QA)。自事業所の所在市町村の取扱いを必ず一次情報で確認。 大阪市 - 法人内規・契約書の改訂
法人の重要事項説明書・契約書で署名・押印の扱いが古いままのケースがあります。押印欄の削除、電子同意の規定、**代替手段(メール等)**の明記を。 - “本人確認”の代替設計
署名・押印を外すほど、**本人確認のプロセス設計(誰が・いつ・どう記録するか)**が問われます。**標準手順書(SOP)**を作り、職員間でばらつきをなくすのが実地指導対策の近道です。
監査・実地指導で揉めないための「記録の黄金ルール」
- 説明した証跡:説明者・日時・媒体(対面/オンライン/電話)・提示資料(v◯.◯PDF等)
- 同意の証跡:電子署名画像/メール返信スクショ/録音メモ(ファイル名と保存場所)
- 交付の証跡:紙手交/PDF送付(送付ログ)/ポータルDL履歴
- 紐づけ:ケアプランの作成年月日・同意取得日・交付日を一致させ、モニタリングにも同じ用語・日付で記載
- 再同意の基準:本格的な変更(目標・方針・サービス種の追加/廃止・大幅な回数変更)は再説明・再同意。軽微な変更は代替手段での同意記録で可(自事業所の基準書で基準化)。
よくある質問(FAQ)
Q1. ケアプランは「署名なし・押印なし」で本当に大丈夫?
条件付きで可能です。厚労省は署名・押印を求めないことが可能と明示し、代替手段の明示と電磁的な説明・同意・交付を原則容認しました。自治体や法人の運用差があるため、最新のローカルルールは必ず確認してください。
Q2. うちの自治体は「署名は要・押印は不要」と言っています。従うべき?
はい。自治体QAに従って署名は確実に取得し、押印は求めない運用で問題ありません。電子署名やタブレットサイン、メール返信など電子的署名も可としている自治体が多いです。 大阪市
Q3. 「軽微な変更」のたびに署名が必要?
代替手段での同意記録(メール・電話記録・会議記録への明記等)で足ります。ただし、プランの骨格が変わる本格変更は再説明・再同意を原則に。基準は事業所SOPに明文化しましょう。
Q4. 紙で交付しなくても大丈夫?
利用者等の事前承諾があれば、電磁的交付(PDF等)が原則認められます。相手の閲覧環境(スマホ・PC)や希望を事前確認し、紙を希望される方には紙で交付しましょう。
実務テンプレート:同意取得の文面(そのまま使えます)
1) メールでの同意依頼テンプレ
件名:居宅サービス計画書(第1表〜第7表)同意のお願い
本文:◯◯様
平素よりお世話になっております。◯◯居宅介護支援事業所です。
本メールに、最新の居宅サービス計画書(PDF)を添付いたしました。内容をご確認のうえ、**「内容を確認し、同意します」**とご返信ください。
※紙での交付をご希望の場合はその旨ご返信ください。
(担当:◯◯/連絡先:◯◯)
→ 返信メール(日時・送信者)が同意の証跡。計画書・モニタリングへ「◯年◯月◯日 メール同意取得」の記載を。
2) 電話での口頭同意・記録テンプレ
【記録例】
2025/09/03 14:10〜14:20/説明者:CM田中
介護保険最新計画(第1〜7表)内容・目標・サービス種・回数・負担額を説明。本人◯◯様・長男◯◯様が内容に同意。交付:PDFメール送付(本日)。再質問なし。
→ 可能なら通話録音。録音の有無・保存先を記録末尾に追記。
3) ケアプラン本文への明記例
【第1表末尾】
本計画について、◯年◯月◯日、本人・家族へ説明し同意を得た。同意取得手段:電子署名(タブレット)/交付方法:PDF送付(同日)。問い合わせ先:◯◯居宅(担当◯◯)。
→ 担当者会議記録の**「結論」「次回開催時期」**にも整合的に記載。
失敗しない運用フロー(チェックリスト)
- 自治体・法人の最新方針(署名要否・電子可否)を確認
- 同意取得手段を選択(対面署名/電子署名/メール/電話)
- 説明資料を一本化(PDF版・紙版の整合)
- 日時・説明者・同意者のログ化(台帳・ソフトの履歴)
- 交付の証跡(手交/送信ログ/DL履歴)を保存
- ケアプラン・会議記録・モニタリングへ同一用語・同一日付で追記
- 軽微/本格変更の基準表を職員周知(再同意の要否が一目で分かる)
- 年次で棚卸し(テンプレ更新、職員研修、監査想定の模擬点検)















