【コピペOK】ポータブルトイレのケアプラン文例200事例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
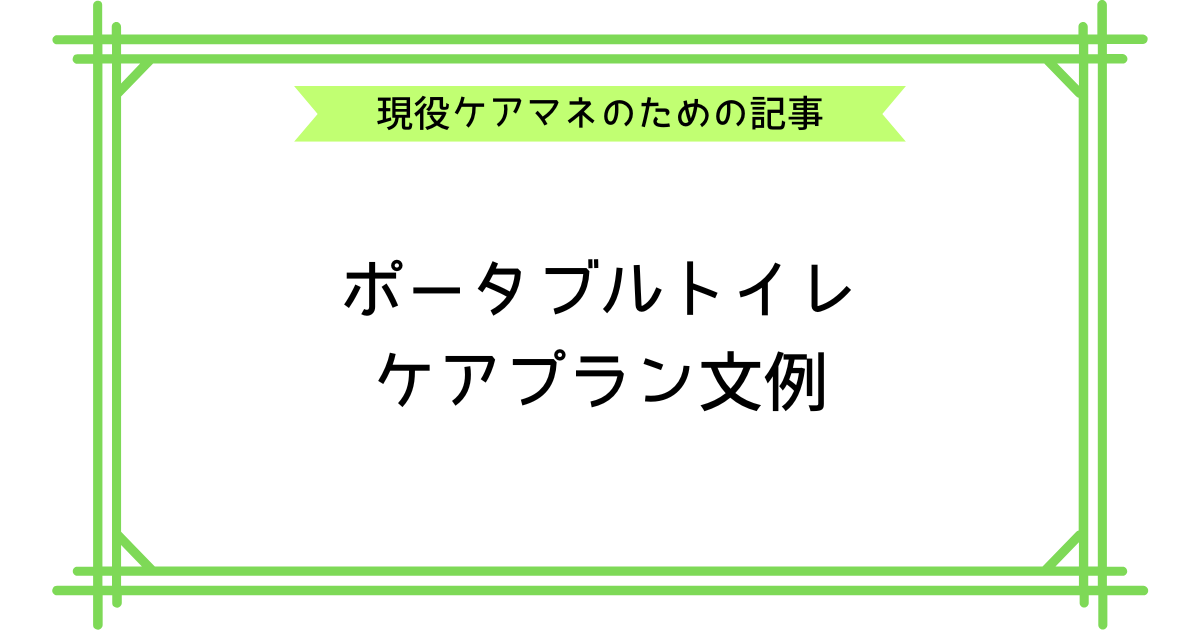
ポータブルトイレ(PT)は、夜間の移動負担を軽減し、排泄の自立度を高める有効な福祉用具です。
一方で「臭気」「転倒」「処理手順」「皮膚トラブル」「見た目の抵抗感」などの課題が生じやすく、環境整備・手順の標準化・観察と記録・多職種連携が成功の鍵になります。
本記事では、現場ですぐに貼って使える文例を長期目標/短期目標/サービス内容の3区分で200パターン掲載します。
目次
長期目標(ポータブルトイレのケアプラン文例)
- ポータブルトイレを安全に使用し、排泄の自立度を維持・向上する。
- 夜間のトイレ移動を最小限にし、転倒リスクを低減する。
- 本人の尊厳を守り、安心して排泄できる環境を整える。
- 臭気対策を徹底し、居室で快適に過ごせる。
- 皮膚トラブル(かぶれ・褥瘡周囲悪化)を予防する。
- 失敗への不安を軽減し、排泄意欲を保つ。
- 家族の負担を軽減し、継続可能なケア体制を作る。
- 排泄記録に基づき、適切な水分・排便コントロールを維持する。
- 排泄リズムを整え、夜間の安眠を確保する。
- 見た目の抵抗感を減らし、受け入れを促進する。
- 導線と設置位置を最適化し、移乗をスムーズに行う。
- 清潔保持と消毒を標準化し、感染リスクを最小化する。
- 適切な座面高・肘掛調整で安全な立ち座りを実現する。
- 本人のプライバシーを尊重したケアを継続する。
- 認知症があっても迷わず使用できる環境表示を整える。
- 便秘・尿路感染を予防し、体調を安定させる。
- 失禁時も羞恥心に配慮した対応で安心感を保つ。
- 排泄後の手指衛生を習慣化し、衛生的に過ごす。
- 訪問看護・医師・薬剤師と連携し、薬剤調整を適切に行う。
- 本人の生活習慣を尊重し、ベストな利用回数・時間帯を確立する。
- 介助者が統一手順で介助し、事故ゼロを目指す。
- 夜間の見守り体制を整え、不安を軽減する。
- 下肢筋力・バランスを維持し、移乗の自立を支える。
- 口腔・水分・食物繊維のバランスで良好な便性を保つ。
- 排泄後の陰部洗浄と保湿で皮膚を保護する。
- 家屋改修までの移行期ツールとして有効活用する。
- 体調変化に応じ、便器・バケツ・防臭具の種類を適切に選ぶ。
- 見守りセンサー等を併用し、夜間の安全を高める。
- 本人の選好(色・形・カバー)を反映し、アドヒアランスを高める。
- 家族が自信を持って清掃・消毒・組み立てを行える。
- 生活リズムに合った誘導で失敗を減らす。
- 患者の dignity を守る声かけ・環境配慮を徹底する。
- 体調悪化時も在宅で運用可能な体制を維持する。
- 排泄に関する羞恥・罪悪感を軽減し前向きに過ごす。
- 脱水・過飲の偏りをなくし適正な尿量を維持する。
- 便座のクッション性・保温性を調整し快適性を高める。
- 夜間の歩数・移動距離を抑え、疲労を軽減する。
- 事故・汚染発生時の対応手順を家族と共有する。
- 臭気・衛生面で周囲への心理的負担を減らす。
- 看取り期にも尊厳を守りつつ安楽に排泄できる。
- 定期評価に基づき、用具・導線・ケアを継続改善する。
- 服薬(利尿薬・便秘薬)の時間設定を最適化する。
- 在宅でも通院・デイ利用と両立できる排泄体制を保つ。
- 本人の意思決定を尊重し、使用・非使用を選択できる。
- 介護保険レンタル・購入の費用対効果を高める。
- 夜間も安心して眠れ、昼間の活動意欲を保つ。
- 皮膚・粘膜の健康を守り、感染症を予防する。
- 家族・介護者の身体的負担(腰痛等)を軽減する。
- 多職種での情報共有を習慣化し、支援の一貫性を保つ。
- 本人らしい生活を在宅で継続できるよう支援する。
短期目標(ポータブルトイレのケアプラン文例)
- ベッド横にPTを設置し、夜間の移動距離を最短化する。
- 座面高を大腿骨水平+踵接地に合わせて再調整する。
- 肘掛・フットスペースを本人の動作に合わせて微調整する。
- 立ち上がり時の掛け声を統一し、タイミング介助で安全性を高める。
- 夜間○回のトイレ誘導を固定時間で実施する。
- 就寝前の水分量を見直し、夜間尿をコントロールする。
- 利尿薬の内服時間を主治医と相談し変更を検討する。
- 失敗時の対応手順(除染→洗浄→乾燥→記録)を標準化する。
- 座位保持クッションで骨盤後傾を予防する。
- 便座クッション・保温便座カバーで冬期の不快を軽減する。
- 便器内に消臭ゲル・凝固剤を使用し臭気を抑える。
- 使用後は速やかに蓋を閉じ、バケツを処理する。
- 消臭スプレーの使用タイミングを「処理後」に統一する。
- 片付け動線(洗面所・浴室)を整理し、こぼしを防止する。
- 手袋・エプロン・マスクのPPEを準備し、衛生手順を徹底する。
- 陰部洗浄→乾燥→保湿→保護クリームの順でケアする。
- 尿量・回数・色調を日誌に記録し、脱水や感染兆候を把握する。
- 便性(ブリストルスケール)を記録し、食事・薬剤調整に活かす。
- 失禁後は皮膚の発赤・掻痒を観察し看護へ報告する。
- 夜間照明を足元灯+センサーライトに変更する。
- 室温・湿度を季節に応じて調整し、夜間覚醒を減らす。
- 便座→ベッドへの移乗はスライディングボードを併用する。
- 移乗手順を写真付きで掲示し、家族と共有する。
- 服薬カレンダーで便秘薬・整腸薬の飲み忘れを防ぐ。
- 水分目標○ml/日を設定し、日中の摂取を促す。
- 食物繊維・発酵食品を取り入れ、自然排便を促す。
- 就寝前の「声かけ・誘導・手指衛生」をルーチン化する。
- 認知症の方には視覚サイン(トイレマーク・矢印)を設置する。
- 衣類は前開き・伸縮素材に変更し、着脱を容易にする。
- ベッド柵を活用し、立ち上がり補助を安全に行う。
- 体調不良時はオムツ併用へ一時切替し皮膚を保護する。
- 便器洗浄は中性洗剤→流水→乾燥→消毒の順で実施する。
- バケツは使用毎に洗浄・乾燥し、カビ・臭気を防ぐ。
- 消臭・凝固剤の補充在庫を週1回確認する。
- 介助者の腰痛予防に前傾姿勢回避・足幅調整を徹底する。
- 起床時・就寝前・利尿薬内服後に誘導を重点化する。
- 座面から踵までの距離を調整し、足底接地を確保する。
- 便座蓋の色コントラストを上げ、視認性を高める。
- トイレットペーパー・おしり拭きを手の届く位置に固定する。
- 便器の注水量・洗浄水温を適正化する(機能付きの場合)。
- トイレ後の手指消毒を習慣化する。
- 臭気の強い日は換気回数を増やし、空気清浄機を併用する。
- 便秘傾向時は温罨法・腹部マッサージを併用する。
- 便意サイン(落ち着きなさ・そわそわ)を観察し声かけする。
- ベッドとPTの距離を肘掛一歩で届く位置に再配置する。
- マット類は厚み・滑り止め性能を見直す。
- 夜間呼出ベルの位置を手元に固定する。
- 使用後のゴミ(手袋・おしり拭き)分別ルールを徹底する。
- 家族へ「臭気は処理の遅れで増す」ことを説明し即時処理を促す。
- 衛生用品の月次使用量を可視化し、発注ミスを防ぐ。
- 皮膚保護剤・清拭料の刺激性を見直し、低刺激品に変更する。
- こぼし時の床清掃手順(吸水→洗浄→消毒)を統一する。
- 便座の幅・奥行きを再評価し、骨盤安定を図る。
- 見た目が気になる方にはカバー・パーテーションで配慮する。
- 家族・介護者へ羞恥配慮の声かけ例を周知する。
- 便器内の水量や消臭剤量を季節で調整する。
- デイ通所日は日中排泄を促し、夜間負担を軽減する。
- 排泄日誌の週次レビューで誘導時間を最適化する。
- 処理場(浴室)の段差・滑りを改善する。
- 片麻痺の方は健側肘掛を強化し、立ち座りを安定化する。
- むくみ・頻尿時は医師へ相談し内服調整を検討する。
- 夜間徘徊傾向がある日は誘導回数を増やす。
- 服薬による口渇対策(氷片・うがい)で頻尿を緩和する。
- 排尿後の残尿感がある場合は姿勢と時間を見直す。
- 便器のふち掃除を重点化し、臭源を断つ。
- 夏季は換気+扇風機で処理時の不快を軽減する。
- 冬季は室温低下を防ぎ、起立時の血圧変動に注意する。
- 起立不能時の緊急対応手順(オムツ併用・清拭)を共有する。
- 訪問看護と連携し、皮膚トラブルの早期介入を図る。
- 排泄に前向きになれる声かけ(成功の言語化)を行う。
- 便座昇降の練習を日中のリハで行い、夜間に備える。
- 介助者は「押す・引く」を避け、重心移動で支える。
- 失敗時は責めず受容的に関わり、不安を軽減する。
- 家族へ洗浄・消毒・乾燥・保管のコツを動画や写真で伝える。
- 便器の割れ・緩み・足ゴム劣化を月1回点検する。
- 防臭袋・凝固剤の使い分け基準を掲示する。
- 補助灯・ナイトライトの電池切れを点検する。
- 受診前日は夕食後の誘導を追加し、失敗を減らす。
- 体調悪化時はPT→ポータブルシャワー併用で清潔保持する。
- 週1回のカンファで問題点・改善策を共有する。
サービス内容文例(ポータブルトイレのケアプラン文例)
- 訪問介護が夜間のPT誘導と見守りを行う。
- 訪問看護師が皮膚観察・陰部ケア・感染予防指導を実施する。
- 福祉用具専門相談員が座面高・肘掛・設置位置を調整する。
- ケアマネが排泄記録を基に誘導時間の最適化を調整する。
- 介護職が就寝前の声かけ・誘導・手指衛生を支援する。
- 看護師が便秘・利尿薬など薬剤のタイミングを医師と調整する。
- 介護職が汚染時の標準手順で除染・洗浄・消毒を行う。
- 福祉用具が消臭・凝固剤の選定と在庫管理を助言する。
- 介護職がベッド周囲の導線・照明を整備する。
- 看護師が残尿感・排尿困難の評価と受診調整を行う。
- 介護職が衣類・寝具の洗濯・乾燥で衛生を維持する。
- ケアマネが家族へ羞恥配慮の声かけ・対応例を共有する。
- 訪問看護が陰部洗浄・保湿・皮膚保護の手順を指導する。
- 介護職がPTの洗浄・乾燥・保管を毎回実施する。
- 福祉用具が手すり・スロープ等の併用を提案する。
- ケアマネが見守りセンサー導入の可否を調整する。
- 介護職が消臭・換気・空気清浄機の運用を標準化する。
- 看護師が尿路感染の兆候を観察し医師に報告する。
- 介護職が就寝前の水分・温罨法で便通を整える。
- 福祉用具が便座クッション・保温カバーを手配する。
- 介護職がスライディングボード・介助ベルトを使用する。
- 看護師がオムツ併用時の皮膚トラブルを予防・介入する。
- ケアマネが通所サービスと誘導計画を連携する。
- 介護職がナイトライト・足元灯の点検を行う。
- 訪問看護が臭気源の特定と改善策を提案する。
- 福祉用具がPT機種の変更・更新を検討する。
- 介護職が処理場の段差・滑り対策を実施する。
- 看護師が水分・食物繊維量を評価し栄養士と連携する。
- ケアマネが家族の負担に応じサービス量を調整する。
- 介護職が便器ふち・蓋の重点清掃を行う。
- 訪問看護が失敗時の心のケア・傾聴を行う。
- 福祉用具が防臭袋・凝固剤の在庫管理表を作成する。
- 介護職が手袋・エプロンなどPPEの補充点検を行う。
- 看護師が利尿薬時間の変更による夜間尿の変化を評価する。
- ケアマネが月次カンファで課題・解決策を共有する。
- 介護職が視覚サイン・パーテーションでプライバシーを確保。
- 訪問看護が被服・寝具の肌当たりを評価し助言する。
- 福祉用具がクッション・手すりの再調整を行う。
- 介護職が転倒リスクの高い夜間に近接見守りを実施する。
- 看護師が皮膚保護剤・保湿剤の適正使用を指導する。
- ケアマネが緊急時連絡網・対応手順を整備する。
- 介護職が洗面・手指衛生の動線を整える。
- 訪問看護が尿量・尿色の記録方法を統一する。
- 福祉用具がPTの破損・劣化を点検し交換を提案する。
- 介護職が就寝前の整容・着替えを支援する。
- 看護師が便性に応じた薬剤・食事の調整を提案する。
- ケアマネが家族向け操作・清掃マニュアルを配布する。
- 介護職が処理後の床・壁の拭き上げを徹底する。
- 訪問看護が残尿測定や受診助言を行う。
- 福祉用具が臭気対策備品(ゲル・消臭器)を提案する。
- 介護職が夜間コール位置を手元へ固定する。
- 看護師が尿路感染疑い時の迅速受診を調整する。
- ケアマネが費用負担・レンタル契約を助言する。
- 介護職がベッド柵・手すりの固定を再確認する。
- 訪問看護が皮膚トラブル時のドクターへの報告を行う。
- 福祉用具が便器容量・形状の合う機種を再選定する。
- 介護職が夜間巡視で失敗の早期発見・対応を行う。
- 看護師が陰部洗浄の湯温・手順を教育する。
- ケアマネが通所・訪看のスケジュールを排泄リズムに合わせる。
- 介護職が洗剤・消毒剤の希釈・保管を適正化する。
- 訪問看護が腹部マッサージ・温罨法を指導する。
- 福祉用具がスライディングボードや介助ベルトを提供する。
- 介護職が在庫切れ防止のチェックリストを運用する。
- 看護師が薬剤変更後の夜間尿の変化をモニタリングする。
- ケアマネが見守り体制(家族・事業所)を再構築する。
- 介護職が季節に応じた換気・空調調整を行う。
- 訪問看護がオムツ併用時のスキンケアを継続する。
- 福祉用具がパーテーション・カバーで視覚的配慮を強化する。
- 介護職が処理動線の滑り止め・段差ケアを実施する。
- 多職種が定例カンファで効果を評価し計画を更新する。
まとめ
ポータブルトイレ活用の成否は、設置位置×座面・肘掛の個別調整×誘導のタイミング×衛生・臭気対策×皮膚保護×尊厳ケアにかかっています。
上記200の【コピペOK】文例は、監査対応しやすい汎用表現で整理しています。
実際のケアプランでは、頻度・担当・具体的指標(尿量/便性/皮膚状態/失敗回数/臭気レベル等)を追記して完成度を高めてください。















