高齢者は何歳から?前期高齢者と後期高齢者について解説
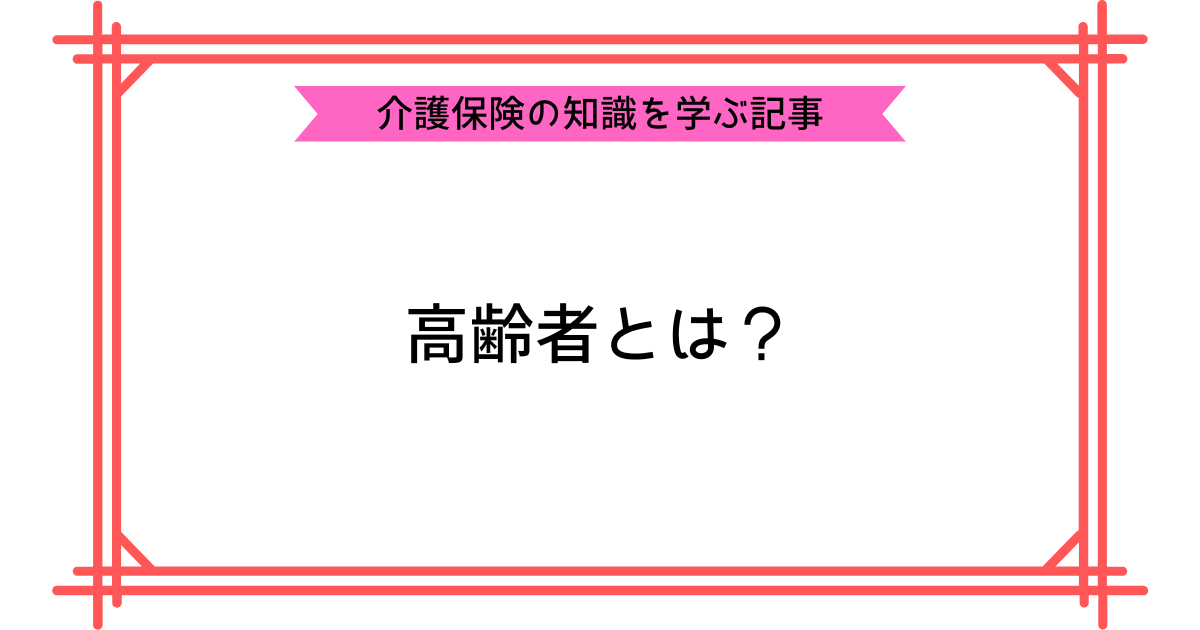
「高齢者って何歳からなの?」「前期高齢者・後期高齢者って聞くけれど、どんな違いがあるの?」
日本は世界でも有数の長寿国であり、医療や介護の現場だけでなく、日常生活でも「高齢者」という言葉を耳にする機会が多くなっています。
しかし、高齢者の定義は意外とあいまいに思われがちです。
本記事では、高齢者は何歳からを指すのか、さらに前期高齢者と後期高齢者の違いについて分かりやすく解説します。また、それぞれの世代の特徴や社会制度との関わりについても紹介します。
高齢者は何歳から?
一般的な定義
日本では、65歳以上の人を「高齢者」と呼ぶのが一般的です。これは、国連やWHO(世界保健機関)が「65歳以上を高齢者」と定義していることに基づいています。
法律や制度での扱い
- 老人福祉法:65歳以上を高齢者と規定
- 介護保険制度:65歳から第1号被保険者となり、介護サービスを利用できる
- 高齢者雇用安定法:65歳までの雇用確保措置を義務付け
つまり、医療や福祉制度では「65歳」が一つの基準になっています。
前期高齢者と後期高齢者の違い
高齢者はさらに前期高齢者と後期高齢者に区分されます。
- 前期高齢者:65歳〜74歳
- 後期高齢者:75歳以上
この区分は、医療制度や社会保障制度で重要な意味を持っています。
前期高齢者(65歳〜74歳)
- まだ健康で活動的な人が多い
- 定年後も働いている人も多い
- 医療制度では「高齢者医療制度」に該当せず、国保や健保に加入
後期高齢者(75歳以上)
- 加齢による心身機能の低下が顕著になる時期
- 医療や介護のニーズが増える
- 「後期高齢者医療制度」に自動的に加入
前期高齢者の特徴と社会的役割
健康状態
65〜74歳の前期高齢者は、生活習慣病などの慢性疾患を持ちながらも、比較的元気に生活している人が多いです。
社会的活動
- 再雇用やパート勤務などで働き続ける人が増加
- ボランティアや地域活動に参加
- 孫の世話や家庭内での役割を担う
「まだ現役」として社会に関わる力を持つのが前期高齢者の特徴です。
後期高齢者の特徴と課題
健康状態
75歳を超えると、身体機能や認知機能の低下が目立ち始め、医療や介護を必要とする割合が増加します。
医療制度との関係
後期高齢者は自動的に「後期高齢者医療制度」に加入します。所得に応じて1割〜3割の自己負担で医療を受けられる仕組みです。
社会的課題
- 介護サービスの利用が増える
- 独居高齢者や老老介護の増加
- 社会的孤立や経済的不安
後期高齢者は、医療や介護の制度をいかに活用するかが生活の質を左右します。
高齢者区分がもたらす社会的意義
- 医療・介護制度の基準
前期・後期で区分することで、医療保険制度や介護保険の負担割合が明確になります。 - 政策のターゲット設定
「健康寿命の延伸」「介護予防」など、年代ごとに異なる政策を打ち出しやすくなります。 - 社会的認識の共有
65歳から高齢者という基準があることで、社会全体で「高齢者支援」を考えるきっかけになります。
高齢者=65歳は変わる可能性も?
近年は平均寿命の延びとともに「65歳はまだ若い」という声も多くなっています。
日本老年学会は、高齢者の定義を「75歳以上」に引き上げるべきという提言を行ったこともあります。
- 65〜74歳は「准高齢者」
- 75〜89歳を「高齢者」
- 90歳以上を「超高齢者」
今後、社会の高齢化に伴って「高齢者の定義」が見直される可能性もあります。
まとめ
高齢者は一般的に65歳以上を指し、さらに
- 前期高齢者:65〜74歳
- 後期高齢者:75歳以上
と区分されます。
前期高齢者はまだ活動的で社会参加が盛んな一方、後期高齢者は医療や介護のニーズが高まりやすいのが特徴です。
高齢者区分は、医療・介護制度や社会政策を支える重要な仕組みであり、私たち一人ひとりが理解しておくべき基礎知識です。















