介護保険で福祉用具をレンタルできないもの・できるものを解説
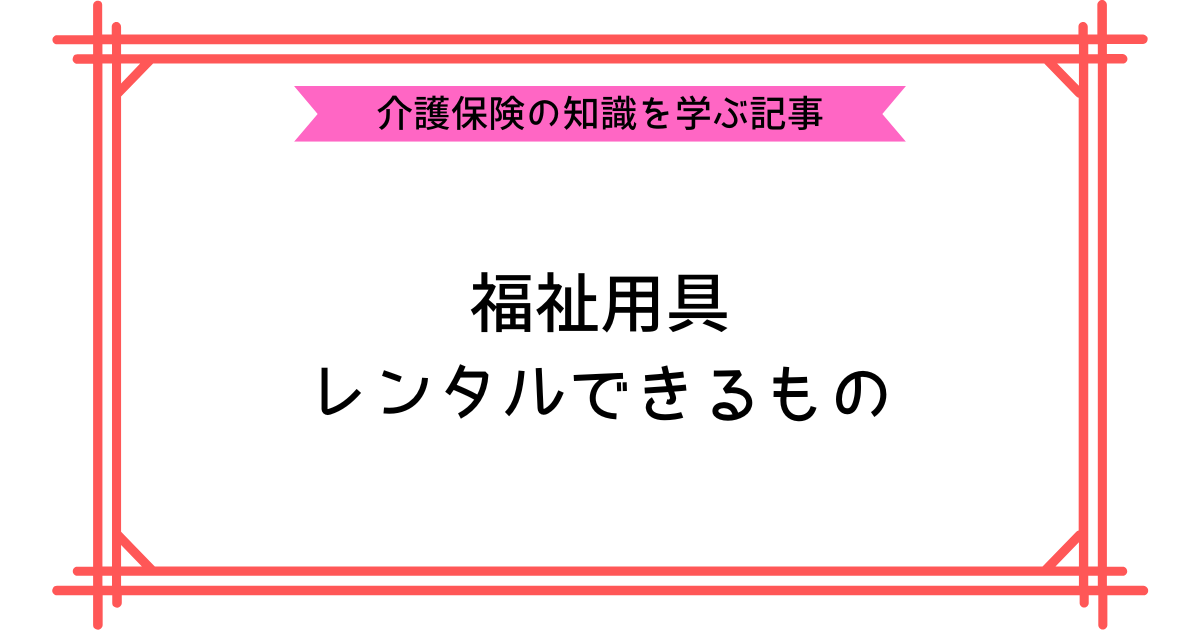
介護保険を利用すると、在宅生活を支えるためにさまざまな福祉用具をレンタルできます。
しかし、「どの福祉用具がレンタル対象なのか」「購入しなければならないものはどれか」と疑問に思う方も多いでしょう。
特に、介護保険制度ではレンタルできるものとできないものが明確に区分されているため、事前に知っておくことが大切です。
この記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具と、できないもの(購入対象になるもの)について、詳しく解説します。
さらに、なぜ区分があるのか、利用者や家族が注意すべきポイントについても整理します。
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の説明と合わせてご覧いただくことで、よりスムーズに制度を利用できるでしょう。
介護保険における福祉用具レンタルの仕組みとは?
介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けた人が日常生活を送るうえで必要な福祉用具をレンタルまたは購入できます。
レンタル(貸与)の特徴
- 月額料金を支払い、必要な期間だけ借りる
- 故障時の交換やメンテナンス費用はレンタル料に含まれる
- 状態の変化に応じて返却・交換が可能
- 自己負担は原則1割(所得により2割・3割)
購入の特徴
- 一度購入すれば自分のものになる
- 年間10万円を上限に介護保険が適用
- シャワーチェアやポータブルトイレなど、衛生的にレンタルできないものが対象
このように、福祉用具は「レンタル」と「購入」で対象が分けられています。
介護保険でレンタルできる福祉用具
介護保険でレンタルできるものは、原則13品目に定められています。代表的なものを詳しく見ていきましょう。
1. 車いすおよび車いす付属品
- 自走用、介助用、電動車いすなど
- クッションやブレーキ補助装置などの付属品もレンタル可能
2. 特殊寝台(介護用ベッド)
- 背上げや高さ調整ができる電動ベッド
- マットレスやサイドレールも含まれる
3. 床ずれ防止用具
- 体圧分散マットレス
- エアマットレス
4. 体位変換器
- 自動で体位を変えてくれる機器
5. 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
- 室内で簡単に設置できる据え置き型手すり
6. スロープ
- 車いすでの出入りをサポートする持ち運び可能なスロープ
7. 歩行器・歩行補助つえ
- 折りたたみ式歩行器、シルバーカー、四点杖など
8. 認知症老人徘徊感知機器
- 赤外線センサーやマットセンサー
9. 移動用リフト(つり具を除く)
- 床走行型や据え置き型のリフト
これらは、利用者の身体状況に合わせて短期間から長期間まで必要に応じて借りられるのがメリットです。
介護保険でレンタルできない福祉用具(購入対象)
一方で、衛生面や個別対応の必要性から、レンタルではなく購入が原則とされているものがあります。介護保険では年間10万円を上限に購入費用が支給されます。
購入対象となるのは以下の5品目です。
1. 腰掛便座
- ポータブルトイレ
- 補高便座(便座の高さを上げるもの)
2. 入浴補助用具
- シャワーチェア
- 浴槽用手すり
- 浴槽内すのこ
3. 簡易浴槽
- 工事を伴わずに設置できる浴槽
4. 移動用リフトのつり具部分
- 個々の体格や状態に合わせた吊り具はレンタル不可
5. 自動排泄処理装置の交換可能部品
- レシーバーやチューブなど、衛生的に使い回せない部分
なぜ「レンタルできないもの」があるのか?
衛生面の問題
ポータブルトイレやシャワーチェアなどは、直接身体や排泄に関わるため、レンタルでは不衛生になるリスクがあります。
個別対応の必要性
吊り具や排泄処理装置の部品は利用者ごとに体格や状態に合わせる必要があり、共用に適さないため購入対象となっています。
経済的合理性
一度購入すれば長期間使えるものは購入対象にし、利用者の体調変化によって使わなくなる可能性があるベッドや車いすなどはレンタル対象にする、という合理的な区分です。
レンタルと購入を併用する際の注意点
- 事前申請が必要
福祉用具購入は、市区町村への申請と承認が必要です。 - 指定事業者から利用すること
介護保険の対象となるのは、指定を受けた事業者からのレンタル・購入に限られます。 - 限度額を超えた場合は全額自己負担
レンタルは要介護度ごとの「区分支給限度基準額」、購入は「年間10万円まで」という制限があります。超えると全額自己負担になります。 - ケアマネジャーのケアプランに位置づけが必要
介護保険を利用するためには、ケアマネが作成するケアプランに福祉用具の利用内容を明記する必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q:ベッドや車いすは購入できないのですか?
A:介護保険の制度上はレンタルが原則です。ただし、医師の意見や特例が認められる場合に購入できるケースもあります。
Q:購入した福祉用具は翌年も保険が使えますか?
A:はい。ただし、年度ごとに10万円までの上限があり、毎年リセットされます。
Q:要支援認定でも利用できますか?
A:要支援1・2でも利用可能です。ただし、予防給付(介護予防サービス)としての位置づけになります。
まとめ
介護保険で利用できる福祉用具は、レンタル対象と購入対象に明確に分かれています。
- レンタルできるもの:車いす、介護ベッド、歩行器、床ずれ防止用具など13品目
- レンタルできないもの(購入対象):ポータブルトイレ、シャワーチェア、簡易浴槽、吊り具、自動排泄処理装置の部品など
この区分は、衛生面・個別対応・経済性を考慮して設定されています。利用者や家族は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら、必要な福祉用具を限度額の範囲内で賢く活用することが大切です。















