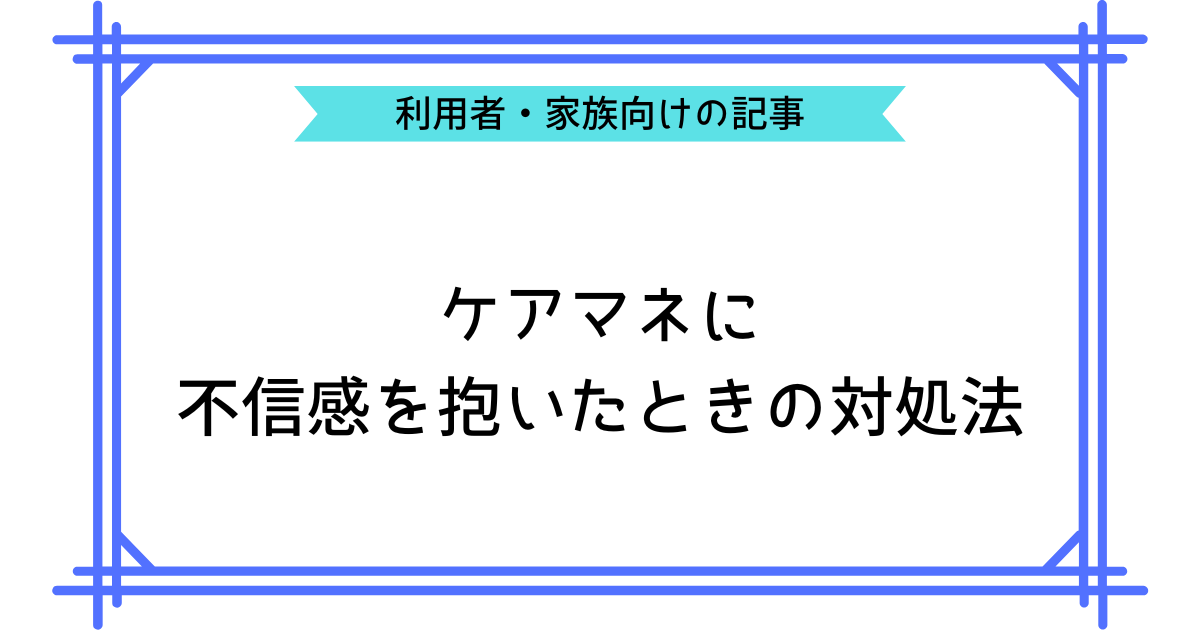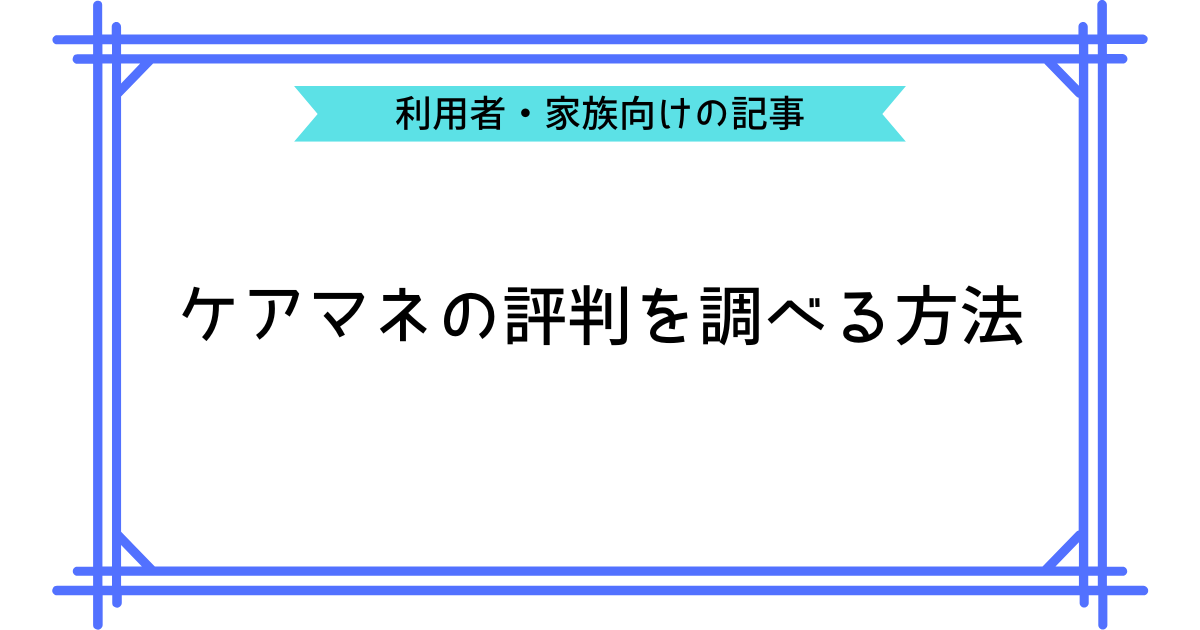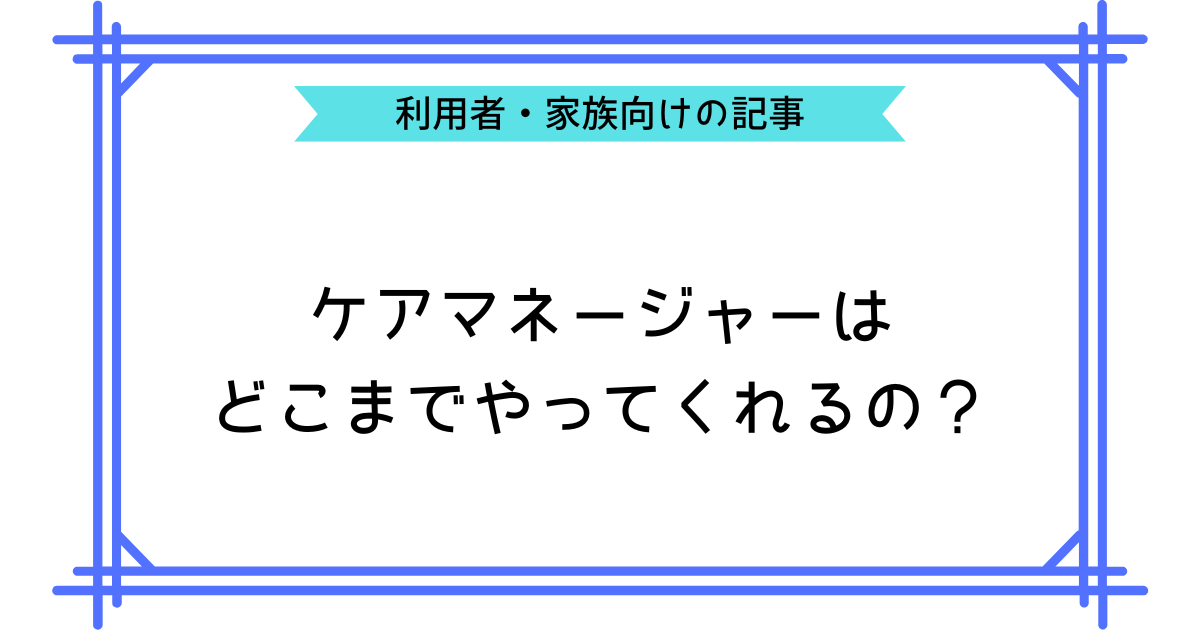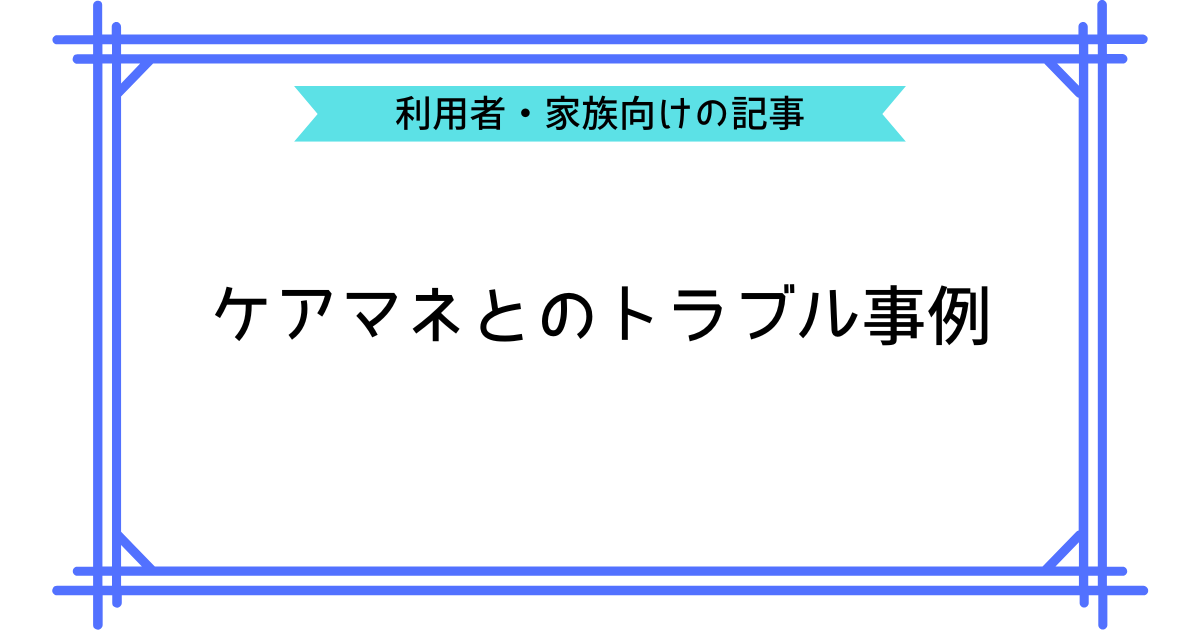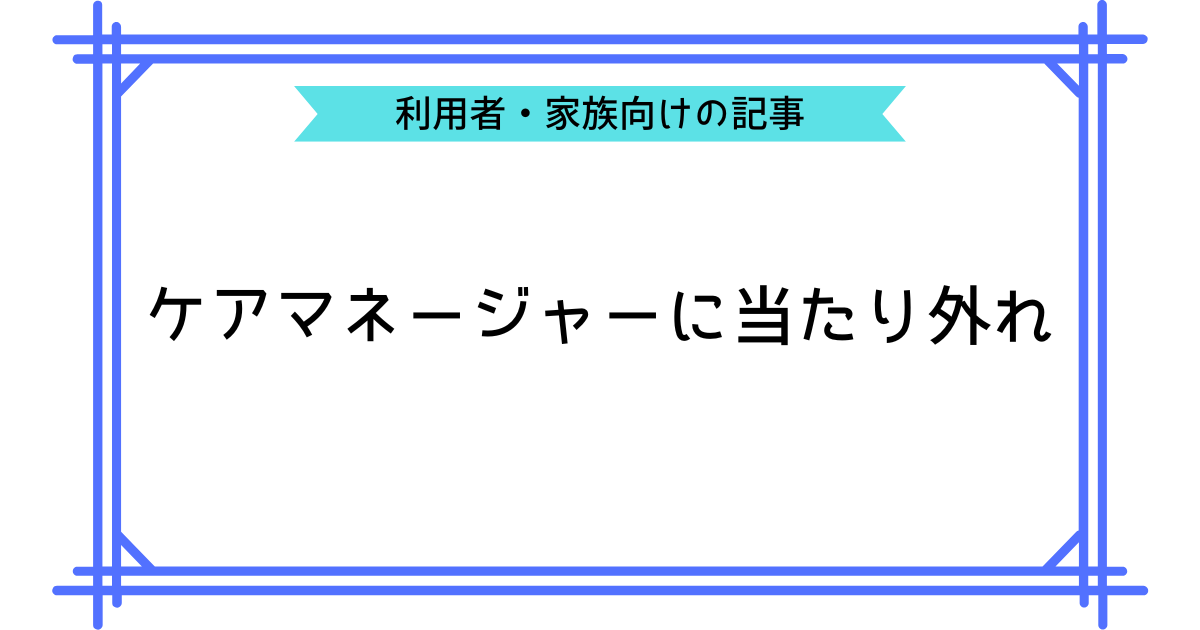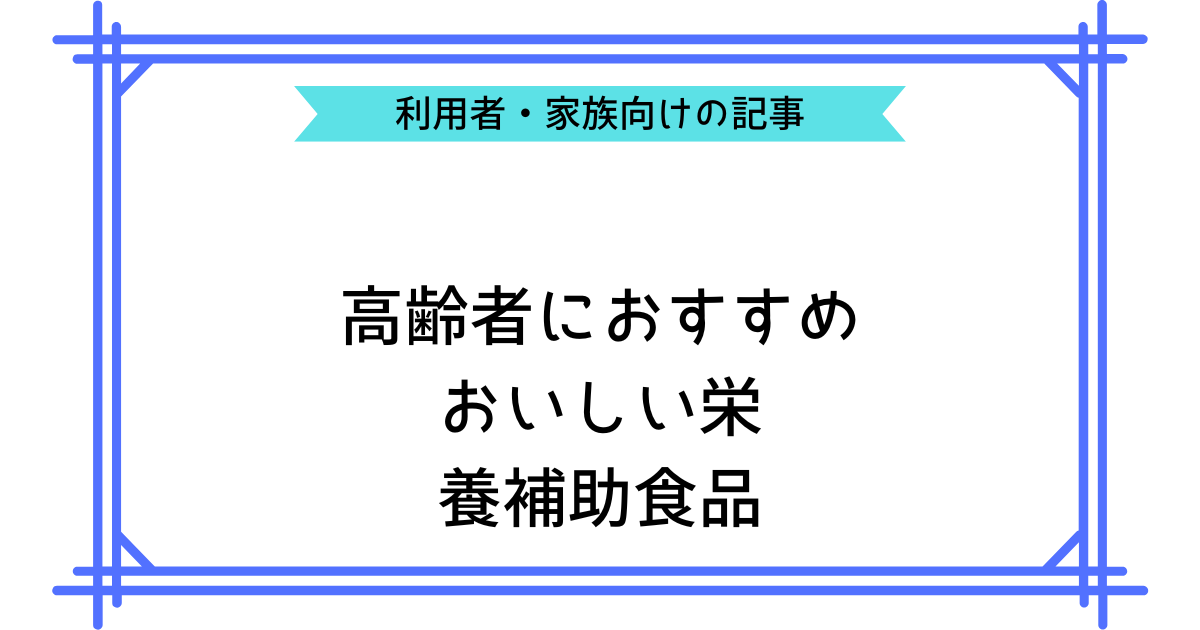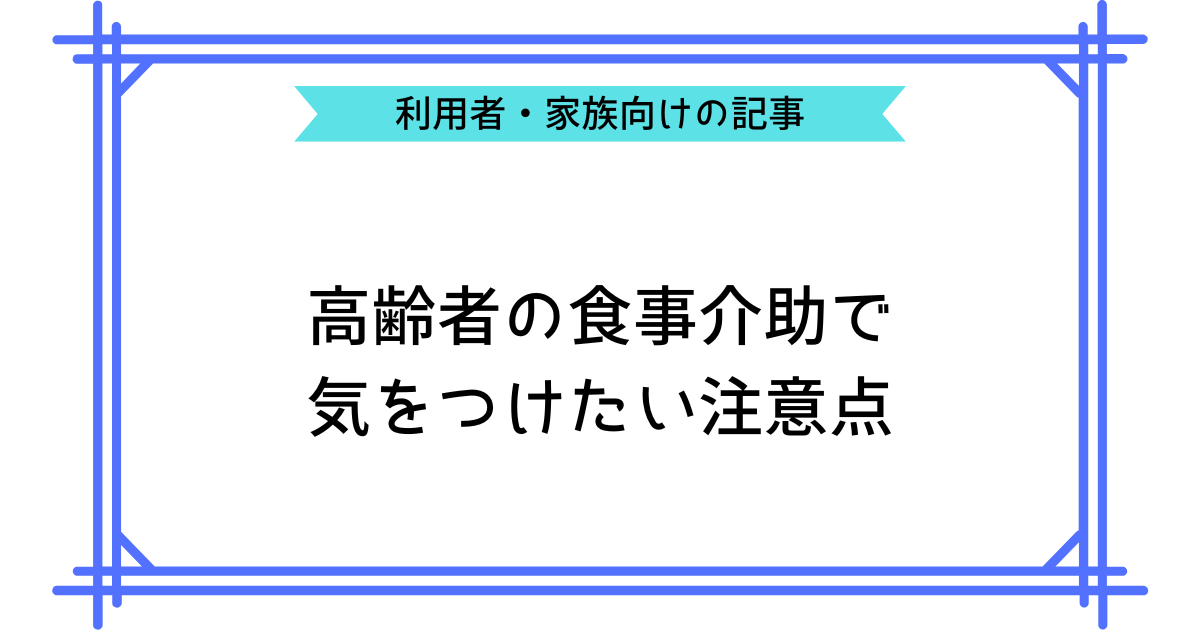ケアマネは施設を探してくれないの?家族が知っておくべき対応方法を解説
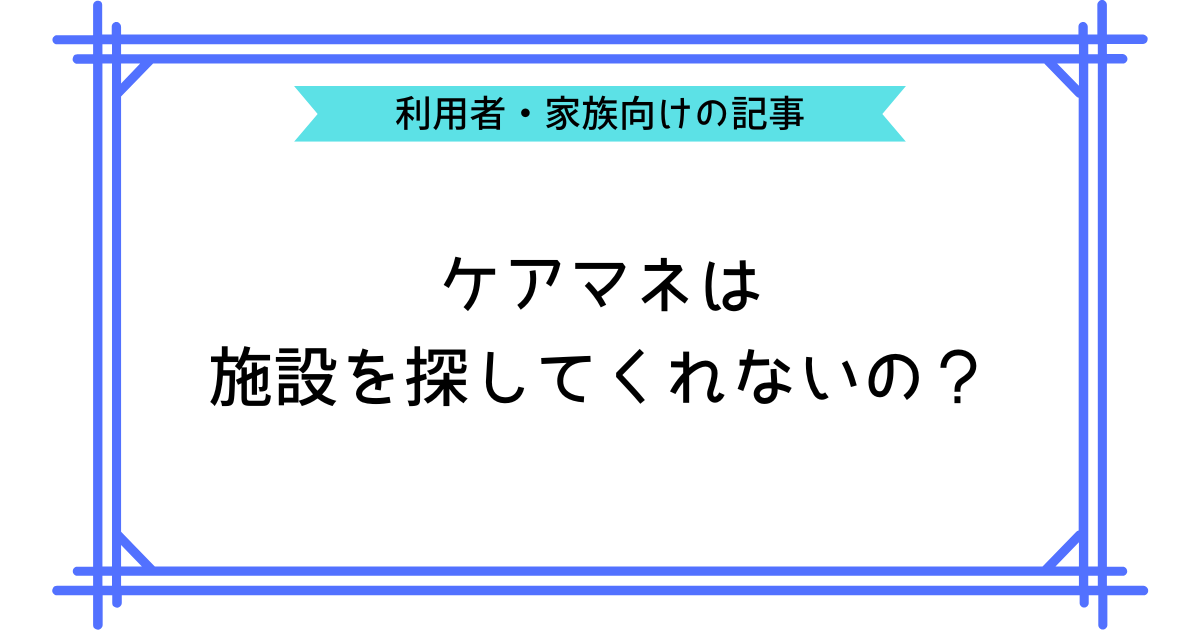
高齢の親や家族の介護が必要になり「そろそろ施設に入所させたい」と考えたとき、最初に相談するのがケアマネジャーという方も多いでしょう。
しかし実際には「ケアマネが施設を探してくれない」「紹介してくれない」と感じる家族も少なくありません。
なぜケアマネが施設探しを積極的にしてくれないのか、その背景や理由を知ることで、より良い対応方法が見えてきます。
本記事では、家族向けにわかりやすく解説していきます。
ケアマネは本当に施設を探してくれないのか?
ケアマネの役割は、基本的に 在宅生活を支えるためのケアプラン作成とサービス調整 です。
そのため、施設への入居先を積極的に探すのは本来の業務範囲から外れるケースがあります。
とはいえ、相談すれば情報提供やアドバイスをしてくれる場合も多く、「まったく対応しない」というわけではありません。
つまり「探してくれない=冷たい対応」ではなく、制度上の役割や業務範囲によって限界がある、というのが正しい理解です。
ケアマネが施設を探してくれない主な理由
制度上の役割の違い
ケアマネは居宅介護支援事業所に所属し、主に在宅サービスの調整を担います。特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの入居相談は、直接施設や地域包括支援センターが窓口になることが多いため、ケアマネが主体的に施設探しをする立場ではありません。
利用者の意思を尊重する必要がある
ケアマネは本人の希望を大切にする立場です。本人が「まだ自宅で暮らしたい」と考えている場合、家族から「施設に入れてほしい」と言われても、すぐに施設探しに動けないことがあります。
施設情報の提供に限界がある
施設は地域に数多くあり、それぞれ料金体系や入所条件が異なります。ケアマネが全ての施設情報を網羅するのは難しいため、基本的には「情報提供まで」とし、具体的な見学や申込みは家族が行うケースが一般的です。
家族ができる具体的な対応方法
1. 施設探しの窓口を知る
施設探しのメイン窓口は以下のようなところです。
- 各施設の相談員(直接問い合わせ)
- 地域包括支援センター
- 介護相談窓口(自治体や民間サービス)
ケアマネに情報をもらいつつ、家族も主体的に行動するとスムーズです。
2. ケアマネには「相談ベース」で頼む
「施設を紹介してください」ではなく「候補を探したいので情報を教えてください」と伝えることで、ケアマネから地域の施設や相談先のリストをもらえることがあります。依頼の仕方を工夫するのがポイントです。
3. 家族が主体的に見学・比較する
施設選びは生活や費用に直結する大切な決定です。ケアマネ任せにせず、家族自身が複数の施設を見学し、料金・雰囲気・立地を比較検討することが重要です。
ケアマネと上手に連携するためのコツ
誤解を避けるコミュニケーション
「ケアマネは施設を探してくれない」という不満を持つ家族は多いですが、まずは業務範囲を理解することが大切です。その上で「情報提供をお願いしたい」と具体的に頼むとスムーズに協力してもらえます。
施設入居後もケアマネの役割はある
特養や老健などに入所すると、施設のケアマネに担当が変わることになります。しかし、入居までの手続きや在宅生活とのつなぎ役として、居宅ケアマネのサポートは重要です。「入居後は関係ない」と思わず、最後まで協力してもらいましょう。
まとめ
「ケアマネが施設を探してくれない」と感じるのは珍しくありませんが、それは冷たい対応ではなく、制度上の役割の違いが関係しています。
ケアマネは施設探しの専門職ではありませんが、情報提供やアドバイスはしてくれます。
家族としては、地域包括支援センターや施設の相談員にも積極的にアプローチし、ケアマネと連携しながら主体的に動くことが大切です。
施設選びは家族にとって大きな決断ですが、複数の視点で情報を集めることで、安心して最適な選択ができるでしょう。