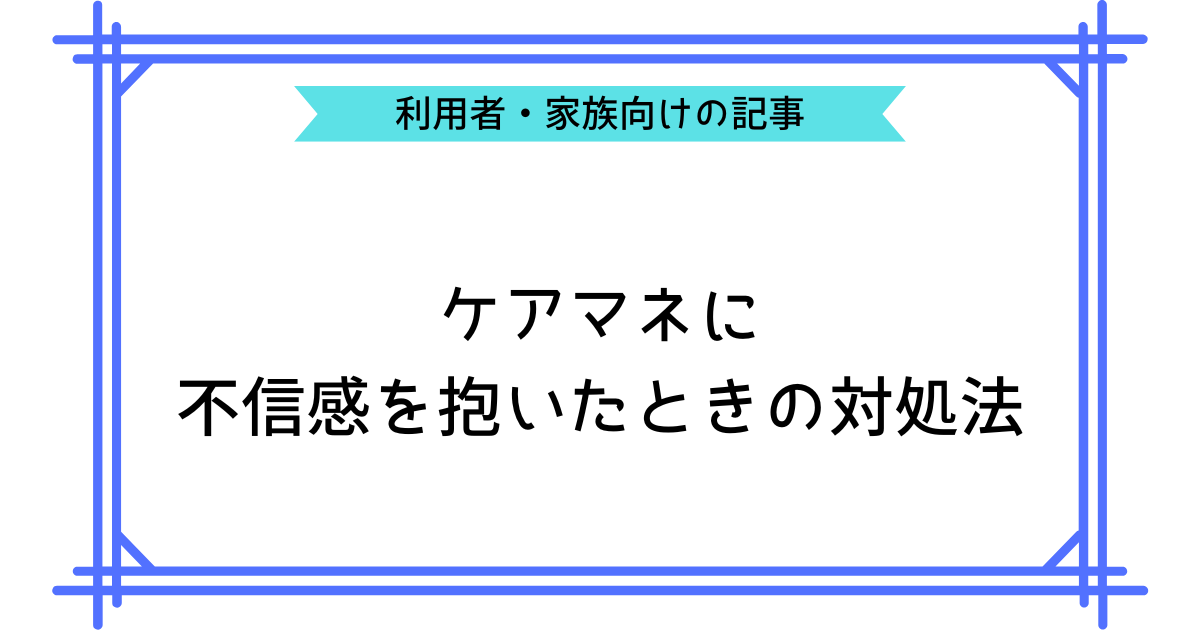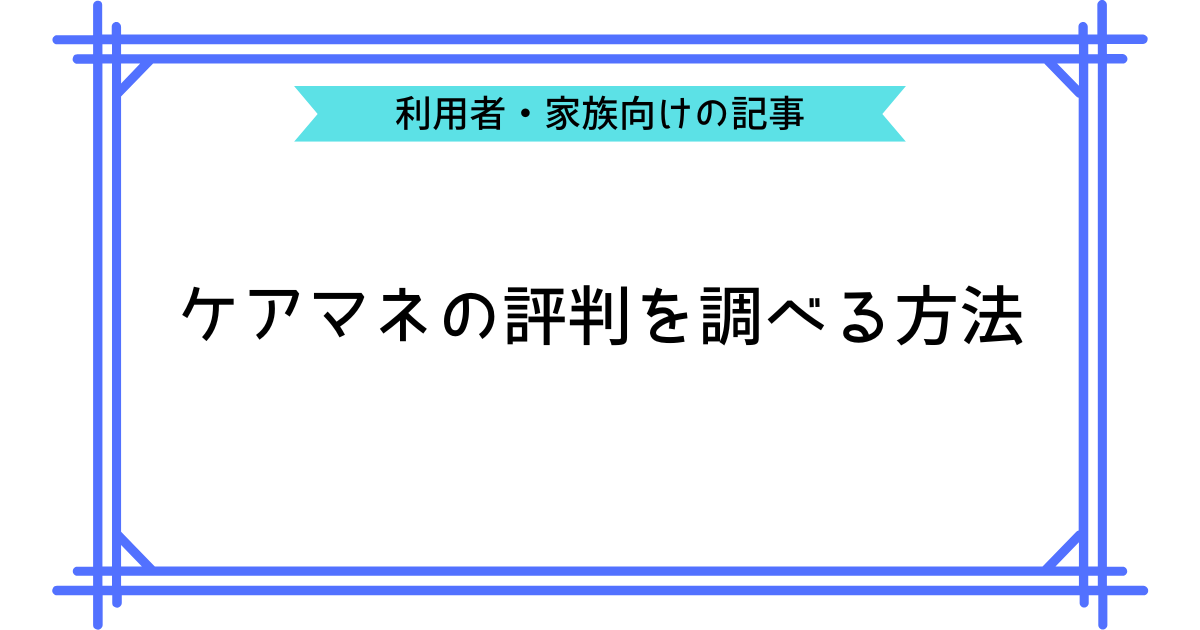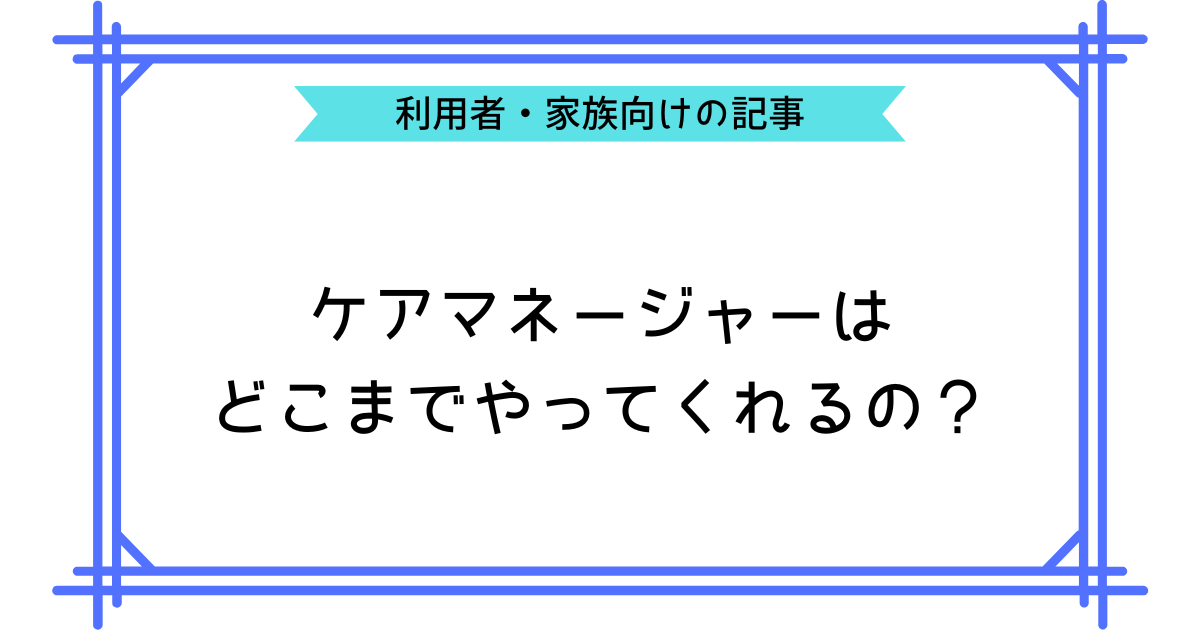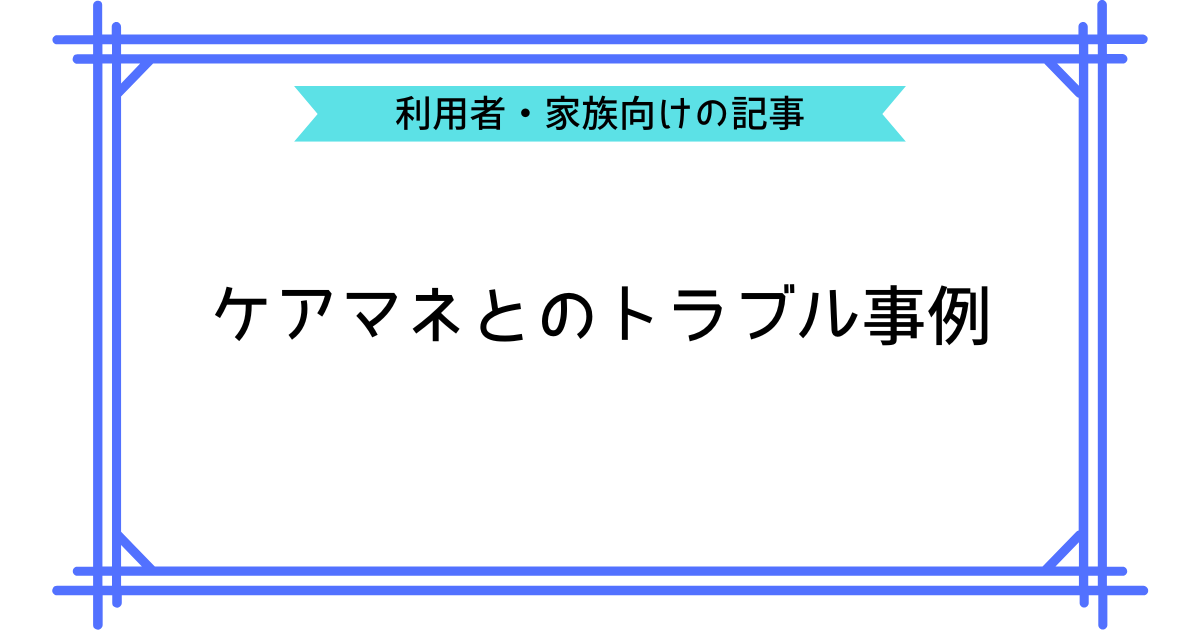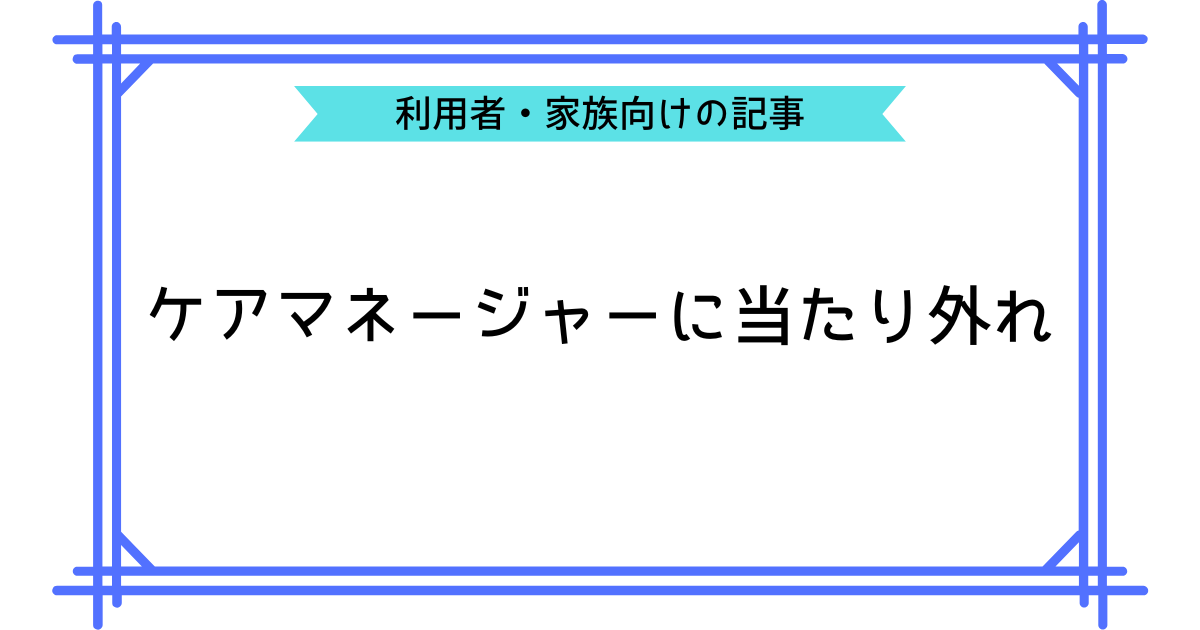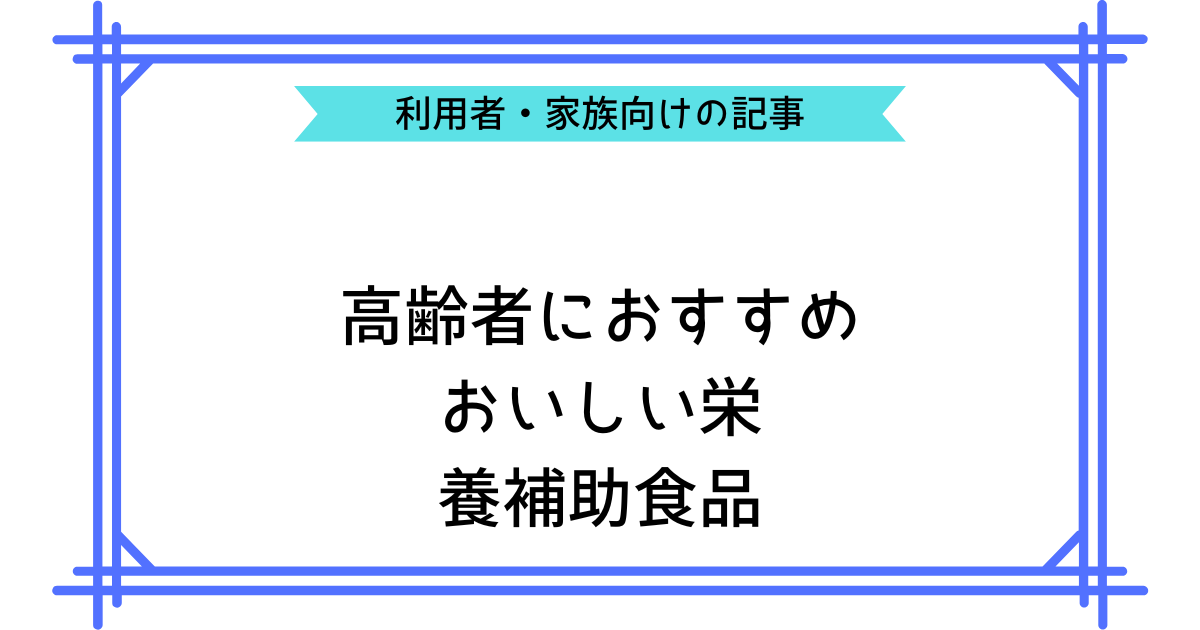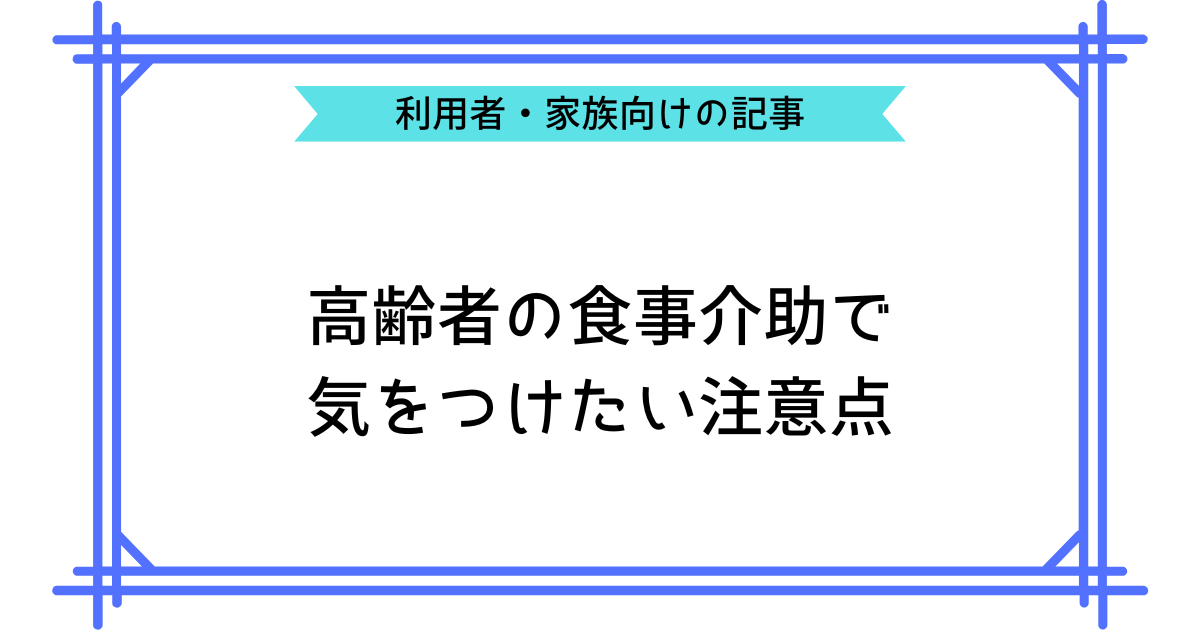ヘルパーができること・できないこと一覧を徹底解説!家族が知っておくべきルール
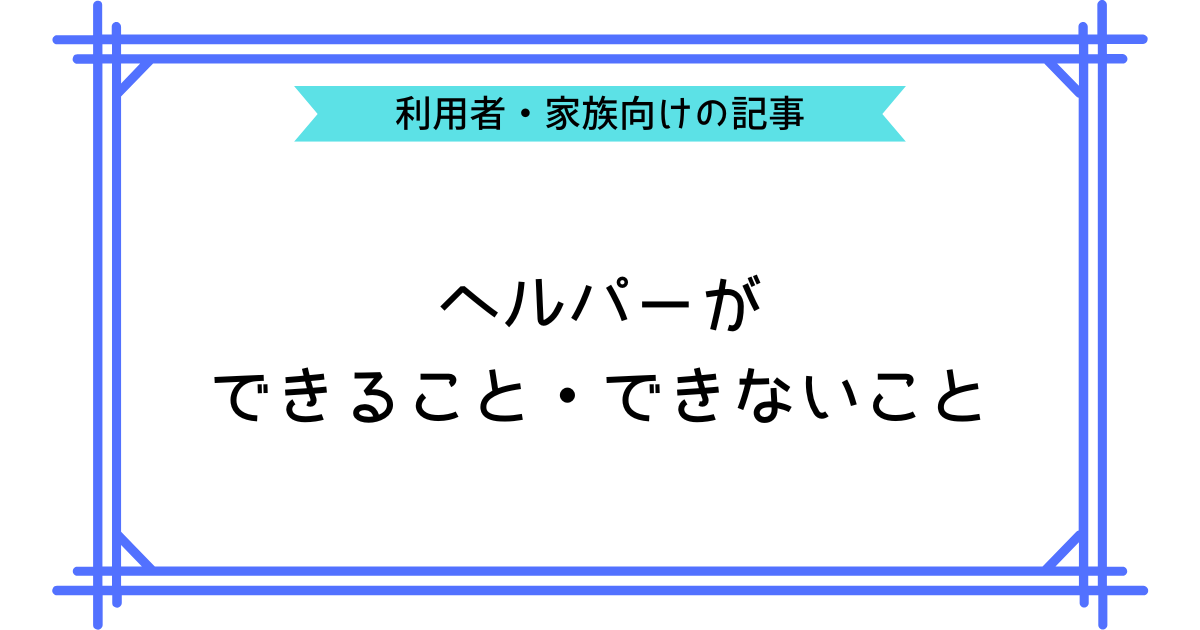
訪問介護(ホームヘルプサービス)は、要介護者が自宅で安心して暮らすために欠かせないサービスです。
しかし「ヘルパーさんはどこまでやってくれるの?」「お願いしたら断られたけど、なぜ?」と疑問を持つ家族も多いのではないでしょうか。
実は、ヘルパーができること・できないことは介護保険制度で明確に定められており、原則として“介護の一環に該当するかどうか”が基準となります。
本記事では、利用者や家族が誤解しやすい点を含めて、一覧形式で分かりやすく解説します。
訪問介護(ホームヘルパー)の役割とは?
訪問介護員(ホームヘルパー)は、要介護認定を受けた方に対して、自宅で日常生活を送るための支援を行います。主なサービス内容は以下の2つに分類されます。
- 身体介護:入浴介助、排泄介助、食事介助など、直接利用者の身体に触れて行う介助
- 生活援助:掃除、洗濯、買い物、調理など、利用者の生活を支える日常的な援助
ただし、これらはすべて「利用者本人のため」に限られており、家族の家事や医療行為などはできないと定められています。
ヘルパーができること・できないこと一覧
身体介護に関すること
| できること | できないこと |
|---|---|
| 入浴・シャワーの介助 | 家族の入浴介助 |
| 排泄介助(トイレ・オムツ交換) | ペットの排泄処理 |
| 食事介助(口に運ぶ、見守り含む) | 調理済みの食事を家族に提供 |
| 体位変換、ベッド上での移動介助 | マッサージや医療行為 |
| 外出介助(通院同行など、必要性が認められる場合) | レジャーや買い物の付き添い |
生活援助に関すること
| できること | できないこと |
|---|---|
| 利用者本人の部屋の掃除 | 家族全員の部屋の掃除 |
| 本人が使う衣類の洗濯 | 家族の衣類や布団の洗濯 |
| 本人の食事の調理 | 家族全員分の食事作り |
| 本人の日用品の買い物 | 贅沢品や家族用の買い物 |
| 薬の受け取り(医師の指示あり) | 本人以外の薬の受け取り |
医療行為に関すること
ヘルパーは医療従事者ではないため、原則として医療行為はできません。ただし、一部の「医療的ケア」が認められるケースもあります。
できること
- 点眼薬をさす
- 湿布の貼付・軟膏塗布(医師の指示あり)
- 座薬の挿入(条件付き)
できないこと
- 注射、点滴、胃ろうの管理
- インスリン注射
- 褥瘡の処置
これらは看護師や訪問看護ステーションの役割になります。
ヘルパーにお願いできない理由を理解する
介護保険制度のルール
「本人の生活を支えること」が原則です。家族のための家事や日常的でない依頼は制度の対象外となるため、断られるのは当然のことといえます。
安全性の確保
ヘルパーは医療行為を行う資格を持っていないため、万が一事故が起きた場合に大きなリスクとなります。そのため医療に関わる部分は訪問看護など別のサービスを利用する必要があります。
公平性の観点
もし家族のための家事を引き受けてしまうと、他の利用者との公平性が失われます。介護保険制度はあくまで「要介護者本人」のための制度です。
家族が混同しやすい「グレーゾーン」の事例
掃除の範囲
本人の部屋や使用しているトイレ・浴室は掃除できますが、家族が主に使う部屋や共有部分の掃除は原則できません。ただし、本人の生活に必要と判断されれば一部対応可能な場合もあります。
買い物の範囲
本人が日常的に使う食品や日用品は購入できますが、嗜好品や家族用の品は対象外です。どうしても必要な場合は、ケアマネジャーに相談して生活援助の範囲を調整する必要があります。
食事作り
本人の分は可能ですが、同居家族の分は原則不可です。ただし、同じ鍋で作らざるを得ない場合は「本人分を取り分ける形」で対応するケースもあります。
ヘルパーを上手に活用するためのコツ
ケアマネジャーに相談する
「これはお願いできるの?」と迷ったときは、まず担当ケアマネジャーに確認しましょう。ケアプランに位置付けられれば、制度の範囲内で柔軟にサービスが利用できます。
訪問看護との併用を考える
医療的ケアが必要な場合は、訪問介護ではなく訪問看護を利用することで安心して対応できます。介護と医療を組み合わせることで、在宅生活がより安全に継続できます。
家族と役割分担をする
ヘルパーにできない部分は家族や地域サービスで補うことが現実的です。役割分担を明確にすることで、家族の負担も軽減され、ヘルパーも効率的に働けます。
まとめ
ヘルパーができること・できないことは、介護保険制度に基づき明確に線引きされています。
- できること:本人の入浴介助・排泄介助・食事介助・本人の掃除や洗濯・買い物など
- できないこと:家族の家事・医療行為・本人以外のための対応など
「断られた=冷たい対応」ではなく、制度上のルールや安全性の観点からの判断であることを理解することが大切です。迷ったときはケアマネジャーに相談し、訪問介護・訪問看護・家族の役割を組み合わせていくことで、安心できる在宅生活が実現できます。