【コピペOK】センサーマットのケアプラン文例を100紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
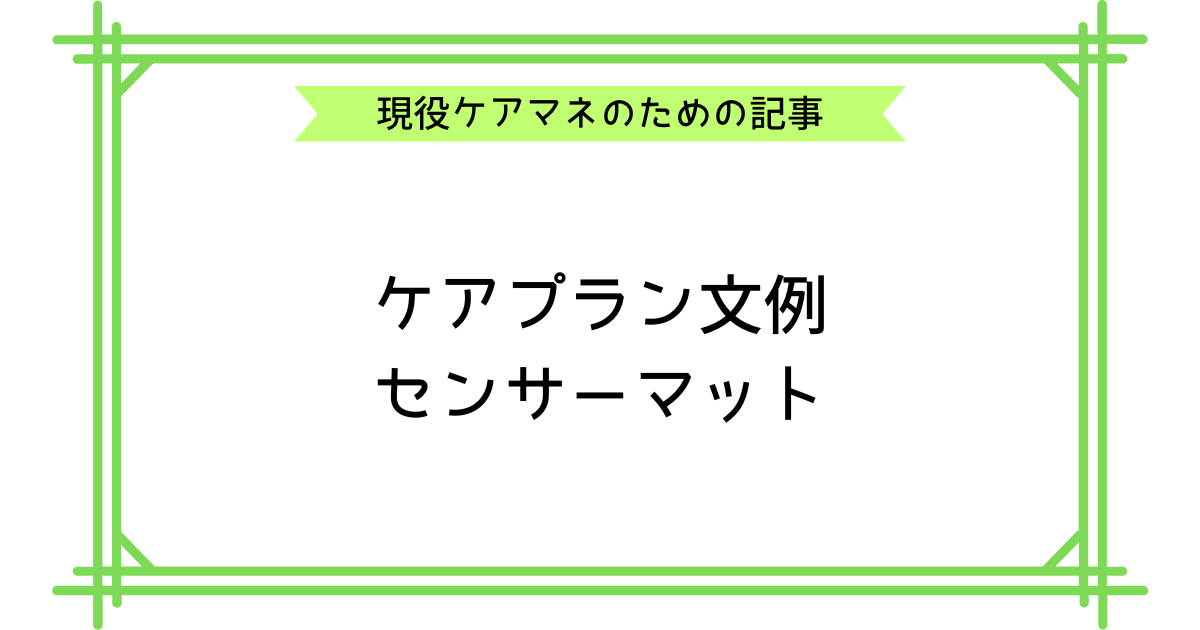
高齢者の介護現場では、転倒や転落、夜間の徘徊による事故のリスクが常に存在します。
その予防策として広く利用されているのが センサーマット です。
ベッドや出入口に設置することで、利用者の動きを感知し、職員や家族が迅速に対応できるようになります。
ケアプランにセンサーマットを盛り込むことで、安全性の向上・安心した生活・介護者の負担軽減 に直結します。
この記事では、【コピペOK】センサーマットのケアプラン文例を100事例 紹介します。
目次
センサーマットのケアプラン文例100
【基本的な安全確保】
- センサーマットを使用し、ベッド離床時にアラームで知らせる。
- 夜間の離床を感知し、職員が速やかに対応できるようにする。
- 転倒防止のため、センサーマットをベッドサイドに設置する。
- 出入口に設置し、徘徊を感知して事故を防ぐ。
- 車椅子移乗時にセンサーマットを活用する。
- 利用者が起き上がった際に介助者へ通知する。
- ベッドからの転落リスクに備え、センサーマットを配置する。
- トイレ移動前にアラームで知らせ、介助につなげる。
- 夜間の徘徊時に早期対応できるようにする。
- 利用者が無断で外出しないよう、玄関に設置する。
【転倒予防】
- センサーマットで離床を感知し、転倒を未然に防ぐ。
- 転倒歴があるため、センサーマットを常時使用する。
- 不安定な歩行が見られるため、感知後に介助を行う。
- 転倒リスクの高い時間帯に重点的に使用する。
- センサーマットの感知により夜間の転倒事故を減らす。
- 起き上がり時のふらつきを早期に確認する。
- 廊下での転倒を防ぐため、出入口に設置する。
- ベッドからの立ち上がりを感知し、見守りを強化する。
- 起床直後の転倒を防ぐよう支援する。
- トイレに急ぐ動作を早期に感知する。
【徘徊・離院対応】
- 認知症による徘徊を感知し、安全に対応する。
- 夜間に施設外へ出ないよう玄関に設置する。
- 徘徊による事故を防ぐために感知システムを導入する。
- 徘徊時は速やかに職員が対応し、安全を確保する。
- ベッドからの離床後に徘徊につながらないよう支援する。
- 認知症利用者の見守りをセンサーマットで補う。
- 出入口での感知により、徘徊を早期に把握する。
- 外出のリスクがある場合はセンサーマットを優先的に使用する。
- 徘徊傾向のある利用者の夜間安全を確保する。
- 離院防止のため、センサーマットで行動を確認する。
【夜間対応】
- 夜間の離床を感知し、見守りを強化する。
- 夜間転倒のリスクがあるため常時使用する。
- 夜間の徘徊を感知し、介助につなげる。
- 夜間巡視の負担を軽減する。
- 夜間の排泄介助をタイミングよく行う。
- 夜間の不安を軽減するため、職員がすぐ対応できるようにする。
- 夜間せん妄に伴う離床を早期に発見する。
- 夜間の異常行動を感知し、安全を確保する。
- 夜間の安心感を高めるために導入する。
- 夜間対応の質を高め、職員の負担を軽減する。
【家族支援】
- 家族が不在時も安全を確保するために使用する。
- 家族が安心して外出できるようセンサーマットを活用する。
- 家族の介護負担軽減を目的に導入する。
- 家族にアラームの使い方を説明する。
- 家族が夜間休めるようセンサーマットを利用する。
- 家族に日中の使い方を指導する。
- 家族に緊急時の対応方法を伝える。
- 家族の不安を軽減する目的で使用する。
- 在宅生活継続のために家族と協力して活用する。
- 家族に定期的に使用状況を報告する。
【施設職員支援】
- 職員が速やかに対応できるよう通知システムと連動する。
- センサーマットで業務効率を高める。
- 職員の巡視回数を減らし、業務負担を軽減する。
- 職員間で使用ルールを統一する。
- 事故発生時の対応時間を短縮する。
- センサーマットの記録を職員で共有する。
- アラーム誤作動への対応方法を明確にする。
- 職員研修を行い、正しく使用できるようにする。
- 夜勤者の負担軽減を目的に導入する。
- 施設全体で安全管理体制を強化する。
【環境整備】
- ベッドサイドにマットを設置し、離床を感知する。
- トイレ前に設置し、移動を感知する。
- 出入口に設置し、徘徊を防止する。
- 居室に合わせて設置場所を調整する。
- 設置位置を定期的に見直す。
- 床の段差をなくし、マットが安定するようにする。
- 電源や配線の安全を確認する。
- 設置状況を職員間で共有する。
- 利用者の動線に合わせた配置を行う。
- 必要に応じて複数台を使用する。
【心理的支援】
- センサーマットの存在を説明し安心感を与える。
- 利用者に「安全のため」と説明し不安を軽減する。
- センサーマット使用に抵抗がある場合は傾聴する。
- 利用者が安心して休めるよう声かけを行う。
- センサーマット導入で本人の孤独感を軽減する。
- 利用者に成功体験を積ませ、安心して使用できるようにする。
- 不安時には職員がそばに行くことを約束する。
- 本人の気持ちを尊重し、使用方法を調整する。
- センサーマットを安心材料として活用する。
- 家族と連携し心理的負担を軽減する。
【将来を見据えた支援】
- 使用状況を定期的にモニタリングする。
- 転倒リスクの変化に応じて使用を見直す。
- 身体機能低下に応じて使用を継続する。
- 状況改善が見られた場合は使用を中止する。
- 利用者の希望に応じて使用可否を検討する。
- 他の福祉用具と組み合わせて使用する。
- 使用により介護負担が軽減されたか評価する。
- 医師・看護師と連携し、適切な使用を続ける。
- 将来的な在宅継続を見据えて活用する。
- ケアプランを定期的に見直し、必要性を再検討する。
【その他・多職種連携】
- 看護師と連携し、医療的管理と合わせて活用する。
- 理学療法士と協力し、安全な移動を支援する。
- 介護職員間で情報共有し、対応を統一する。
- ケアマネジャーと連携し、サービス調整を行う。
- 家族と協議し、使用目的を明確にする。
- 記録を残し、事故防止に役立てる。
- 定期的にアラーム作動状況を確認する。
- メーカーの点検を受け、安全を確保する。
- 多職種で会議を行い、効果を検討する。
- センサーマットを通じて「安全・安心な生活」を目指す。
まとめ
センサーマットは、転倒予防・離床感知・徘徊対応・夜間の安全確保・家族や職員の負担軽減 に大きな効果を発揮します。
今回紹介した100のケアプラン文例は、居宅・施設・訪問介護など幅広い場面でそのまま活用でき、利用者の安全と安心を高めるための実用的な内容です。
利用者の状況に応じてアレンジし、最適なケアプラン作成にご活用ください。















