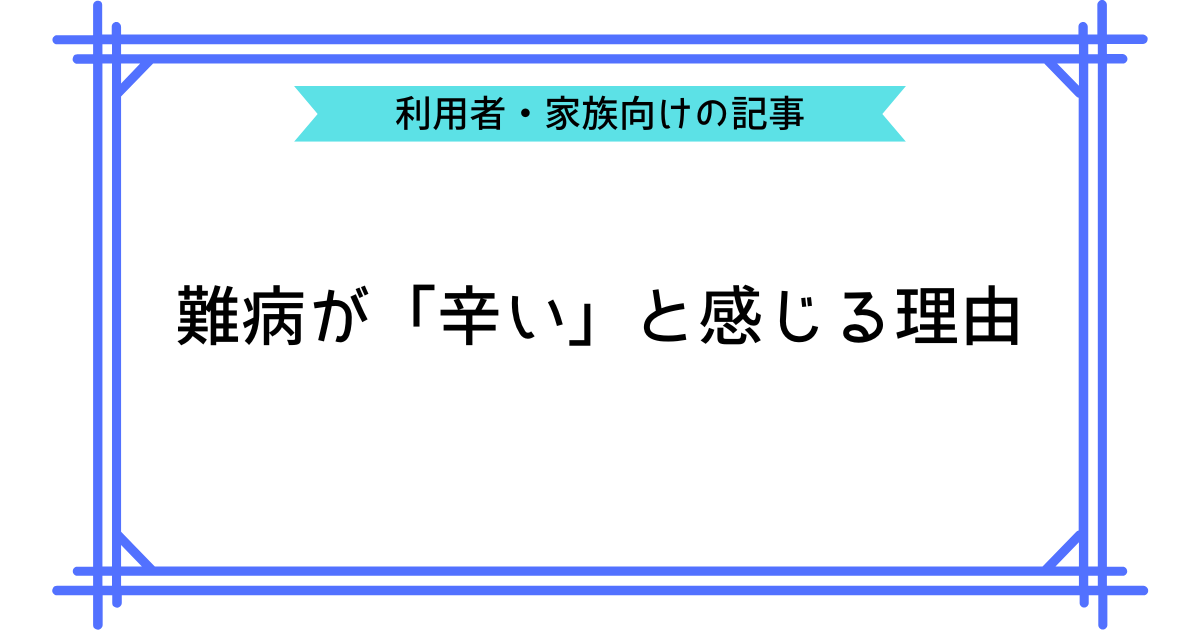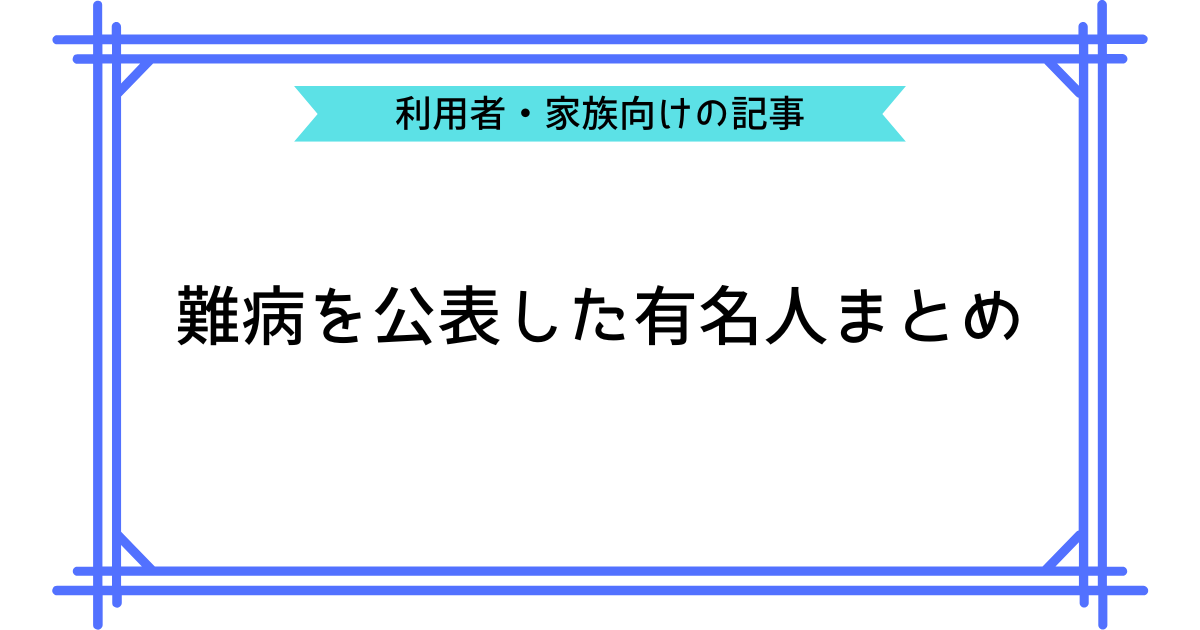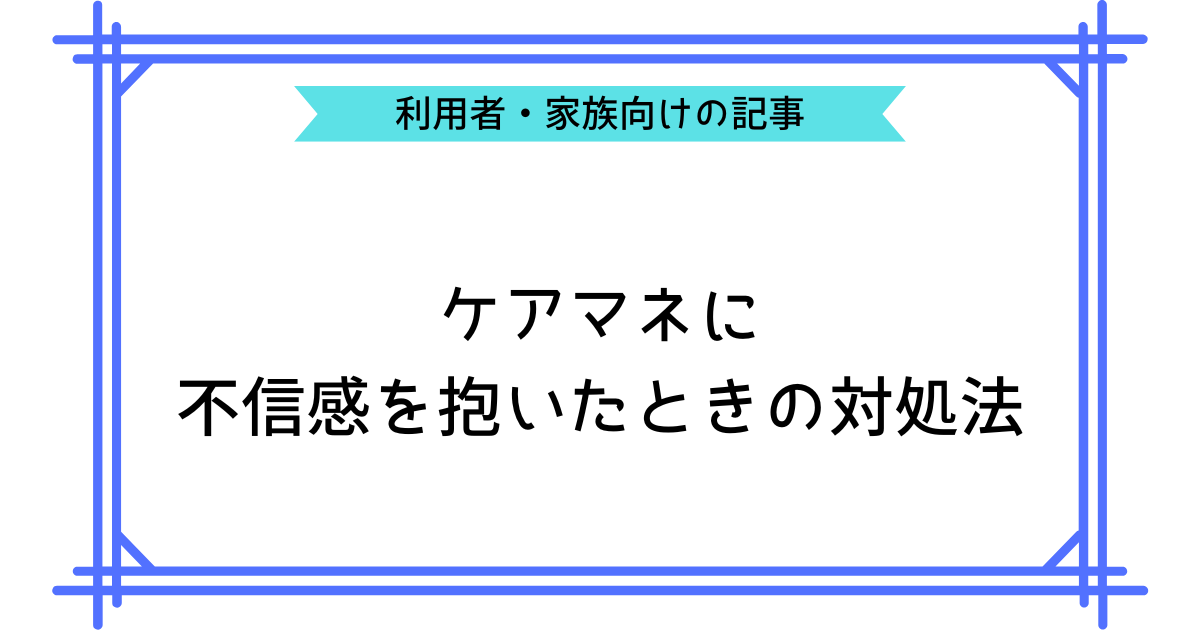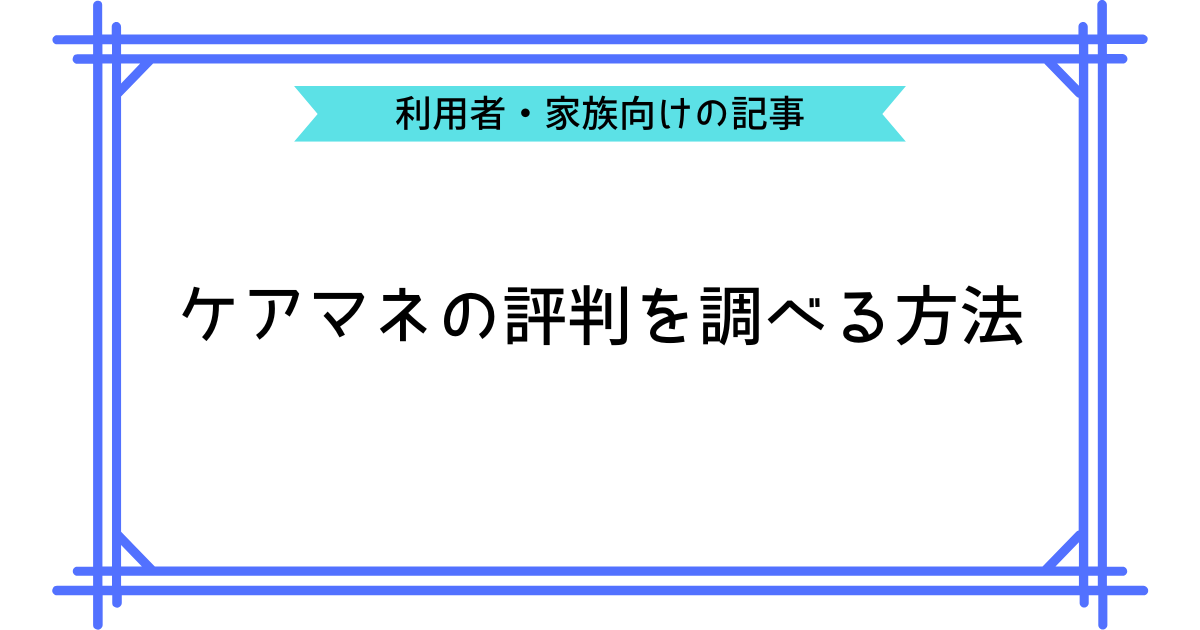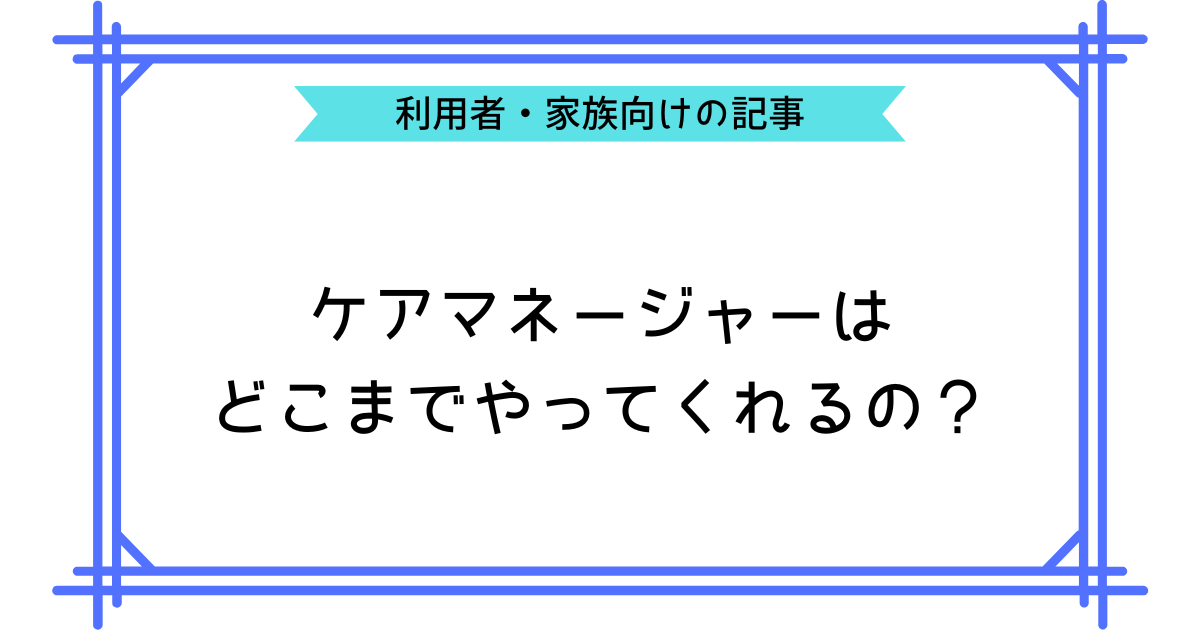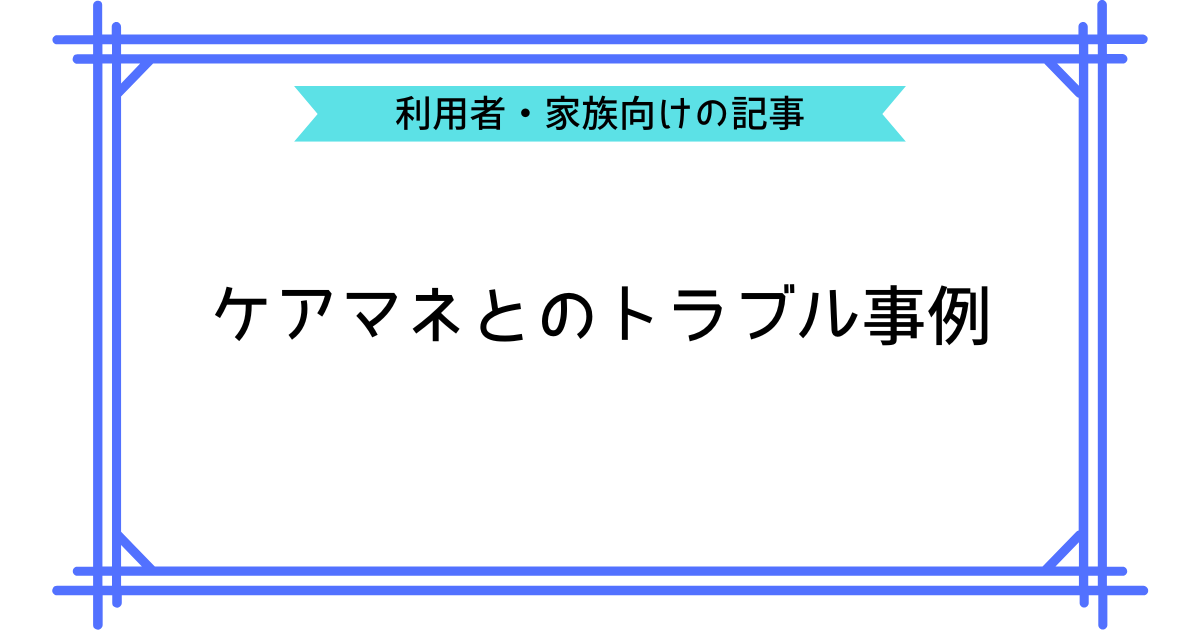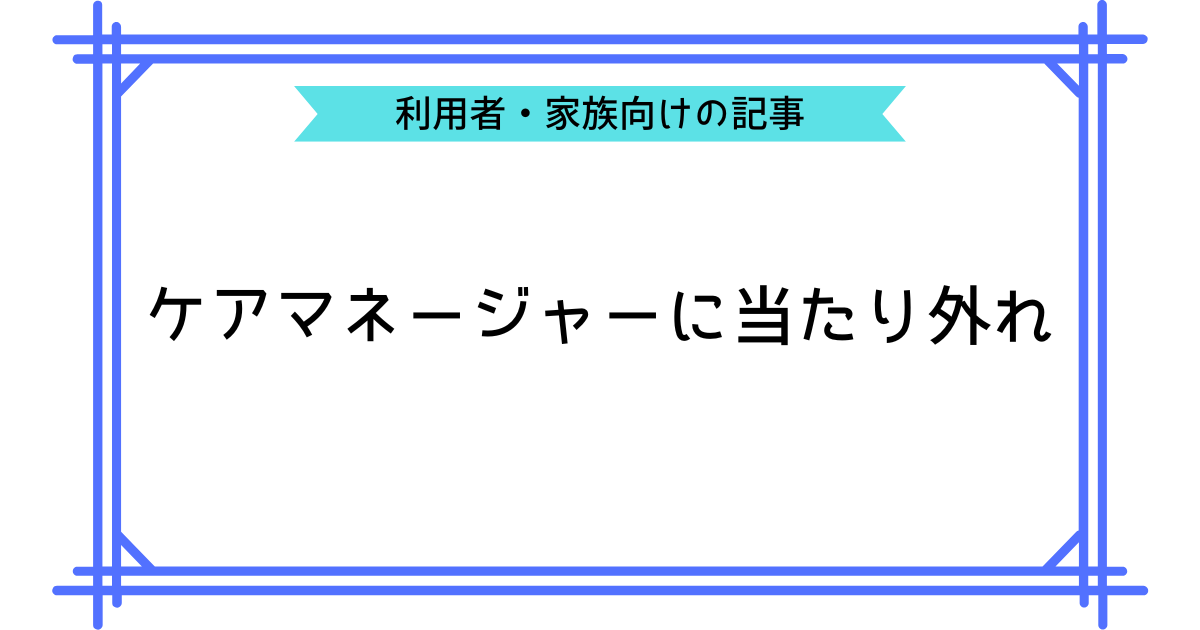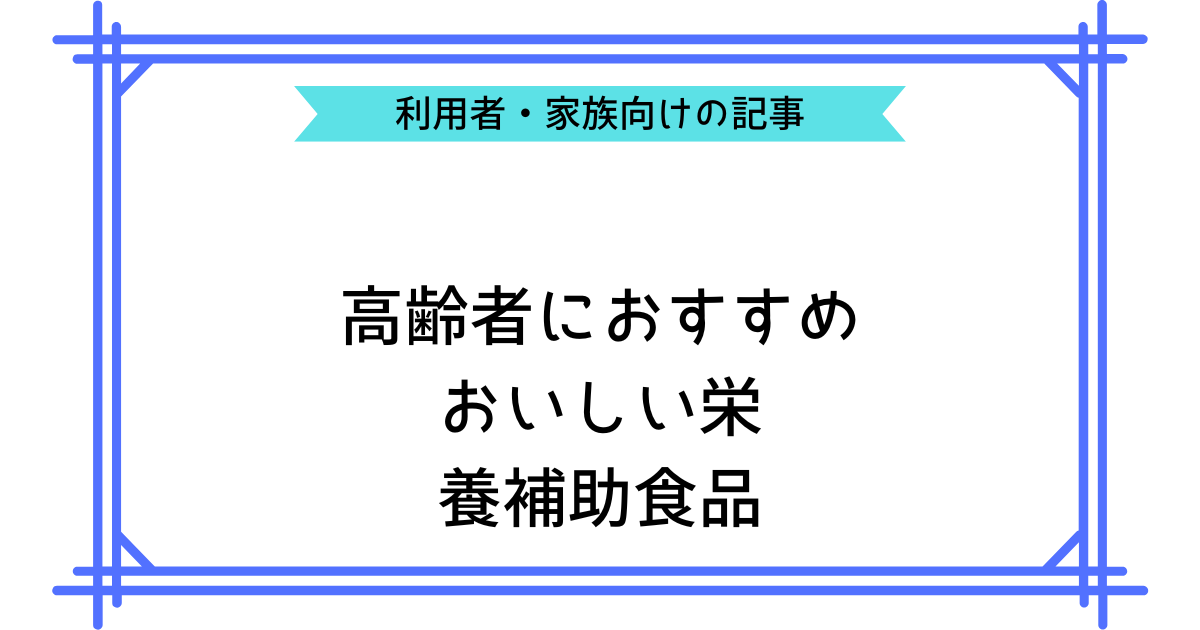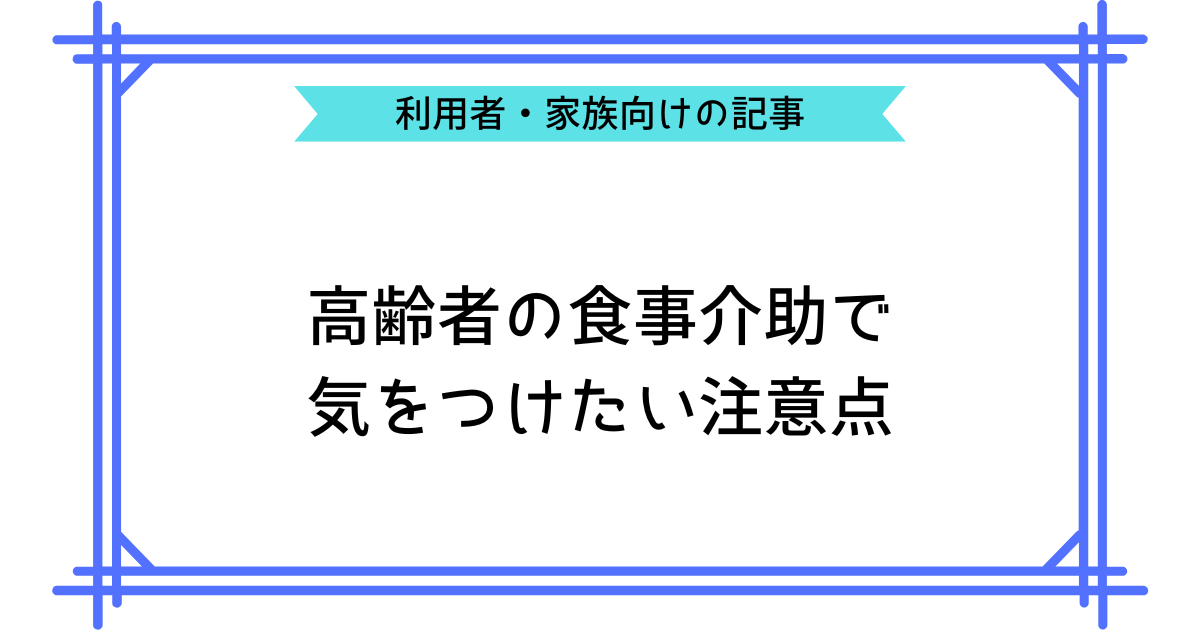日本人に多い難病とは?患者数の多い代表疾患と生活への影響をわかりやすく解説
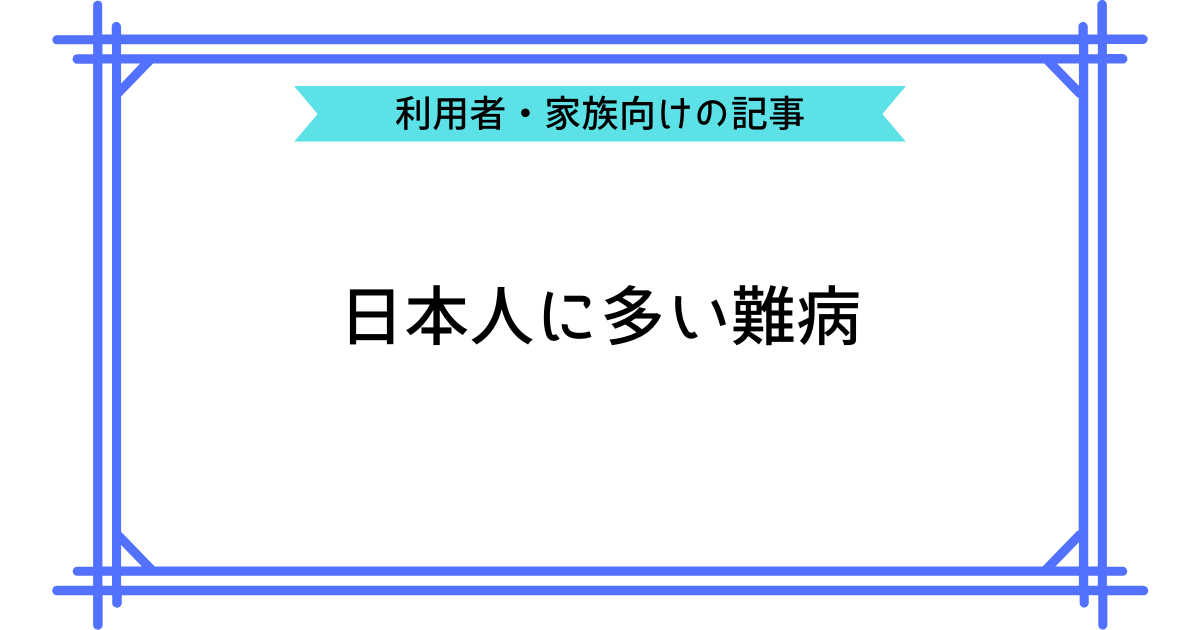
日本人に多い難病とは?定義と現状を理解する
難病とは、原因が不明であったり、根本的な治療法が確立されていない病気を指し、厚生労働省が定める「指定難病」は2025年現在で338疾患にのぼります。日本では「難病法」に基づき、患者や家族への医療費助成や生活支援が行われています。なかでも「日本人に多い難病」は、患者数が多く社会的な影響も大きいため、医療や福祉の現場で特に注目されています。患者数が多いということは、医療機関の対応体制や研究が進みやすいという側面もありますが、同時に社会全体での理解が求められる課題でもあります。本記事では、日本人に多い難病をランキング形式で紹介し、その特徴や症状、生活への影響を詳しく解説します。
日本人に多い難病ランキング|患者数からみる現状
第1位:潰瘍性大腸炎(約22万人以上)
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が起こる炎症性腸疾患で、厚生労働省の調査によると日本での患者数は年々増加し、2025年時点で22万人以上とされています。症状としては血便や下痢、腹痛、発熱などが繰り返し現れ、慢性的に続くため生活の質(QOL)を大きく下げます。20〜30代の若年層に発症が多く、仕事や学業に支障をきたすケースも少なくありません。寛解と再燃を繰り返すため、長期的な治療と自己管理が必要です。日本人に特に多い背景には、食生活の欧米化や腸内環境の変化が指摘されています。
第2位:クローン病(約7万人以上)
潰瘍性大腸炎と同じく炎症性腸疾患に分類されるクローン病は、消化管のどの部位にも炎症が起こり得る疾患です。若年層での発症が多く、長期にわたる下痢や腹痛、体重減少が特徴です。症状の重さだけでなく、食事制限や手術が必要になる場合が多く、患者の生活は大きく制約されます。日本では患者数が7万人を超えており、難病の中でも増加傾向が顕著な疾患のひとつです。
第3位:全身性エリテマトーデス(SLE:約6万人以上)
自己免疫疾患の代表格である全身性エリテマトーデス(SLE)は、免疫が自分の臓器や組織を攻撃してしまう病気です。関節痛や皮膚症状、腎臓障害、肺や心臓への影響など多岐にわたる症状があり、寛解と再発を繰り返します。日本では特に女性に多く、患者数は6万人を超えています。治療にはステロイド薬や免疫抑制剤が使われますが、副作用も強いため、日常生活の調整が不可欠です。
第4位:パーキンソン病(約15万人以上)
中高年以降に多い神経変性疾患であるパーキンソン病は、手足の震えや筋肉のこわばり、動作緩慢などの運動障害を特徴とします。進行すると転倒や寝たきりにつながることもあり、高齢化社会の日本において患者数は増加しています。2025年時点で15万人以上が罹患しているとされ、介護保険サービスを利用する高齢者の中でも多く見られる疾患です。薬物療法やリハビリで症状を緩和しながら長期的に向き合う必要があります。
第5位:筋萎縮性側索硬化症(ALS:約1万人以上)
ALSは運動ニューロンが徐々に壊れていくことで、全身の筋力が失われていく難病です。発症後数年で呼吸筋が侵され人工呼吸器が必要になる場合も多く、社会的にも注目される難病のひとつです。患者数は1万人以上と他疾患に比べ少ないものの、進行の速さや介護負担の大きさから「最も辛い難病」と言われることがあります。日本ではiPS細胞を用いた治療研究が進められており、将来的な治療法確立が期待されています。
第6位:重症筋無力症(約2万人以上)
神経と筋肉の接合部分に異常が起こり、筋肉に力が入らなくなる病気です。まぶたが下がる、ものが飲み込みにくい、呼吸困難などの症状が出現し、日常生活に大きな支障をきたします。日本人の患者数は2万人以上とされ、男女ともに幅広い年齢層で発症が見られます。
第7位:間質性肺炎(特発性肺線維症など:約6万人以上)
肺が硬くなり、酸素を取り込みにくくなる疾患群です。進行すると呼吸困難が強まり、外出や会話が困難になるケースもあります。日本では高齢者を中心に増加傾向にあり、死亡率も高い難病として知られています。
難病が日本人に多い理由と背景
難病の中には、日本人特有の生活習慣や遺伝的背景が影響していると考えられるものもあります。特に潰瘍性大腸炎やクローン病は、食生活の欧米化やストレス社会の影響で患者数が急増しました。また、自己免疫疾患は女性に多く、妊娠や出産などライフイベントとの関係も指摘されています。高齢化が進む日本では、神経変性疾患や呼吸器系の難病も増えており、社会全体での対応が急務となっています。
日本人に多い難病と生活支援制度
難病患者を支えるために、日本では「難病医療費助成制度」が整備されています。これは指定難病に認定された患者が、医療費の自己負担を軽減できる仕組みです。また、障害者手帳や介護保険制度の利用によって、日常生活の支援や福祉サービスを受けることも可能です。難病は完治が難しいため、医療だけでなく生活全般を支える制度の活用が重要です。患者会やサポートグループの存在も、孤独感を和らげる大きな力となっています。
難病と向き合うための工夫と社会的理解
日本人に多い難病は、患者数が多いだけに医療体制や研究が比較的進んでいますが、それでも完治に至る治療法はまだ限られています。そのため、患者や家族は「病気と共に生きる工夫」を日々積み重ねています。食事制限や服薬管理、リハビリの継続、在宅医療の導入などが代表的です。さらに、社会全体が難病に対する理解を深めることで、偏見や誤解を減らし、より暮らしやすい環境を整えていくことが求められます。
まとめ
日本人に多い難病には、潰瘍性大腸炎やクローン病、パーキンソン病、全身性エリテマトーデスなどがあり、患者数は年々増加しています。これらは日常生活に大きな影響を与え、患者本人だけでなく家族や社会全体に課題をもたらしています。ランキングを通じて代表的な疾患を紹介しましたが、どの難病も「辛さ」は数字では測れません。重要なのは、正しい知識と制度の活用、そして社会的な理解と支援の広がりです。本記事が「日本人に多い難病」への理解を深め、患者や家族を支える一助となれば幸いです。