小規模多機能型居宅介護と訪問看護は併用できる?制度の仕組みと注意点を解説
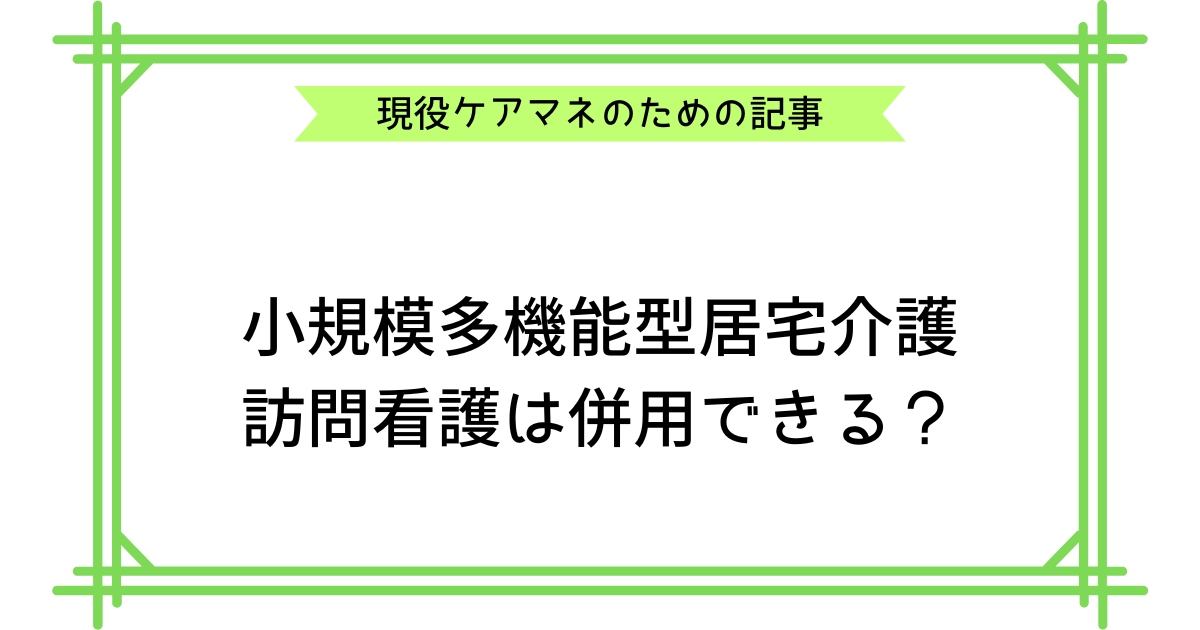
地域密着型サービスの一つである「小規模多機能型居宅介護」は、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて柔軟に支援できるサービスです。一方、医療ニーズの高い方に欠かせないのが「訪問看護」です。
ここでよくある疑問が「小規模多機能型居宅介護と訪問看護は併用できるのか?」という点です。実際には制度上のルールや例外が存在するため、正しく理解していないとケアプラン作成やサービス利用でトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の併用の可否や注意点、実際の活用方法を詳しく解説します。ケアマネジャーや看護師、介護職、利用者家族に役立つ内容をまとめました。
小規模多機能型居宅介護とは?
小規模多機能型居宅介護(以下、小規模多機能)は、地域密着型サービスとして位置づけられており、「通い(デイサービス的機能)」「訪問(訪問介護的機能)」「泊まり(ショートステイ的機能)」を柔軟に組み合わせて提供できるサービスです。
- 登録定員は29人以下
- 通いは1日18人程度まで
- 泊まりは9人程度まで
- 登録した事業所を中心に、生活全般の支援を受けられる
最大の特徴は、「一人の利用者に対して一つの事業所が包括的に関わる」という点です。利用者や家族にとっては、顔なじみのスタッフに継続的に支援してもらえる安心感があります。
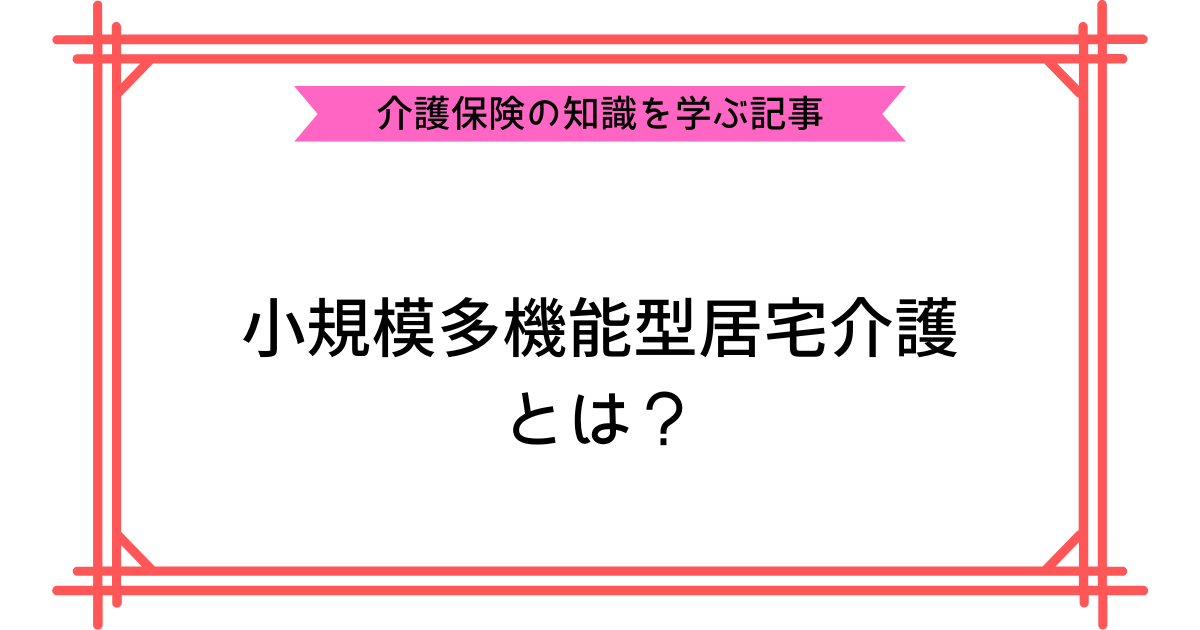
訪問看護とは?
訪問看護は、医師の指示に基づいて看護師やセラピストが自宅を訪問し、医療的ケアを提供するサービスです。
- バイタルチェック(血圧、体温、脈拍など)
- 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
- 点滴や服薬管理
- 在宅酸素や人工呼吸器の管理
- 終末期ケア(ターミナルケア)
医療依存度の高い高齢者や、病気を抱えながら在宅生活を送る方にとって不可欠なサービスです。
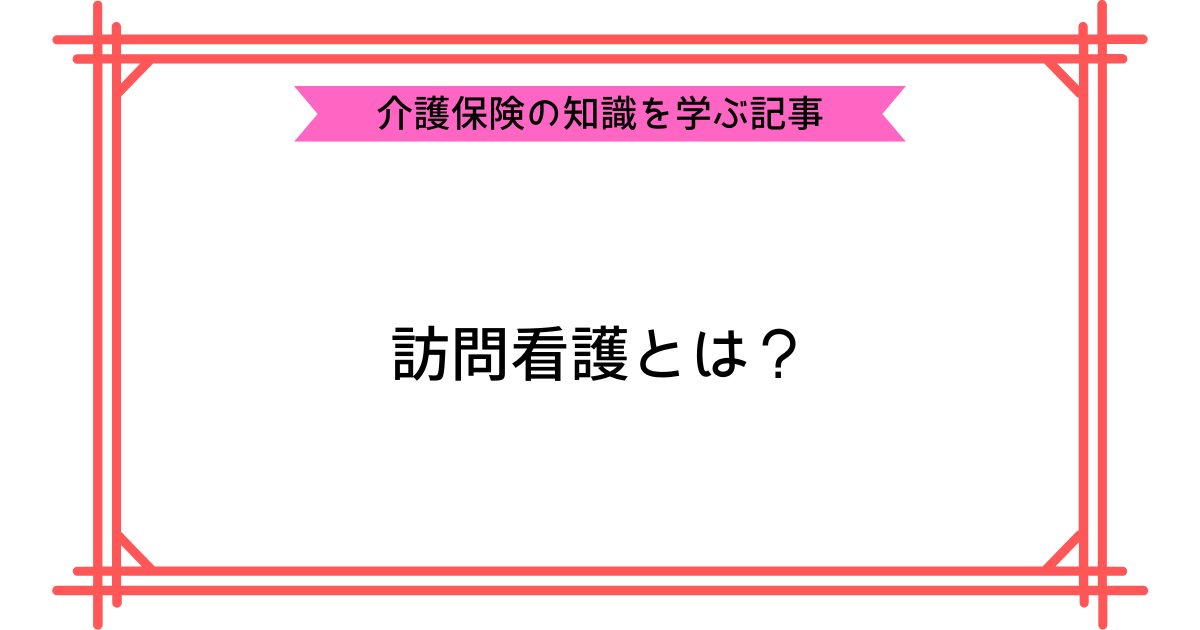
小規模多機能と訪問看護の基本的なルール
原則として、小規模多機能を利用する場合は他の介護保険サービスと併用できないとされています。理由は、小規模多機能が包括的に「通い・訪問・泊まり」を提供する仕組みであり、他サービスと重複すると給付が二重になるからです。
しかし例外的に、訪問看護は併用が認められています。
併用が可能な背景
- 小規模多機能の「訪問」は生活援助や身体介護が中心であり、医療的ケアには対応できない場合が多い
- 訪問看護は医師の指示のもとで行われる医療サービスであり、性質が異なる
- 利用者の医療ニーズに応じて、介護サービスと医療サービスの両立が必要になる
このため、小規模多機能と訪問看護は介護保険制度上でも「併用可」とされています。
小規模多機能と訪問看護を併用する具体例
実際の現場で想定される併用例を挙げてみましょう。
- 認知症の方が小規模多機能を利用しつつ、在宅酸素の管理のため訪問看護を受ける
- 脳梗塞後の後遺症で身体介護が必要な方が小規模多機能を利用し、褥瘡ケアのため訪問看護を併用する
- ターミナル期の方が小規模多機能で生活支援を受けながら、疼痛コントロールのため訪問看護を導入する
このように、生活支援=小規模多機能、医療ケア=訪問看護という役割分担が基本です。
併用する際の注意点
ケアプラン上の位置づけ
ケアマネジャーは、訪問看護を位置づける際に「小規模多機能の包括的支援では対応できない医療行為があるため」と明記する必要があります。
情報共有
小規模多機能の職員と訪問看護師の間で、利用者の体調や生活状況の情報を密に共有することが不可欠です。連携不足は、サービスの重複や抜け漏れの原因になります。
費用負担
小規模多機能は定額制(包括報酬)である一方、訪問看護は回数に応じて費用が発生します。家族に十分に説明し、納得を得たうえで導入することが大切です。
医師の関与
訪問看護は必ず医師の指示書が必要です。医療ニーズの変化に応じて、定期的に主治医と方針を確認する必要があります。
小規模多機能と訪問看護を効果的に併用するポイント
- 本人と家族の希望を丁寧に聞き取る
- ケアマネジャーが両サービスを調整し、役割分担を明確にする
- 医療ニーズの変化に応じて柔軟にサービスを見直す
- 定期的なカンファレンスを開催し、情報共有を徹底する
まとめ
小規模多機能型居宅介護は「通い・訪問・泊まり」を包括的に支えるサービスですが、医療的ケアが必要な場合は訪問看護を例外的に併用することが認められています。
- 小規模多機能=生活支援の中心
- 訪問看護=医療ケアの中心
という役割分担を理解し、ケアプランに適切に位置づけることが重要です。併用の際には情報共有と費用説明をしっかり行い、利用者と家族にとって安心できる支援体制を整えましょう。















