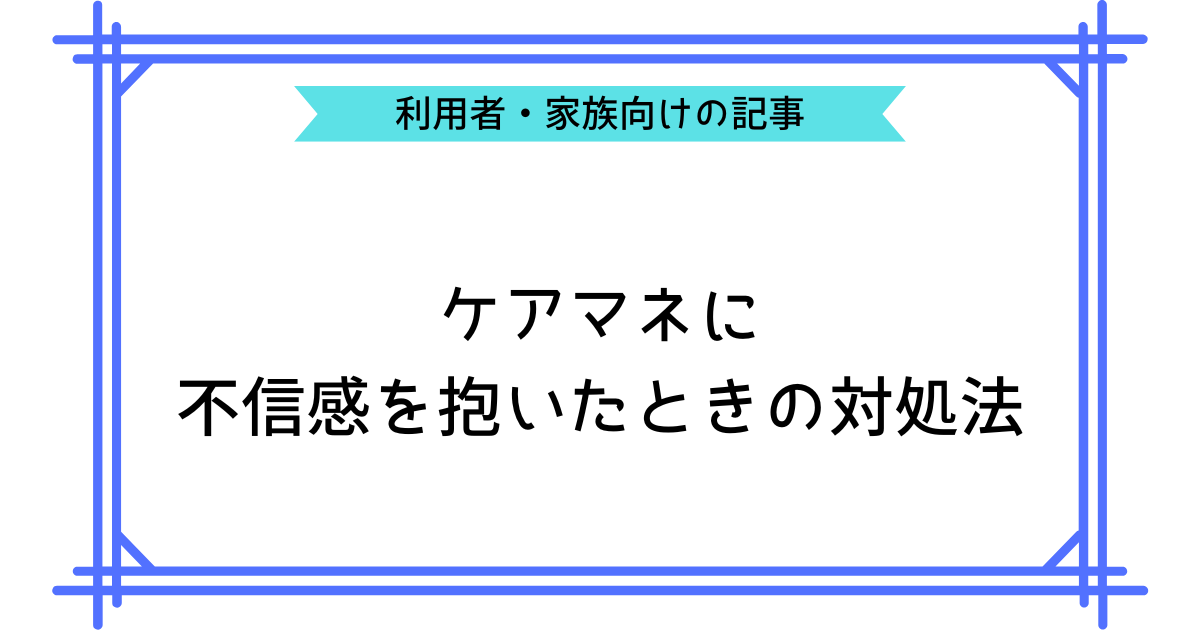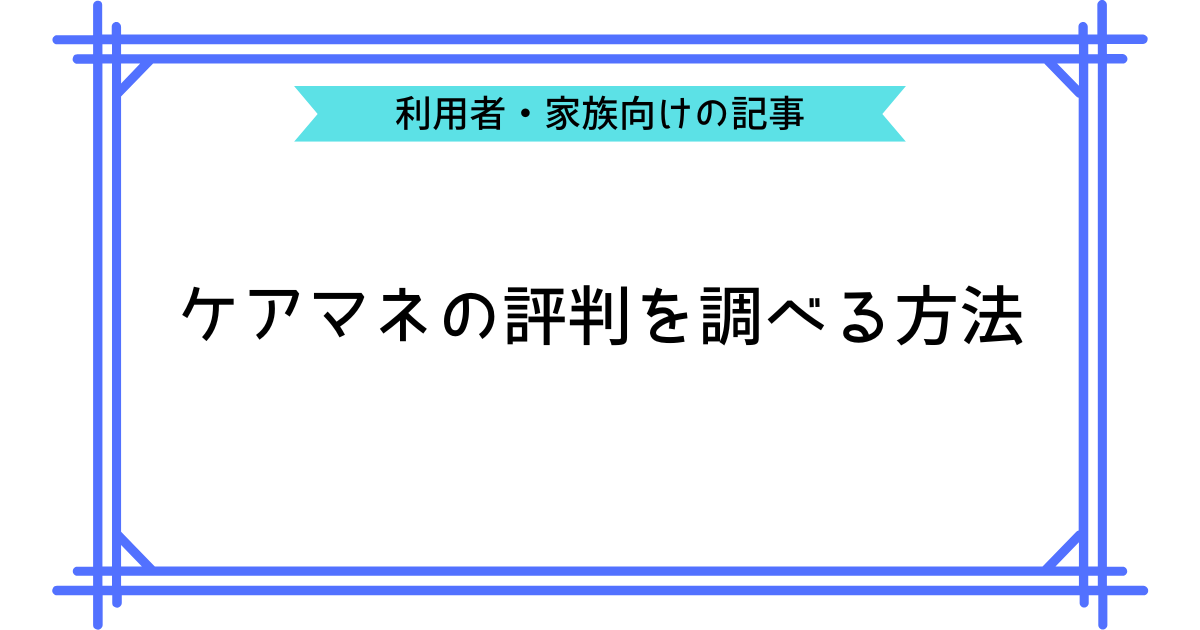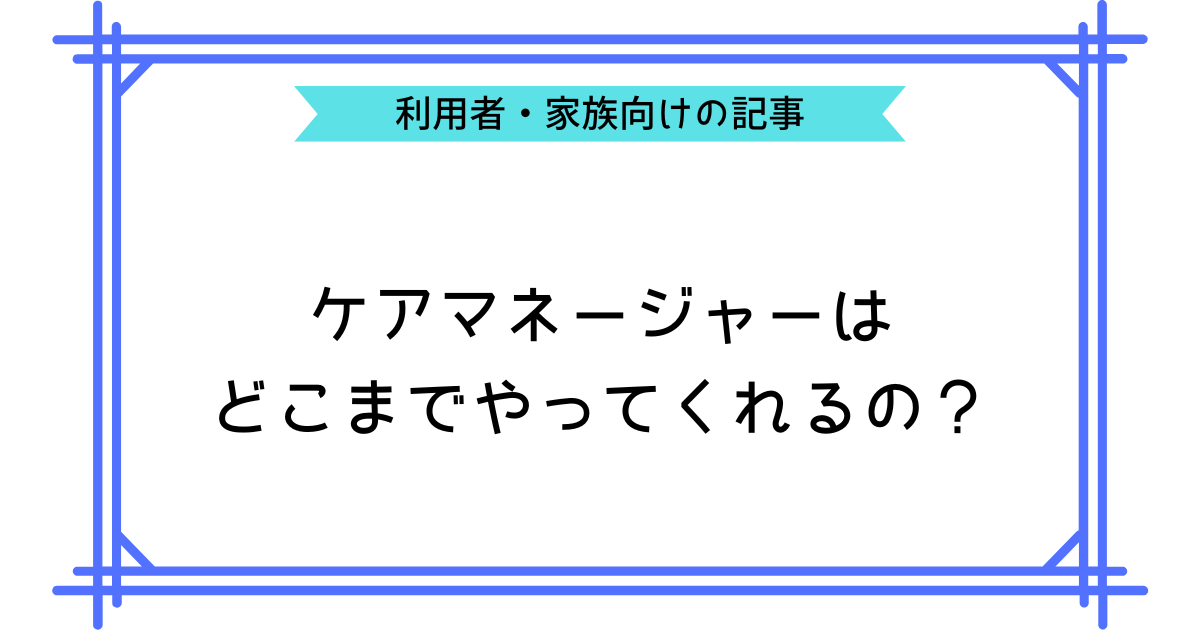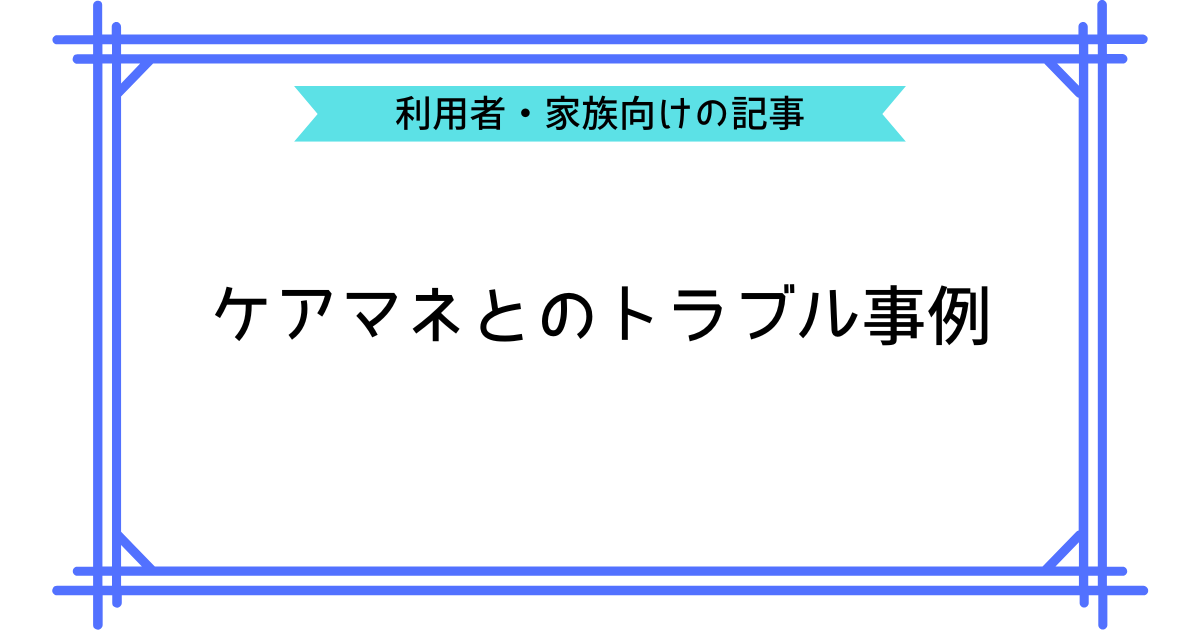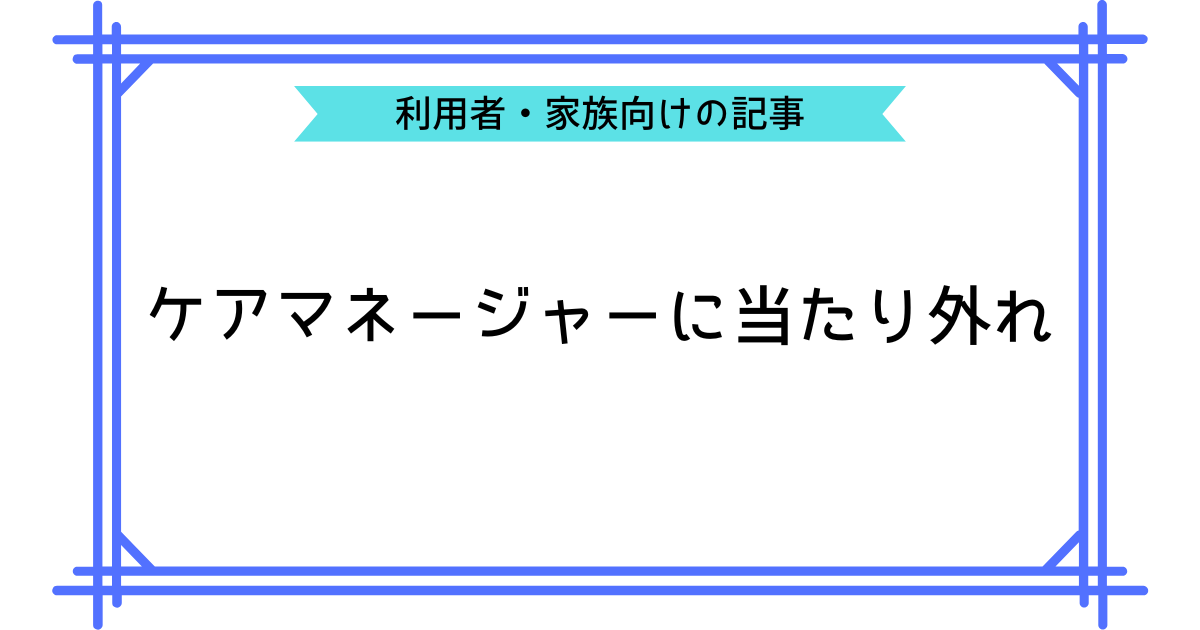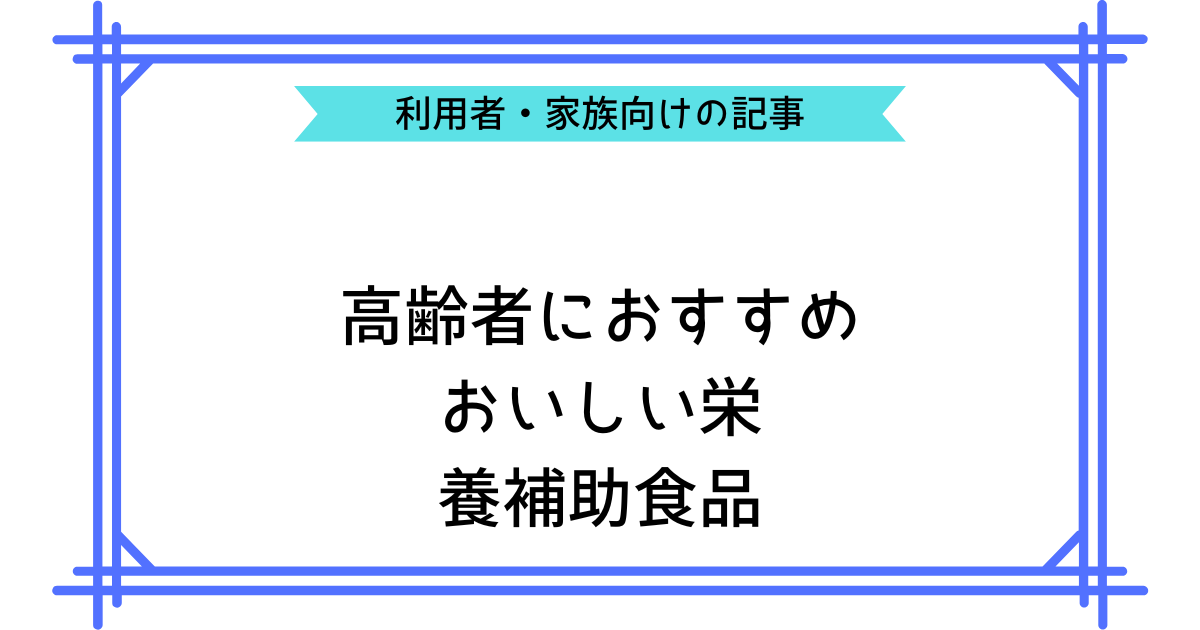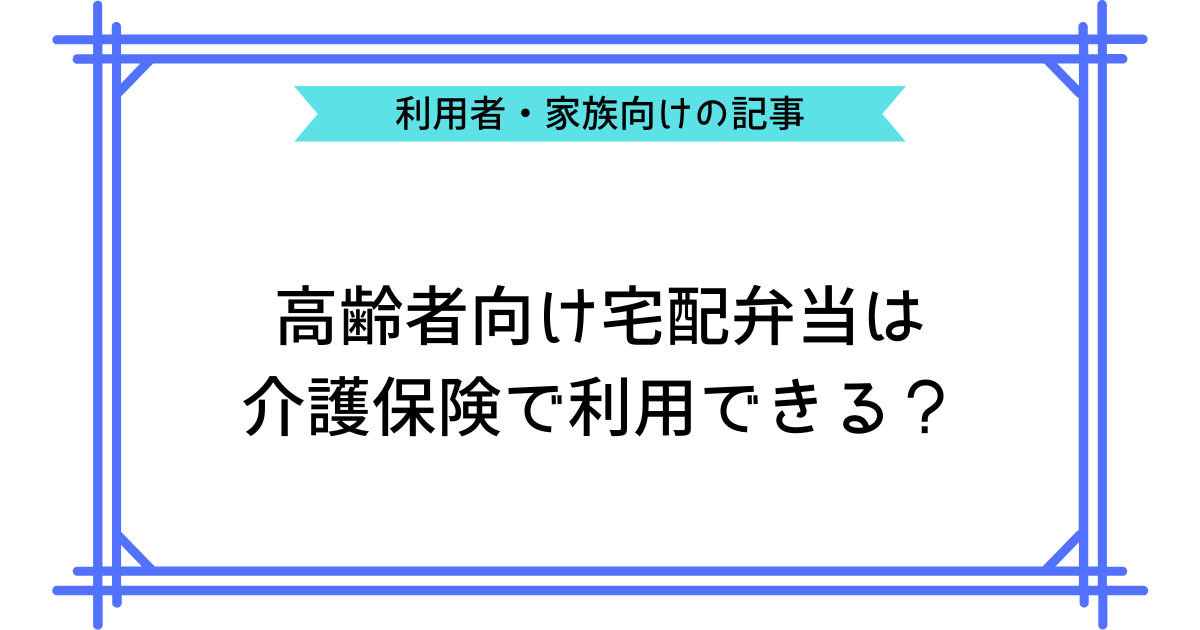高齢者の食事介助で気をつけたい注意点|家族が知っておきたい安全な介助の方法
当ページのリンクには広告が含まれています。
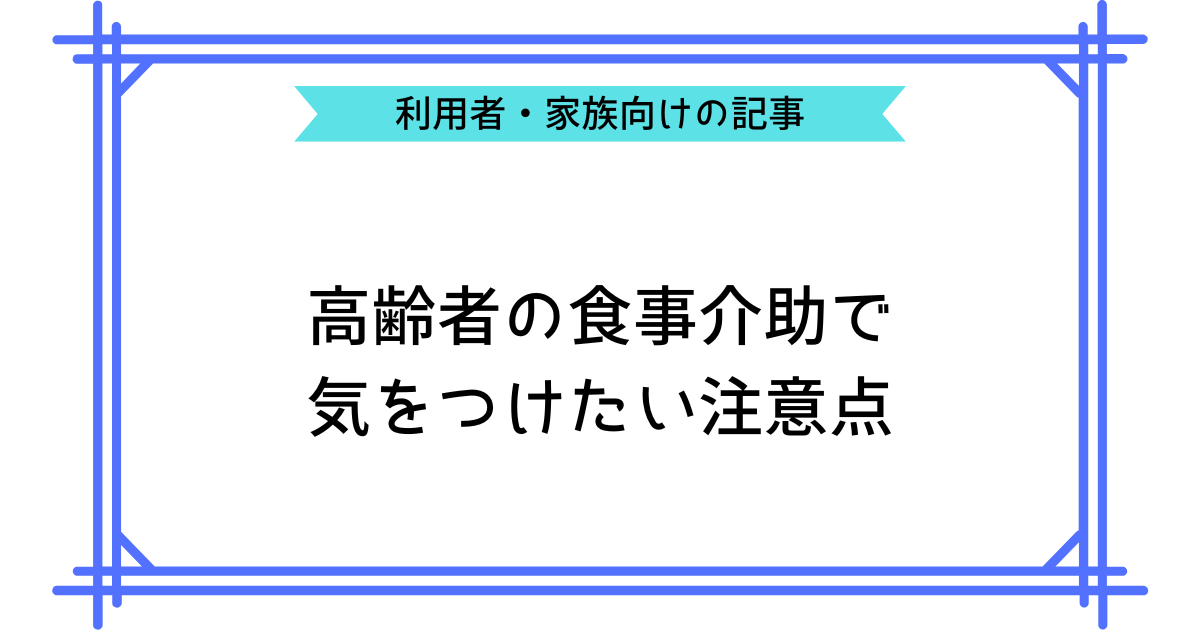
高齢になると、嚥下機能(食べ物を飲み込む力)や咀嚼力(噛む力)が低下し、食事中にむせたり、誤嚥(食べ物が気管に入ること)が起きやすくなります。
そのため、高齢者の食事介助では、ただ「食べさせる」だけでなく、安全面や心理面への配慮が欠かせません。
本記事では、ご家庭で家族が高齢者の食事介助を行う際に気をつけたい注意点を、姿勢・食事内容・介助の仕方・声かけのポイントなど具体的に解説します。
目次
食事介助で最も大切なのは「姿勢の確保」
高齢者の食事介助でまず意識すべきは、食べるときの姿勢です。誤嚥の多くは姿勢不良によって起こります。
正しい姿勢のポイント
- 椅子や車椅子に座り、背筋をまっすぐに保つ
- 足は床またはフットレストにしっかりつける
- 顎を少し引いた姿勢を取る(上を向くと飲み込みにくい)
- ベッド上の場合は背もたれを 30〜45度程度 起こす
姿勢を整えることで、食べ物が食道へスムーズに流れやすくなり、むせ込みや誤嚥を予防できます。
食事内容にも工夫が必要
介助の際は、食べ物の形状や硬さにも注意しましょう。
誤嚥を防ぐための工夫
- 水分はそのままだと気管に入りやすいため、とろみをつける
- 硬いもの・パサつきやすいもの(乾いたパン・おせんべいなど)は避ける
- 一口の量は少なめにする
- 嚥下食やソフト食など、本人の嚥下状態に合わせた調理形態にする
また、栄養バランスを整えることも大切です。主食・主菜・副菜を組み合わせ、少量でもエネルギーとたんぱく質を補える食事が望ましいです。
食事介助の仕方の注意点
スプーンの使い方
- スプーンは口の奥まで入れず、唇に軽く触れる位置で止める
- 口に入れたらすぐに引かず、本人が舌で取り込むのを待つ
オールステンレスハンドル (スポンジNS-2付)
ペース配分
- 1口ごとにしっかり飲み込んだか確認してから次を運ぶ
- 本人のペースを尊重し、急がせない
介助する位置
- 本人の斜め前から介助すると、自然に飲み込みやすい
- 真横や背後からの介助は誤嚥につながりやすいため避ける
声かけや心理面の配慮
食事介助は「安全に食べる」ことだけでなく、「楽しく安心して食べられる雰囲気」をつくることも大切です。
- 「美味しそうですね」「ゆっくりどうぞ」と優しく声をかける
- 無理に食べさせず、本人の意思を尊重する
- 食欲がないときは、好物を少量取り入れる
- 食事中はテレビなどの刺激を減らし、落ち着いた環境を整える
食事は栄養補給だけでなく、生活の楽しみでもあります。安心できる雰囲気をつくることで、食欲が増すこともあります。
食後のケアも忘れずに
食事が終わった後のケアも重要です。
- 食後30分程度は座位を保つ(逆流や誤嚥防止)
- 口腔ケアを行い、食べかすや細菌を除去する(誤嚥性肺炎予防につながる)
- 水分補給を促し、口内や喉の乾燥を防ぐ
食後の対応まで丁寧に行うことで、誤嚥や体調不良を防げます。
あわせて読みたい

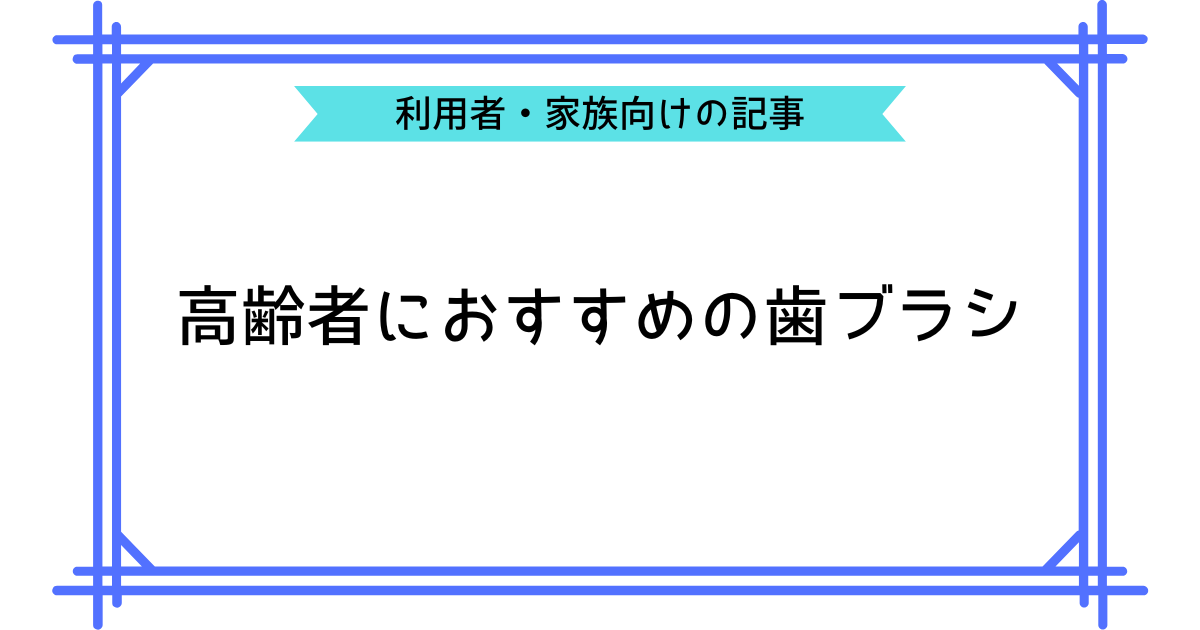
高齢者におすすめの歯ブラシ・歯磨き粉・口腔ケアアイテムとは?
高齢になると、加齢や持病、服薬の影響により歯や口腔環境に変化が現れます。虫歯や歯周病だけでなく、口の乾燥(ドライマウス)、入れ歯の使用、嚥下機能の低下など、...
まとめ
高齢者の食事介助では、姿勢を整えること、食事の形態を工夫すること、スプーンの使い方やペース配分に注意することが重要です。
また、声かけや雰囲気づくりで「楽しい食事時間」にする工夫も欠かせません。
さらに食後の座位保持や口腔ケアを徹底することで、誤嚥性肺炎などのリスクを減らせます。
家族が正しい注意点を理解して介助することで、高齢者の安全で快適な食生活を支えることができます。