支給限度額とは?わかりやすく解説|介護保険サービスを使う前に知っておきたい基礎知識
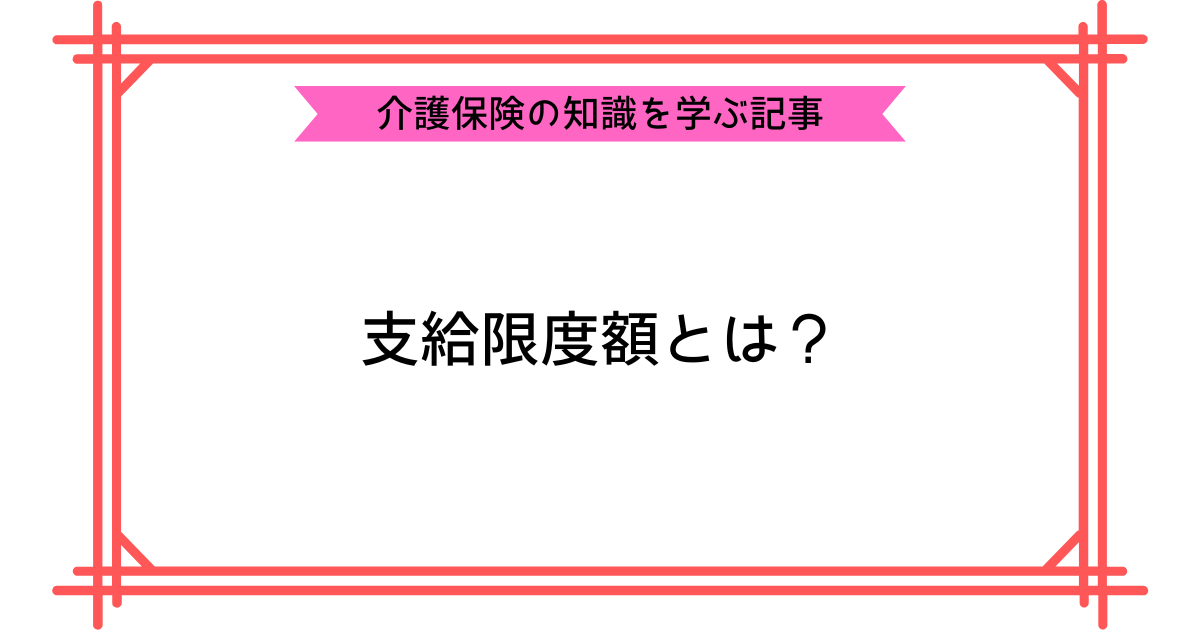
介護保険を利用する際によく耳にする「支給限度額」。
しかし「具体的にどういう意味?」「自分はいくらまで使えるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
支給限度額とは、介護保険サービスを1か月に利用できる上限のことです。
この上限を超えると全額自己負担になってしまうため、正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、介護保険の支給限度額をわかりやすく解説し、実際に利用する際の注意点も紹介します。
支給限度額とは?
支給限度額とは、介護保険サービスを1か月にどれだけ利用できるかを示す「上限金額(単位数)」のことです。
介護保険では要介護度ごとにこの枠が決められており、限度額の範囲内であれば1割〜3割の自己負担で利用できます。
しかし、この限度額を超えると介護保険が適用されず、サービス費用を全額自己負担することになります。そのため、サービスをどのように組み合わせるかは、ケアマネジャーと相談しながら調整することが重要です。
要介護度別の支給限度額(2024年度基準)
介護度によって使える単位数(1単位=約10円)が決まっています。以下は1か月あたりの目安です。
- 要支援1:5,003単位(約50,000円相当)
- 要支援2:10,473単位(約104,000円相当)
- 要介護1:16,765単位(約167,000円相当)
- 要介護2:19,705単位(約197,000円相当)
- 要介護3:27,048単位(約270,000円相当)
- 要介護4:30,938単位(約309,000円相当)
- 要介護5:36,217単位(約362,000円相当)
(※実際の自己負担額は所得区分により1割・2割・3割に変動します)
支給限度額を超えるとどうなる?
自己負担が増える
限度額を超えた分については介護保険が適用されず、サービス費用の 全額を自己負担 しなければなりません。
サービスの組み合わせを見直す必要がある
訪問介護やデイサービス、訪問看護などを組み合わせると、限度額を超えやすくなります。その場合はケアマネジャーが調整し、優先度の高いサービスを残して計画を立て直すことになります。
支給限度額の注意点
サービス利用は単位で管理される
金額ではなく「単位」で管理されているため、サービスごとの単位数を把握しておくことが重要です。
区分変更で限度額が変わる
要介護度が変わると支給限度額も変動します。状態が悪化すれば枠が広がり、改善すれば枠が小さくなります。
介護保険外サービスもある
配食サービスや買い物代行など、一部の支援は介護保険の対象外です。その場合は支給限度額に含まれず、全額自己負担になります。
家族が押さえておきたいポイント
- 支給限度額は「介護度ごとに決められた1か月の上限」
- 限度額を超えると全額自己負担になる
- ケアマネと相談しながらサービスを組み合わせることが大切
- 区分変更や介護度の変化で支給限度額は変わる
まとめ
支給限度額とは、介護保険サービスを利用する際に「どこまで自己負担が軽減されるか」を示す上限のことです。
限度額内であれば1〜3割負担で利用できますが、超えた分は全額自己負担になります。
介護サービスを安心して使うためには、自分の要介護度の支給限度額を理解し、ケアマネジャーと相談しながら計画的に活用することが大切です。















