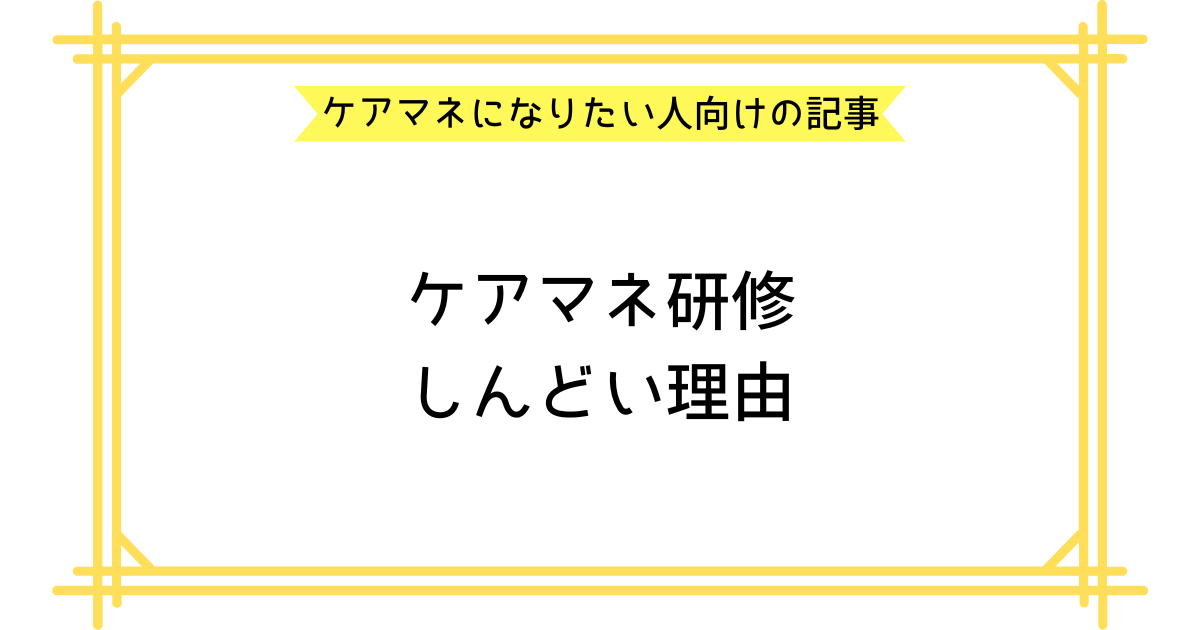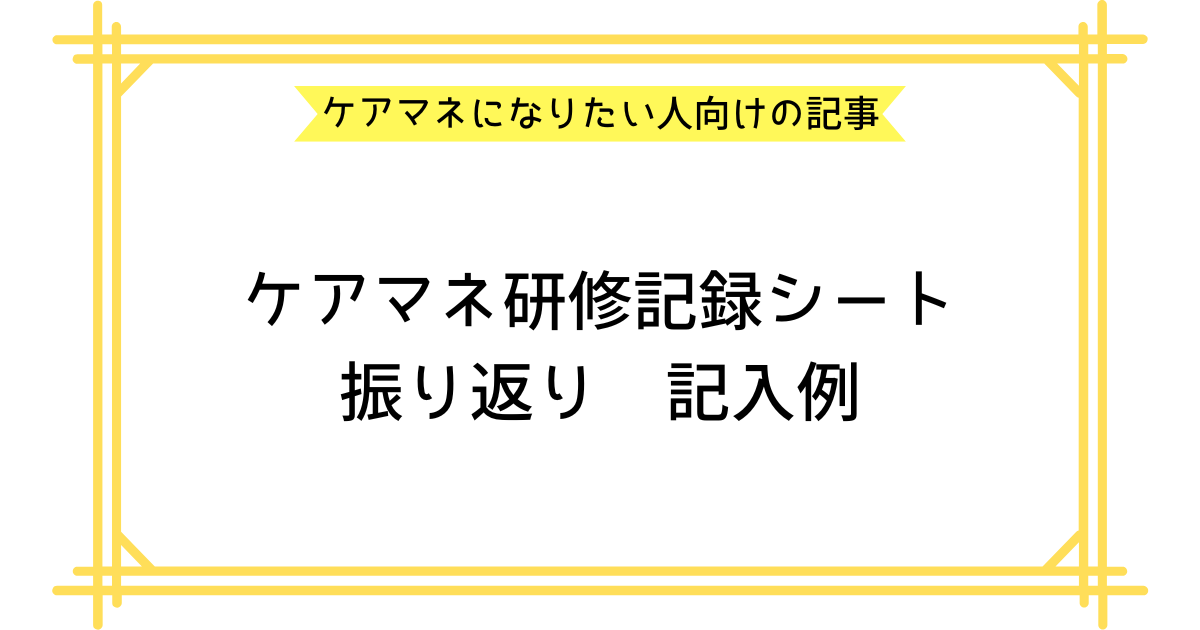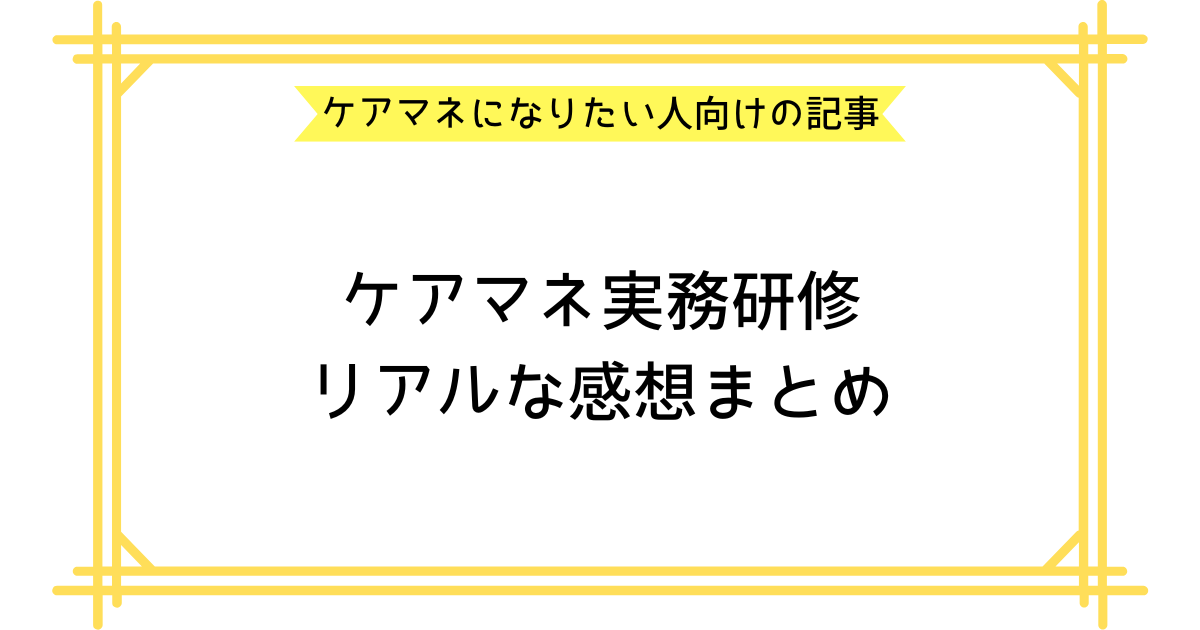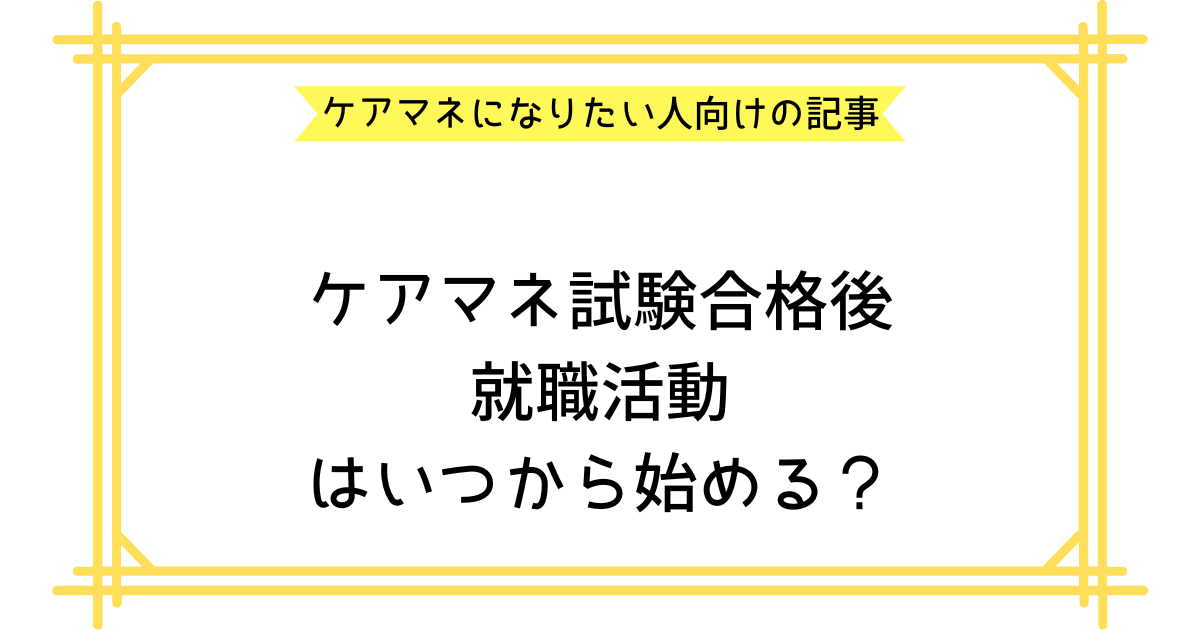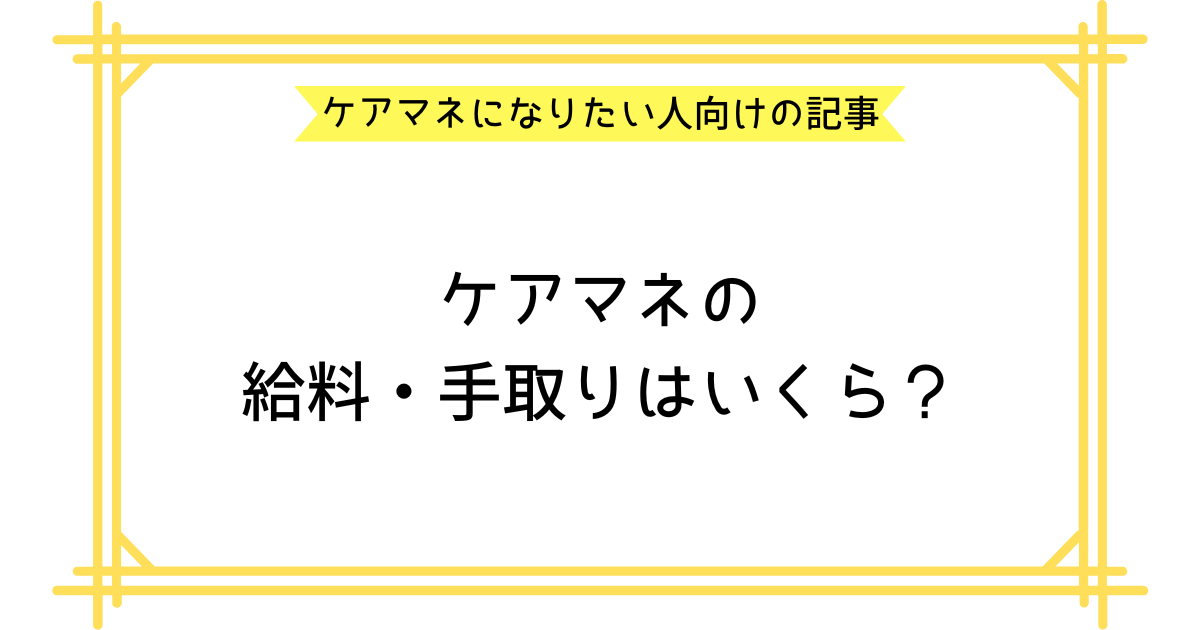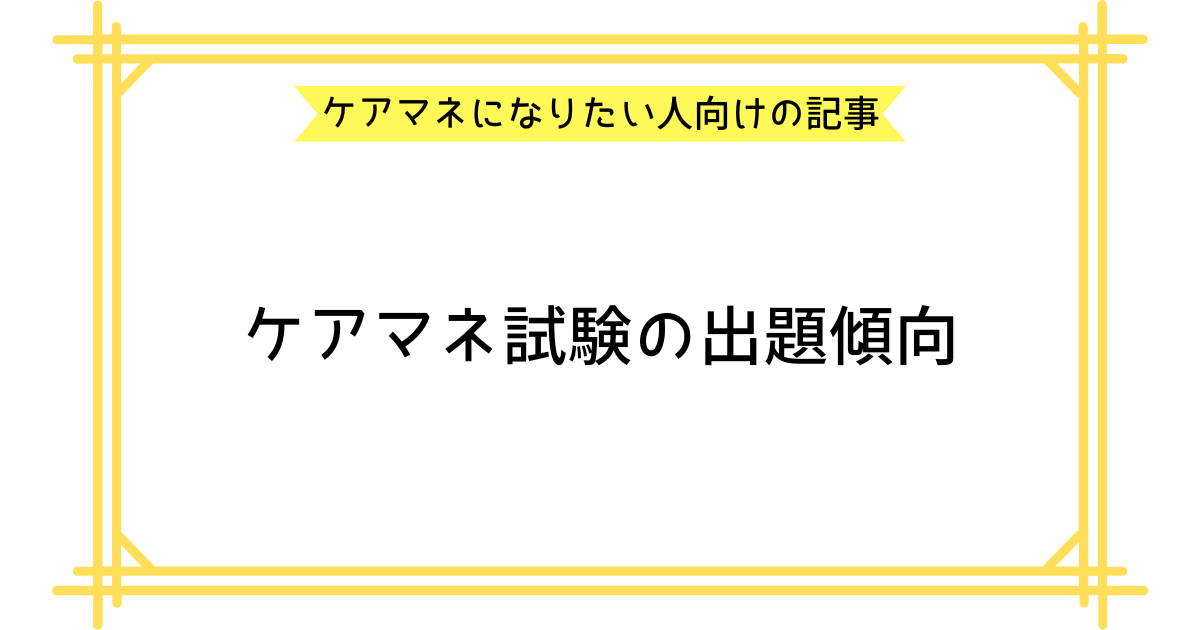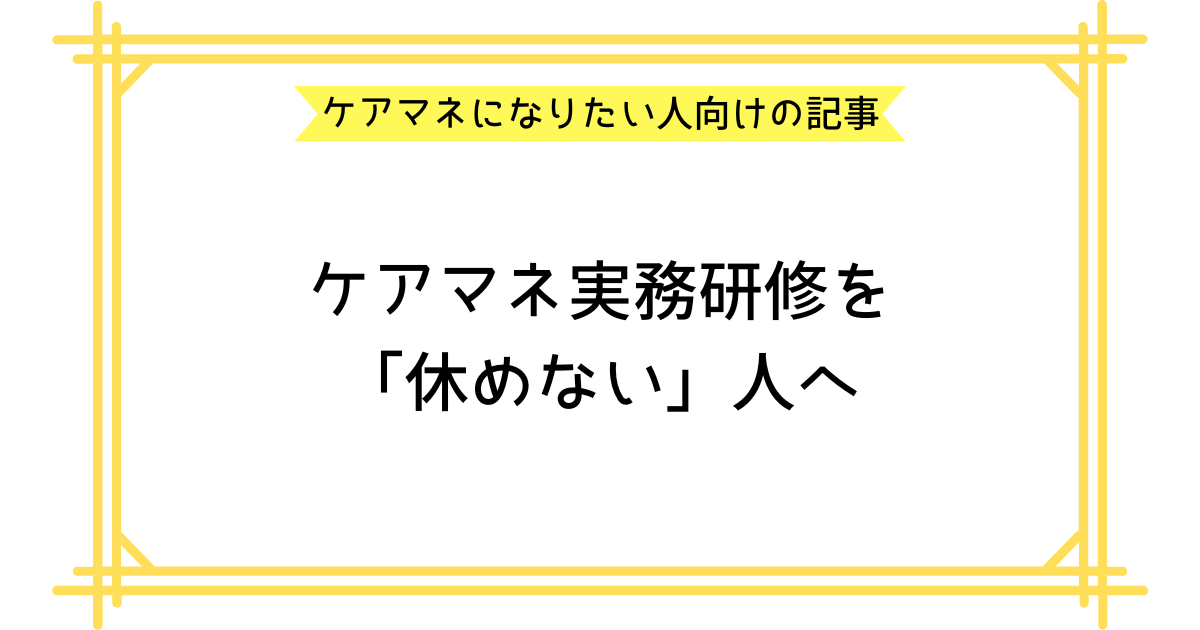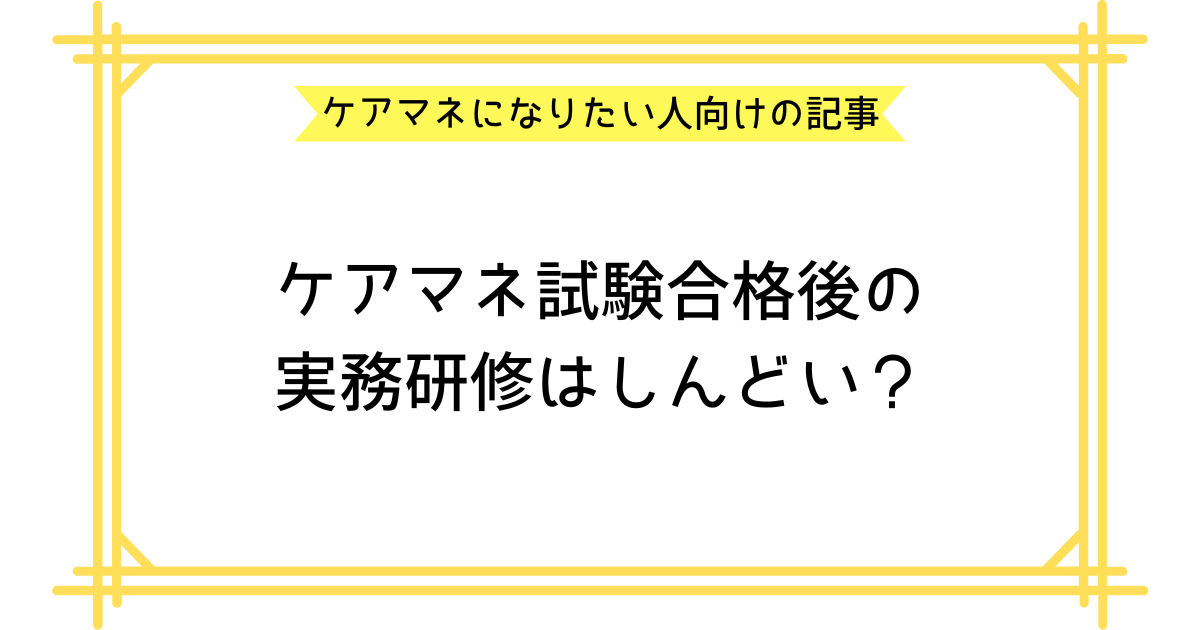ケアマネ試験合格後の実習は手土産は必要なのか?不要な理由を解説
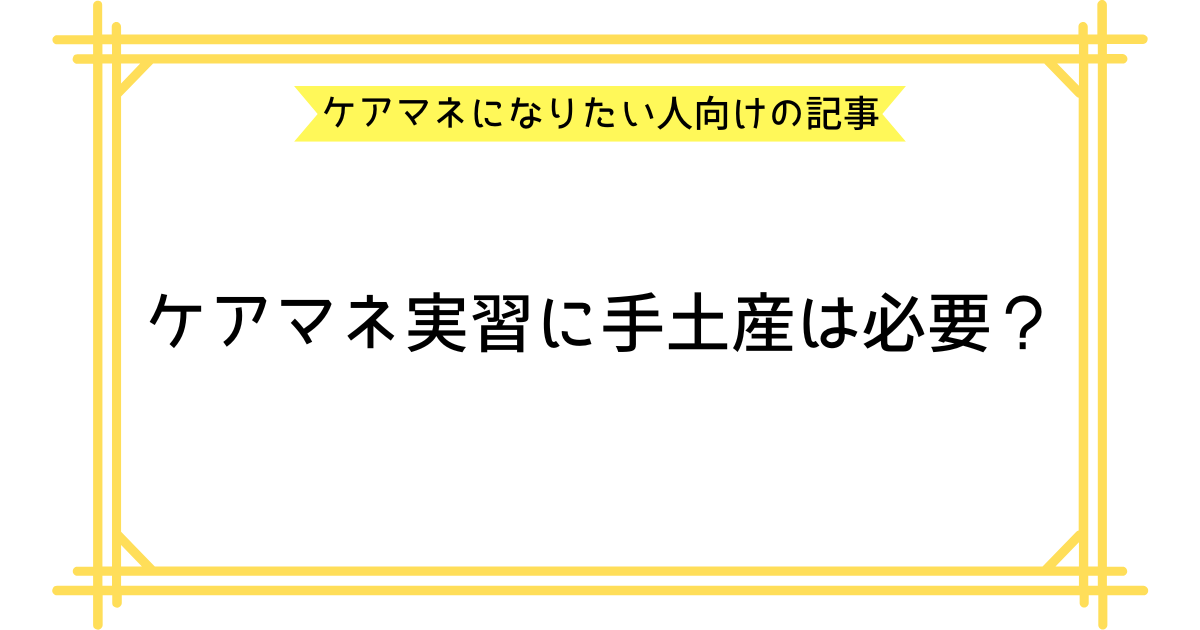
ケアマネ試験に合格し、いよいよ実習に臨む段階になったとき、「実習先に手土産を持って行くべきか?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
感謝の気持ちを表すために何か持って行きたいと思う一方で、実際に手土産が必要なのか迷うところです。
この記事では、ケアマネ実習で手土産が不要な理由について解説し、適切なマナーについても紹介します。
安心して実習に臨むためのポイントを押さえましょう。
ケアマネ実習で手土産が不要な理由
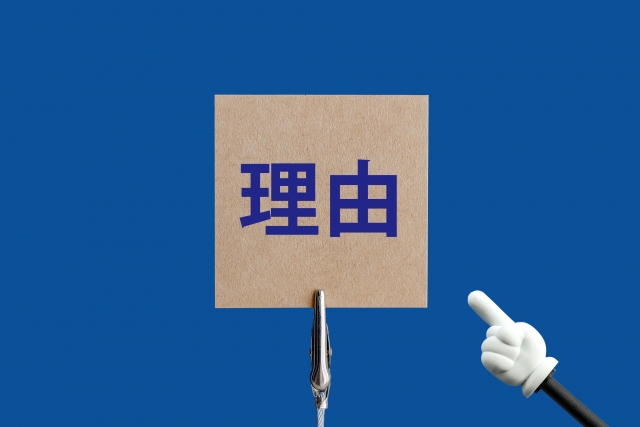
ケアマネ試験合格後の実習において、手土産が必ずしも必要ではない理由にはいくつかのポイントがあります。
以下では、その理由を詳しく解説します。
理由1:手土産を渡すことが一般的でない
ケアマネ実習では、そもそも手土産を渡す慣習がほとんどありません。多くの事業所では、実習生が来ることは研修の一環として受け入れているため、特別な対応を求めているわけではありません。そのため、手土産がないからといって失礼になるわけではなく、むしろ相手が気を遣ってしまうケースもあります。
ポイント
- 実習はあくまで学びの場であり、贈り物が重視されているわけではない。
- 事業所側も手土産を受け取る文化がないケースが多い。
- 手土産があることで逆に負担に感じられる可能性がある。
理由2:倫理的に受け取りが難しいケースが多い
ケアマネージャーや介護事業所では、公正・公平な対応が求められます。そのため、手土産を受け取ること自体が倫理的に問題視されるケースが少なくありません。特に公的機関や自治体関連の事業所では、贈り物を受け取ることが規則で禁止されていることもあります。
ポイント
- 利用者や家族からの贈答品に関するルールが厳しいため、実習生からの手土産も同様に扱われる。
- 受け取ってしまうと他の実習生との公平性が損なわれるため、事業所側が困ることも。
- 「受け取らない方が無難」と考える事業所が多い。
理由3:実習の本質は学びにある
実習はあくまで「学ぶ場」であり、手土産を持参することが目的ではありません。ケアマネージャーとして必要なスキルや知識を学び取ることが最優先です。そのため、実習先のスタッフに対して失礼にならないよう、真摯な態度で取り組むことこそが重要です。
ポイント
- 実習先への感謝は、手土産よりも「学ぶ姿勢」で示すべき。
- 挨拶や報告、連絡、相談をしっかり行うことが好印象につながる。
- 実習中に積極的に質問し、意欲を示すことが最大の礼儀。
手土産が不要でも心がけるべきマナー

手土産が不要だからといって、マナーを軽視して良いわけではありません。
以下のポイントを押さえ、礼儀正しく実習に臨みましょう。
1. 初日の挨拶を丁寧に
実習初日は特に大切です。
きちんと自己紹介をし、学ばせていただく感謝の気持ちを伝えましょう。
例文
「本日からお世話になります〇〇です。ケアマネージャーとしての知識と技術をしっかり学びたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。」
2. 実習中の態度が最も大事
手土産よりも大切なのは、実習中の態度や姿勢です。
積極的に学び、指導者やスタッフに対して感謝の気持ちを示すことが重要です。
ポイント
- 指導者の話をメモするなど、学ぶ意欲を示す。
- 指示があった際には迅速かつ丁寧に対応する。
- 感謝の言葉を忘れずに伝える。
3. 実習終了時にお礼を伝える
実習が終わった際には、しっかりとお礼を伝えましょう。
書面で感謝の気持ちを伝えるのも良い方法です。
例文
「このたびは実習で貴重な経験をさせていただき、誠にありがとうございました。現場で学んだことを糧に、今後も努力してまいります。」
まとめ

ケアマネ試験合格後の実習で手土産を持って行く必要は基本的にありません。
むしろ、手土産を渡すことで相手に気を遣わせてしまうリスクもあります。
実習の本質は学びにあり、丁寧な挨拶や感謝の気持ちをしっかりと伝えることで、十分に礼儀を尽くすことができます。
実習中の態度が最も評価されるポイントですので、真摯な姿勢で学びを深めましょう。