【ケアマネ丸パクリOK】難聴のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
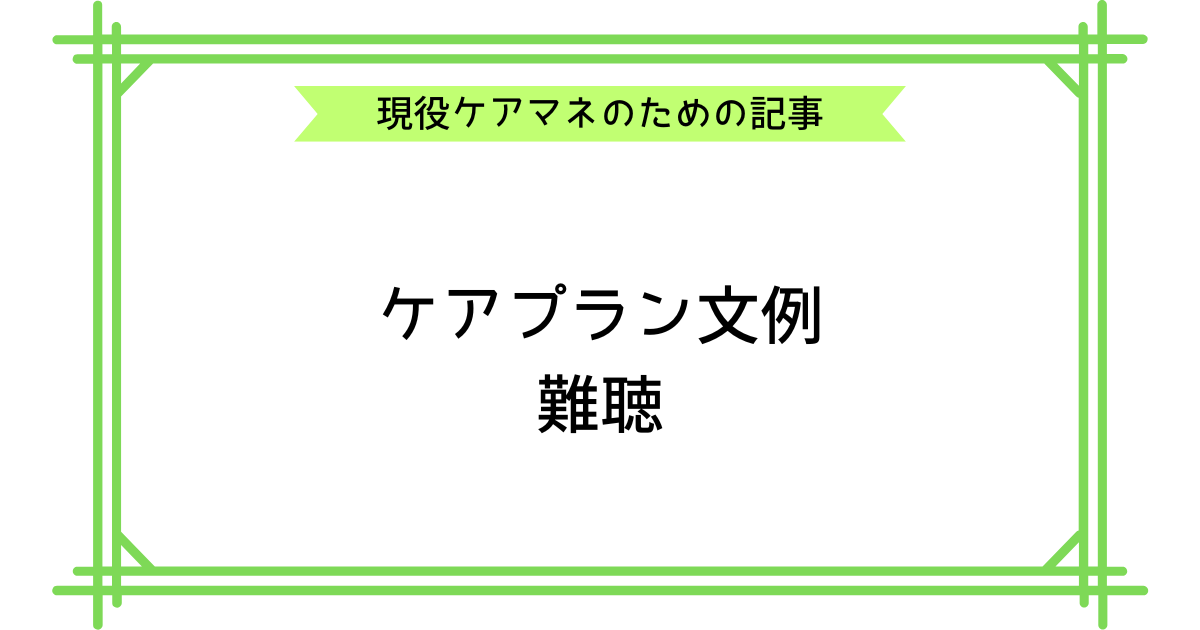
高齢者に多く見られる「難聴」は、生活上の支障だけでなく、孤立感や認知症リスクの上昇とも関連しています。聞こえづらさから会話や社会参加が減り、本人のQOL低下や家族の負担増加につながることも少なくありません。
ケアマネジャーは、難聴の利用者に対して「安全な生活環境の整備」「円滑なコミュニケーション支援」「社会的孤立予防」といった観点からケアプランを作成することが重要です。
本記事では、難聴に対応したケアプラン文例を 100事例 紹介します。利用者の状態に応じてそのままコピー&ペーストして活用でき、少しアレンジするだけで幅広いケースに対応可能です。
目次
コミュニケーション支援に関する文例
- 会話時は本人の正面に立ち、口元が見えるように話す。
- 補聴器を適切に使用できるよう、定期的に点検する。
- 聞き取りやすいよう、短く区切ってゆっくり話す。
- 大きな声ではなく、はっきりと発音して話しかける。
- 重要事項は口頭だけでなくメモや掲示物で伝える。
- 訪問介護時は、最初に声をかけてから近づく。
- 電話では聞き取りづらいため、家族を通して伝える。
- 補聴器電池の交換を忘れないよう、家族と協力する。
- 集会や行事参加時には前方席を確保する。
- 医師や職員との会話内容を家族と共有し、伝達漏れを防ぐ。
- 話しかける前に軽く肩を叩いて注意を促す。
- 環境騒音を減らし、聞き取りやすい場を整える。
- 表情やジェスチャーを交えたコミュニケーションを行う。
- 訪問者名や予定を紙に書き、分かりやすく伝える。
- 会話時は一度に複数人が話さないよう配慮する。
- ビデオ通話や文字表示機能を活用し、遠方の家族とも交流する。
- 補聴器が合わない場合は、専門外来に相談する。
- 日常会話は繰り返し確認しながら行い、誤解を防ぐ。
- 緊急時の連絡方法として、文字通信やチャットを用意する。
- 本人の希望に合わせたコミュニケーション方法を尊重する。
安全確保に関する文例
- 呼びかけに気づきにくいため、見守りセンサーを設置する。
- 玄関チャイムを光や振動で知らせる機器を導入する。
- 火災報知器を光や振動で知らせるタイプに変更する。
- 交通の音が聞こえにくいため、外出時は付き添いを行う。
- 夜間の見守りを強化し、緊急時にも対応できるようにする。
- ガスや湯沸かし器の使用時は自動停止機能付き機器を導入する。
- 来客に気づきやすいよう、インターホンに映像機能を活用する。
- 安全確保のため、定期的に住環境を点検する。
- 火災や災害時の避難経路を事前に確認しておく。
- 外出時は携帯電話や連絡手段を必ず持参する。
- 電話が聞こえにくい場合は、家族に代理連絡を依頼する。
- 通院時には医師の説明を同席者が確認し、安全に治療を受ける。
- 緊急時に光や振動で知らせるアラーム機器を導入する。
- 外出時は反射材を身に付け、事故防止につなげる。
- 薬の服薬管理を見える化し、飲み忘れを防ぐ。
- 居室のテレビ音量を下げる工夫を行い、火災警報などに気づきやすくする。
- 緊急時の連絡手段として、家族や近隣住民と協力体制を整える。
- 電話が困難な場合は、FAXやメールを利用する。
- 災害時に必要な情報を文字や掲示で確認できるようにする。
- 難聴による不安を軽減し、安心して生活できる環境を整える。
生活支援に関する文例
- 家族と一緒にテレビを観る際、字幕を利用する。
- 買い物時は店員とのやりとりを家族がサポートする。
- デイサービスでは職員がゆっくり話しかける。
- 趣味活動に参加できるよう、文字や表示を活用する。
- 補聴器を定期的に清掃し、良好に使用できるよう支援する。
- 医療や介護の説明は、文字資料を併用して行う。
- 金銭管理時に聞き間違いがないよう、確認を徹底する。
- 家電操作方法を文字でまとめ、分かりやすくする。
- 音声案内が聞き取りにくい機器は、家族が操作補助する。
- 趣味や習い事を継続できるよう、難聴への配慮を行う。
- 本人が安心して買い物できるよう、メモを準備する。
- 医療機関での説明は、同席者が記録して共有する。
- 生活上の予定をカレンダーや掲示板で明示する。
- デイサービス活動時は、職員が補足説明を行う。
- 補聴器使用を習慣化できるよう、毎日の確認を行う。
- テレビやラジオの利用時に字幕や文字起こしを活用する。
- 外出支援時に、会話内容を繰り返し確認する。
- 複数人での会話では、まとめ役を設ける。
- 本人の生活意欲を高めるため、聞こえに配慮した活動を支援する。
- 難聴を考慮し、ストレスの少ない生活環境を整える。
社会参加に関する文例
- デイサービス参加時に職員が聞こえに配慮する。
- 地域行事に参加する際は、文字資料を提供する。
- サロン活動では、少人数のグループに参加できるよう配慮する。
- 友人との会話時は、静かな場所を選ぶ。
- 地域包括支援センターと連携し、社会参加機会を増やす。
- 孫との交流を図るため、文字や筆談を活用する。
- ボランティア活動参加時に、難聴を考慮した役割を担う。
- 地域の健康教室に参加できるよう、支援者が同伴する。
- 趣味活動を通じて交流を維持する。
- 難聴による孤立を防ぐため、地域交流を定期的に行う。
- 本人の興味関心に合わせた活動を取り入れる。
- 通院や買い物時に、社会的交流が持てるよう支援する。
- 電子機器を活用し、遠方の友人と交流を維持する。
- 季節行事に参加できるよう、周囲が配慮する。
- 職員が仲介役となり、会話をスムーズにする。
- 集会や会合では、文字による資料を用意する。
- 趣味活動に取り組み、社会的孤立を防ぐ。
- 難聴があっても安心して参加できる行事を選ぶ。
- 孫との交流を促進し、生活意欲を高める。
- 社会的孤立を防ぎ、QOLを維持する。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に難聴への理解を深めてもらう。
- 家族が会話方法を学び、支援できるようにする。
- 家族会議を開き、支援方法を確認する。
- 家族が安心して介護できるよう、情報を共有する。
- 家族に補聴器の管理方法を説明する。
- 家族が筆談を活用できるよう、準備を行う。
- 難聴による本人の孤立を家族が理解する。
- 家族全員で静かな環境を作るよう協力する。
- 家族が一緒に社会活動に参加する。
- 家族に緊急連絡方法を伝える。
- 家族の介護負担を軽減するため、外部サービスを導入する。
- 環境騒音を減らし、聞こえやすい居住空間を作る。
- 家族に定期的に難聴への配慮を確認してもらう。
- 家族が医師の説明を一緒に受け、治療方針を理解する。
- 難聴に配慮した生活環境を整える。
- 家族が本人の気持ちを尊重し、孤立を防ぐ。
- 外部サービスを活用し、家族の介護負担を軽減する。
- 本人の希望に沿った生活環境を調整する。
- 難聴によるストレスを家族と共有し、解消策を考える。
- 本人と家族が安心して暮らせるよう、環境整備と支援を行う。
まとめ
難聴のケアプランは、単なる「聞こえづらさの支援」にとどまらず、 コミュニケーション方法の工夫・安全確保・社会参加・家族支援 を多角的に組み込むことが重要です。
今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーがそのままコピペして活用できるよう整理しています。
利用者の生活背景や希望に応じて文例を組み合わせ、最適なプランを作成することで、本人の安心と生活の質の向上につながります。















