【ケアマネがコピペで使える】脳梗塞・脳出血のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
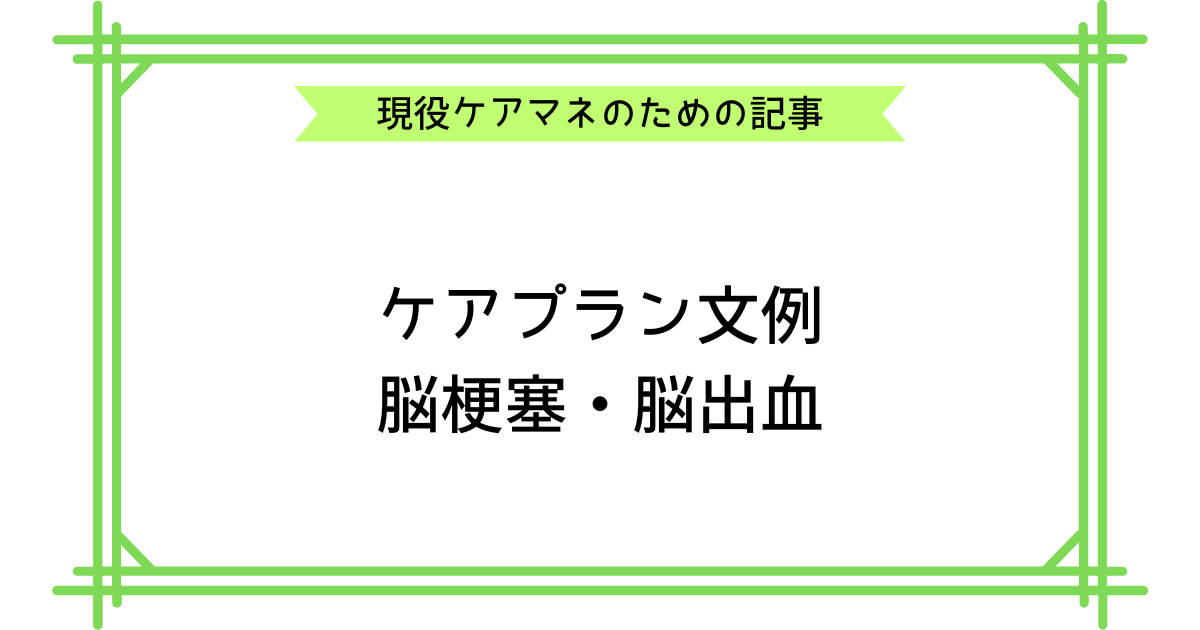
脳梗塞や脳出血を発症した利用者は、麻痺や言語障害、嚥下障害などの後遺症に加え、再発予防や生活習慣の改善が求められます。自宅療養を続けるには、 リハビリ支援・日常生活動作の補助・服薬や通院管理・再発予防・家族支援 など、多角的なケアが必要です。
ケアマネジャーがケアプランを作成する際には「利用者の身体機能」「生活意欲」「家族の介護力」を踏まえて、具体的で再現性のある目標やサービス内容を盛り込むことが大切です。
本記事では、脳梗塞・脳出血の後遺症を持つ方へのケアプラン文例を 100事例 にまとめました。状況別に分類していますので、そのままコピー&ペーストで使えるだけでなく、利用者の状況に合わせたアレンジにも活用できます。
目次
身体機能維持・リハビリ支援に関する文例
- 毎日決まった時間にリハビリを実施し、運動習慣を継続する。
- 理学療法士の指導に基づき、下肢筋力の維持訓練を行う。
- 上肢機能訓練を繰り返し行い、麻痺側の可動域を維持する。
- 作業療法を取り入れ、日常生活動作の自立を支援する。
- 起立訓練を継続し、立位保持能力を高める。
- 歩行器を使用し、安全に歩行練習を行う。
- 自主リハビリを日課とし、生活意欲を高める。
- 退院時のリハビリ計画を在宅でも継続する。
- デイケアでの機能訓練に参加し、身体機能を維持する。
- 移乗訓練を繰り返し行い、自立度を高める。
- 家庭内でのストレッチを習慣化し、関節拘縮を予防する。
- バランス訓練を取り入れ、転倒予防を図る。
- 段差昇降の練習を行い、外出機会を広げる。
- 体幹機能を高める運動を取り入れる。
- 筋力低下を防ぐため、軽い負荷の運動を続ける。
- リハビリ日誌を活用し、進捗を本人・家族と共有する。
- 作業療法を通じて趣味活動を再開できるよう支援する。
- 失語症に対して言語療法を実施する。
- 嚥下訓練を行い、誤嚥性肺炎を予防する。
- 定期的にリハビリ評価を行い、計画を見直す。
日常生活動作(ADL)の支援に関する文例
- 更衣動作を自立して行えるよう、衣類を工夫する。
- 食事動作を支援し、自分で食べられる部分を増やす。
- 入浴動作を分担し、自立部分を尊重する。
- 排泄動作をスムーズに行えるよう、福祉用具を導入する。
- ベッドからの起き上がりを自立できるよう支援する。
- 車椅子移乗を安全に行えるよう介助方法を工夫する。
- 台所で簡単な家事ができるよう環境整備を行う。
- 歯磨きや洗顔など整容動作を自立できるよう支援する。
- 外出時の着脱衣を容易にするため、衣類を選定する。
- 自助具を活用し、食事や更衣の自立を促す。
- トイレまでの動線を確保し、排泄の自立を支援する。
- 家庭内で役割を担えるよう、簡単な家事を取り入れる。
- 介助量を減らし、本人の自立度を高める工夫を行う。
- 入浴時に安全に洗体できるよう、浴室手すりを設置する。
- 居室内の移動を容易にするため、段差を解消する。
- 福祉用具を用い、起居動作の自立を支援する。
- 食事姿勢を安定させるため、専用椅子を活用する。
- 簡単な掃除を行えるよう、使いやすい道具を導入する。
- ベッド周辺を整理整頓し、動作を安全に行える環境を作る。
- 家族と協力し、日常生活動作の練習を継続する。
服薬・通院・再発予防に関する文例
- 医師の指示に従い、毎日の服薬を確実に行う。
- 血圧測定を習慣化し、再発予防に役立てる。
- 通院を忘れないよう、家族と予定を共有する。
- 再発予防のため、減塩食を継続する。
- 薬の飲み忘れを防ぐため、服薬カレンダーを使用する。
- 通院時は家族が同伴し、説明内容を共有する。
- 医師の指示を家族と共有し、療養に活かす。
- 禁煙を継続し、再発リスクを低減する。
- 節酒を習慣化し、生活習慣改善を図る。
- 定期的に血液検査を受け、健康状態を確認する。
- 合併症のリスクを医師と確認し、適切に対応する。
- 食生活を見直し、血圧・血糖管理を徹底する。
- 脳梗塞再発予防のため、体重管理を行う。
- 家族と協力し、服薬・食事・生活習慣を支える。
- 医療職と連携し、在宅での療養を継続する。
- 通院負担を軽減するため、送迎支援を活用する。
- 医師の治療方針を理解し、療養生活に反映する。
- 定期受診の前に血圧・服薬記録を整理して持参する。
- 脳出血再発予防のため、ストレス軽減を図る。
- 脳梗塞・脳出血の既往を踏まえ、生活習慣病全般の予防に努める。
心理・社会参加に関する文例
- 家族や友人との交流を増やし、孤立を防ぐ。
- デイサービスに参加し、社会的交流を継続する。
- 孫とのふれあいを通じて生活意欲を高める。
- 趣味活動を継続し、生活の張りを持つ。
- グループ活動に参加し、社会性を維持する。
- 外出機会を増やし、生活リズムを整える。
- 退院前に行っていた活動を在宅で再開する。
- 趣味を通じて認知機能低下を予防する。
- デイケアで仲間と交流し、リハビリ意欲を維持する。
- ボランティア活動を通じて役割を担う。
- 家族と共に外食や買い物を楽しむ。
- 季節の行事に参加し、生活に変化を持たせる。
- 趣味や文化活動を継続できるよう支援する。
- 地域包括支援センターと連携し、社会参加を支援する。
- 孤立感を軽減するため、近隣住民と交流する。
- 日記を活用し、生活の振り返りを行う。
- コミュニケーション機会を増やし、気分の落ち込みを防ぐ。
- 家族と一緒に外出を計画し、楽しみを持つ。
- リハビリ仲間と交流し、意欲を維持する。
- 社会参加を通じてQOLを向上させる。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に介助方法を指導し、負担軽減を図る。
- 介護負担を軽減するため、福祉用具を導入する。
- 家族が安心して介護できるよう、情報を共有する。
- 介護負担を軽減するため、訪問介護を活用する。
- 家族が休養できるよう、ショートステイを利用する。
- 家族会議を開き、介護体制を確認する。
- 家族に介助の工夫を伝え、事故を予防する。
- 医師や看護師と家族が連携し、在宅生活を支える。
- 家族に心理的サポートを行い、介護疲れを防ぐ。
- 家族の負担を見える化し、外部サービスを調整する。
- 居室をバリアフリー化し、安全に生活できるようにする。
- 手すりやスロープを設置し、移動の安全性を高める。
- ベッド周囲を整理し、転倒リスクを減らす。
- 浴室環境を整備し、安全に入浴できるようにする。
- トイレ環境を整え、排泄の自立を支援する。
- 家族に介護知識を提供し、安心して支援できる体制を作る。
- 介護サービスを適切に組み合わせ、家族の負担を軽減する。
- 緊急時の対応方法を家族と共有し、安心して生活できるようにする。
- 在宅生活を継続できるよう、医療・介護サービスを調整する。
- 利用者と家族が共に安心して暮らせるよう、支援体制を整える。
まとめ
脳梗塞・脳出血の利用者へのケアプランでは、 身体機能維持・ADL支援・服薬管理・再発予防・心理支援・家族支援 のすべてをバランスよく盛り込むことが重要です。
今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーがそのまま活用できる形式に整理しています。
利用者の状態や希望に応じて文例を組み合わせて使うことで、より現実的で効果的なケアプランを作成することができます。















