【完全版】介護保険の住宅改修は20万円まで?「3段階リセット」ルールを徹底解説!
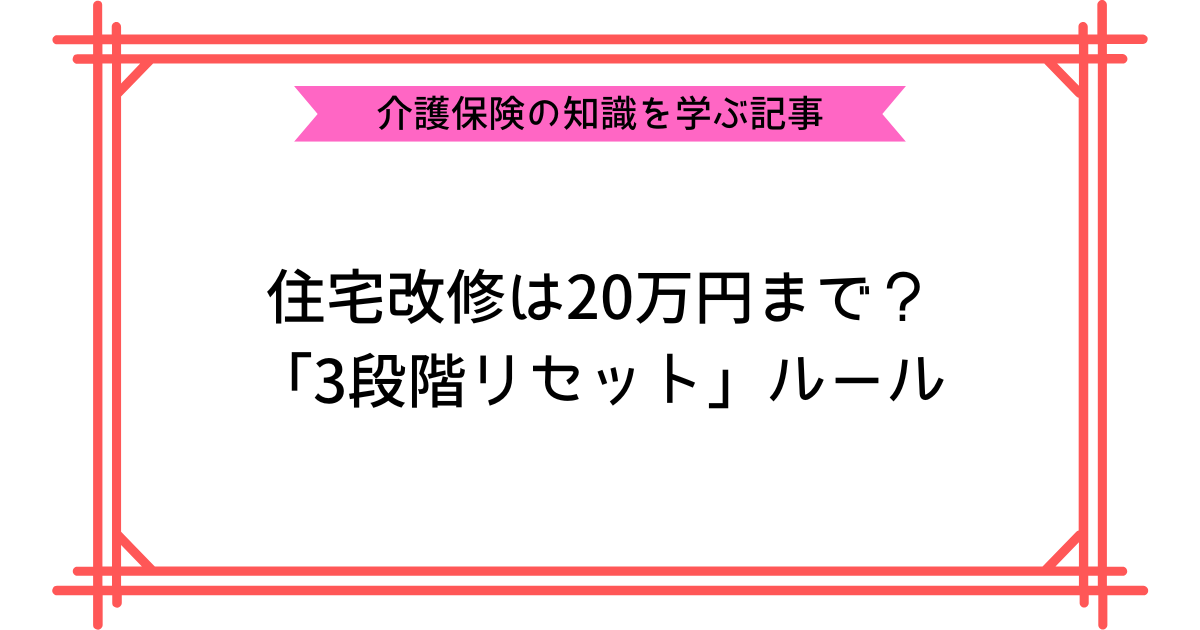
介護保険制度には、要介護者が自宅で安全に生活を続けるために「住宅改修費の支給制度」が用意されています。この制度を利用すれば、手すりの設置や段差解消などの住宅改修を 原則20万円まで(自己負担1〜3割)公的保険で補助を受けられます。
しかし、「20万円の枠は一度使ったら終わりなのか?」「引っ越したら再度使えるのか?」「要介護度が変わるとリセットされるのか?」といった疑問を持つ方も多いです。実際には「3段階のリセットルール」があり、条件を満たすと再度20万円まで利用可能になります。
本記事では、この仕組みをわかりやすく解説し、ケアマネジャーや利用者が安心して住宅改修制度を活用できるようにまとめました。
介護保険の住宅改修とは?20万円まで利用できる仕組みを解説
介護保険における住宅改修費は、利用者が在宅で自立した生活を送るために必要な改修工事を対象に給付される制度です。対象工事には、手すりの取り付け、段差解消、床材変更、引き戸や洋式便器への交換などがあります。
上限は 20万円(原則一生涯で1回) で、実際には1割〜3割が自己負担となり、残りを介護保険が負担します。たとえば工事費用が18万円なら、自己負担は1.8万円(1割負担の場合)で済みます。
ただし「一生涯で1回限り」とは限らず、特定の条件を満たすことで 再度20万円の枠が使えるリセット制度 が設けられています。これが「3段階リセットルール」と呼ばれる仕組みです。
住宅改修の「3段階リセット」ルールとは?
住宅改修費は原則20万円までですが、以下の3つの条件に該当すると、再度リセットされて新たに20万円の枠が利用できます。
① 要介護度が大きく上がった場合
要支援から要介護、あるいは要介護2から要介護4など、明らかに身体状況が変化した場合 は、新たなニーズに応じて再度20万円の枠が使えます。
② 住所変更(引っ越し)した場合
住宅改修は「居住する住宅」が対象のため、転居先の住宅 で新たに改修が必要となった場合は再度20万円まで利用できます。
③ 特別な事情で市区町村が認めた場合
災害などによって住宅が損壊した、やむを得ない事情で大幅に生活環境が変わったなどの場合、市町村が認めればリセットが可能です。
つまり、「要介護度の大幅変化」「引っ越し」「特別事情」の3段階がリセット条件となり、最大で複数回利用できる仕組みになっています。
住宅改修で使える工事の種類
介護保険が適用される住宅改修は限定されています。代表的な工事を整理すると次のとおりです。
- 手すりの設置(廊下・階段・トイレ・浴室など)
- 段差の解消(敷居撤去、スロープ設置など)
- 滑りにくい床材への変更
- 開き戸から引き戸への変更
- 和式便器から洋式便器への取り替え
- その他上記工事に付随する小規模な工事
対象は「安全確保」「自立支援」に直結するものに限られる点がポイントです。バリアフリー目的でも、介護保険対象外の工事(増築・大規模リフォームなど)は給付されません。
住宅改修の申請方法と流れ
住宅改修費を利用するには、事前申請が必要です。流れは以下のとおりです。
- ケアマネジャーが必要性をアセスメント
- 改修プランを作成(工事業者の見積書や図面を準備)
- 市区町村へ事前申請(理由書・申請書類を提出)
- 承認後に工事を実施
- 工事完了後に領収書などを添えて市区町村に請求
- 利用者に自己負担分を除いた金額が払い戻される
「事後申請」では認められないため、必ず 事前申請 を行うことが重要です。
住宅改修を活用する際の注意点
住宅改修費を利用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 原則20万円が限度額(超えた分は全額自己負担)
- 1割〜3割の自己負担がある
- 工事内容は介護保険対象工事に限定される
- 必ず事前申請が必要
- リセットは「要介護度上昇」「転居」「特別事情」の3パターンのみ
制度を正しく理解していないと「20万円を使い切ったらもう終わり」と誤解してしまうケースも多いため、ケアマネジャーや役所と相談しながら進めることが大切です。
まとめ|住宅改修は「20万円まで」+「3段階リセット」で賢く使おう
介護保険の住宅改修は、利用者の自立支援と家族の介護負担軽減に直結する重要な制度です。20万円までの補助に加え、条件次第で再度利用できる「3段階リセット」の仕組みを知っておくと、長期的に安心して在宅生活を送ることができます。
ケアマネジャーは、利用者の生活環境や介護度の変化に応じて柔軟に提案し、最適な住宅改修をサポートすることが求められます。















