事業対象者とは?わかりやすく解説|介護保険制度の基礎知識
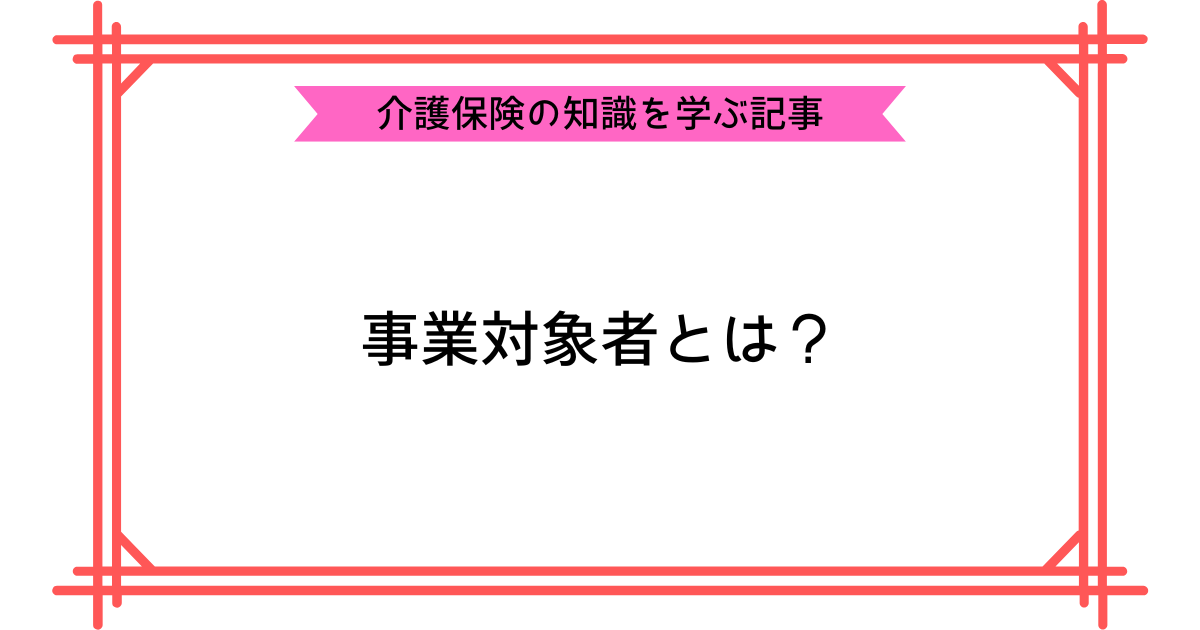
介護保険制度を調べていると「事業対象者」という言葉を目にすることがあります。
しかし、「要支援や要介護と何が違うの?」「事業対象者だとどんなサービスが受けられるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、事業対象者の定義や認定の流れ、利用できるサービス、メリット・注意点をわかりやすく解説します。
高齢のご家族を介護している方や、これから介護保険を利用しようと考えている方に役立つ内容です。
事業対象者とは?わかりやすく解説
事業対象者とは、介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」に該当しなかったものの、今後の生活に支援が必要になる可能性が高い高齢者 を指します。
つまり、現時点では介護度はつかないけれど、筋力低下や閉じこもり傾向、物忘れなどが見られ、このまま放置すると要介護状態になってしまうリスクがある人が対象です。
要支援・要介護に比べて軽度ではありますが、「予防的な支援を受けることで元気な生活を続けられる」ことが目的となっています。
事業対象者と要支援・要介護の違い
「事業対象者」「要支援」「要介護」は似ていますが、それぞれ異なる位置づけがあります。
- 要介護:入浴・排泄・食事などで日常生活に大きな介助が必要な状態
- 要支援:生活の一部で介助や支援が必要な状態
- 事業対象者:現時点で大きな介助は不要だが、将来的に要支援・要介護になる可能性が高い状態
事業対象者は「要支援になる前の段階」と考えるとイメージしやすいでしょう。
どうすれば事業対象者に認定されるのか?
事業対象者は「要介護認定を申請したけれど、非該当となった人の一部」が該当します。
- 介護保険の要介護認定を申請
- 調査や主治医意見書をもとに審査
- 要支援・要介護に該当しなければ「非該当」と判定される
- その中で生活機能が低下している場合に「事業対象者」となる
つまり、いきなり事業対象者の申請をするのではなく、要介護認定の結果として判定される仕組み になっています。
事業対象者が利用できるサービス
事業対象者は、介護保険の「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)を利用できます。
- 通所型サービス(デイサービスでの運動・機能訓練など)
- 訪問型サービス(ヘルパーによる掃除・買い物支援など)
- 介護予防プログラム(体操教室、栄養指導、口腔ケアなど)
- 地域の交流活動(サロン、ボランティア支援など)
これらは「要介護にならないための予防」を目的としているため、必要な支援を受けながら元気に生活を続けることができます。
事業対象者になるメリット
事業対象者と認定されることで、以下のようなメリットがあります。
- 要介護状態になる前に、予防的な支援を受けられる
- デイサービスや体操教室で社会参加ができる
- 生活支援(掃除や買い物代行)により日常生活が楽になる
- 専門職からのアドバイスで生活習慣を見直せる
特に「閉じこもりがち」「体力低下が心配」という方にとって、地域とつながりながら生活を続けられる点が大きな利点です。
注意点:事業対象者は軽度だからこそ予防が大切
事業対象者は「今は軽度だけれど、将来的に要介護になるリスクが高い」という位置づけです。そのため、支援を受けずに放置してしまうと、数年以内に要介護へ進行してしまう可能性があります。
ケアマネジャーや地域包括支援センターと連携しながら、運動・栄養・口腔ケア・社会参加 をバランスよく取り入れることが重要です。
まとめ|事業対象者は「要支援の前段階」として理解しよう
「事業対象者」とは、介護保険制度で要介護認定が非該当だったものの、生活機能の低下があり今後支援が必要と判断された高齢者を指します。
要支援や要介護の一歩手前だからこそ、予防的な支援を受けて健康寿命を延ばすことができる段階 です。
ご家族に事業対象者と認定された方がいる場合は、早めに総合事業を活用し、介護状態にならないよう取り組むことをおすすめします。















