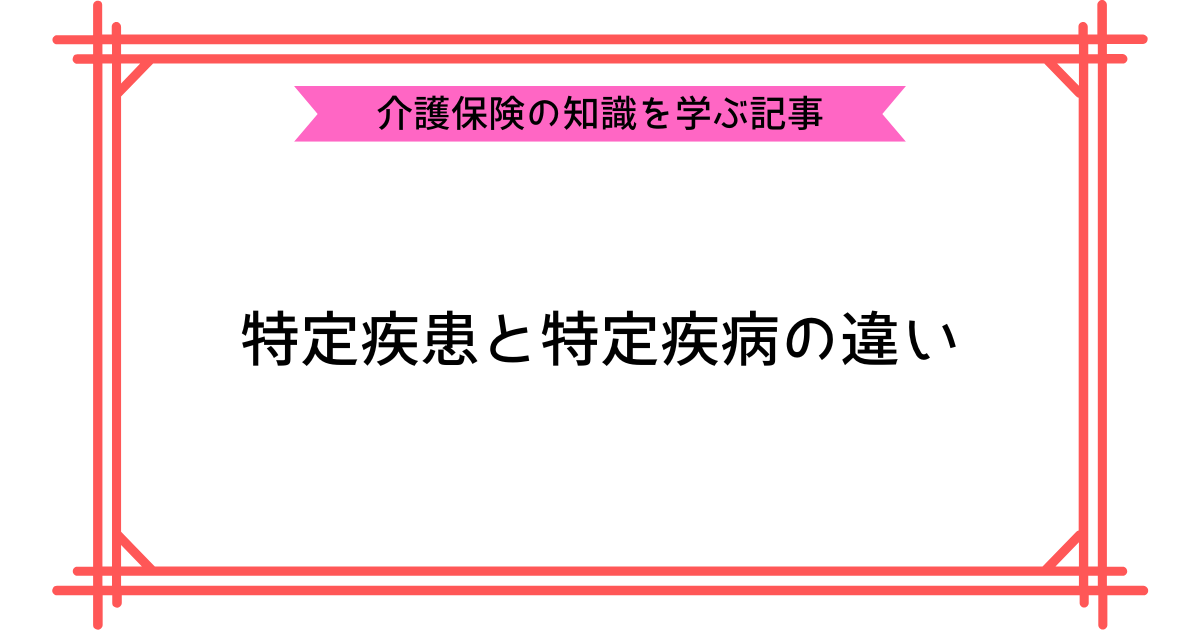高齢者虐待防止法とは?わかりやすく解説|介護職・家族が知っておくべきポイント
当ページのリンクには広告が含まれています。

高齢化が進む日本では、家庭や施設での「高齢者虐待」が社会問題となっています。
そこで2006年に施行されたのが 「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」 です。
しかし、「どんな内容なの?」「誰に関係があるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、高齢者虐待防止法の目的・定義・虐待の種類・通報義務 をわかりやすく解説します。
目次
高齢者虐待防止法とは?
高齢者虐待防止法とは、正式名称を 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 といいます。
2006年(平成18年)4月に施行され、
- 高齢者虐待の早期発見と防止
- 養護者(家族など)に対する支援
- 市町村による保護・対応体制の整備
を目的に制定されました。
つまり、虐待を受けている高齢者を守るだけでなく、介護を担う家族の負担を減らし「虐待が起きない環境づくり」を支える法律なのです。
高齢者虐待の種類(5類型)
法律では「虐待」の種類を5つに定義しています。
- 身体的虐待
殴る・叩く・無理に体を押さえつけるなど、身体に危害を加える行為。 - 介護・世話の放棄(ネグレクト)
食事を与えない、入浴や清潔を保たない、医療を受けさせないなど、必要なケアを怠る行為。 - 心理的虐待
怒鳴る、侮辱する、無視するなど、精神的に苦痛を与える行為。 - 性的虐待
性的な行為を強要する、体を不必要に触るなど。 - 経済的虐待
年金や預貯金を本人の意思に反して使う、生活費を渡さないなどの金銭的搾取。
通報義務について
高齢者虐待防止法では、虐待を発見した場合の 通報義務 を定めています。
- 介護職や医療職などの専門職:虐待を知った場合、速やかに市町村へ通報する義務がある
- 一般の住民:義務ではないが、通報できる(努力義務)
通報先は、市町村の 地域包括支援センターや高齢福祉課 です。匿名でも通報可能で、通報者が不利益を受けないよう守られています。
高齢者虐待防止法の特徴
この法律は「罰則」よりも「支援」に重点を置いています。
- 家族が虐待をしてしまう背景には、介護疲れや孤立などがある
- 市町村は、虐待を防ぐだけでなく 養護者を支えるための相談・サービス提供 を行う責任がある
つまり、「虐待=悪意」と決めつけるのではなく、介護者と高齢者の両方を守る仕組み が法律に盛り込まれています。
高齢者虐待防止法が関係する場面
- 在宅介護での家族介護
- 施設介護(特養・老健など)での職員による虐待
- 地域で高齢者の様子がおかしいときの通報
- ケアマネジャーがケアプラン作成時に虐待を疑った場合
介護や医療の現場だけでなく、地域の誰もが関わる可能性のある法律です。
まとめ|高齢者虐待防止法は「高齢者と家族を守る法律」
高齢者虐待防止法とは、虐待を受ける高齢者を守ると同時に、介護者を支援して虐待が起きにくい環境を整える法律です。
- 虐待は 身体的・ネグレクト・心理的・性的・経済的 の5種類
- 専門職には 通報義務 がある
- 市町村は 高齢者と養護者の双方を支援する責任 を持つ
私たち一人ひとりがこの法律を理解し、地域での見守りや早期発見につなげることが、高齢者の安心した暮らしを守る第一歩となります。