ケアマネは財産管理できる?できない?法的根拠と正しい対応を解説
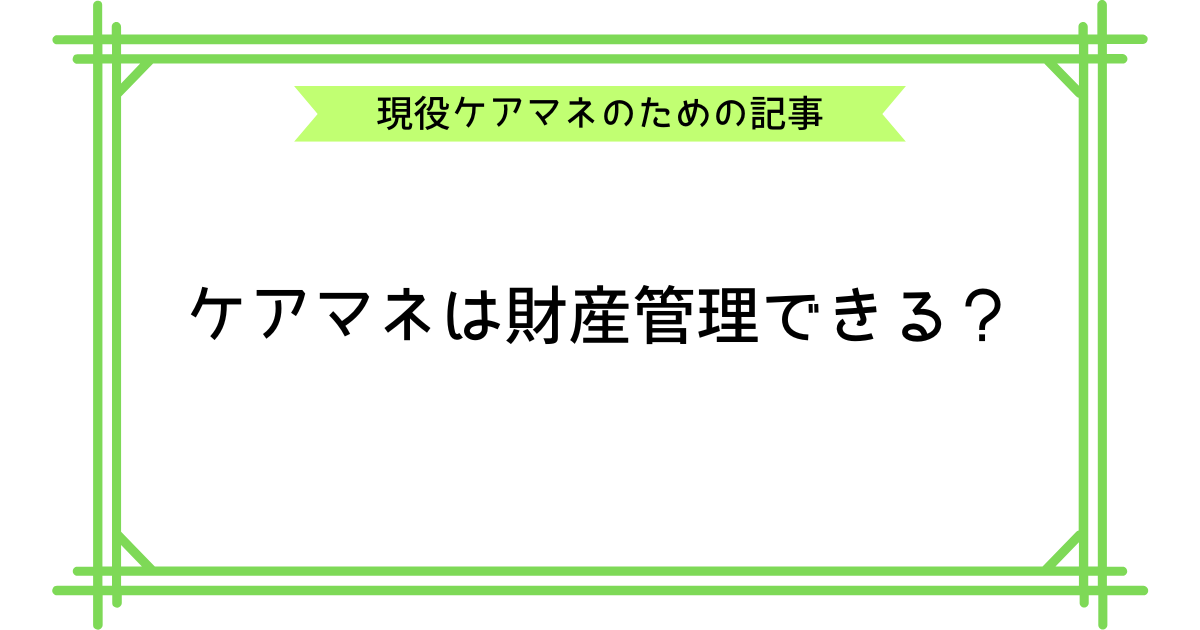
「ケアマネジャー(介護支援専門員)は利用者の財産を管理してくれるの?」
「銀行の手続きやお金の出し入れを頼めるの?」
介護に関わる家族や利用者から、しばしばこうした質問を受けます。しかし結論から言うと、ケアマネが利用者の財産管理を行うことはできません。
この記事では、ケアマネが財産管理をできない理由、法律上の根拠、家族が安心してお金を守るための正しい方法をわかりやすく解説します。
介護の現場で誤解されやすいポイントを整理し、安心してサービスを利用するためのヒントを紹介します。
ケアマネの業務範囲とは?
ケアマネの主な仕事は以下の通りです。
- 利用者や家族からの相談支援
- ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
- サービス担当者会議の開催
- サービス事業所との連絡・調整
- モニタリングと給付管理
つまり、介護サービスの利用に関するコーディネートが役割であり、財産や金銭の管理は業務範囲外です。
ケアマネが財産管理できない理由
1. 法律上の制約
介護支援専門員の業務は介護保険法で定められています。そこには「財産管理」や「金銭の代理」は含まれていません。もし行った場合、業務範囲外行為としてトラブルや法的責任を問われる可能性があります。
2. 利用者保護の観点
財産管理は本人や家族にとって非常に重要な行為です。ケアマネが関与すると、横領や不正利用といったトラブルに発展するリスクがあります。そのため、制度上も禁止されています。
3. 公平中立性の確保
ケアマネは利用者にとって公平中立な立場で支援を行う必要があります。もし財産管理を行えば、利害関係が発生し、公平性が保てなくなる恐れがあります。
財産管理が必要なときに利用できる制度
「ケアマネに頼めないなら、誰が財産を守ってくれるの?」という疑問に対しては、以下の制度があります。
成年後見制度
判断能力が不十分な高齢者に対して、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理します。
- 預貯金の出し入れ
- 契約手続き
- 財産の保全
などを代理で行うことができます。
任意後見制度
元気なうちに信頼できる人を後見人として契約しておく制度です。将来判断力が低下したときに備える方法として利用されています。
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
社会福祉協議会が行っている事業で、**日常的な金銭管理(生活費の支払い、公共料金の支払い補助など)**をサポートしてくれます。成年後見制度より簡易的に利用できます。
ケアマネが関わることができる範囲
ケアマネは直接財産管理はできませんが、以下のような間接的な関わりは可能です。
- 財産管理が必要な利用者を見つけ、成年後見制度の利用を勧める
- 社会福祉協議会の生活支援事業につなげる
- 弁護士や司法書士などの専門職を紹介する
- 家族へ説明し、適切な手続きに導く
つまりケアマネは「財産を守るための制度や人につなぐ」役割を担うことができます。
家族が注意すべきトラブル事例
1. ケアマネが通帳や印鑑を預かる
これは制度違反であり、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
2. サービス事業者や第三者に任せてしまう
知人や事業者が「代わりに管理してあげる」と言っても、契約外の行為はトラブルの温床になり得ます。
3. 契約書や制度を利用しない管理
口約束でお金の管理を任せることは非常に危険です。必ず制度や契約に基づく管理が必要です。
ケアマネと家族がうまく連携するためのポイント
- 財産に関する依頼は絶対にしない
- 必要な制度をケアマネに相談し、紹介してもらう
- ケアマネには「お金」ではなく「生活支援の調整」を依頼する
- 曖昧な対応を避け、制度に基づいた支援を受ける
まとめ
ケアマネージャーは介護サービスのコーディネーターであり、財産管理は業務範囲外で禁止されています。
財産管理が必要な場合は、成年後見制度・任意後見制度・日常生活自立支援事業などを活用することが正しい方法です。
ケアマネには直接管理を依頼するのではなく、適切な制度や専門職につないでもらうことを意識しましょう。
そうすることで、大切な財産を守りながら安心して介護生活を続けることができます。















