ケアマネがやってはいけないことってどんなこと?分かりやすく解説
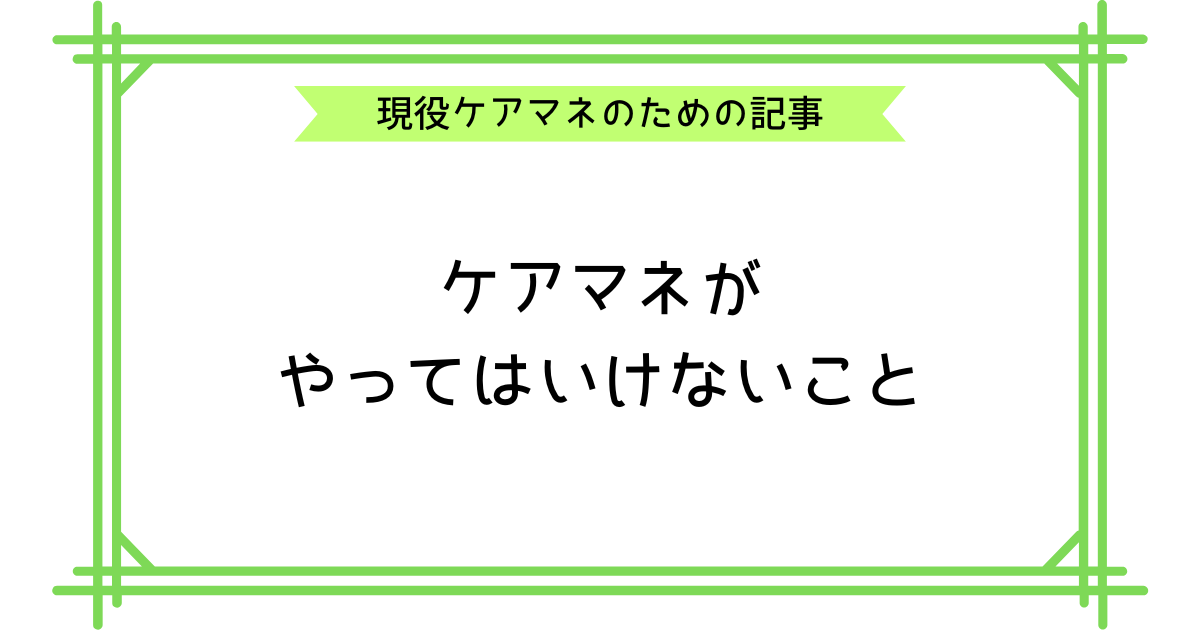
介護の現場で利用者や家族の頼れる存在である「ケアマネジャー(介護支援専門員)」。
介護保険制度の中心的役割を担う一方で、絶対にやってはいけない行為も明確に定められています。
法律や倫理、制度上のルールを知らずに違反してしまうと、資格停止や業務停止処分など重いペナルティにつながる場合も。
この記事では、ケアマネがやってはいけないことを分かりやすく解説し、注意すべきポイントやトラブルを防ぐための心構えも紹介します。
ケアマネが「やってはいけないこと」とは?
ケアマネは、要介護者の介護サービス利用をサポートする専門職であり、中立・公正な立場で業務を行う義務があります。
そのため、下記のような行為は厳しく禁止されており、違反した場合は行政処分や訴訟リスクも生じることになります。
利用者の意思を無視したケアプラン作成
■ 解説
ケアマネジャーの最も大切な役割は、本人・家族の希望に沿ったケアプランを作成することです。にもかかわらず、利用者の意思確認を怠り、一方的にケアプランを作成・変更することは、制度上も倫理上も重大な違反です。
■ 具体例
- 本人が望んでいない施設入所を勝手に進める
- 利用者に説明なく訪問回数やサービス内容を変更する
特定の事業所へのサービス誘導(利益誘導)
■ 解説
ケアマネが中立な立場を忘れ、特定の事業所ばかりを勧めたり、自社サービスに偏らせる行為は「不正誘導」とされます。これは、ケアマネとしての中立性を損なう重大な倫理違反です。
■ 具体例
- 自分が所属する法人のデイサービスばかりを勧める
- 他事業所への紹介を一切せず、利用者に選択肢を与えない
サービス担当者会議を開かずにプランを変更する
■ 解説
ケアプランの変更時には、原則としてサービス担当者会議を開催し、関係職種間での情報共有・調整を行う必要があります。勝手に変更した場合、チームケアが成り立たなくなる可能性があるため、非常に危険です。
■ 例外あり
緊急や軽微な変更の場合は、省略可能とされていますが、その際にも記録の保存が義務づけられています。
経済的利益を受け取る(キックバック・謝礼)
■ 解説
利用者や事業所から、金銭や物品などの対価を受け取ることは、明確に法律で禁止されています。いわゆるキックバック(紹介料)や謝礼の受け取りは、発覚すれば処分の対象となります。
■ 具体例
- 事業所から紹介料として商品券をもらう
- 利用者から高額な贈り物を受け取る
書類の改ざん・虚偽記載
■ 解説
介護保険制度において、書類はサービス提供の証拠であり、給付の根拠にもなります。ケアマネが書類を改ざんしたり、虚偽の内容を記載することは不正請求に直結し、処分対象となります。
■ 具体例
- サービス提供していない日を提供済みにする
- ケアプランにないサービスを記載する
個人情報の漏洩・管理不
■ 解説
ケアマネは、利用者の住所、病歴、家族関係、収入など機微な情報を扱うため、個人情報保護の意識が必須です。紛失や無断持ち出し、第三者への漏洩は、利用者本人の信頼を損なうだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
■ 具体例
- 家族に無断で他の事業所に情報を送付する
- 利用者のファイルを自宅に持ち帰る(規定がない場合)
虚偽のモニタリング報告やモニタリングの未実施
■ 解説
モニタリングは、ケアプランが適切に実施されているか、生活に変化がないかを確認する大切な業務です。実施せずに「行った」と記録したり、形だけの報告にすることは、不正と見なされます。
■ 具体例
- 訪問せずに電話で済ませたのに「訪問」と記録する
- モニタリングの頻度が基準を下回っている
まとめ
ケアマネジャーは、高齢者の暮らしを支えるプロフェッショナルとして、制度的な責任と倫理的な意識の両方が求められます。
今回紹介したような「やってはいけない行為」は、制度違反だけでなく、利用者の信頼を大きく損なう行為でもあります。
- 本人・家族の意思を尊重しない
- 中立性を欠いたサービス誘導
- 書類の不備・不正
- モニタリングや会議の省略
- 個人情報管理の甘さ
- 経済的利益の受け取り
これらを回避するためにも、常に制度のルールを確認し、チームと連携を取りながら丁寧な対応を心がけることが大切です。
ケアマネとしての信頼と専門性を守るために、日々の業務を振り返りながら誠実に取り組みましょう。















