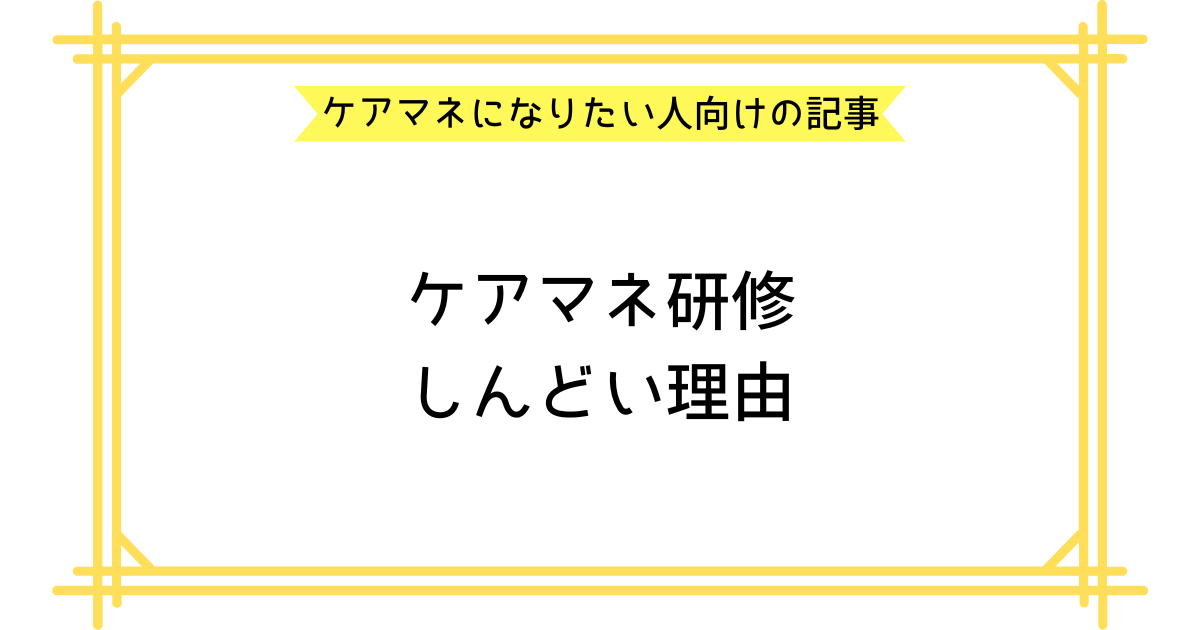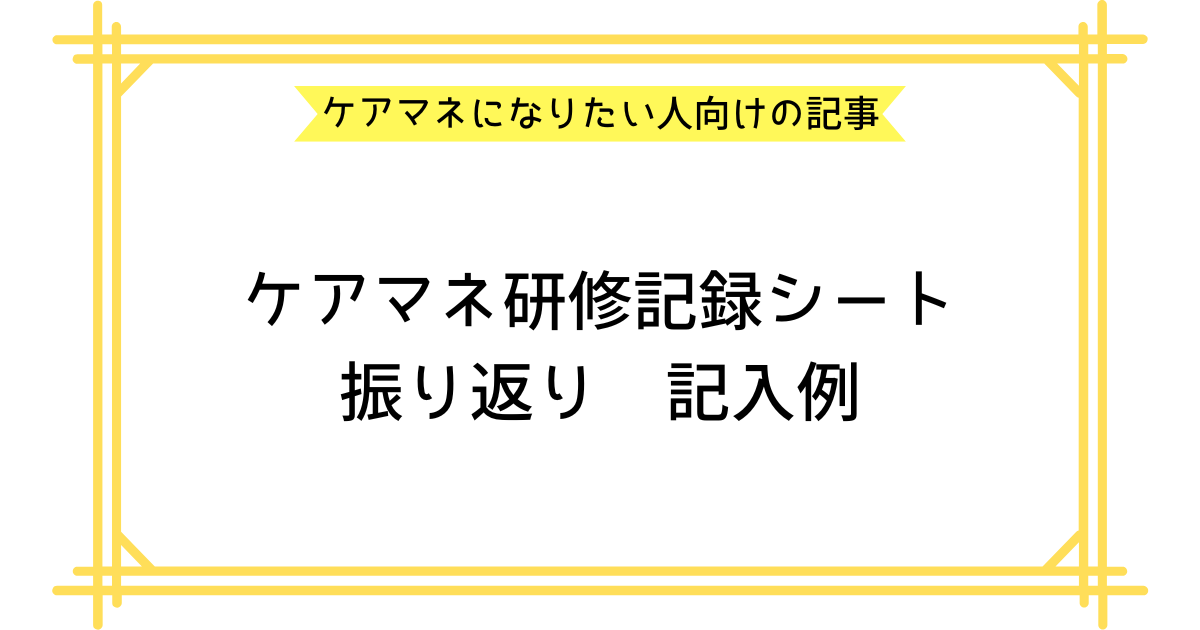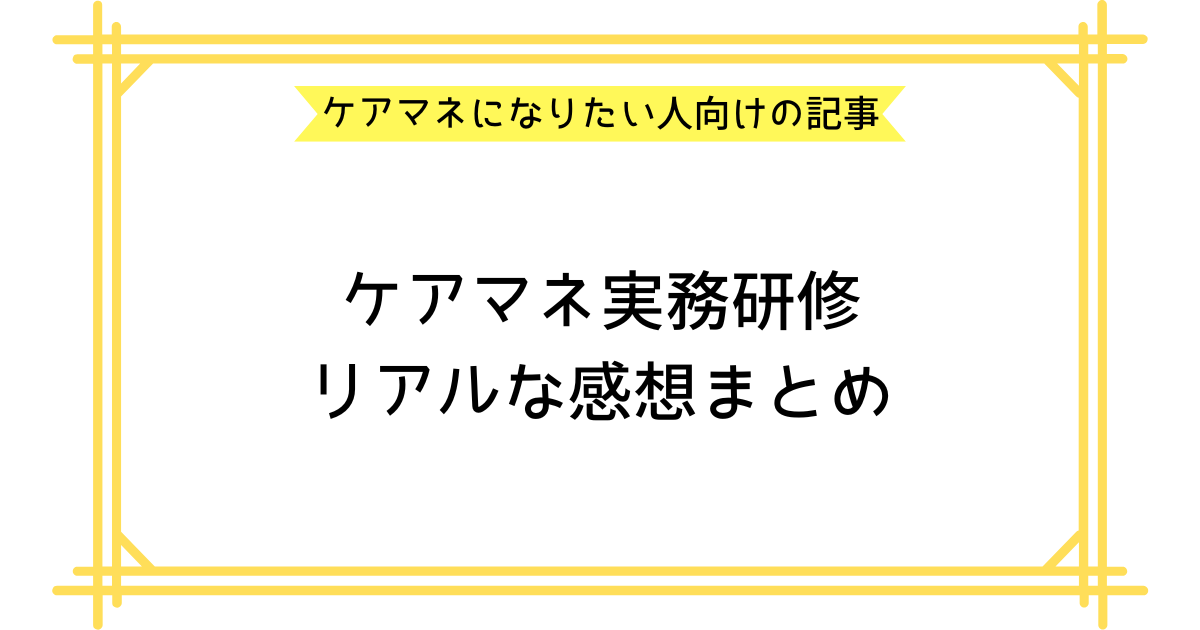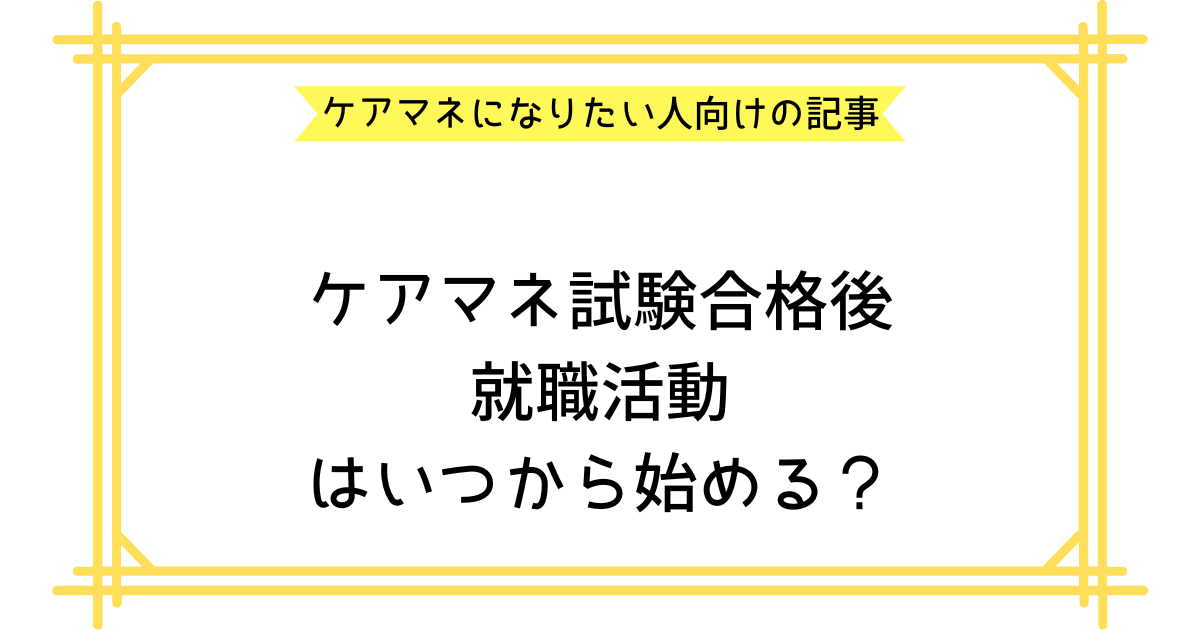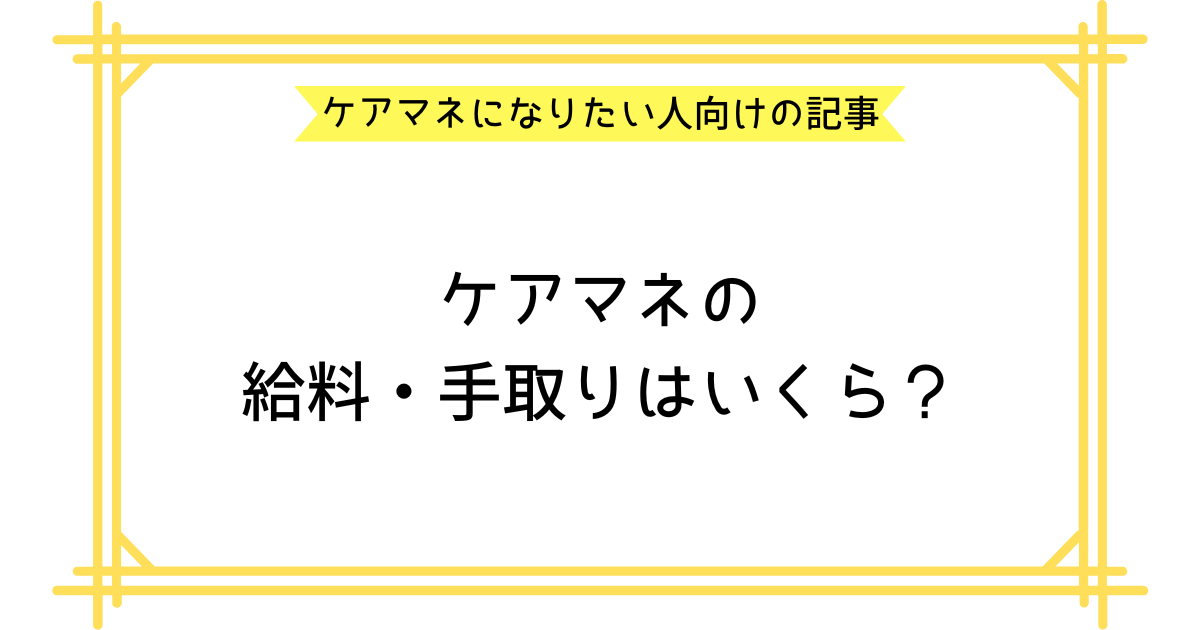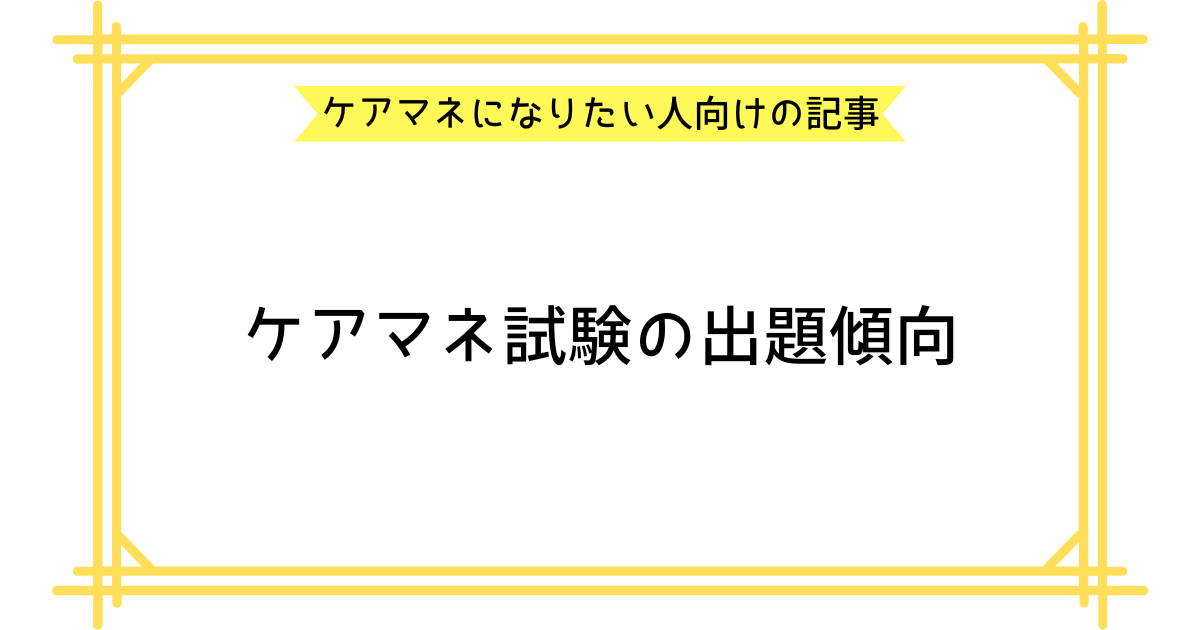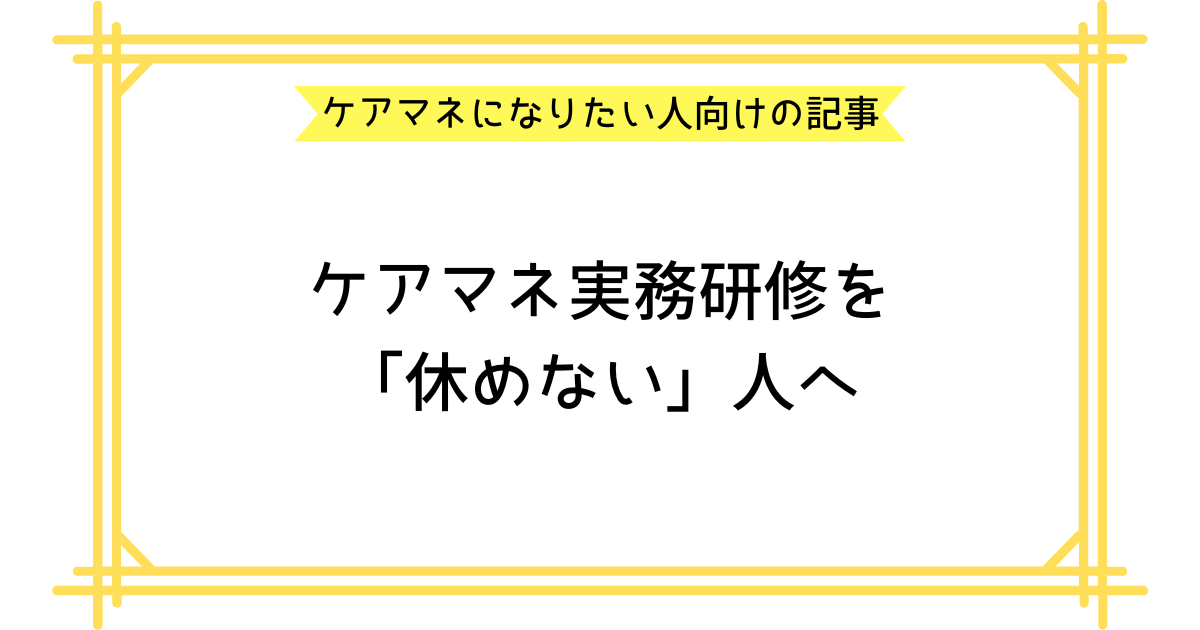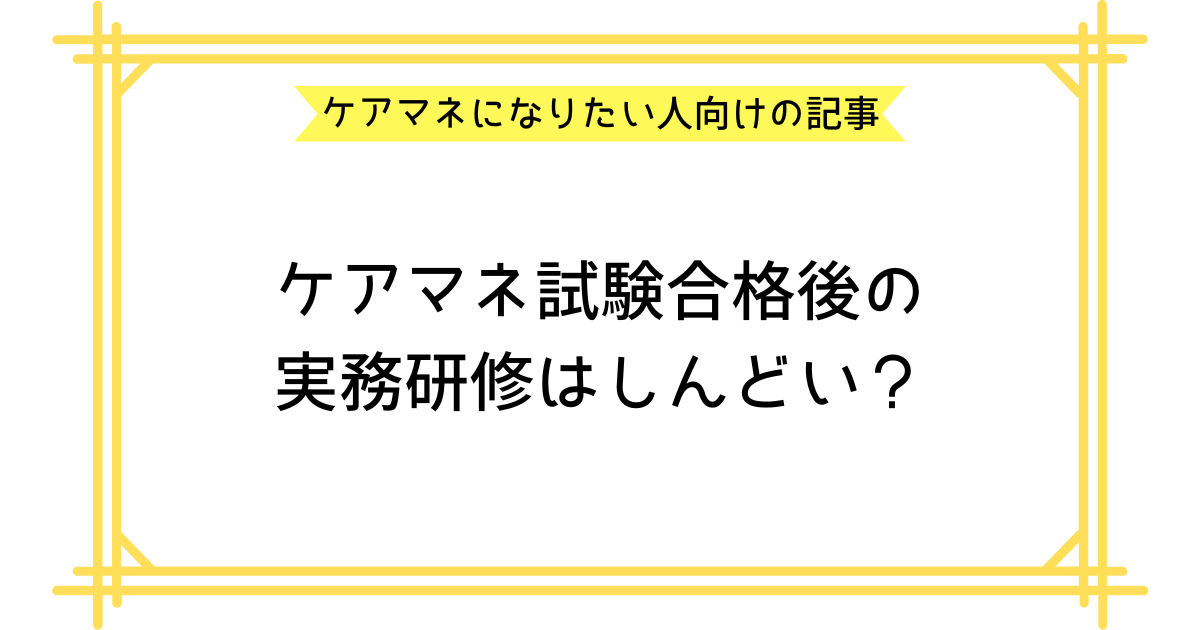介護支援専門員とケアマネの違いとは?わかりやすく解説
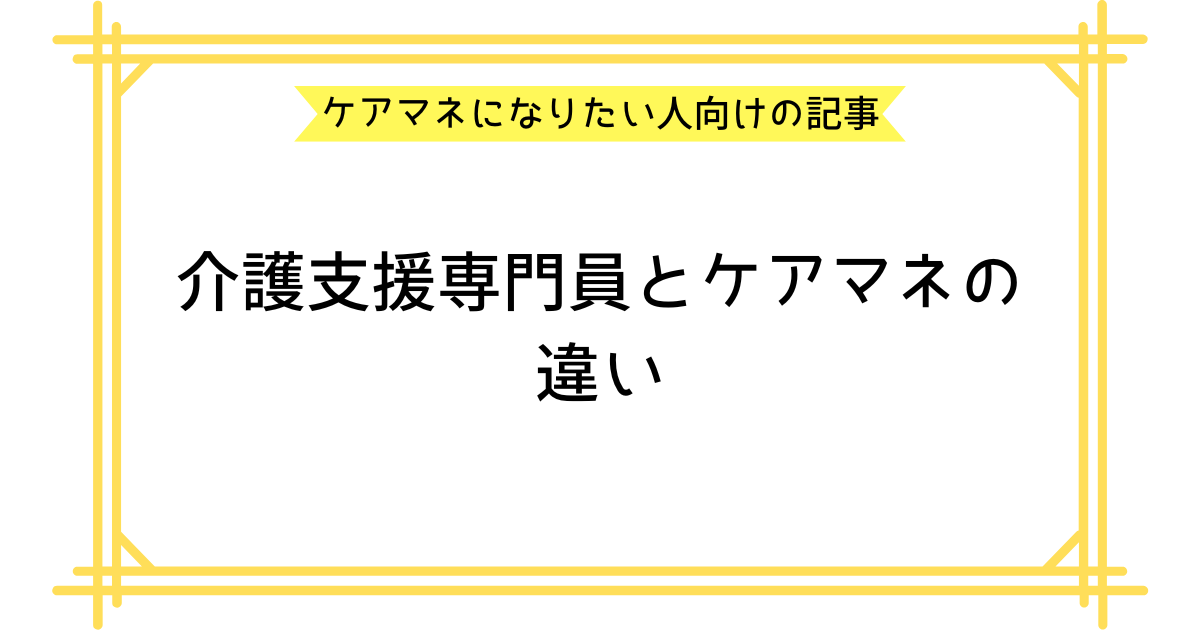
介護の現場でよく耳にする「介護支援専門員」と「ケアマネ」。
この2つの言葉、何がどう違うの?と疑問に思ったことはありませんか?
実は、これらは同じ職種を指しており、呼び方が異なるだけです。
本記事では、「介護支援専門員」と「ケアマネ」の違いや意味の背景、ケアマネジャーの仕事内容や1日の流れまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
介護業界に興味のある方や、今後ケアマネを目指す方はぜひ参考にしてください。
介護支援専門員とケアマネの違いとは?言い方が違うだけ
「介護支援専門員」と「ケアマネ」は、実は同じ職業を指しています。「介護支援専門員」は正式な資格名であり、公的文書や制度上で使われる表現です。一方、「ケアマネ」は「ケアマネジャー」の略称で、日常会話や現場で広く使われている呼び方になります。どちらも、介護が必要な人に対してケアプランを作成し、介護サービスの調整や支援を行う役割を担います。つまり、言い方の違いだけであり、職務内容や責任は同じです。混乱しやすい用語ですが、「ケアマネ=介護支援専門員」と覚えておけば問題ありません。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険制度の中核を担う専門職で、介護が必要な人に対して最適なサービスを選定・調整する役割を持っています。利用者本人や家族と面談し、生活状況や身体状況を把握した上で、介護サービス事業者と連携してケアプランを作成します。また、定期的なモニタリングを行い、利用者の状況変化に応じたプランの見直しも行います。医療・福祉・介護の知識と高いコミュニケーション力が求められ、まさに介護のコーディネーターとして重要な役割を果たします。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の一日の流れ
ケアマネジャーの一日は、デスクワークと訪問業務がバランスよく組み合わさった構成となっています。たとえば、午前中は事務所で前日の記録整理や新たなケアプランの作成を行い、その後、利用者宅を訪問して聞き取り調査を実施します。午後は担当する医療機関や介護サービス事業者と会議や連携調整を行うこともあります。加えて、必要に応じてモニタリング訪問を行い、サービスの継続性や質を確認します。事務処理も多いため、パソコン作業も欠かせません。曜日や月によっては、サービス担当者会議や認定調査の同行もあり、多忙ながらも変化に富んだ業務内容です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容
ケアマネジャーの主な仕事内容は、ケアプランの作成・見直し、サービス事業者との調整、そして利用者の生活を継続的に支えるためのモニタリングです。利用者の状態に応じたサービスを選定し、複数の事業者と連携して実行に移します。さらに、要介護認定の申請代行や主治医への情報提供、介護保険制度に基づいた各種手続きの支援も行います。単なる事務作業ではなく、利用者の生活に深く関わる責任ある仕事であり、その分、やりがいや達成感も大きい仕事です。
まとめ
「介護支援専門員」と「ケアマネ」は、呼び方が異なるだけで、同じ専門職を指します。
正式な資格名が「介護支援専門員」であり、現場では「ケアマネ」と呼ばれることが一般的です。
ケアマネジャーは、介護が必要な方の生活を支える重要な存在であり、その仕事内容は多岐にわたります。
日々の業務では、利用者や家族、事業者との連携を通じて、介護サービスの質と継続性を高めることが求められます。
これから介護業界で働きたい方や、ケアマネを目指している方は、この違いを理解し、自分の将来像を描く参考にしてみてください。