ケアマネにオンコールはあるの?実態や大変さ、働き方の工夫を解説
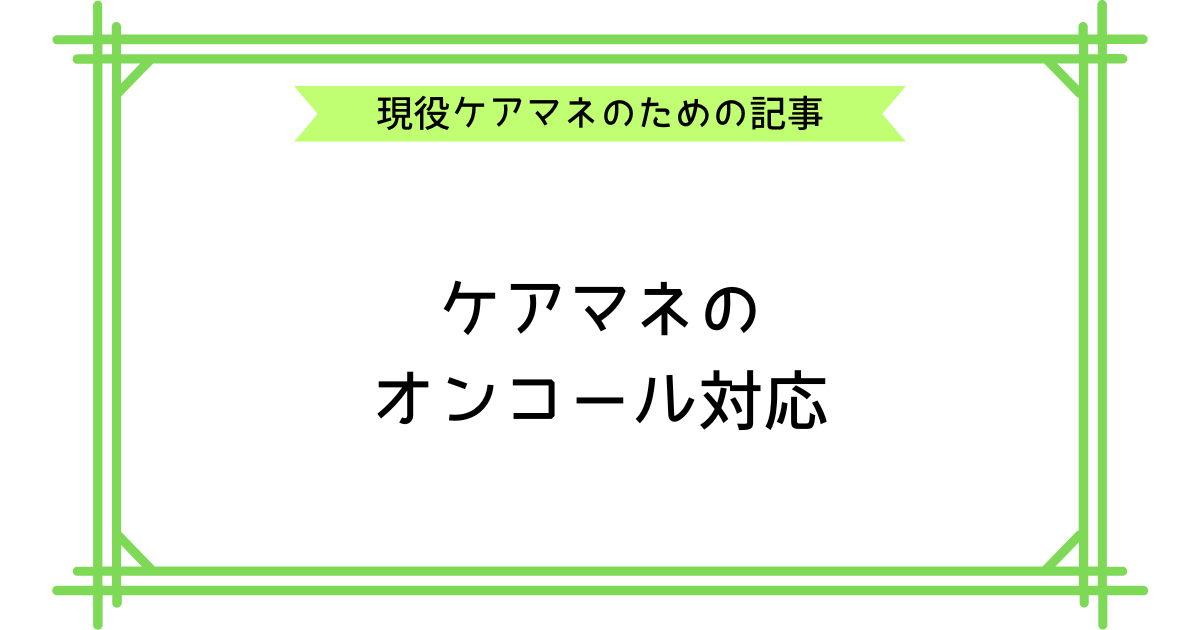
「ケアマネジャー(介護支援専門員)にオンコールはあるの?」
介護職や看護職では夜間や休日に呼び出し対応をする「オンコール体制」がありますが、ケアマネにも同じような働き方があるのか疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、ケアマネの勤務形態によってオンコール対応の有無は異なります。
本記事では、ケアマネにオンコールがある場合とない場合の違いや、実際にどんな対応を求められるのか、大変さとその対策について詳しく解説します。
これからケアマネを目指す方や、転職を考えている方に役立つ内容です。
ケアマネにオンコールはあるのか?
ケアマネ業務は基本的に平日日中が中心で、介護職や看護職のように夜間オンコールが常に必須というわけではありません。
しかし、勤務先の種類や事業所の方針によってはオンコール対応が求められるケースもあります。
- 居宅介護支援事業所:原則オンコールはなし。夜間対応は訪問介護や訪問看護の事業所が担う。
- 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設ケアマネ:夜間や休日に急変やトラブルがあった場合、連絡を受けることがある。
- 小規模事業所や地域包括支援センター:人員体制によっては、当番制でオンコール対応を求められる場合がある。
つまり「どこで働くか」によってオンコールの有無が変わるのが実態です。
ケアマネがオンコール対応する場面の具体例
オンコール対応がある場合、ケアマネはどのような連絡を受けるのでしょうか。
代表的な事例を紹介します。
施設ケアマネの場合
- 夜間に入所者が転倒し、救急搬送の必要があるときの連絡調整
- 家族への緊急連絡と対応方針の説明
- 看取り期の利用者が容体変化を起こした際の連絡・記録対応
地域包括支援センターの場合
- 高齢者の安否確認要請
- 深夜の徘徊などで警察や家族から相談が入るケース
- 緊急的なショートステイ利用調整
居宅ケアマネの場合(まれに発生)
- 家族からの緊急相談(「サービスを増やしたい」「急に状態が悪化した」など)
- サービス事業所からの報告(急変対応後の連絡など)
このように、直接現場に駆けつけることは少なくても「電話による調整」「家族への説明」が求められることがあります。
ケアマネのオンコールはどれくらい大変なのか?
精神的な負担が大きい
夜間や休日に電話が鳴るだけで「何かあったのでは」と緊張し、常に気が休まらないと感じるケアマネもいます。
頻度は事業所によって差がある
施設ケアマネの場合はオンコールが発生しやすいですが、居宅ではほとんどないことが一般的です。ただし小規模な法人ではケアマネも含めた「持ち回り体制」を敷いている場合があります。
直接対応は少ないが責任は重い
実際に現場に出向くことは稀ですが、判断や家族説明の責任を担うため、精神的なプレッシャーがかかります。
ケアマネがオンコールに対応するメリット・デメリット
メリット
- 緊急時の対応経験が積めるためスキルアップにつながる
- 家族からの信頼を得やすい
- 法人内での評価が高まる可能性がある
デメリット
- プライベートの時間が拘束される
- 睡眠不足や疲労につながる
- 精神的なストレスが蓄積する
オンコールの負担を軽減する方法
当番制や分担制を導入する
事業所内でオンコールを持ち回りにすることで、負担を一人に集中させない工夫が必要です。
ルールを明確にする
「どのケースでケアマネに連絡するか」を職員間でルール化し、不必要な連絡を減らすことが大切です。
ICTを活用する
記録共有や安否確認システムを導入することで、夜間の不要な問い合わせを減らすことが可能です。
転職を検討する
「オンコールは絶対に避けたい」という人は、居宅介護支援事業所など原則オンコールがない職場を選ぶのも有効な選択肢です。
まとめ
ケアマネにオンコールがあるかどうかは 勤務先によって異なる のが実態です。
- 居宅介護支援事業所 → 基本的にオンコールなし
- 施設ケアマネ → 急変時の連絡や家族対応でオンコールがあることも
- 地域包括支援センター → 緊急相談でオンコール対応が発生するケースも
オンコールは直接現場に駆けつけることは少ないものの、精神的な負担は大きいのが特徴です。
どうしても負担に感じる場合は、オンコールがない職場を選ぶ、当番制を導入するなどの工夫が必要です。
ケアマネとして長く働くためには、自分に合った働き方を選び、オンコールの有無も含めて転職先を慎重に検討することが大切だといえるでしょう。















