【令和7年10月改定対応版】育児・介護休業法についてわかりやすく解説
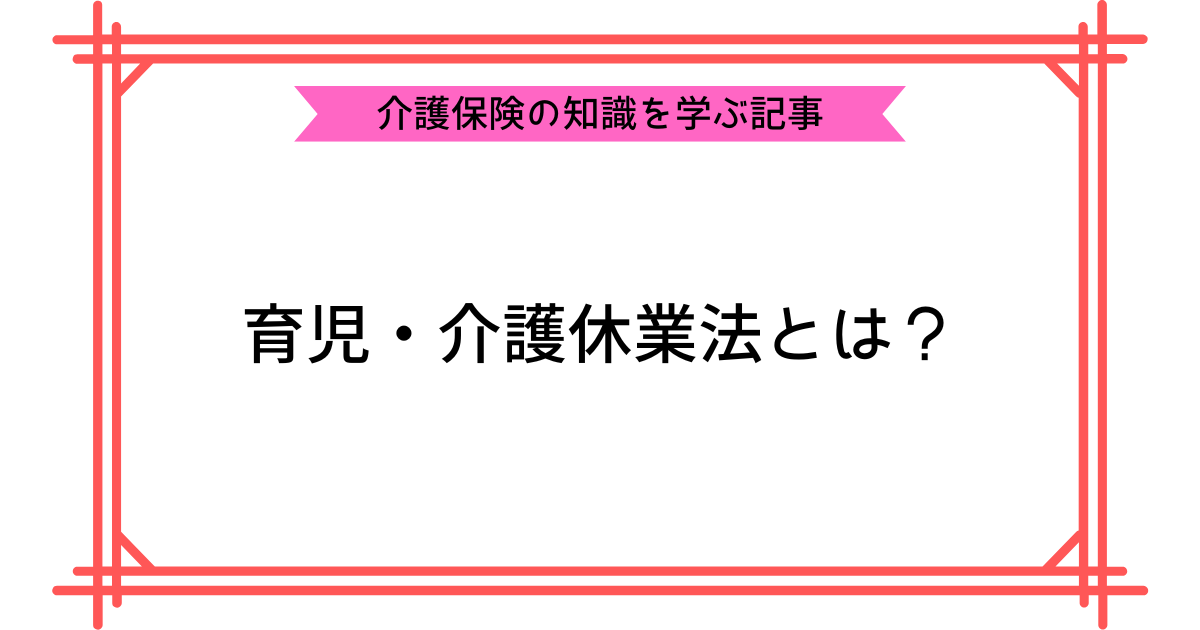
育児・介護休業法が令和7年(2025年)に改正され、仕事と育児・介護を両立させたい労働者・利用者・企業にとって重要な変更が入ります。
「どこがどう変わるのか分からない」「自分の職場は対応できるだろうか」と不安な方も多いでしょう。
本記事では、令和7年10月1日施行の改正を含めたポイントを、ケアマネなど福祉・介護・サービス関係者にも分かりやすく整理します。
育児・介護休業法とは何か
育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、1992年に施行され、育児や介護のために働くことが困難な時期でも、労働者が働き続けられるように制度上の支援を行うことを目的とする法律です。育児休業・介護休業制度、育児・介護休暇、育児目的の制度などが含まれています。改正は、働き方の多様化や少子高齢化の進行、介護離職の防止など社会ニーズの変化を受けて行われています。
改正の背景・目的
令和7年改正の大きな背景・目的は以下の通りです。
- 育児・介護によって働けなくなること(離職など)を減らす
- 育児期・介護期に柔軟な働き方を実現させる
- 労働者自身の意向を確認・配慮する仕組みを強化する
- 男女ともに仕事と育児を両立できるようにする
- 企業に対して必要な制度整備や周知義務を強化する
改正の概要と施行時期
改正は主に令和7年(2025年)4月1日と10月1日の二段階で施行されます。4月1日から先行するもの、10月1日から新たに義務化または変更されるものがあります。以下に、令和7年10月1日からの主要な改正ポイントを中心に解説します。
令和7年10月1日からの主要改正ポイント
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(義務)
3歳から小学校就学前までの子を育てる労働者に対して、事業主は以下の「選択すべき措置」の中から2つ以上を講じる必要があります。労働者はその中から1つを選択して利用できます。
選択肢となる措置例は以下の通りです。
- 始業・終業時刻の変更(時差出勤や始業遅れ等)
- テレワークの導入(在宅または準じる場所での就業を含む)
- 保育施設の設置・運営等の便宜の提供(ベビーシッター手配など)
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、時間単位取得可能なもの)
- 短時間勤務制度の利用(例えば1日の労働時間を6時間とする)
個別の意向の聴取および配慮の義務化
3歳未満の子を養育する労働者に対して、事業主は「個別の周知」と「意向の確認」を行う必要があります。これは、働き方の選択肢があることをしっかり伝え、必要であれば配慮をすることを義務付けるものです。対象時期は子が3歳になる前までの一定期間で、復帰時や制度利用中など、状況の変化にも応じて対応することが望ましいとされています。
育児・介護休業取得状況の公表義務の拡大
これまで従業員数1,000人を超える企業が対象でしたが、令和7年10月からは300人超の企業も対象となり、「男性の育児休業等取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が義務となります。
その他の改正ポイント(令和7年4月からすでに施行済の内容)
10月改正以外にも、4月施行分での改正事項にも注意が必要です。主なものは次の通りです。
- 子の看護休暇(子の看護等休暇)の対象年齢拡大で、小学校就学前までの子が対象となったこと
- 所定外労働(残業など)の免除対象者の拡大(3歳未満から小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大)
- 短時間勤務制度(3歳未満の子育て)について代替措置にテレワークを追加
- 育児目的のテレワーク導入が努力義務化されたこと
ケアマネ・福祉関係者が知っておくべき影響・ポイント
育児・介護休業法の改正は、企業・労働者だけでなく、ケアマネなど福祉・介護業界にも影響があります。以下の点を押さえておきましょう。
- 利用者の家族が働きやすくなる可能性
- 事業所との連携がより重要になる
- 利用者に制度を案内できるようになる
- 制度利用を前提としたケアプラン策定が必要になる
10月改定対応で事業者・企業が取るべき具体的対応
事業所や企業は、法改正に対応するために以下の準備が必要です。
- 就業規則等の改定:制度を明文化する
- 労働者代表との協議:措置選択にあたって協議する
- 個別周知・意向確認体制:復帰時や制度利用時に面談等を行う
- 公表義務対応:取得率データを収集・公表できる体制を整える
- 勤務体制の柔軟化:テレワークや短時間勤務制度を整備する
よくある質問(FAQ)
Q:3歳以上の子どもがいるが、小学校就学まではどんな制度が使える?
A:10月の改正で柔軟な働き方を実現するための措置が対象になります。選択できる制度が増えるので相談してみましょう。
Q:育児休業中の復帰後、働き方を変えたいがどうすればいい?
A:個別の意向確認が制度上義務化されており、復帰時などに希望を伝えることで事業主の配慮が求められます。
Q:介護をする家族がいるが、どんな休暇・制度が使える?
A:介護休業・介護休暇などが対象で、要件の緩和や取得しやすくなる改正があります。
まとめ
令和7年10月改定対応版の育児・介護休業法は、特に「育児期の柔軟な働き方の義務化」「意向確認」「制度の公表義務の拡大」といった点が大きなポイントです。
企業や事業所は就業規則改定や制度整備、労働者への周知・意向確認といった準備が必要です。ケアマネ・福祉関係職・利用者の家族としても、この改正によって仕事と育児・介護の両立がより現実的になる制度が強化されたことを知り、必要な相談や支援を促していく役割があります。
制度を正しく理解し、活用できるかどうかが、仕事・家庭・介護のバランスをとる鍵となります。















