介護保険の住宅改修費支給限度基準額とは?わかりやすく解説
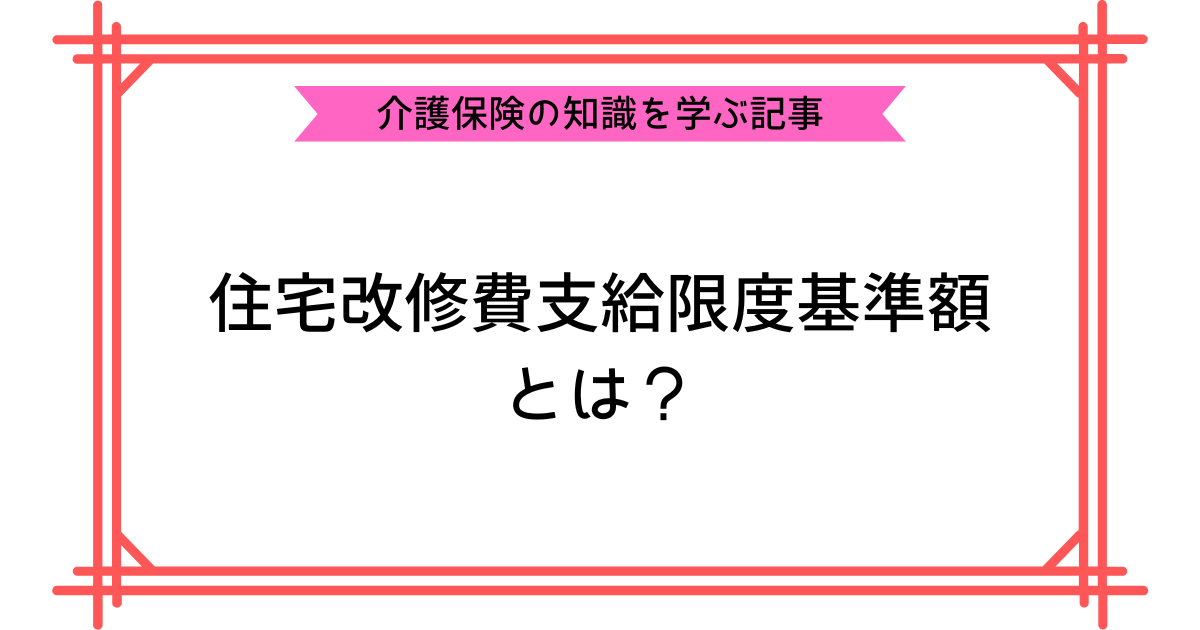
介護保険制度を利用するときに知っておきたいのが「住宅改修費支給限度基準額」です。
高齢者や要介護者が安心して在宅生活を送るためには、住環境を整えることが欠かせません。
段差の解消や手すりの設置といった住宅改修は転倒防止や自立支援に直結しますが、その費用をすべて自己負担するのは大きな負担となります。
介護保険には、こうした住宅改修をサポートする制度があり、一定額まで保険給付を受けられる仕組みが整っています。
しかし「限度額はいくら?」「どんな工事が対象?」「自己負担はどうなるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、介護保険の住宅改修費支給限度基準額の仕組み、対象工事、利用の流れ、注意点をわかりやすく解説します。
住宅改修費支給限度基準額とは?
定義
住宅改修費支給限度基準額とは、介護保険で利用できる住宅改修の費用に対して設定されている給付の上限額のことです。
限度額
- 原則として 20万円まで(自己負担1〜3割を除いた残額が給付)
- 利用者1人あたりで設定されており、1回きりではなく条件に応じて再利用も可能
例:20万円の工事を行った場合、自己負担1割の人なら2万円負担、残り18万円が介護保険から支給されます。
住宅改修で対象となる工事
介護保険で認められる住宅改修工事は、厚生労働省で6種類に限定されています。
- 手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などへの設置 - 段差の解消
敷居の撤去、スロープ設置、浴室床のかさ上げ - 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
畳をフローリングに変更、浴室の床材を滑りにくいものにする - 引き戸などへの扉の取り替え
ドアを引き戸や折れ戸に変更、ドアノブをレバー式に交換 - 洋式便器への便器の取り替え
和式から洋式へ交換 - その他これらに付随する工事
手すり設置に伴う壁の下地補強など
限度額の利用方法
一度きりではなく、条件付きで再利用可能
原則20万円ですが、次の場合には再度利用が認められます。
- 要介護度が3段階以上上がった場合
- 転居して新しい住宅に住む場合
支払い方法
- 償還払い方式:いったん全額を支払い、後日保険給付分が払い戻される
- 受領委任払い方式:自己負担分だけ支払い、残りは事業者が自治体に請求(自治体によって導入状況が異なる)
住宅改修の手続きの流れ
- ケアマネジャーへ相談
必要性を確認し、ケアプランに位置づける。 - 事前申請
工事の見積書、改修理由書、住宅改修が必要な理由書(医師の意見書など)を添えて自治体に提出。 - 承認後に工事実施
事前に承認を受けずに工事すると、介護保険の適用外になるため注意。 - 工事完了後、支給申請
領収書を添付して申請。自治体から支給される。
支給限度基準額に含まれない費用
- エアコン設置や内装工事など、介護と直接関係ない工事
- 住宅の新築や全面改装
- 利用者本人ではなく家族の利便性向上が目的の工事
これらは介護保険の対象外で、全額自己負担となります。
覚えておきたいポイント
ケアマネジャーの役割
- 利用者の身体状況と生活環境を把握
- 改修内容が保険対象かどうかを判断
- 申請書類や手続きのサポート
利用者・家族の注意点
- 事前申請を忘れると自己負担になる
- 20万円を超える部分は全額自己負担
- 将来の生活を見据えた改修計画を立てることが大切
よくある質問(Q&A)
Q:20万円を超える工事はどうなりますか?
A:超えた部分は全額自己負担です。例えば30万円の工事なら、20万円までが保険対象、残り10万円は自己負担となります。
Q:賃貸住宅でも使えますか?
A:はい。家主の承諾があれば賃貸でも利用可能です。
Q:要支援の人も利用できますか?
A:要支援1・2でも対象となり、介護予防の観点から活用できます。
まとめ
介護保険の住宅改修費支給限度基準額とは、在宅生活を安全・快適にするために介護保険が適用される住宅改修費用の上限(20万円)のことです。
- 対象工事は6種類に限定
- 原則20万円までが支給対象(1〜3割は自己負担)
- 条件により再度利用可能
- 利用には必ず事前申請が必要
住宅改修は、転倒予防や自立支援に直結する大切なサービスです。ケアマネジャーや事業者と相談しながら、制度を賢く活用して在宅生活の安心を確保しましょう。















