リハビリテーション会議とは?進め方・医師の参加・目的・議事録・頻度まで徹底解説
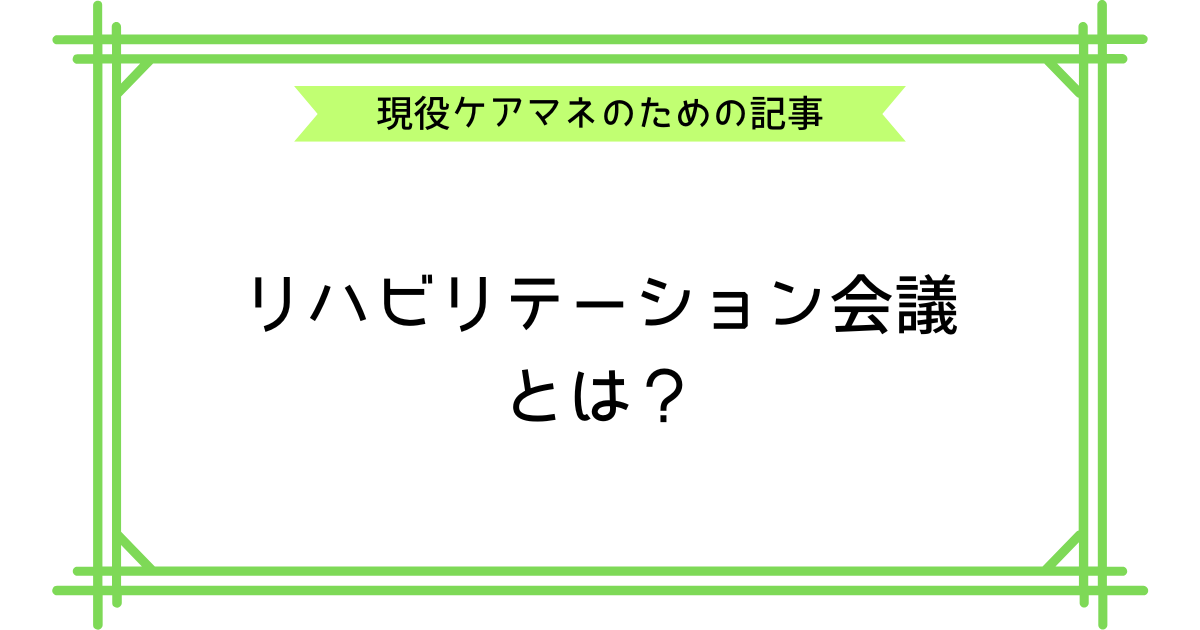
介護保険サービスにおける「リハビリテーション会議」とは、通所リハビリテーション(デイケア)や訪問リハビリテーションを提供する上で欠かせない会議です。リハ職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)や医師を中心に、利用者の心身の状態に合わせたリハビリ計画を立案・評価する役割があります。
しかし、現場では「リハビリテーション会議の正確な目的は?」「進め方はどうすればいいのか」「医師は必ず参加しなければならないのか」「議事録はどう残すのか」「頻度はどのくらいか」といった疑問がよく聞かれます。
本記事では、リハビリテーション会議の意味や進め方、医師の参加のルール、目的、議事録の書き方、開催頻度まで、介護事業所やケアマネジャー、リハ職が押さえておくべきポイントを徹底解説します。
リハビリテーション会議とは?
リハビリテーション会議とは、通所リハビリや訪問リハビリを行う際に、医師の指示に基づいて多職種が連携し、リハビリ計画の立案・実施・評価を行う会議です。介護保険制度上も開催が義務づけられており、単なる形式的な会議ではなく、算定要件を満たすうえでも重要な役割を果たしています。
この会議を通して「利用者にとって適切なリハビリ目標は何か」「実際にどの程度達成できているのか」を確認し、必要に応じて計画を修正していきます。つまり、リハビリテーション会議は利用者の生活の質(QOL)を高めるための土台となる仕組みなのです。
リハビリテーション会議の目的
リハビリテーション会議には大きく分けて以下の目的があります。
- 利用者の身体機能や生活機能を正確に把握する
- 医師やリハビリ職、看護師、介護職が情報を共有する
- 利用者と家族の希望を踏まえたリハビリ計画を立てる
- 計画を実施した結果を評価し、必要なら修正する
- ケアプラン全体にリハビリの方針を反映させる
特に重要なのは、利用者本人の生活をどう支えるかという視点です。単に筋力をつける、歩けるようにするというだけではなく、「自宅でトイレに行けるようにする」「家族と一緒に食事を楽しむ」など、生活に直結した目標を立てることが目的となります。
リハビリテーション会議の進め方
リハビリテーション会議の進め方は事業所ごとに多少の違いはありますが、一般的な流れは以下の通りです。
- 開催準備
利用者の基本情報、最近のADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の変化、医療情報を整理する。 - 開会・目的確認
「本日の会議では、◯◯さんの歩行状態を評価し、今後のリハビリ計画を見直す」など、会議の目的を共有する。 - 現状報告
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリの進捗を報告する。看護師からは健康状態、介護職からは日常生活の様子を共有する。 - 評価と課題整理
本人の現状をもとに「できるようになったこと」「まだ困難なこと」を整理する。 - 今後の方針決定
リハビリの長期目標・短期目標を確認し、具体的なプログラムや支援方法を決定する。 - 利用者・家族への説明
決定した内容を分かりやすく伝え、同意を得る。 - 議事録の作成
会議の内容を文書化し、保管・共有する。
進め方のポイントは、利用者本人や家族の意向をしっかり反映させることです。
現場の専門職の意見だけでなく、本人の「やりたいこと」を尊重したプランを作ることで、リハビリの効果も高まります。
リハビリテーション会議における医師の参加
リハビリテーション会議には、医師の関与が必須とされています。通所リハビリや訪問リハビリの算定要件でも「医師の指示の下で計画を作成すること」が定められているためです。
ただし、必ずしも医師本人が会議に同席しなければならないわけではありません。実務上は以下の形が認められています。
- 医師が直接出席する
- 医師が事前にリハビリ計画を確認・署名する
- 医師がICT(オンライン会議)を通じて参加する
重要なのは、医師が計画に責任を持って関与していることを証明できるかどうかです。リハ職や看護師だけで会議を進め、医師の関与が不十分な場合は算定要件を満たさないため注意が必要です。
リハビリテーション会議の議事録
リハビリテーション会議を開催したら、必ず議事録を作成し、保存する義務があります。議事録には以下の内容を盛り込むのが一般的です。
- 利用者の氏名・介護度・基本情報
- 開催日時・場所・参加者(職種名も記載)
- 会議の目的
- 現状の評価(心身機能、ADL、IADL、認知機能など)
- 今後のリハビリ方針(長期目標・短期目標)
- 利用者や家族の意向
- 合意内容と次回開催予定
議事録は監査や加算算定の根拠資料となるため、客観的かつ具体的に記載することが重要です。「歩行が改善した」ではなく「歩行距離が10mから20mに延びた」と具体的に書くことで、記録の信頼性が高まります。
リハビリテーション会議の頻度
リハビリテーション会議は、少なくとも3か月に1回以上の開催が義務づけられています。これは介護報酬算定要件でも明確に定められている基準です。
ただし、利用者の状態に大きな変化があった場合には、3か月を待たずに随時開催することも可能です。例えば、脳梗塞後の急な機能低下や、骨折後のリハビリ方針の見直しなどが該当します。
施設や事業所によっては、利用者や家族の要望に応じて1か月ごとに小規模な評価会議を行うケースもあります。
リハビリテーション会議とサービス担当者会議の違い
リハビリテーション会議と混同されやすいのが、ケアマネジャーが主催する「サービス担当者会議」です。
- リハビリテーション会議:リハビリに特化した会議。医師やリハ職が中心。
- サービス担当者会議:ケアプラン全体を多職種で調整する会議。ケアマネジャーが中心。
両者は目的が異なるため、どちらか一方だけで良いというものではなく、連携して開催されることが理想的です。リハビリの目標や方針をサービス担当者会議に反映させることで、生活全体を見据えたケアプランになります。
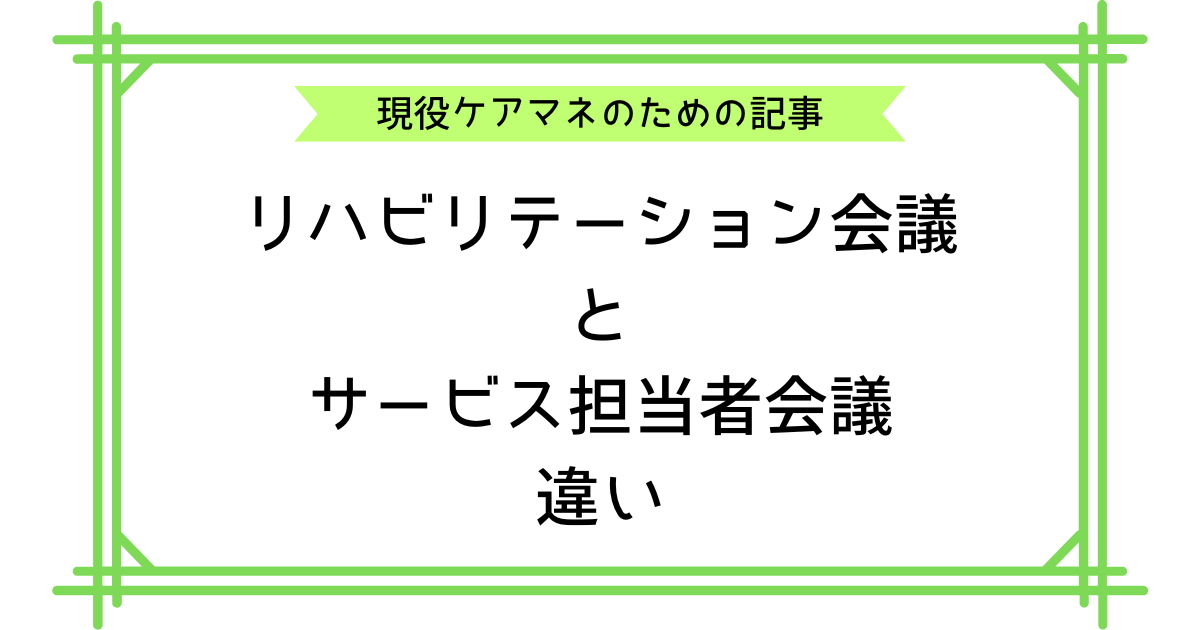
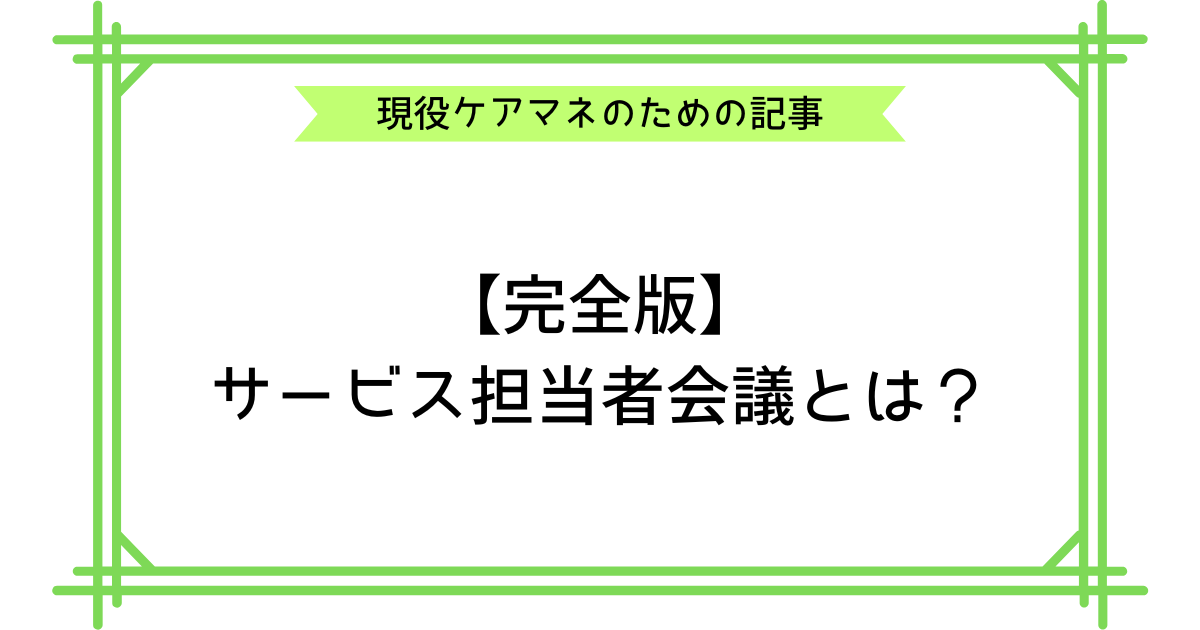
リハビリテーション会議の課題と今後の展望
現場では「医師が忙しくて参加が難しい」「議事録作成が負担」「利用者や家族の意向が十分反映されない」といった課題があります。
今後は、オンライン参加の活用や議事録のICT化、多職種間の情報共有システムの普及が進むことで、よりスムーズな開催が可能になるでしょう。また、利用者本人の意思決定支援(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)と結びつけて開催する動きも広がりつつあります。
まとめ
リハビリテーション会議とは、通所リハビリや訪問リハビリを提供する上で必須となる会議であり、利用者の生活機能を維持・改善するために欠かせない仕組みです。
- 目的:リハビリ計画の策定・評価・修正
- 進め方:準備 → 現状報告 → 評価 → 方針決定 → 利用者説明 → 議事録作成
- 医師の参加:必ず関与が必要(直接参加・署名・オンライン)
- 議事録:算定要件の根拠となるため必須
- 頻度:3か月に1回以上が義務
正しく理解し、実務に落とし込むことで、リハビリテーション会議は単なる制度対応ではなく、利用者と家族の生活の質を高める大切な場となります。















