特定疾患と特定疾病の違いをわかりやすく解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
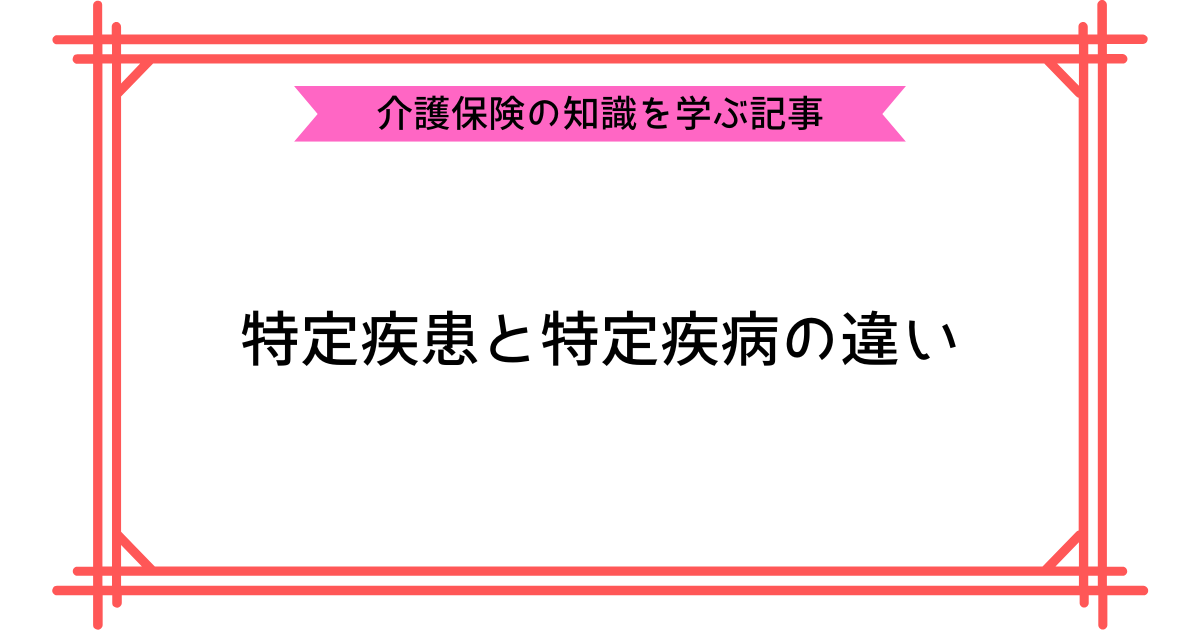
介護や医療の分野でよく耳にする「特定疾患」と「特定疾病」。
名前が似ているため混同しやすいですが、制度上の意味や対象はまったく異なります。
この記事では、特定疾患と特定疾病の定義・対象となる病気・制度上の違い をわかりやすくまとめました。
試験対策だけでなく、介護や医療の現場で利用者の相談に乗る際にも役立つ内容です。
目次
特定疾患とは?
「特定疾患」とは、難病対策として国が医療費助成の対象とする疾患 を指します。
厚生労働省が指定しており、1972年に始まった難病対策の中で導入された用語です。
- 医療費助成の対象になる
- 難病に分類される
- 指定疾患は数百種類に及ぶ
代表的なものとして、ベーチェット病、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス(SLE)などが挙げられます。
つまり「特定疾患=医療費助成の対象となる難病」のことです。
特定疾病とは?
一方「特定疾病」とは、介護保険制度で40〜64歳の第2号被保険者が介護保険を利用できる対象となる16種類の病気 を指します。
要介護認定は原則65歳以上であればどんな原因でも介護保険を利用できますが、40〜64歳では「加齢に伴って発症する病気」に限定されています。これが「特定疾病」です。
特定疾病の代表例
- がん(回復見込みがないもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脳血管疾患
- 骨粗鬆症による骨折
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 末期腎不全
全部で16種類が厚生労働大臣により指定されています。
特定疾患と特定疾病の違いを整理
では、この2つの用語の違いをまとめてみましょう。
| 項目 | 特定疾患 | 特定疾病 |
|---|---|---|
| 制度 | 難病対策事業 | 介護保険制度 |
| 対象者 | 年齢制限なし | 40〜64歳の第2号被保険者 |
| 内容 | 医療費助成を受けられる疾患 | 介護保険サービスを利用できる疾患 |
| 疾患数 | 数百種類(難病) | 16種類 |
| 代表例 | ベーチェット病、潰瘍性大腸炎、SLEなど | がん、ALS、脳血管疾患、COPDなど |
このように、制度・対象・目的が異なるため、用語を正しく使い分けることが大切です。
試験対策での覚え方
- 特定疾患=難病=医療費助成
- 特定疾病=介護保険=16種類の病気
「疾患(医療)」「疾病(介護)」と漢字で区別して覚えると混乱しにくくなります。
まとめ|特定疾患と特定疾病の違いを理解しよう
- 特定疾患 は「難病対策」で医療費助成が受けられる病気
- 特定疾病 は「介護保険制度」で40〜64歳が対象となる病気
- 名前は似ているが、制度・対象者・目的は全く異なる
介護や医療の試験では頻出テーマです。利用者や家族への説明の際にも役立つ知識なので、両者の違いをしっかり押さえておきましょう。















