【丸パクリコピペOK】要介護4のケアプラン文例を100事例紹介
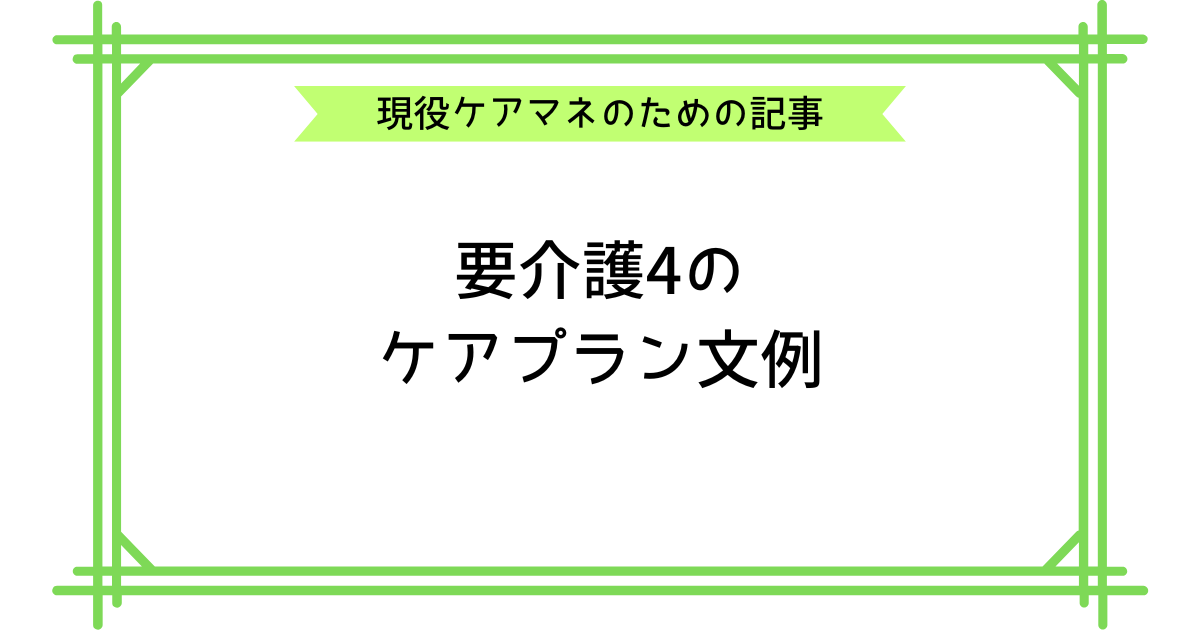
要介護4は、食事や排泄、入浴、移動といった日常生活動作のほとんどに介助が必要な状態を指します。
また、認知症の進行や複数の疾患を抱えるケースも多く、医療的ケアや家族支援も欠かせません。
ケアマネジャーは利用者本人の尊厳を守りつつ、家族の介護負担を軽減し、在宅生活を継続できるように支援内容を盛り込む必要があります。
ここでは【丸パクリコピペOK】でそのまま使える「要介護4のケアプラン文例」を100事例紹介します。
要介護4ケアプラン文例【基本的な生活支援編】
文例1:入浴介助
週3回の入浴介助を行い、清潔保持と心身のリフレッシュを図る。転倒予防のため必ず2人体制で介助し、安全を確保する。
文例2:清拭対応
発熱や体調不良で入浴できない場合は清拭を実施し、皮膚の汚れや発汗を除去して清潔を保つ。
文例3:食事介助
嚥下機能に配慮し、きざみ食やとろみ付き食を提供する。食事は全介助とし、誤嚥予防に努める。
文例4:排泄介助
定時のトイレ誘導とオムツ交換を行い、排泄パターンを記録しながら皮膚トラブルを防ぐ。
文例5:水分補給
脱水予防のため、1日1500mlを目安に水分摂取を促す。嚥下状態を観察し、むせ込みがあれば医師に報告する。
文例6:更衣介助
衣類の着脱を介助し、可能な部分は本人の意思を尊重して動作を行ってもらう。
文例7:口腔ケア
毎食後に口腔ケアを実施し、義歯の洗浄や口腔内の清潔を保つことで誤嚥性肺炎を予防する。
文例8:体位変換
2時間ごとに体位変換を行い、褥瘡の発生を予防する。皮膚状態を観察して記録する。
文例9:移乗介助
ベッドから車椅子への移乗を全介助で行い、安全に居室外へ移動できるよう支援する。
文例10:整容支援
髭剃りや整髪を介助し、清潔感を維持して本人の尊厳を守る。
文例11:起床介助
朝の起床時に声かけと身体支援を行い、生活リズムを安定させる。
文例12:就寝支援
就寝前の排泄・口腔ケアを実施し、快適に眠れる環境を整える。
文例13:居室清掃
週2回居室清掃を行い、衛生的で快適な生活空間を維持する。
文例14:洗濯介助
衣類の洗濯・乾燥・収納を代行し、清潔な衣類で生活できるようにする。
文例15:買い物代行
必要な生活用品を代理購入し、家族の負担を軽減する。
文例16:ゴミ出し
家庭ゴミを定期的に処分し、衛生的な住環境を確保する。
文例17:食事準備
栄養バランスを考慮し、医師の指示に従った食事を調理する。
文例18:配膳介助
食事を本人の前まで運び、スプーンで介助しながら摂取を支援する。
文例19:洗面介助
洗面動作を介助し、顔や手の清潔保持を徹底する。
文例20:季節対応
夏季はエアコンで室温調整を行い、冬季は保温を徹底することで体調を崩さないようにする。
要介護4ケアプラン文例【医療的ケア・健康管理編】
文例21:服薬管理
服薬カレンダーを使用し、訪問介護で確実な服薬支援を行う。
文例22:バイタル測定
訪問看護で週2回、体温・血圧・脈拍・SpO2を測定し、異常があれば医師に報告する。
文例23:褥瘡予防
エアマットを導入し、皮膚の発赤や損傷がないか毎日観察する。
文例24:糖尿病管理
血糖値を定期的に測定し、食事と薬の管理を徹底する。
文例25:在宅酸素療法
酸素療法中はチューブ抜去や転倒を防ぐよう見守る。
文例26:点滴管理
必要に応じて訪問看護が点滴を行い、実施後は全身状態を確認する。
文例27:排痰ケア
痰が多いときは吸引器を用いて呼吸を楽にし、窒息を防止する。
文例28:呼吸管理
呼吸状態を観察し、SpO2低下時は医師へ迅速に連絡する。
文例29:栄養管理
管理栄養士の指導に基づき、栄養不足を防ぐ食事内容を工夫する。
文例30:胃ろう管理
胃ろうからの栄養注入を行い、チューブの清潔を維持する。
文例31:インスリン注射
主治医の指示に従い、訪問看護がインスリン注射を実施する。
文例32:感染症予防
手洗い・マスクを徹底し、感染リスクを減らす。
文例33:排尿管理
バルーンカテーテルを清潔に保ち、尿路感染を防ぐ。
文例34:便秘予防
排便状況を確認し、水分・食物繊維の摂取を支援する。
文例35:体重管理
週1回体重測定を行い、急激な増減がないか確認する。
文例36:転倒予防
室内の段差を解消し、歩行時は介助者が付き添う。
文例37:服薬副作用観察
服薬後の状態を観察し、副作用が疑われる場合は医師へ報告する。
文例38:睡眠管理
夜間の不眠がないか観察し、必要に応じて医師に相談する。
文例39:皮膚トラブル予防
乾燥部位に保湿を行い、かゆみや発赤を予防する。
文例40:訪問診療連携
定期的な訪問診療と連携し、状態の変化を共有する。
要介護4ケアプラン文例【認知症ケア編】
文例41:徘徊防止
玄関にセンサーを設置し、夜間徘徊を早期に発見できる体制を整える。
文例42:見当識障害支援
カレンダーや時計を設置し、日付や時間を本人にわかりやすく示す。
文例43:不安軽減
本人の好きな音楽を流し、落ち着いた環境を整える。
文例44:興奮時対応
興奮が見られた際は静かな場所に誘導し、安心できる声かけを行う。
文例45:同じ質問への対応
繰り返しの質問には穏やかに答え、不安感を増大させないよう支援する。
文例46:記憶支援
日常の予定をホワイトボードに書き出し、視覚的に確認できるようにする。
文例47:夜間不眠対応
夜間は照明を薄暗くし、安心して眠れる環境を整える。
文例48:拒否への対応
介助を拒否した際は一旦間を置き、改めて声かけを行う。
文例49:家族支援(認知症理解)
家族に認知症ケアの方法を説明し、対応力を高める。
文例50:趣味活動支援
本人が好む折り紙や塗り絵を取り入れ、認知機能の維持を図る。
文例51:昼夜逆転への対応
昼間にできるだけ活動量を増やし、夜間は静かな環境を整えることで昼夜逆転を改善する。
文例52:幻覚への対応
幻覚が見られた際は否定せず、安心感を与える声かけを行い、症状が強い場合は医師へ報告する。
文例53:妄想への対応
被害妄想が出現した際は否定せず、共感的に対応し、安心できる環境を整える。
文例54:拒食への対応
食事を拒否する場合は本人の好きな食材を取り入れ、少量から提供する。
文例55:同じ話の繰り返し対応
同じ話を繰り返す際は穏やかに傾聴し、不安感を減らす。
文例56:暴言への対応
暴言があった場合は受け止めつつ距離を取り、本人の落ち着きを待つ。
文例57:家族とのトラブル対応
家族への暴言や攻撃がある際は介入し、安心できる環境に誘導する。
文例58:パニック時対応
急な混乱やパニックが起こった際は、静かな環境に誘導して落ち着けるよう支援する。
文例59:道具の誤使用防止
危険物は手の届かない場所に保管し、安心して生活できる環境を整える。
文例60:家族への精神的支援
認知症ケアに関する情報を家族に提供し、不安を軽減する。
要介護4ケアプラン文例【家族支援・環境整備編】
文例61:介護負担軽減
家族の介護負担を軽減するため、定期的にショートステイを利用する。
文例62:福祉用具導入
電動ベッドを導入し、介助時の腰痛や身体負担を減らす。
文例63:手すり設置
廊下やトイレに手すりを設置し、安全に移動できるようにする。
文例64:スロープ設置
玄関にスロープを設置し、車椅子での外出を可能にする。
文例65:照明改善
夜間の転倒防止のため、廊下やトイレに自動点灯式照明を設置する。
文例66:段差解消
居室や廊下の段差を改修し、車椅子や歩行器で安全に移動できるようにする。
文例67:ベッド周囲環境調整
ベッド周囲を整理し、移乗や介助がしやすい環境を整える。
文例68:エアコン管理
夏場の熱中症予防のため、適切な室温管理を家族と共有する。
文例69:換気徹底
感染予防のため、定期的に窓を開けて換気を行う。
文例70:家具配置変更
転倒防止のため家具の配置を工夫し、通路を広く確保する。
文例71:家族介護技術指導
訪問看護師が家族へ介助方法を指導し、安全な介護を実践できるようにする。
文例72:レスパイト支援
介護疲れを防ぐため、定期的にデイサービスを利用する。
文例73:福祉用具のメンテナンス
車椅子やベッドの点検を行い、安全性を確保する。
文例74:入浴環境整備
浴槽に手すりやシャワーチェアを設置し、安全に入浴できるようにする。
文例75:排泄環境整備
ポータブルトイレを設置し、夜間も安心して排泄できる環境を整える。
文例76:防犯対策
徘徊や外出時に備え、玄関にセンサーを設置する。
文例77:災害時支援
災害時の避難方法を家族と確認し、連絡手段を確保する。
文例78:介護用品補充
オムツや清拭用具を定期的に補充し、家族の負担を軽減する。
文例79:訪問介護連携
訪問介護と家族が情報共有し、支援の一貫性を保つ。
文例80:地域包括との連携
地域包括支援センターと連携し、介護者の相談支援を行う。
要介護4ケアプラン文例【社会参加・在宅継続編】
文例81:デイサービス利用
週2回デイサービスを利用し、入浴とレクリエーションを行う。
文例82:訪問リハビリ
理学療法士の訪問リハビリを受け、関節可動域の維持を図る。
文例83:訪問マッサージ
週1回訪問マッサージを利用し、血行促進と疼痛緩和を図る。
文例84:外出支援
月1回家族と一緒に近隣公園へ外出し、気分転換を図る。
文例85:趣味活動支援
デイサービスで塗り絵や手芸を行い、生活の楽しみを持つ。
文例86:音楽療法
好きな音楽を流し、情緒の安定を図る。
文例87:読書支援
拡大文字の本を用意し、読書の機会を提供する。
文例88:テレビ鑑賞支援
好きな番組を一緒に見て、共感的な会話を促す。
文例89:社会交流支援
地域の交流会に参加し、他者との関わりを維持する。
文例90:季節行事参加
デイサービスの季節行事に参加し、季節感を楽しむ。
文例91:園芸活動
家庭菜園で簡単な作業を行い、達成感を得る。
文例92:買い物支援
家族と一緒にスーパーへ同行し、社会参加の機会を持つ。
文例93:在宅生活継続支援
訪問介護・訪問看護・家族支援を組み合わせ、在宅生活を継続する。
文例94:介護保険サービス活用
必要に応じて訪問入浴を導入し、生活の質を高める。
文例95:短期入所利用
家族の休養や介護負担軽減のため、ショートステイを利用する。
文例96:看取りケア
終末期には訪問看護と連携し、本人の意思を尊重したケアを行う。
文例97:緊急対応体制
緊急時にはかかりつけ医と訪問看護が迅速に対応できる体制を整える。
文例98:家族会参加
家族会に参加し、他の介護家族との交流を通じて支援を得る。
文例99:意思決定支援
本人の希望を尊重し、ケアプランに反映する。
文例100:在宅看取り希望
家族と本人の希望に沿い、自宅での看取りを支援する体制を整える。
まとめ
要介護4のケアプランは、日常生活支援から医療的管理、認知症ケア、家族支援、社会参加支援まで幅広い内容が必要です。
本記事の100事例を活用することで、ケアマネジャーは利用者の生活状況や希望に合わせたプランを効率的に作成でき
ます。コピー&ペーストで使いながら、実際の状況に応じて加筆・修正してください。















