【パクリOK例文あり】利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果
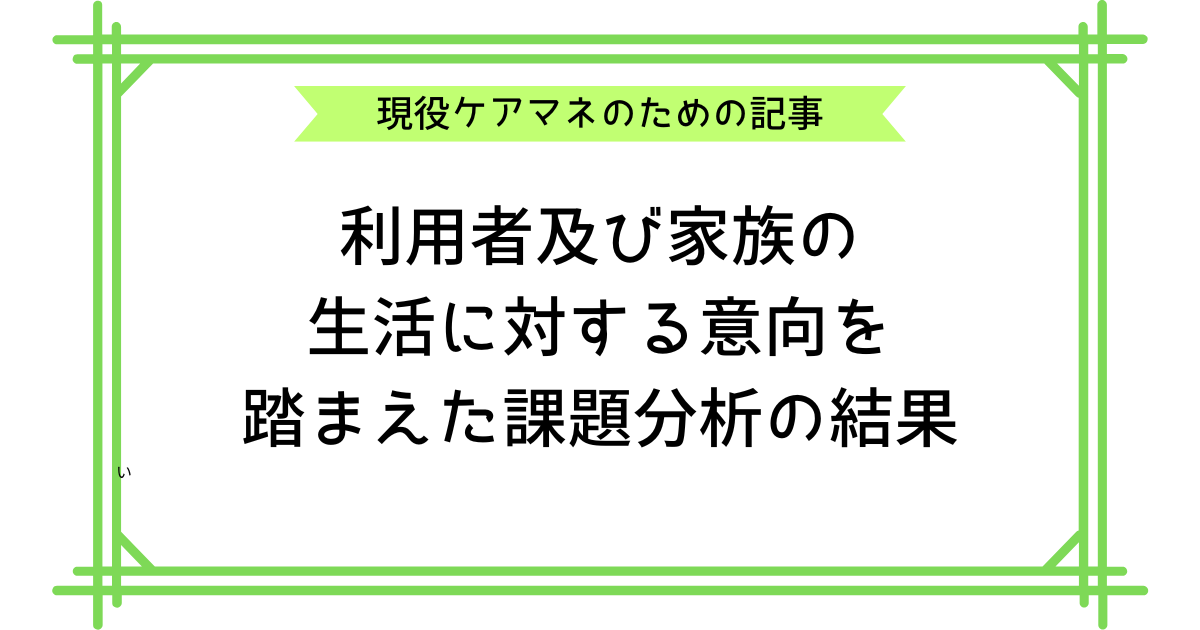
ケアプラン第1表に記載する「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」は、ケアマネジャーがもっとも悩みやすい部分のひとつです。
「どう表現すれば良いかわからない」「似たような文章ばかりになってしまう」と感じている方も少なくありません。
この記事では、【パクリOK例文】を300文まとめました。
日常生活・身体機能・認知症・医療的ケア・家族支援・在宅継続の6つのカテゴリに分けてご紹介します。
日々のケアプラン作成の参考にしてください。
【例文】利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果
生活全般に関する例文
利用者は自宅での生活継続を希望しているが、独居で日常生活に不安がある。
本人は「できることは自分でやりたい」と意欲を示すが、家事全般に介助が必要である。
食事の準備が困難で、栄養バランスが偏りやすい。
掃除や洗濯が滞り、生活環境の清潔保持に課題がある。
ゴミ出しが難しく、衛生面への支援が必要である。
日中ほとんど横になって過ごしており、活動量の低下が懸念される。
服薬管理が自己では難しく、誤薬のリスクがある。
入浴を楽しみにしているが、安全に一人で行うのは困難である。
着替えに時間がかかり、身だしなみが整わない。
孤独感が強く、会話や交流の機会を増やす必要がある。
買い物を自分で続けたいと希望しているが、歩行に不安がある。
電話対応や金銭管理に混乱が見られる。
季節に応じた衣服の準備が難しい。
自宅のバリアフリー化が不十分で、転倒リスクがある。
光熱費や家計管理に不安があり、家族の支援が必要である。
家庭菜園を続けたいと希望するが、体力的に困難になっている。
調理を続けたいと考えているが、火の消し忘れが見られる。
水分摂取が少なく、脱水のリスクがある。
ゴミの分別ができず、地域ルールに従えないことがある。
ペットの世話が困難となり、生活負担となっている。
自宅の片付けができず、転倒しやすい環境になっている。
洗濯物をため込み、不衛生な状態になりやすい。
外出を希望するが、交通機関の利用に不安がある。
自宅での生活を希望するが、災害時の避難体制に不安がある。
趣味活動を続けたいと希望しているが、体力低下で困難がある。
一人で過ごす時間が多く、閉じこもり傾向がある。
生活全般で介助を受けつつ、自分の意思を尊重されたいと希望している。
食器洗いが困難で、台所が不衛生になりやすい。
衣替えができず、衣類が散乱している。
「自宅で最期を迎えたい」と希望している。
室内の換気が不十分で、生活環境が悪化している。
テレビや新聞などの情報収集が難しく、社会参加が減少している。
農作業を続けたいと考えているが、体力的に限界がある。
家事を自分で行いたいと考えているが、転倒のリスクがある。
修繕や電球交換が困難で、家屋の安全性に課題がある。
服薬を一部自立しているが、確認が必要である。
近隣住民との交流を希望しているが、外出が減少している。
家庭内の整理整頓ができず、事故の危険がある。
ゴミをため込みやすく、衛生環境が悪化している。
外食を楽しみにしているが、移動手段に不安がある。
自宅での生活を希望しているが、独居で緊急時対応に不安がある。
模様替えを楽しみにしているが、介助が必要である。
入浴を自立して行いたいが、転倒歴があり支援が必要である。
旅行を希望しているが、健康状態に課題がある。
孫との交流を楽しみにしており、体力維持が求められる。
「家族に迷惑をかけたくない」と語っている。
食事摂取量が減少しており、栄養管理が必要である。
園芸活動を続けたいが、体力の低下が見られる。
ペットとの生活を望んでおり、その支援が必要である。
地域行事に参加したいと考えているが、移動が困難である。
身体機能・ADLに関する例文
歩行が不安定で転倒リスクが高く、見守りが必要である。
階段昇降が困難で、外出の機会が制限されている。
ベッドからの起き上がりに時間がかかり、介助が必要である。
立ち上がり動作にふらつきがあり、支援が必要である。
長距離歩行が困難で、車椅子の利用が望まれる。
トイレ動作は一部自立しているが、夜間は失禁が多く支援が必要である。
食事動作は自立しているが、嚥下機能に低下が見られる。
入浴時に浴槽のまたぎが困難で、転倒リスクが高い。
更衣に時間がかかり、季節に応じた対応ができない。
排泄後の清拭が困難で、介助が必要である。
立位保持が短時間しかできず、日常生活に支障がある。
調理中の立ち姿勢が不安定で、転倒の危険がある。
筋力低下が顕著で、リハビリによる維持が望まれる。
呼吸機能の低下があり、長時間の活動が困難である。
外出時に杖を使用しているが、不安定さが残る。
手指の巧緻動作に低下が見られ、細かい作業が難しい。
嚥下に時間がかかり、誤嚥のリスクがある。
歩行補助具を使用しているが、屋外での利用に不安がある。
夜間トイレへの移動が困難で、ポータブルトイレの活用が必要である。
体位変換が困難で、褥瘡リスクがある。
関節痛が強く、動作が制限されている。
入浴介助がないと清潔保持ができない。
排尿コントロールが難しく、失禁が見られる。
嚥下時にむせがあり、見守りが必要である。
起居動作に時間を要し、生活リズムが乱れやすい。
歩行速度が遅く、周囲の安全確保が必要である。
介助があれば歩行可能だが、一人では困難である。
調理時に包丁の使用が危険で、支援が必要である。
身体の痛みにより活動が制限されている。
食事に時間がかかり、栄養摂取が不十分になりやすい。
下肢のむくみが強く、歩行に影響がある。
移動範囲が室内に限定され、閉じこもり傾向がある。
姿勢保持が難しく、転倒のリスクがある。
トイレまでの移動に不安があり、介助が必要である。
調理や洗濯などの家事動作に時間がかかる。
歩行距離が短く、活動範囲が狭い。
立位でのバランスが悪く、転倒歴がある。
ベッドから車椅子への移乗に介助が必要である。
階段の昇降ができず、居住環境に制限がある。
痛みが強く、外出の意欲が低下している。
更衣に手間取り、外出の準備が遅れる。
嚥下困難があり、刻み食やゼリー食を必要とする。
夜間の頻尿により睡眠が妨げられている。
運動機能維持のため、継続的なリハビリが望まれる。
介助により歩行は可能だが、自立は難しい。
呼吸苦が出やすく、活動が制限される。
動作の緩慢さが目立ち、日常生活に支障がある。
動作に時間がかかり、本人の自立意欲を阻害している。
全身の体力低下があり、活動量が減少している。
屋外での移動が不安定で、転倒リスクがある。
認知症・精神面に関する例文
認知症の進行により服薬管理が困難である。
物忘れが増加し、金銭管理に不安がある。
同じ質問を繰り返し、不安感が強い。
夜間せん妄があり、見守りが必要である。
徘徊が見られ、安全確保が課題となっている。
家族の顔を忘れることがあり、介護負担が増している。
判断力が低下し、日常生活に支障がある。
被害妄想が出現し、家族との関係に影響がある。
感情の起伏が激しく、対応に工夫が必要である。
服薬拒否が見られ、服薬管理が困難である。
趣味への関心が低下し、生活意欲が落ちている。
時間や場所の見当識が低下している。
調理や火の管理が困難で、事故の危険がある。
買い物で不必要な物を購入してしまう。
夜間の不眠が強く、昼夜逆転がある。
同じ話を繰り返し、周囲が疲弊している。
幻覚が見られ、生活に不安がある。
気分の落ち込みが強く、抑うつ傾向がある。
易怒性があり、介護拒否が見られる。
認知症の進行により、家族の介護負担が増加している。
金銭詐欺などへの被害リスクがある。
徘徊で警察に保護されることがある。
物の置き場所がわからず混乱している。
認知症により火の元管理ができない。
服薬を忘れることが多く、健康管理が難しい。
季節や曜日の認識ができなくなっている。
家族の介護に対する不安が大きい。
認知症により入浴を拒否することがある。
同居家族のストレスが高まっている。
夜間の不穏行動により家族の睡眠が妨げられている。
認知機能低下により調理が困難である。
幻覚による不安で外出を拒否している。
言語理解力が低下し、意思疎通に困難がある。
記憶障害により予定を忘れることが多い。
被害妄想により介護サービスを拒否している。
生活リズムの乱れが強く、介護が難しい。
認知症により金銭トラブルが増えている。
物を紛失しやすく、家族の負担が増えている。
感情のコントロールが難しくなっている。
社会的なつながりが減少している。
一人での外出に危険が伴う。
認知症の進行により排泄の失敗が増えている。
介護拒否が強く、サービス利用に至らない。
精神的な不安が強く、安心できる環境が必要である。
周囲の人に攻撃的な言動が見られる。
物事の手順がわからなくなっている。
服薬管理が困難であり、家族がサポートしている。
記憶障害により生活全般に支障がある。
介護者のストレスケアが必要である。
医療的ケア・健康管理に関する例文
糖尿病の管理が必要であり、食事や服薬支援が重要である。
血圧管理が不安定であり、定期的な健康チェックが求められる。
心疾患があり、体調管理に注意が必要である。
呼吸器疾患により酸素療法を導入している。
胃ろうによる栄養管理が必要である。
透析治療を継続しており、送迎支援が必要である。
服薬数が多く、管理が困難である。
高齢に伴い体力低下が顕著である。
がん治療の副作用により体調不良が見られる。
褥瘡のリスクがあり、体位変換が必要である。
インスリン自己注射が困難で、支援が必要である。
嚥下障害があり、誤嚥のリスクが高い。
心不全により安静が必要である。
在宅酸素療法の継続が必要である。
パーキンソン病により動作が緩慢である。
服薬を自己管理できず、家族の協力が必要である。
食欲不振が続き、栄養状態が悪化している。
慢性疼痛があり、生活に制限がある。
感染症予防が必要で、衛生管理が課題となっている。
体温変動が激しく、健康管理が難しい。
医療機器の管理が本人では困難である。
服薬副作用のモニタリングが必要である。
抗がん剤治療に伴う副作用が強く、支援が必要である。
夜間の呼吸苦があり、安眠できない。
持病により定期通院が欠かせない。
便秘が強く、排便コントロールが必要である。
慢性的な下痢があり、脱水リスクがある。
ADL低下に伴いリハビリの継続が必要である。
てんかん発作のリスクがあり、注意が必要である。
精神疾患の既往があり、服薬管理が重要である。
慢性腎不全により食事制限がある。
嚥下障害で経口摂取が難しい。
関節リウマチにより動作制限がある。
頻繁な通院で家族の負担が大きい。
心疾患により日常生活に制限がある。
在宅点滴管理が必要である。
医療依存度が高く、専門職の支援が欠かせない。
退院後の体調変化に注意が必要である。
健康管理が本人では難しく、訪問看護が必要である。
服薬数が多く、副作用リスクがある。
終末期医療を希望している。
医師の指示に基づくケアが必要である。
体重減少が顕著で、栄養管理が求められる。
血糖コントロールが難しい。
睡眠障害が続き、生活に支障がある。
高血圧のコントロールが不十分である。
定期的な採血や検査が必要である。
医療機関との連携が欠かせない。
健康意識が低く、指導が必要である。
家族支援に関する例文
家族は介護負担の軽減を希望している。
同居家族は仕事を持ち、日中の介護が難しい。
介護経験がなく、不安を抱えている。
介護者が高齢で、体力的に限界がある。
家族は在宅介護を続けたいが、支援が必要である。
介護者の休養のため、ショートステイ活用が望まれる。
家族の介護ストレスが強い。
介護方法について家族への指導が必要である。
家族は入所も検討している。
介護負担が増し、心身の疲労が見られる。
家族は本人の希望を尊重したいと考えている。
介護に伴い家族の就労に支障がある。
介護により家計に負担が生じている。
家族の協力が得にくい。
家族内で介護の分担が難しい。
介護者の健康状態が悪化している。
家族の理解不足が課題となっている。
介護の継続に不安を感じている。
家族間で介護方針に意見の違いがある。
介護と育児の両立が難しい。
介護と仕事の両立に悩んでいる。
介護サービスの利用に消極的である。
家族の支援体制が整っていない。
介護知識が不足している。
介護負担が強く、離職のリスクがある。
家族が精神的に疲弊している。
介護に対する不安が大きい。
介護方法の習得が必要である。
家族の介護意欲は高いが、体力が不足している。
介護で睡眠不足になっている。
家族の生活リズムが乱れている。
介護に対する家族の協力が限定的である。
家族は本人の意向を尊重しつつ負担軽減を望んでいる。
介護経験が浅く、戸惑いが多い。
介護により家族の健康管理が不十分になっている。
家族が疲労困憊している。
介護方法が不適切な場合がある。
介護に伴い家族のストレスが高まっている。
介護に関する情報不足が課題である。
介護負担が限界に近づいている。
介護により家族関係が悪化している。
介護と学業の両立が難しい。
介護により社会参加が制限されている。
介護方法の改善が必要である。
家族は本人と共に生活を続けたいと考えている。
家族の介護力が不足している。
介護と家庭生活の両立が困難である。
介護により経済的負担が大きい。
家族が安心できる支援が求められている。
在宅継続・施設入所検討に関する例文
本人は在宅での生活を強く希望している。
独居で支援体制が不十分である。
家族は施設入所も視野に入れている。
本人は自宅で過ごしたいが、介護力が不足している。
在宅生活を続けたいが、夜間の対応が困難である。
施設入所への抵抗感がある。
本人は最期まで自宅で生活したいと望んでいる。
介護力不足により在宅生活が難しい。
施設入所を検討する時期にきている。
本人は在宅生活を続けたいと強く訴えている。
家族は施設入所を希望しているが本人は拒否している。
在宅生活の継続にサービス利用が不可欠である。
本人は在宅死を望んでいる。
施設入所を検討するが、本人の希望は在宅である。
在宅介護に限界が見えている。
本人は在宅での生活にこだわりがある。
施設入所を検討しているが費用面に不安がある。
在宅生活継続には医療的支援が必要である。
家族は在宅介護を希望している。
本人は自宅での生活を望むが、支援体制が不足している。
在宅生活の維持には多職種連携が必要である。
施設入所を避けたいという本人の希望が強い。
在宅生活を続けるには環境整備が必要である。
本人は施設入所に不安を抱いている。
在宅生活の継続には介護サービスの充実が必要である。
家族は在宅介護に限界を感じている。
本人は施設入所を希望していない。
在宅での療養生活を望んでいる。
施設入所も選択肢として検討している。
本人の意向は在宅生活の継続である。
家族は在宅生活を支えたいと考えている。
在宅生活には訪問看護が不可欠である。
本人は「自宅で過ごしたい」と強く希望している。
施設入所を避けたいが、介護力が不足している。
在宅生活には介護サービスの増加が必要である。
本人の希望を尊重しつつ施設入所を検討する必要がある。
在宅生活継続には住宅改修が必要である。
本人は自宅での生活に安心感を持っている。
施設入所は望んでいない。
在宅生活を続けるには介護者の支援が欠かせない。
本人は「最後まで自宅で」と希望している。
在宅生活に限界がある。
施設入所を検討するが本人は拒否している。
在宅生活の維持に介護サービスが必要である。
本人は在宅療養を希望している。
施設入所には抵抗がある。
在宅生活を継続するには家族支援が重要である。
本人は自宅での生活を希望しており、その実現に支援が必要である。
まとめ
「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」は、本人や家族の思いと現状の課題をつなげる重要な記載です。
今回紹介した300文を参考にすれば、ケアプラン作成時の表現の幅が大きく広がります。
必要に応じて言葉を入れ替えて使うことで、より利用者一人ひとりの状況に即したケアプランを作成することができます。















