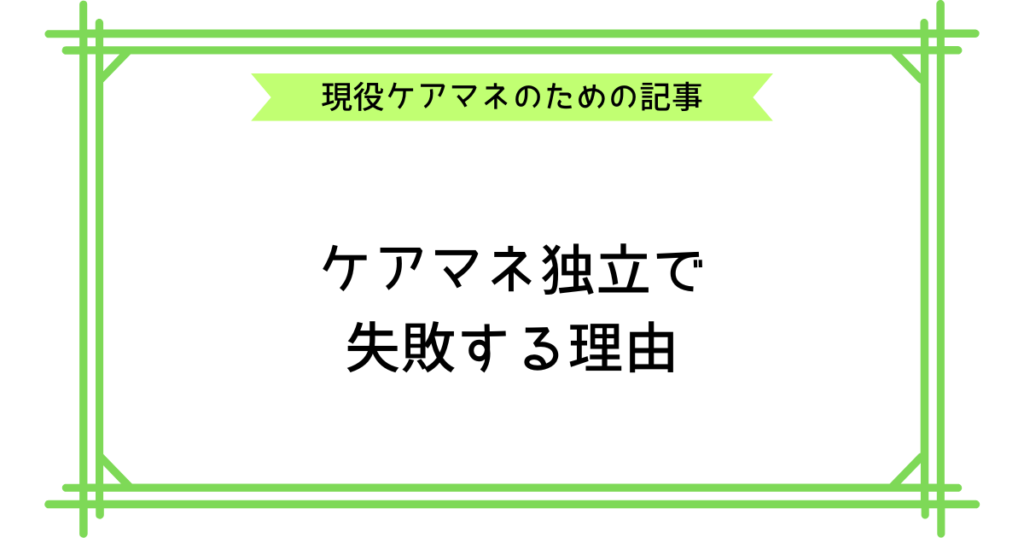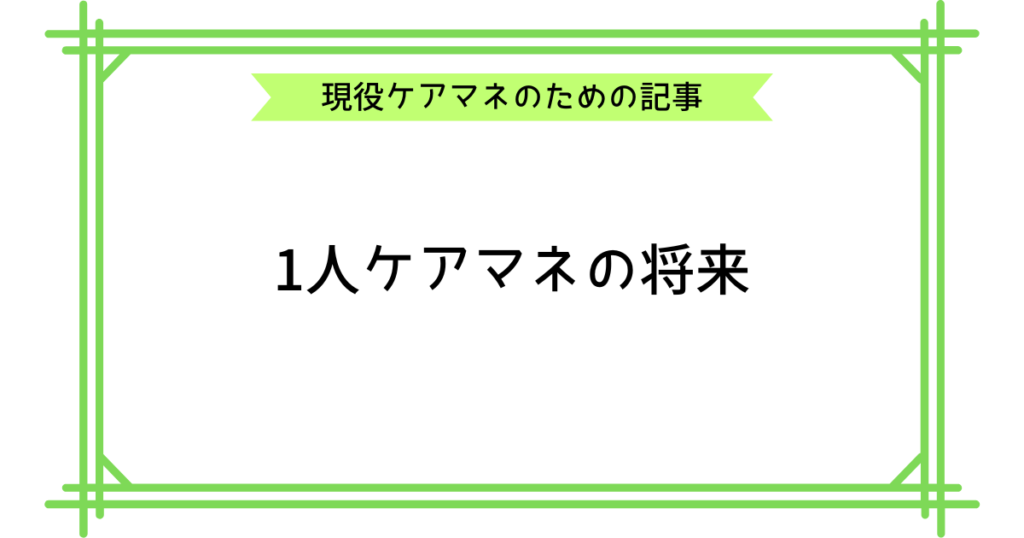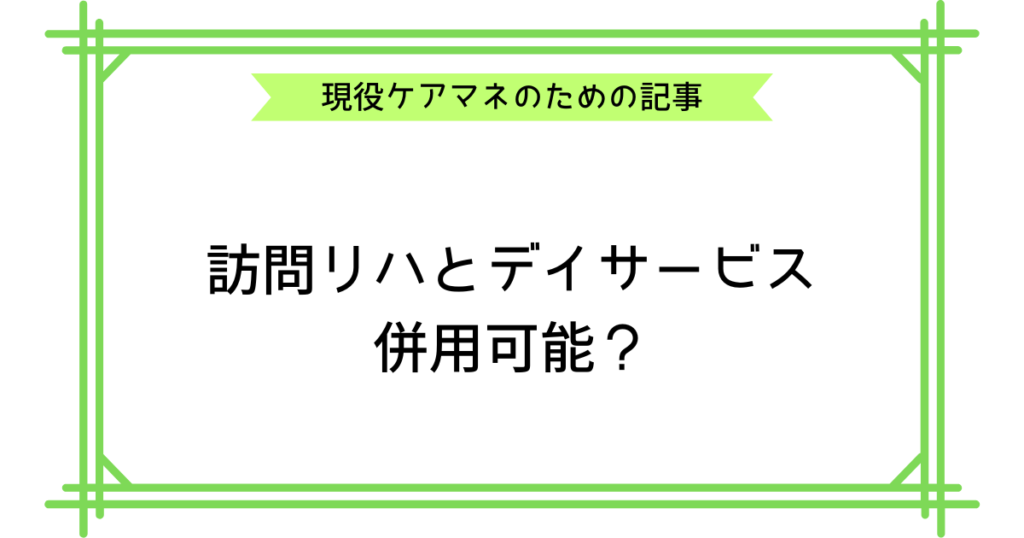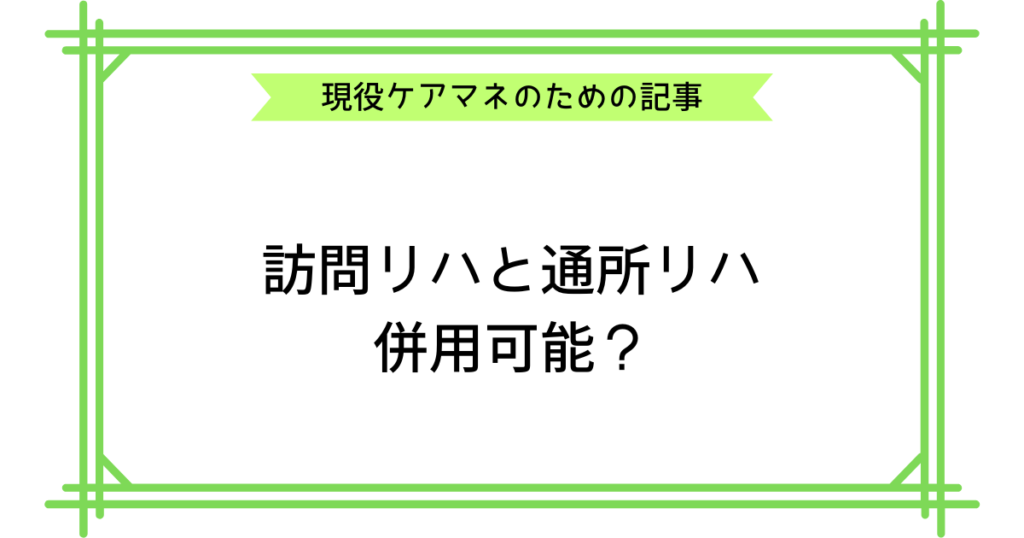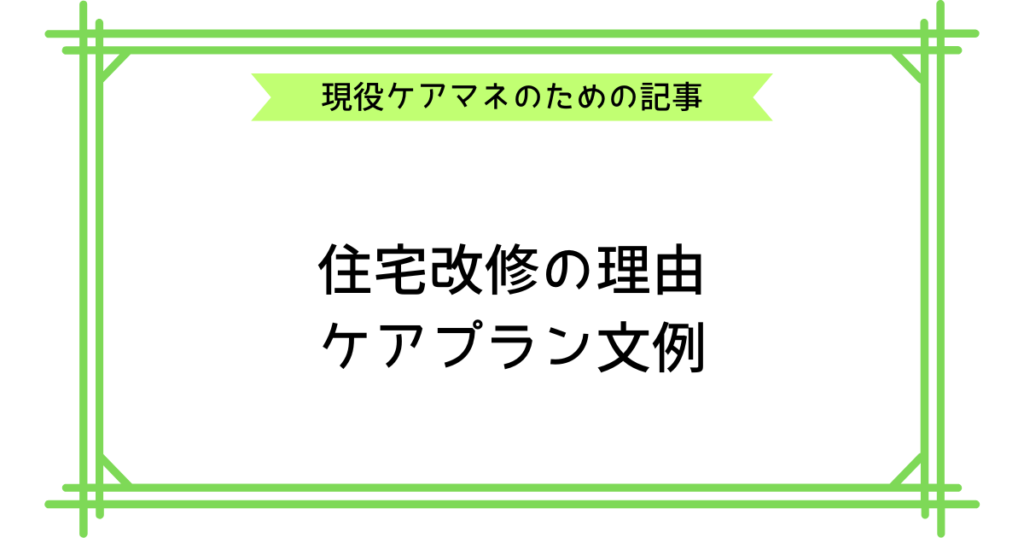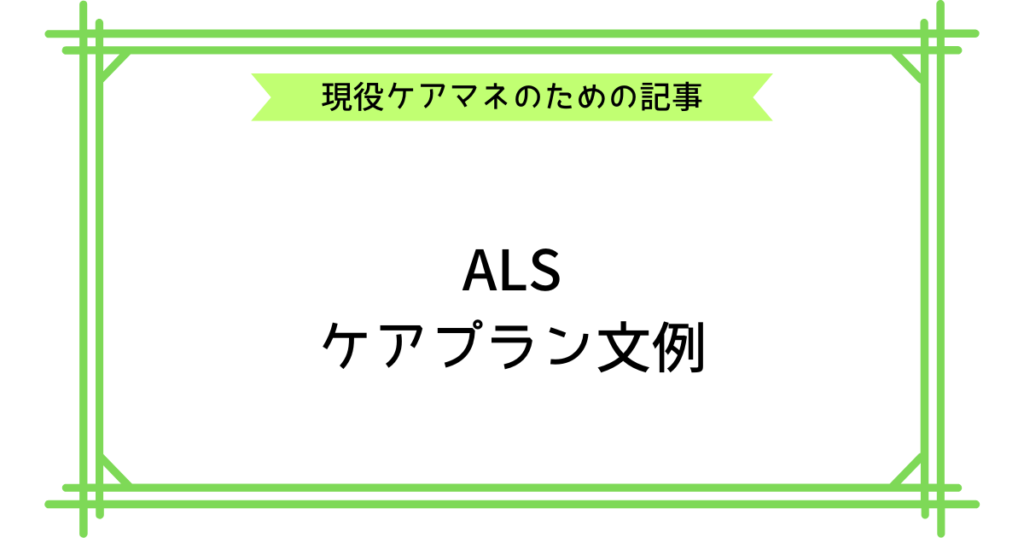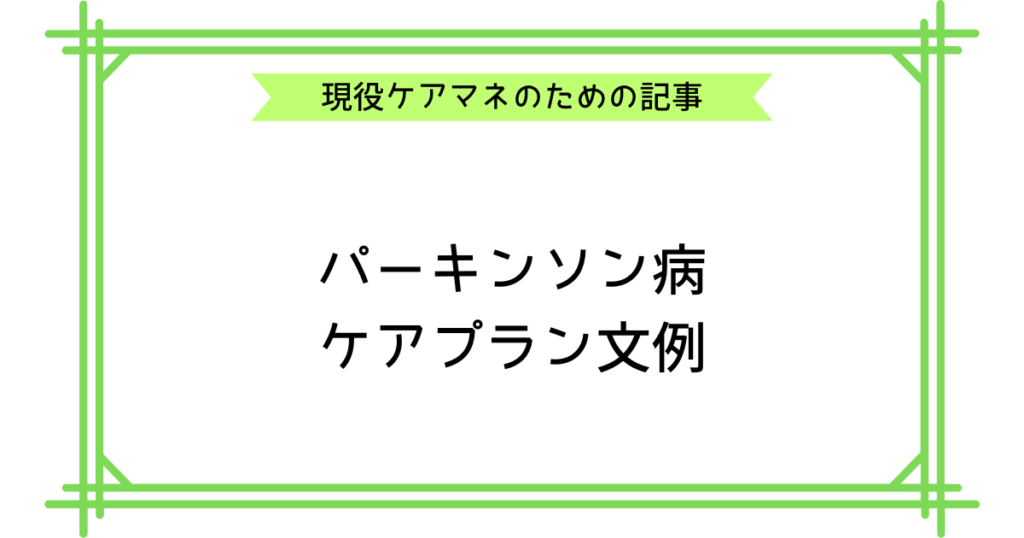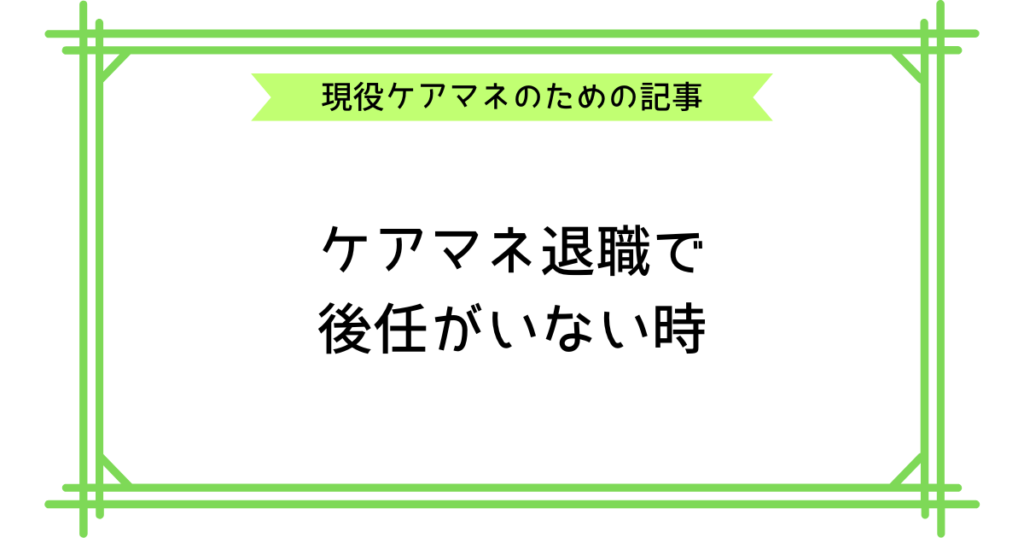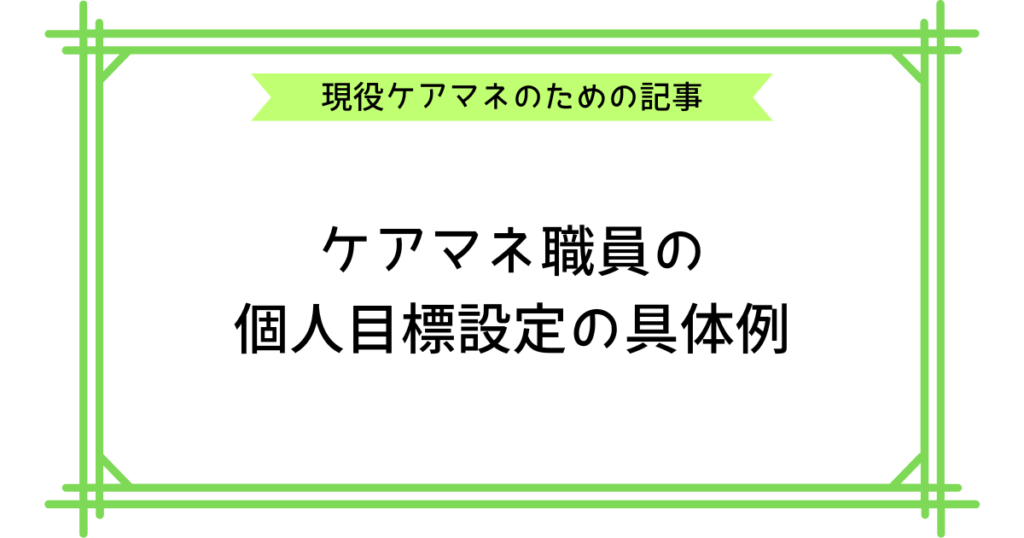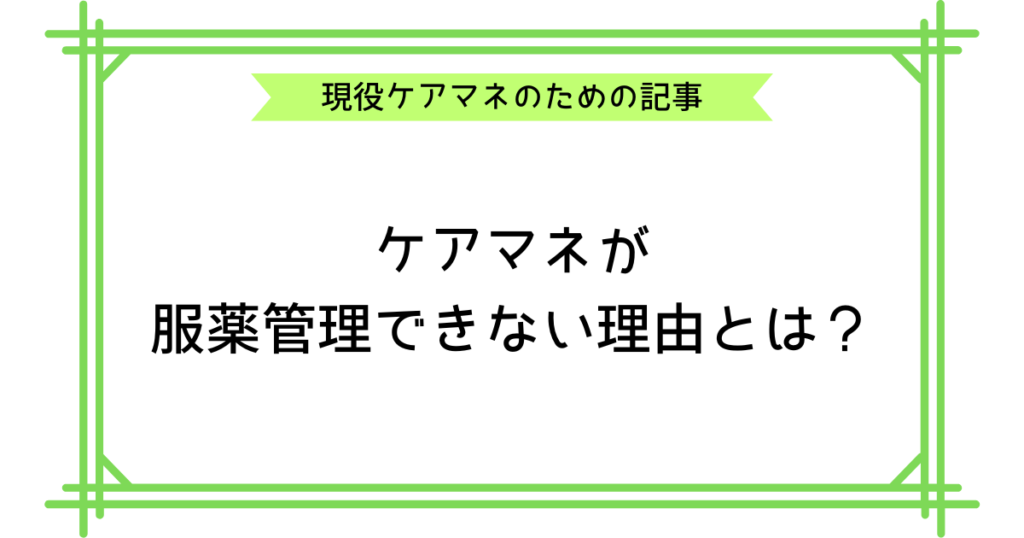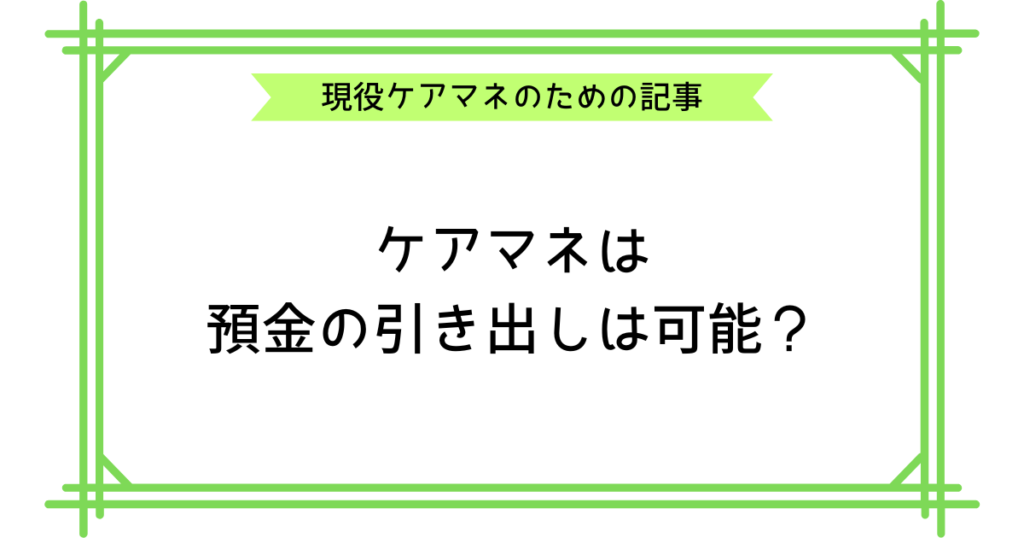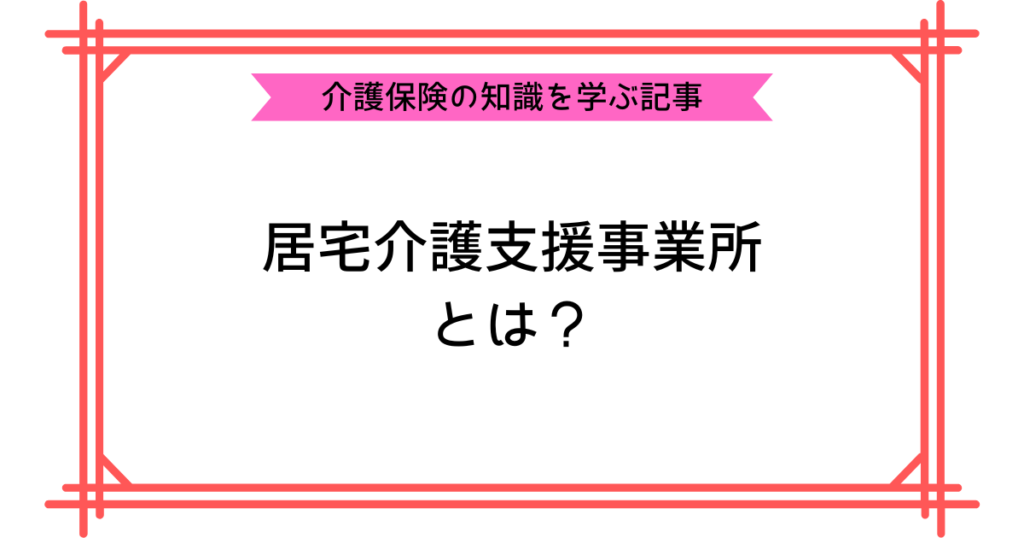記事一覧
-

ケアマネ独立で失敗する理由とは?避けるためのポイントを徹底解説
「ケアマネとして独立開業したいけど、失敗したらどうしよう…」 近年、居宅介護支援事業所を立ち上げて独立を目指すケアマネジャーは少なくありません。 しかし現実には、開業したものの数年で廃業してしまうケースも多く、「ケアマネ独立は失敗しやすい」... -

一人ケアマネの今後について推測!将来的にどうなる?
介護業界のなかで長年議論されてきたテーマの一つに「一人ケアマネ(単独型居宅介護支援事業所)」のあり方があります。 人員基準を満たす最低ラインで運営できる仕組みは、小規模な地域や独立系ケアマネにとっては必要な制度でした。 しかし近年の法改正... -

訪問リハビリとデイサービスは併用可能なのか?厚生労働省の根拠を元に解説
利用者やご家族、そしてケアマネジャーからもよく相談されるのが「訪問リハビリとデイサービスは一緒に使えるの?」という疑問です。 自宅でのリハビリも、施設でのリハビリやレクリエーションもどちらも必要なケースは少なくありません。 しかし法的なル... -

訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?禁止?法的根拠を元に解説
結論(訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?) 訪問リハビリと通所リハビリの併用そのものは可能です(例:週に訪問リハ+別日に通所リハ、同日でも可)。 ただし同一時間帯の重複は不可です。「通所サービス+訪問サービス」を同じ時間に使うと、訪問... -

【コピペOK】住宅改修の理由のケアプラン文例200事例を紹介
住宅改修は、在宅生活を続けるために欠かせない支援のひとつです。 しかし、ケアマネジャーがケアプランに「住宅改修の理由」を記載する際、「どう書けばいいのか」「適切な表現が浮かばない」と悩むことも少なくありません。 この記事では、介護保険の住... -

【コピペOK】ALS(筋萎縮性側索硬化症)のケアプラン文例200事例を紹介
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の利用者に対するケアプラン作成は、進行性の症状に応じて柔軟に対応していくことが求められます。 呼吸器管理、嚥下障害への対応、コミュニケーション支援、そして家族の介護負担軽減など、多面的な視点が必要です。 しかし、い... -

【コピペOK】パーキンソン病のケアプラン文例200事例を紹介
パーキンソン病の利用者に対するケアプラン作成では、運動機能の低下や服薬管理、転倒リスクへの配慮、精神面や家族支援など幅広い観点が求められます。 しかし「文例をどう書けばよいか分からない」と悩むケアマネジャーも少なくありません。 この記事で... -

ケアマネ退職で後任がいない時はどう対応すればよいか?
「ケアマネジャーが退職することになったけれど、後任が見つからない」──介護事業所でよくある悩みです。 居宅介護支援事業所は、ケアマネが不在になると利用者のケアプラン作成や給付管理ができなくなり、運営そのものに大きな影響が出ます。 さらに、利... -

ケアマネ職員の個人目標設定具体例を紹介!そのまま使える例文あり
ケアマネジャー(介護支援専門員)として働く中で、人事評価や年度初めの目標管理シートに「個人目標の設定」を求められることは多いでしょう。 しかし「具体的にどう書けば良いのか分からない」「抽象的になってしまう」と悩む人も少なくありません。 本... -

ケアマネが服薬管理をしてはいけない理由とは?別の方法も紹介
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護サービス利用者やその家族にとって生活を支える大切な存在です。 しかし、実際の現場では「服薬管理もやってほしい」「薬の確認までお願いできないか」といった要望を受けることがあります。 利用者の安全を守る... -

ケアマネは担当利用者の預金の引き出しは可能?不可能?良い方法も紹介
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者の生活全般を支える調整役として重要な役割を担っています。 その中で、利用者や家族から「預金の引き出しをお願いできませんか?」と頼まれることがあります。 特に独居高齢者や認知症の方、家族が遠方に住ん... -

居宅介護支援事業所(ケアマネの事業所)とは?一般人向けにわかりやすく解説
介護保険制度を利用しようとするとき、よく耳にするのが「居宅介護支援事業所」という言葉です。 しかし「デイサービスや訪問介護は分かるけど、居宅介護支援事業所って何をするところ?」「どんな役割があるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょう...