介護認定審査会とは?一般人にもわかりやすく解説
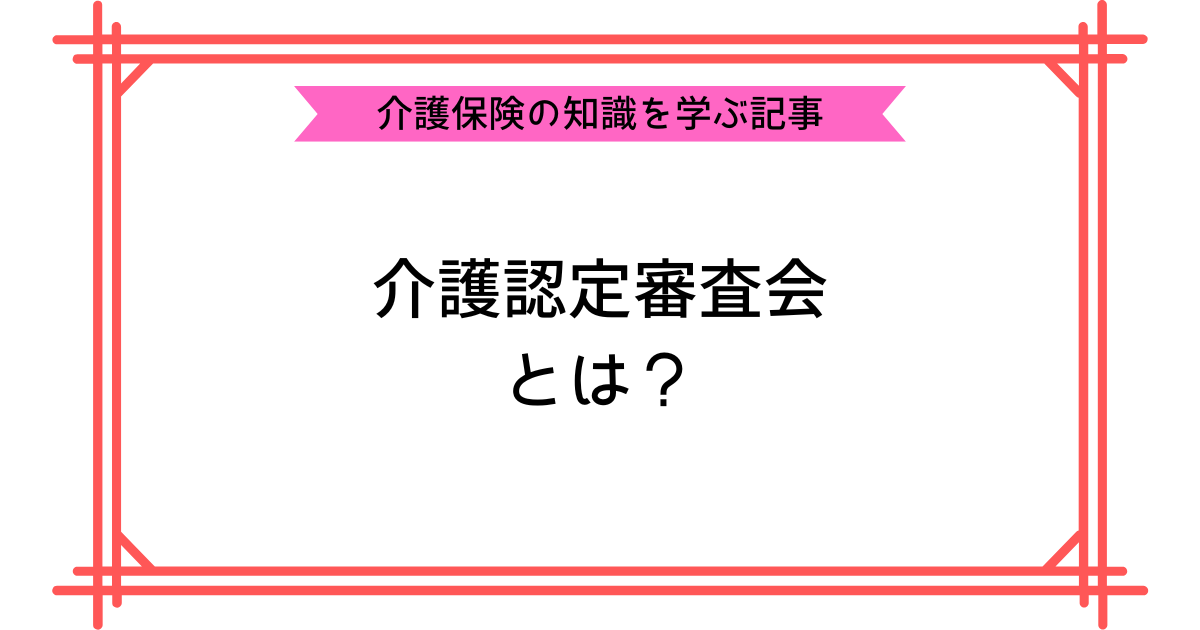
介護サービスを利用するには、まず 要介護認定 を受ける必要があります。
その際に重要な役割を果たすのが 介護認定審査会 です。
しかし「審査会って誰がやっているの?」「どんなことを決めるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、介護認定審査会の仕組みや流れ、どんな人が関わるのかを、介護に詳しくない方にもわかりやすく解説します。
介護認定審査会とは?
介護認定審査会とは、要介護認定の最終判断を行うための専門家会議 のことです。
市区町村が設置し、医師や看護師、介護福祉士、ケアマネジャーなどの専門職が委員として参加します。
認定調査や主治医意見書などの情報をもとに、利用者の心身の状態を総合的に判断し、要介護度(要支援1〜要介護5など)を決定する役割 を担っています。
介護認定審査会のメンバー
審査会には、次のような専門職が参加します。
- 医師(利用者の病状や医学的観点から判断)
- 看護師(生活状況や介護の必要度を評価)
- 介護福祉士やケアマネジャー(介護の実態を把握し評価)
- 理学療法士や作業療法士などリハビリ専門職
複数の分野から専門家が集まることで、公平で多角的な判断ができるようになっています。
認定の流れと審査会の役割
介護認定の流れの中で、審査会は次の段階を担います。
- 申請
利用希望者が市区町村に介護認定を申請します。 - 認定調査
調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を聞き取り・観察します。 - 主治医意見書の作成
かかりつけ医が医学的な意見を記入します。 - 一次判定(コンピュータ判定)
認定調査のデータをもとに、機械的に仮の要介護度を判定します。 - 二次判定(介護認定審査会)
一次判定結果、調査員の特記事項、主治医意見書をもとに、専門家が最終的な要介護度を判定します。
つまり、審査会は「人による判断」を行う重要なプロセス です。
介護認定審査会で決まること
介護認定審査会では、次のようなことが決まります。
- 要支援1〜要介護5などの「要介護度」
- 非該当(介護サービスは不要と判断)
- 認定の有効期間(原則6か月または12か月など)
この審査結果をもとに、利用者は介護サービスを使えるようになります。
審査会に不安を感じる必要はある?
「専門家が集まって話し合う」と聞くと不安になる方もいますが、介護認定審査会は 公平で透明性のある判定 を行うための仕組みです。
利用者本人や家族が直接参加することはありませんが、調査員や主治医が提出した情報をしっかり反映して判断が行われます。
まとめ
介護認定審査会とは、市区町村に設置された専門家の会議で、要介護度を最終的に判定する場 です。
医師・看護師・介護福祉士などの専門家が集まり、調査結果や医師の意見をもとに公平な判断が下されます。
介護サービスを利用するための大切なステップですが、本人や家族が直接関わる必要はなく、安心して任せられる仕組みです。
介護を考える際には、「介護認定審査会」があることで、より正確で公正な認定が行われていることを理解しておくと安心です。















