チームオレンジコーディネーターとは?資格、配置、業務内容などをわかりやすく解説
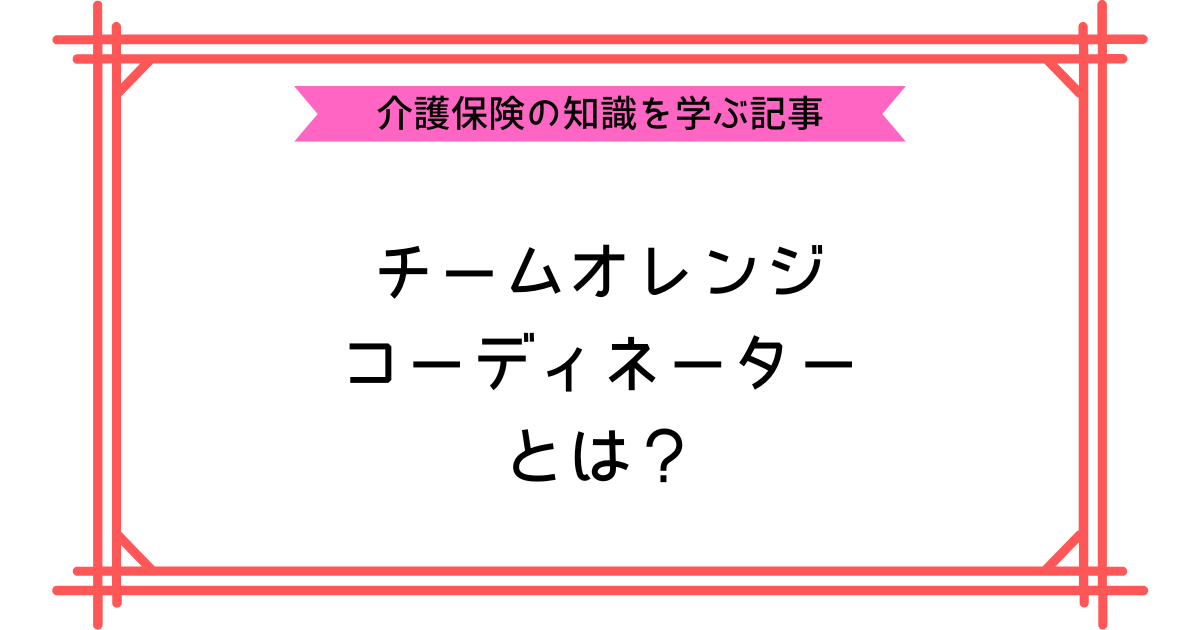
「チームオレンジ」という言葉を聞いたことがありますか?
チームオレンジとは、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域全体で支える仕組みのことです。その中で中心的な役割を担うのが チームオレンジコーディネーター です。
この記事では、チームオレンジコーディネーターの役割や資格、配置基準、具体的な業務内容について、介護や福祉の専門用語に詳しくない方にもわかりやすく解説します。
チームオレンジとは?
チームオレンジとは、認知症になった方を地域ぐるみで支える仕組みの通称です。
厚生労働省が進める「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」をもとに、地域包括支援センターを中心に 医療・介護・福祉・地域住民が連携して支援する体制 を指します。
「オレンジ」は、認知症支援のシンボルカラーとして用いられており、認知症の人が孤立せず地域で生活できることを目標にしています。
チームオレンジコーディネーターとは?
チームオレンジコーディネーターとは、チームオレンジの活動を調整し、地域での認知症支援をスムーズに行うためのキーパーソンです。
認知症の人や家族、地域住民、医療・介護の関係機関をつなぐ 「ハブ(つなぎ役)」 のような存在です。
資格や要件
チームオレンジコーディネーターになるには、特別な国家資格が必要なわけではありません。
ただし、以下のような資格や経験を持つ人が任命されるケースが多いです。
- 主任ケアマネジャー
- 保健師
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 認知症地域支援推進員の経験者
いずれにしても、認知症ケアや地域包括支援に関する知識と経験 が重視されます。
配置について
チームオレンジコーディネーターは、各 地域包括支援センター に配置されます。
市区町村ごとに設置される地域包括支援センターが、地域の認知症施策の拠点であり、そこで認知症支援の調整役として機能します。
自治体によっては、地域の状況に応じて専任や兼任で配置されているケースがあります。
主な業務内容
チームオレンジコーディネーターの業務は多岐にわたりますが、大きく分けると以下の役割があります。
1. 認知症の人や家族の支援
- 生活相談やサービス利用の調整
- 必要に応じて医療機関や介護サービス事業所につなぐ
2. 医療・介護・地域資源の連携調整
- ケアマネジャー、医師、訪問看護、介護サービス事業所などと情報共有
- 多職種会議や地域ケア会議をコーディネート
3. 地域住民への啓発活動
- 認知症サポーター養成講座などを開催
- 地域の理解促進や見守り体制づくりを支援
4. チームオレンジの活動推進
- ボランティアや地域団体と協力し、居場所づくりや交流会を企画
- 地域ぐるみの「認知症にやさしいまちづくり」を実現するための調整役
チームオレンジコーディネーターの意義
- 認知症の人や家族が孤立しないための「つなぎ役」
- 医療・介護・地域を横断する調整役としての存在感
- 住民にとっても「困ったら相談できる人」として安心につながる
認知症は誰にでも起こりうることであり、地域全体での支援が必要です。
その中でコーディネーターは、専門職と地域住民を結びつける キーパーソン として重要な役割を担っています。
まとめ
チームオレンジコーディネーターとは、地域包括支援センターを拠点に配置される認知症支援の調整役です。
特定の国家資格が必要なわけではありませんが、主任ケアマネや保健師など、認知症や地域支援に精通した専門職が任命されることが多いです。
業務内容は、認知症の人や家族の支援、関係機関との連携調整、地域啓発活動など多岐にわたり、地域全体で認知症を支えるために欠かせない存在です。
認知症になっても安心して暮らせる社会を実現するために、チームオレンジコーディネーターは今後さらに重要な役割を果たしていくでしょう。















