認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは?わかりやすく解説
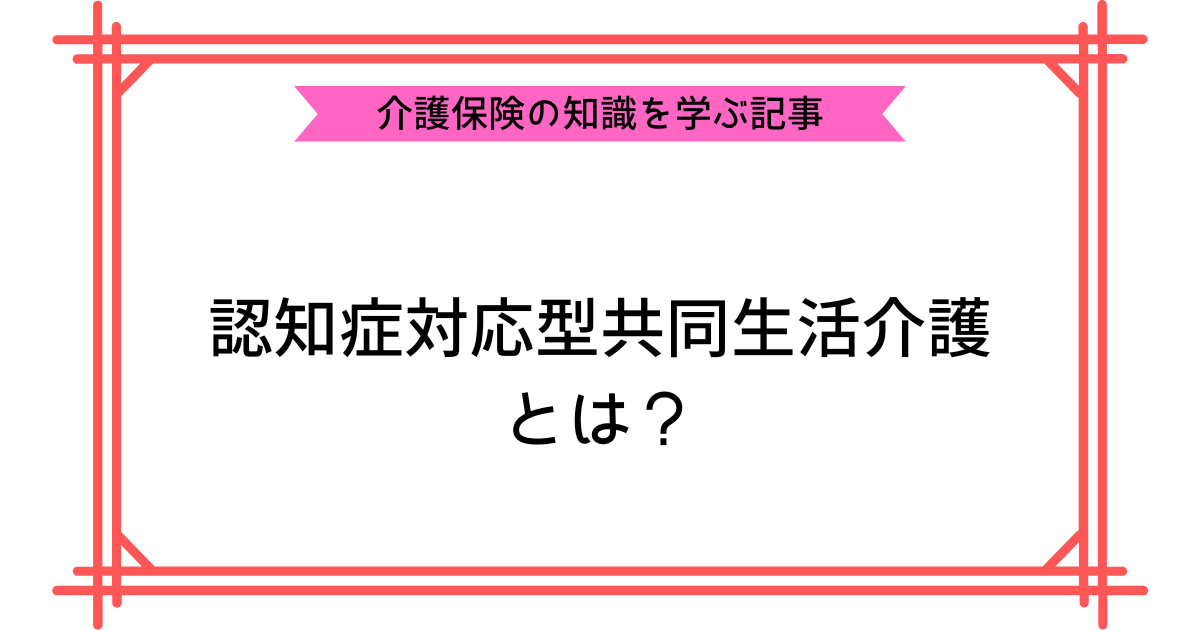
介護保険サービスの中には、聞き慣れない名称が数多くあります。そのひとつが「認知症対応型共同生活介護」です。
一般には「グループホーム」と呼ばれることが多く、認知症高齢者が少人数で共同生活を送りながら、介護スタッフの支援を受ける仕組みを指します。
認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、生活の場とケアの一体的な支援が不可欠です。
しかし、「どんなサービス内容なのか」「利用できる条件は?」「費用はどれくらい?」といった疑問を抱くご家族も多いでしょう。
本記事では、認知症対応型共同生活介護の概要、特徴、対象者、利用の流れ、費用、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
介護を検討中のご家族や、介護職として学習中の方に役立つ内容です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは?
定義
認知症対応型共同生活介護とは、介護保険法で定められた地域密着型サービスのひとつで、認知症の高齢者が少人数(5〜9人)で共同生活を営みながら介護や生活支援を受けるサービスです。
施設というより「住まい」の機能が強く、食事の準備や掃除、洗濯などを職員と一緒に行いながら、家庭的な雰囲気の中で過ごせることが特徴です。
目的
- 認知症による症状の進行を緩やかにする
- 生活のリズムを整え、本人の残存能力を活かす
- 地域との関わりを保ち、孤立を防ぐ
- 家族の介護負担を軽減する
利用できる対象者
認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
- 介護保険の 要支援2以上または要介護1〜5の認定者
- 医師により 認知症の診断 を受けている方
- 施設が所在する市区町村に住民票がある方
- 集団生活に支障がない方(自傷・他害行為がないことが前提)
つまり、軽度〜中度の認知症で、日常生活に一定の介助が必要だが、家庭的な環境で暮らすことが可能な人が対象です。
サービス内容
認知症対応型共同生活介護では、主に以下の支援が提供されます。
- 食事の提供・調理支援
入居者も調理に参加できるよう配慮され、自立支援につながる。 - 入浴・排泄・清拭の介助
プライバシーを尊重しながら必要な介助を実施。 - 掃除・洗濯・買い物など生活援助
できる部分は本人が行い、難しい部分を職員が支援。 - 認知症ケア
回想法、音楽療法、レクリエーションを取り入れ、認知機能の維持をサポート。 - 健康管理
医師や看護師と連携し、服薬や体調管理を行う。 - 地域交流
近隣住民やボランティアとの交流を促進し、社会的孤立を防ぐ。
利用定員と運営体制
- 1ユニット9人以下、2ユニット18人程度が一般的
- 24時間体制で介護スタッフが配置される
- 介護福祉士や認知症ケア研修を修了した職員が中心
- 医師や看護師との連携で健康面もサポート
少人数制であるため、一人ひとりの状態に合わせたケアを提供できるのが大きな特徴です。
利用までの流れ
- ケアマネジャーに相談
利用希望を伝え、ケアプランに位置づけてもらう。 - 施設の見学・面談
雰囲気やスタッフとの相性を確認。 - 申込・診断書提出
認知症の診断書や要介護認定結果を提出。 - 契約・入居開始
契約後、必要に応じて試験入居を経て正式入居。
利用費用の目安
費用は「介護保険サービス費用(自己負担1〜3割)」+「食費・居住費・光熱費」などがかかります。
介護サービス費(1割負担の場合)
- 要支援2:約25,000円前後/月
- 要介護1:約27,000円前後/月
- 要介護5:約35,000円前後/月
食費・居住費など
- 食費:約30,000〜40,000円/月
- 居住費:約40,000〜60,000円/月
- 光熱水費・日用品費など:約10,000〜20,000円/月
合計:1か月あたり約12万〜15万円前後が目安です。地域や施設によって差があります。
メリット
- 家庭的な環境で生活できる
施設というより自宅に近い雰囲気で落ち着ける。 - 認知症ケアに特化している
専門職員が対応し、認知症の進行抑制につながる。 - 少人数制で目が行き届く
1ユニット9人以下で、きめ細やかな支援が可能。 - 地域とのつながりを保てる
地域密着型サービスであるため、住み慣れた町で暮らし続けられる。
デメリット
- 入居定員が少なく待機が多い
人気が高く、入居待ちが発生するケースが多い。 - 重度の医療対応は難しい
24時間看護師が常駐していないため、医療依存度が高い人には不向き。 - 費用が比較的高い
食費・居住費を含めると月額10万円以上かかるため、家計に負担となる場合がある。
他の施設サービスとの違い
- 特別養護老人ホーム:重度要介護者も対応可だが、大規模施設。
- 有料老人ホーム:介護付きタイプもあるが、費用が高額になることが多い。
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護):小規模・家庭的で、認知症高齢者に特化。
よくある質問(Q&A)
Q:認知症の診断があれば誰でも入居できますか?
A:要支援2以上の認定と、施設の所在市区町村に住民票があることが条件です。
Q:医療的ケアが必要な人でも利用できますか?
A:吸引や点滴などが必要な方は利用が難しい場合があります。医療連携体制を確認しましょう。
Q:費用はどのくらいかかりますか?
A:自己負担1割の場合、介護費用と生活費を合わせて月12〜15万円前後が目安です。
まとめ
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症高齢者が少人数で共同生活を送りながら、専門職の支援を受ける地域密着型サービスです。
- 対象は要支援2以上の認知症高齢者
- サービスは食事・入浴・排泄介助から生活援助・認知症ケアまで幅広い
- 家庭的な雰囲気で安心できるが、医療的対応は制限がある
- 費用は月12〜15万円前後が一般的
利用を検討する際は、ケアマネジャーに相談し、施設見学や費用の確認をしながら、本人や家族に合った生活の場を選ぶことが大切です。















