小規模多機能型居宅介護(小多機)とは?わかりやすく解説
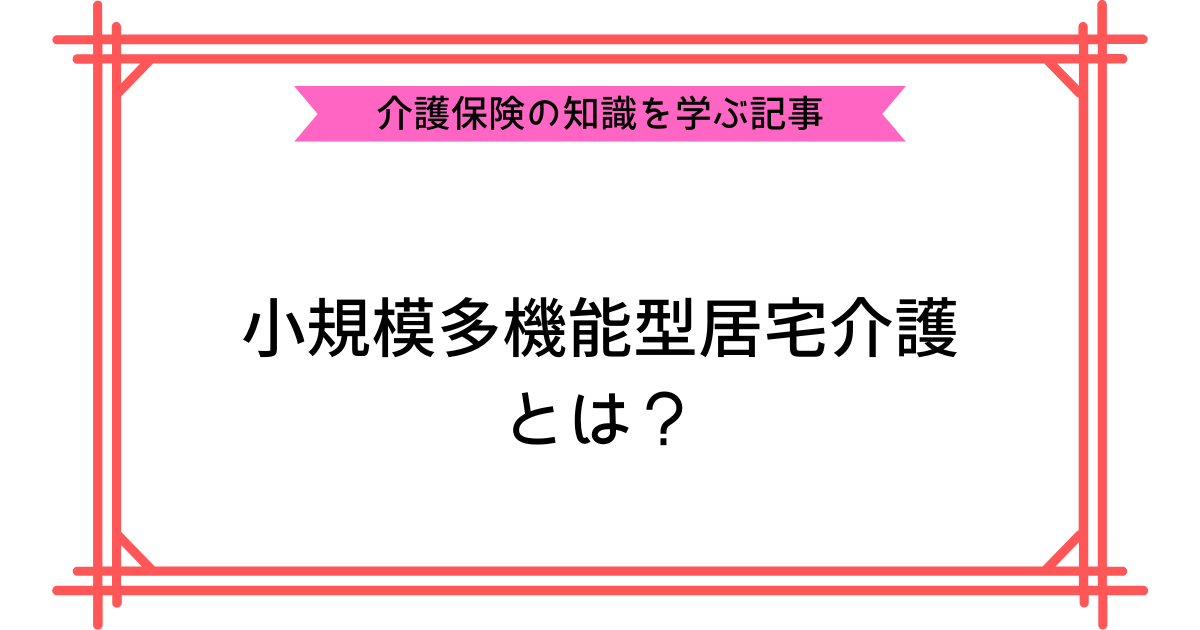
介護保険サービスの中には、「訪問介護」「通所介護(デイサービス)」「ショートステイ」といったサービスがよく知られています。しかし、実際の生活では「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせたい場面も多いのではないでしょうか。
そんなニーズに応えるサービスが小規模多機能型居宅介護(略称:小多機)です。小多機は一つの事業所が、通い・訪問・宿泊のサービスをまとめて提供する仕組みであり、利用者や家族にとって安心感のある柔軟な支援が受けられるのが大きな特徴です。
この記事では、小規模多機能型居宅介護の定義、特徴、対象者、サービス内容、利用方法、費用、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
小規模多機能型居宅介護(小多機)とは?
定義
小規模多機能型居宅介護(小多機)とは、介護保険制度で定められた地域密着型サービスのひとつで、次の3つのサービスを一体的に提供する仕組みです。
- 通い(デイサービス)
- 訪問(ホームヘルプ)
- 泊まり(ショートステイ)
同じ事業所の職員がサービスを担当するため、利用者にとって顔なじみのスタッフから切れ目のない支援を受けられることが特徴です。
目的
- 在宅生活をできる限り長く続けられるよう支援する
- 利用者と家族の安心感を高める
- 突発的なニーズ(急な泊まりや延長)にも柔軟に対応する
対象となる利用者
小多機を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
- 要介護1以上の認定を受けている人(要支援は対象外)
- 事業所が所在する市区町村に住民票がある人
- 在宅生活を継続したいと考えている人
特に、「一人暮らし」「家族が日中不在」「認知症が進んできて不安」といった方に多く利用されています。
サービス内容
小規模多機能型居宅介護では、次のサービスが包括的に提供されます。
1. 通いサービス(デイサービスに近い機能)
- 食事、入浴、排泄、機能訓練など
- レクリエーションや趣味活動を通じた交流
- 利用時間は柔軟で、朝から夕方まで、場合によっては夜間も可能
2. 訪問サービス
- 身体介護(排泄、入浴介助、服薬支援など)
- 生活援助(掃除、洗濯、買い物など)
- 緊急時対応(体調不良時の訪問など)
3. 泊まりサービス(ショートステイ機能)
- 事業所の施設に宿泊可能
- 急な家族の不在や介護負担軽減に対応
- 通いと同じ場所で泊まれるので安心
運営体制と特徴
- 登録定員はおおむね25人程度
- 1日の通い利用は15人前後が上限
- 泊まりは5〜9人程度の小規模対応
- 24時間365日、在宅生活を支える体制
- ケアマネジメントは事業所専任のケアマネジャーが担当
このように、少人数制で家庭的な雰囲気の中、柔軟にサービスを組み合わせられるのが小多機の特徴です。
利用までの流れ
- ケアマネジャーへ相談
現在利用しているケアマネ、または地域包括支援センターに相談。 - 事業所の見学・説明
サービス内容や費用について事業者から説明を受ける。 - 登録契約
利用定員が限られているため、登録制となる。 - ケアプラン作成・利用開始
専任ケアマネが中心となり、通い・訪問・泊まりを組み合わせたプランを作成。
費用の仕組み
小多機の特徴は、月額定額制である点です。
利用料(1割負担の場合の目安)
- 要介護1:約12,000円/月
- 要介護3:約26,000円/月
- 要介護5:約35,000円/月
※自己負担割合(1〜3割)によって変動します。
別途かかる費用
- 食費
- 宿泊費
- 日用品費
- レクリエーション費
このため、1か月あたりの総額は 約7万〜12万円程度 が目安となります。
小規模多機能型居宅介護のメリット
- 顔なじみのスタッフが一貫して支援
通い・訪問・泊まりを同じ職員が担当するため、安心感がある。 - 柔軟な利用が可能
「今日は泊まりたい」「急に訪問が必要になった」といったニーズに対応しやすい。 - 在宅生活の継続に有効
家族の介護負担を軽減しながら、住み慣れた地域で暮らし続けられる。 - 認知症の人にも適している
同じ環境・同じ職員の支援により、不安が少なく生活できる。
デメリット・注意点
- 利用定員が少なく、待機になる場合がある
小規模運営のため、登録枠に空きがないケースも多い。 - 医療的対応が限定される
常勤医師や看護師がいない場合もあり、医療依存度が高い人には不向き。 - 地域限定サービス
原則として事業所が所在する市区町村の住民しか利用できない。 - 費用が定額制のため使わない日も料金が発生
「ほとんど利用しない月」でも基本料はかかる。
他サービスとの違い
- 訪問介護・通所介護・短期入所をバラバラに利用する場合
それぞれ別事業所のスタッフが対応し、連携に時間がかかる。 - 小規模多機能型居宅介護
一つの事業所で一貫してサービス提供 → 切れ目のない支援が可能。
よくある質問(Q&A)
Q:要支援でも利用できますか?
A:いいえ。小多機は要介護1以上が対象です。
Q:医療処置が必要な人でも利用できますか?
A:インスリン注射や胃ろうなどが必要な場合は対応できないこともあります。医療連携体制を確認しましょう。
Q:費用は高いですか?
A:デイサービスや訪問介護を別々に利用するより割安になるケースもあります。特に泊まりを利用する場合にコストメリットが大きいです。
まとめ
小規模多機能型居宅介護(小多機)は、通い・訪問・泊まりを一体的に提供する地域密着型サービスです。
- 対象は要介護1以上の人
- 月額定額制で柔軟にサービスを利用可能
- 顔なじみのスタッフが切れ目なく支援
- 在宅生活の継続に有効で、認知症高齢者にも適している
- ただし、定員制や医療対応の限界などの注意点もある
在宅介護の安心感を高め、家族の介護負担を軽減する有効な選択肢として、小多機は今後ますます注目されるサービスです。利用を検討する際は、ケアマネジャーに相談し、事業所の体制や費用をしっかり確認することが大切です。















